小林浩さんのレビュー一覧
投稿者:小林浩

アメリカの「人道的」軍事主義 コソボの教訓
2002/06/18 18:17
NATO軍のコソボ空爆の背景とアメリカ的人道主義の本質は
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
わが国ではまず何より卓抜な言語学者として知られているチョムスキーだが、2001年9月の米国同時多発テロ事件以後は特にその政治的発言が再注目されている。『9.11』『「ならず者国家」と新たな戦争』『アメリカが本当に望んでいること』はその中でも良く読まれている書目であり、アメリカニズムの暴虐を徹底的に批判する姿勢が鮮烈だ。本書は1999年にアメリカで発刊された書物で、原題にある「ニュー・ミリタリー・ヒューマニズム」とは、ほかならぬアメリカの人道主義を指している。この人道主義は軍事主義の双子の兄弟なのだ。人道と軍事が一体化しているとはなんという卑劣な矛盾だろうか。アメリカの人道主義がいかんなく発揮された1999年のコソボ紛争の実態と背景の詳細な分析を通じ、著者は畳み掛けるようにこの国の外交政策の思い上がりを論破していく。その筆致はまことに怜悧かつ周到であり、アメリカの政治態度——特に各国への軍事介入のおせっかいぶり——に疑問を感じている者にとっては、読み進めるごとに痛快な気分を味わえるだろう。
彼はこう述べる、《レーガン/クリントン時代最大の革新は、国際法や正式の条約や義務をまったくあからさまに拒否するようになったことであり、こうした拒否が、西洋で、歴史上前例のない素晴らしい新時代の「新しい国際主義」と賞賛すらされるようになったことである》と。その通りである。「世界新秩序」においてもっとも耐えがたいことのひとつは、正義や人道の名のもとに行われる「戦争の正当化」だろう。本書の読者は何度もデジャヴュに襲われるに違いない、「これは読んだことがある」と。その感触は正しい。なぜなら、アメリカはコソボ紛争後もくだんの「人道主義」を反省せず、今なお戦争を繰り返しているからであり、チョムスキーは長い間、変幻自在のアメリカニズムへ言論をもって対抗してきたからだ。その意味で、本書は《9.11》の予言でもあったと言える。もう二度と繰り返させないために日本人ができることは何か。「有事法制」が先走るこんにちの政治の窮状を抱える私たちに色々な示唆を与えてくれる本である。なお、この日本語版には、原著にない補論「エピローグ:1999年を振り返って」が収録されている。
※併読をお奨めします→ヴィリリオ『幻滅の戦略』、千田善『ユーゴ紛争はなぜ長期化したか』、山崎佳代子『解体ユーゴスラビア』、『現代思想・臨時増刊号:総特集=ユーゴスラヴィア解体』
人文・社会・ノンフィクションレジ前コーナー5月20日分より
(小林浩/人文書コーディネーター・「本」のメルマガ編集同人)

世界名言集
2002/06/18 18:11
探していたあのことばにきっと会える。座右の銘1340編
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1984年から1989年にかけて岩波文庫の別冊シリーズとして刊行された『ことばの花束』『ことばの贈物』『ことばの饗宴』『愛のことば』を再編して、一冊にまとめたのが本書である。タイトルに金文字をあしらった丁寧な造本のハードカバー(函入)で、本文はスミとアカの二色刷り。岩波文庫として発行された古今東西の古典から、えりすぐりの名文と智慧を集約。全部で1340もの断片が収められており、巻末には著作社名索引、書名索引、文頭索引の三種を配して、読者の便宜を図っている。座右に置きたい、保存版にふさわしい一冊だ。ちなみに引用率ベスト3は、1位が夏目漱石(40回)、2位がシェイクスピア(37回)、3位はともに26回で、ゲーテとモンテーニュだ。なるほど。3位のゲーテからひとこと。「世界は粥(かゆ)で造られてはゐない。君等は懶(なま)けてぐづぐづするな、堅いものは噛まねばならない。喉がつまるか消化するか、二つに一つだ」(『ゲーテ詩集(3)』より)。
※こちらもオススメ、『日本の名随筆』全200巻からエッセンスを凝縮→『随筆名言集』
人文・社会・ノンフィクションレジ前コーナー6月17日分より
(小林浩/人文書コーディネーター・「本」のメルマガ編集同人)

WTO徹底批判!
2002/06/17 17:00
グローバリゼーションの支柱を一刀両断する痛烈なパンフレット
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
スーザン・ジョージといえば『いかにして世界の半分が死ぬか』や『ルガノ・レポート』など、切れ味抜群の世界資本主義システム批判で知られるが、その彼女がWTO(世界貿易機関)の「行き過ぎ」について容赦ない追及の筆を執ったのが、昨年(2001年)パリで刊行された本書だ。彼女は「アタック」という団体を代弁する立場で本書を書いた。「アタック」は「市民を支援するために金融取引への課税を求めるアソシエーション」の略称で、フランスや日本などで反グローバリゼーションの市民運動を展開している。本書が主張する「反グローバリゼーション」とは、超国家的企業の利益がすべてに優先されることへの抗議である。WTOの機能はそうした利益優先主義を結果的に助長しているのだが、ジョージはWTO支配下のグローバリゼーションが世界各国にどのような危機をもたらしつつあるかを鋭く分析している。
WTOは国際的な自由貿易の公正的促進を図るべく様々な規制や基準を設けたり、時には裁判権をも行使できるのだが、いまや世界に対して巧妙な弱肉強食の論理を押し付けるに至っている。WTOとそれに支えられたグローバリゼーションの驚異的な正体が本書で明らかになる。原書にはない、著者による補論や市民運動家の佐久間智子による解説も付されている。フィクションよりも奇異な現実(市民には隠されている真実)が暴かれるのを目の当たりにした読者は、深い戦慄に襲われるだろうが、日本語版序文にある著者の勇気ある希望の宣言を忘れてはなるまい——《われわれは手をたずさえて、金銭だけが至上の価値であることを押しつけてくる「グローバリゼーションに対して、「もうひとつの世界は可能だ」という標語を掲げながら立ち向かっていこうではありませんか》。
※併読をお奨めします→ネグリ『構成的権力』、ガタリ『三つのエコロジー』、ブレッカーほか『世界をとりもどせ』、ボヴェほか『地球は売り物じゃない!』、市民フォーラム2001編『徹底討論WTO』、パブリック・シティズン『誰のためのWTOか?』
人文・社会・ノンフィクションレジ前コーナー5月20日分より
(小林浩/人文書コーディネーター・「本」のメルマガ編集同人)
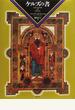
ケルズの書
2002/06/12 12:27
ケルト美術とキリスト教写本の融合による驚愕の聖書マンダラ
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
かのジェイムズ・ジョイスが最上の書物として崇めた「ケルズの書」は、福音書の写本の中でもとりわけ異彩を放つ装飾で知られる。ヨーロッパの先住民族であるケルト文化とキリスト教が融合を果たし、大陸の写本と比べて独創的な装飾と表現をもたらした。日本ではほとんどその中身については知られてこなかったが、本書はフルカラーでこのアイルランドの至宝「ケルズの書」の豪奢なページを紹介している。ヴェラム(子牛の皮)に色とりどりの筆で細やかに描かれた様々な象徴が織り成す宇宙は、圧倒的だ。植物と動物、使徒と怪獣と天使、そして神が、たがいにつながりあって、聖書の世界を荘厳する。それ自体が神獣のようにうねる装飾文字や、無限に絡み合う組紐文様、無限に運動する渦巻きなど、跳梁する多様なイメージが、めまいを誘う。四福音書の書記者たちの神々しさといったらどうだろう。8世紀末頃に成立したという「ケルズの書」を見ることができた幸運な信徒は、まさに奇跡を目の当たりにする思いがしたろう。当時、一冊の写本は一領地とも等価なほど、貴重な宝物だったのだ。豊富な図版と丁寧な解説でこの写本の戦慄的魅力を雄弁に語る、本邦初のガイドブックである。訳者の鶴岡真弓氏による数々のケルト文化論とともにひもときたい。
※12世紀の司祭による「ケルズの書」への言及→『アイルランド地誌』

中世思想原典集成 15 女性の神秘家
2002/06/11 15:57
男性中心の神学的時空を貫通する雷光の如き未聞の大冊
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
驚異的な一巻である。12〜15世紀の代表的な女性神秘思想家17名の著作を集成、ほとんどすべてが本邦初訳だ。ビンゲンのヒルデガルトによる『スキヴィアス(道を知れ)』の抄訳や、マクデブルクのメヒティルトによる『神性の流れる光』の新訳をはじめ、現代風に言えば神とダイレクトに「コンタクト」した修道女たちのめくるめく幻視譚を一望できる。18編収められたテクストの中には、男性司祭によって書かれたという『隠遁修道女戒律』もあるが、そのほかはドイツ、ベルギー、スウェーデン、イタリア、フランス、イギリスといった多彩な出身地をもつ女性たちの著作である。ある者は諸学芸を極めた英才で、ある者は予知能力の持ち主、またある者は王や教皇もその発言を無視し得ぬ「神の代弁者」だった。生前より聖人と仰がれた者もいれば、異端視されて火刑された者もいる。修道院で生涯を過ごした者や、在俗の神秘家もいる。中世思想原典集成のシリーズ中、紅一点である本書に特徴的なのは、神への恋愛にも似た運命的な情熱だと言えようか。法悦とともに降臨するヴィジョンは、時にすさまじいイマジネーションの奔流となる。「(ミサのさなかに)私は霊に引き込まれて忘我状態になった。そこで私は、大きく広く、高く、完徳で飾られた町を見た。町の中央には、たえず開き、秘密のうちに再び閉じる円盤があり、その上に誰かが腰かけていた。その人はじっと静かに坐っていたが、円盤の内部では、神が想像を絶する速さで回転し続けていた」。これは13世紀を生きた、アントワープ出身のハデウェイヒによる幻視のほんの一部分である。彼女たちの召命譚は今も生々しい。
※『中世思想原典集成』既刊書は→こちら
人文・社会・ノンフィクションレジ前コーナー5月13日分より
(小林浩/人文書コーディネーター・「本」のメルマガ編集同人)

テロル機械
2002/06/10 12:10
スピード感あふれる分析、テロリズムの政治解剖学原論
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
フランス五月革命(1968年)世代の中でも、マオイズム(毛沢東主義)系の過激派「プロレタリア左派」の活動家だったローラン・ディスポ(1950-)のことを知っている日本人はほとんど皆無だろう。しかし、知名度を問うことは、1978年に若干28歳の若さで彼が上梓した本書の場合、全く問題にならない。テロリズムとは何かをフランス革命時の恐怖政治にまで遡りながら分析し、小気味良いリズムで「いかにテロル機械に抗するか」を明敏に示していく本書のような好著をシリーズ(エートル叢書)に加えた、編者(鈴木創士氏)および版元の判断は賞讃されるべきである。訳者の苦労と熱意の賜物でもあろうが、本書を貫くテンションの高さは特筆に値する。けっして一息に読み越せる本ではないけれど、ディスポの語り口には読者を引きずり込むバイタリティがある。彼はテロリズムを定義する指標として49もの特徴を掲げて、例えば次のように指摘する、「(1)「国家のテロリズム」という言い方は同語反復である。(2)あらゆる国家にとって恐怖政治はその起源となっており、さらにはその支柱となっている。…中略…(11)権力のテロリストは「完全犯罪」を行う。…中略…(14)誰もがふたつのテロリズムを目の前にしている。すなわち、国家というテロリズムと、それに対抗するテロリズムである。そして互いに相手を犯罪として、つまり非人間的なものとして示そうとする。そして自分たちの側を信じるテロリストにとっては、テロリズムはヒューマニズムなのである」等々。本書はいわゆる「テロリズム史」というよりは、歴史を自由に行き来しつつ、テロルの政治力学がどのように生成し、発現するのか、人間の肉体で言えばいわばその神経中枢における系統的働きを巧みに解明した論考である。時代が移り変わり、外見が変わろうと、テロルの神経的メカニズムは変わらない。新たなテロの脅威の時代と言われるこんにちにおいてもなお、多くの示唆を与えてくれる本である。
※たくさんあります、テロリズム研究→こちら
※エッジの利いた注目作がそろう〈エートル叢書〉既刊は→こちら
人文・社会・ノンフィクションレジ前コーナー6月10日分より
(小林浩/人文書コーディネーター・「本」のメルマガ編集同人)

エリック・ホッファー自伝 構想された真実
2002/06/10 12:09
生誕100年で日本でもリバイバルの予感。感動的な自伝がついに完訳
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
アメリカ西海岸の港湾労働者にして社会哲学者のエリック・ホッファー(1902-1983)の著書は、1960年代から1970年代初頭にかけて立て続けに6点ほど邦訳されてきたのだが、残念なことにすべてが絶版か品切になっている。いわば忘れられた思想家だったわけだが、今回邦訳された彼の自伝をきっかけに、その価値が見直されるのではないか。原書は1983年刊、彼の最後の著書となる本書では、ニューヨークのドイツ系移民の子として生まれた彼の生涯が、一幅の鮮やかな印象画として描かれている。幼い頃の失明、そして視力の突然の快復、教育を受けないまま育ちながら無類の読書好きで、日雇い(あるいは季節)労働者として過ごした日々が率直に綴られている。それらは職業的哲学者が綴るような思索日誌の堅苦しさとは似ても似つかない。彼は生き、働き、感じ、考える。その素朴さが実に好印象だ。本書は詳細に記述されている自伝ではない。原題にあるとおり、これは "Truth Imagined" つまり、思いに映るままの本当のこと、といったニュアンスだろうか。作家の中上健次は「ホッファーのように生きつづけたい」と漏らしたことがあるそうだ。彼の生涯は、世間で言うところの「幸福」なものとは少し違う。経済的に満ち足りていたわけではない。しかしその大きな体躯からにじみ出るようなおおらかなオーラと同居している繊細さを見るとき、彼のように生きてみることをつい想像してみたくなることも確かだ。彼は本書で自分のことばかりを語っているのではなかった。あたかも紡ぎ合わされた一枚のタペストリーのように、ホッファーの思い出の中で様々な人々が垣間見せる素顔は、彼自身の素顔と重なって、なんともいえない印象的な彩りを帯びる。たぶん多くの読者にとっても、本書は長く胸に残る一冊となるだろう。巻末にシーラ・ジョンソンによる、ホッファー72歳の折のインタビューが収録されている。
人文・社会・ノンフィクションレジ前コーナー6月10日分より
(小林浩/人文書コーディネーター・「本」のメルマガ編集同人)

水戸光圀語録 生きつづける合理的精神
2002/06/10 12:08
「黄門様」の智慧と歴史観が見えてくる明解な「語録」
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
徳川光圀(1628-1700)と言えば、諸国漫遊の勧善懲悪ドラマ「水戸黄門」があまりにも有名だが、本当の彼はどんな人物だったのか。本書は『水戸義公全集』(角川書店、品切)や『水戸義公伝記逸話集』(吉川弘文館、品切)などの資料にあたり、光圀自身の言葉や、彼自身のものとして伝えられる言葉を、7つのテーマのもと77項目にまとめて、「黄門様」の実像に迫ったコンパクトな新書である。7つのテーマとは、「人の生き方について」「仕事の心得について」「為政者〈リーダー〉について」「人の使い方について」「人の育て方について」「悪しき習慣について」「歴史について」であり、それぞれが章題となっている。もっとも印象深いのは、最終章「歴史について」だ。日本初の本格的通史と言われる『大日本史』の編纂を指揮した彼は、一大名、一政治家としての枠に囚われず、日本の歴史を客観視しようとする。権力者寄りの史観に媚びることなく、記紀神話を史実とは異なるものととらえたり、南朝を正統と見なすなど、いくつかの決定的側面において、彼の判断は非常に冷静だった。また、門外不出の公家資料を精力的に収集し、保存・公開に努めるなど、一歴史家としても手腕を発揮する。本書の著者もそうした姿勢に着目して、彼の思想が後世に言われるような「尊王思想」とは別の次元にあることを指摘する。77の短い引用(読み下し文)に、それぞれ懇切で簡明な解説が付されており、暗記しておきたい決まり文句も多数。テレビドラマを見ている人も見ていない人も、本書に示された光圀の素顔を十分に楽しめるだろう。
※色々あります、「水戸黄門」本→こちら
人文・社会・ノンフィクションレジ前コーナー6月10日分より
(小林浩/人文書コーディネーター・「本」のメルマガ編集同人)

エリアーデ・オカルト事典
2002/06/10 11:35
世界的宗教学者たちの36編の小論文を収めた贅沢な「読む事典」
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
ルーマニア生まれの偉大な宗教学者エリアーデによる金字塔といえば、晩年作『世界宗教史』(全4巻。ちくま学芸文庫では全8分冊で刊行)が有名だが、彼の編纂による『宗教百科辞典』(全16巻、マクミラン社、未訳)もまた有名である。本書はその百科辞典からオカルティズムにかんする36項目を選んで一冊にまとめたもの。原題は「隠された真理:魔術、錬金術、オカルト」。オカルトとはもともとラテン語で、「隠れたもの」を意味し、現代的ないわゆる「超常現象」とはいささか趣を異にする。「真理」を意味するギリシア語「アレーテイア」が「覆いを取られたもの」という原義を有することを踏まえると、本書の原題は、オカルトとは「隠れたままの真理」を意味する、ということを示しているわけである。エリアーデをはじめ、K・ルドルフやJ・B・ラッセルら31名の碩学が、「オカルティズム」、「呪術・魔術」、「道具・技法・霊力」、「錬金術」の四部に振り分けられた項目ごとに、古今東西にわたる豊富な知識と整理された議論を開陳する。事典なのに36項目しかないのかと思われるかもしれないが、それぞれを小論文として独立させている「大項目主義」が、本書の特徴。引く事典ではなく、読む事典なのだ。たとえば「呪文」の項目は、呪文の条件、音声とことばの力、宗教史における呪文という三つの節に分かれ、第三節目はさらに、エジプト、メソポタミア、ギリシア、中世ヨーロッパ、スーダン、インド、中国、メソアメリカ、現代の呪文、といった記述に細分化される。各項目ごとに文献ガイドも充実しており、なるほどエリアーデの名を冠するだけはある。
※関連書目→ナタフ『オカルティズム事典』、レヴィ『魔術の歴史』
人文・社会・ノンフィクションレジ前コーナー5月13日分より
(小林浩/人文書コーディネーター・「本」のメルマガ編集同人)

東洋文庫ガイドブック
2002/06/04 17:34
迷宮のように林立する、名著700巻へのナヴィゲーター
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
まずは巻頭に掲げられた、東洋文庫編集部による「はじめに」の一節から。「少数派の人々による「古典の宝庫」という評価とそれに見合った権高なラインナップ、奇特な本屋さんの奥深くの棚に潜むという棲息状況、「文庫」のくせに高定価という名称の語義矛盾、箱入り布クロス金箔押し角背のいかめしい外見、購読することはおろか、なまなかな読者には手にとってみることが、あるいは一生のうち一度でも目にすることすらむずかしい……、とまでささやかれてきた叢書・平凡社東洋文庫が、1963年の創刊以来、700巻を超えました」。いやはや、これは自虐などではない。日本の出版界で無二の偉業を地道に成し遂げてきた幸運を如実に語っている言葉である。本書は12人の識者による12通りの切り口で東洋文庫を再紹介したブックガイドだ。さすがに既刊をすべて所有している読者はめったにいないだろうし、どんな書目があるのかもよくは知られていないだろう。巻末の解説目録とあわせて通覧すると、なるほど実に豊穣な一大集成であり、雄大にそびえる高峰をふいに間近に見るが如き、ゾクリとさせる感動がある。幼い頃、絵本で読んだ記憶がかすかにある民話の原典、学生の頃、歴史の教科書でしか見たことのない高名な書目、いままでまったく聞いたこともないような未知なる書物、呪文のような書名だけれど魅力的な名著、奇書のオンパレード。12の「探検」をひもときながら、気になるタイトルにチェックを入れてみよう。そして思い切ってたとえば5点、まとめ買いしてみるといい。それぞれが高価な本だから、高尚なギャンブルになるだろう。はてさてどんな本なのやら、スリル満点の読書へと誘ってくれる必携のガイドだ。
※「東洋文庫」既刊書より→こちら
人文・社会・ノンフィクションレジ前コーナー5月7日分より
(小林浩/人文書コーディネーター・「本」のメルマガ編集同人)

とびきり可笑しなアイルランド百科
2002/06/04 17:31
硬派の論客がユーモアたっぷりにアイルランドの素顔を描く
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
「とびきり」シリーズ第5弾は、イギリスを代表するマルクス主義批評の論客の登場だ。イーグルトンである。1999年に刊行された原書のタイトルは「アイルランド人の真実」。いくらなんでも書き手は硬派の看板だし、これまで『表象のアイルランド』や『聖人と学者の国』など、すぐれたアイルランド文化論を書いてきた先例があるのだから、今回の邦題は行き過ぎなのでは、と眉をひそめる向きもあるかもしれない。しかし、実際本書を手にとって見れば、いかにイーグルトンがユーモアたっぷりの毒舌で、美化された観光用の「アイルランド像」ではなく、原タイトルにある通りのありのままの「真実」を描写しているかが、すぐにわかるだろう。事典風にAからZまでの96の項目で、アイルランドの文化、習俗、政治、著名人について、時に愛情を込め、時にはまさにおもしろ「可笑し」く、親しみやすく論評している。難解な彼の他の研究書に比べても、存分に楽しめる出来だ。二、三の例を挙げるとこんな感じ——「神(God)」の項目では、「アイルランドでは驚くほど人気のある存在で、ロック・グループのU2のリード・シンガーであるボノの次の地位にある」と来る。作家の「ジョイス(Joyce)」は「アイルランドの主産業のひとつで、Tシャツ、夏季留学、パブのはしご、種々のがらくたなどと並ぶものである」と容赦ない。「北アイルランド(Nothern Ireland)」では、「アイルランドでもっとも熱いジャガイモ。北アイルランドと呼ぶだけでも、論争が巻き起こる」。いわゆる『悪魔の辞典』風なブラック・ユーモアに終始するわけではなく、イーグルトンらしい鋭い筆致で、文化政治学の機知をたっぷり盛り込んである。どこから読んでも自由だが、A(アルコール)からZ(ダブリン動物園)までの巧妙な筋立てを追うのもいい。外人向けに書かれてあるので、旅行者の気晴らしにも役立つに違いない。
※「アイルランド」を読む→こちら
人文・社会・ノンフィクションレジ前コーナー5月7日分より
(小林浩/人文書コーディネーター・「本」のメルマガ編集同人)

時の輪 古代メキシコのシャーマンたちの生と死と宇宙への思索
2002/06/04 17:29
古代メキシコのシャーマンから継承された「別の知の体系」の真髄
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
最晩年に著者が自らまとめた、メキシコのヤキ族の呪術師ドン・ファン・マトゥスの語録である。彼が世に問うた8冊の著書(『呪術師と私』から『沈黙の力』まで)のエッセンスだ。まずなにより、組版を含めて造本が素晴らしく美しい。装丁を担当した竹智淳氏は本書のエッジを際立たせることに成功している。その特異性とは何か。それは、本書がドン・ファンについて書かれたことを再録したものなのではなく、ドン・ファン自身の言葉のみを抜き出したという点であり、「売られている本」というよりは、まるで読者一人一人への「贈り物」のようなたたずまいである。一頁ずつに象嵌された短いセンテンスと空白が、読む者の胸の内で不思議な空間をつくり始める。ドン・ファンは語る。世の中のしくみについて人々が自身に言い聞かせているあれこれの思い込みが、彼ら自身を日々の暮らしに縛りつけている。大切なのはそうした思い込みを棄てることだ、と。人間はその思い込みの通りに生きてしまうものだが、それは生のひとつの形象に過ぎない。シャーマンはそうしたひとつひとつにはこだわらず、生の全体像を見て、そこからあらゆる可能性を引き出すのだ。その全体像が「時の輪」と呼ばれるものである。8冊の著書が8つの章になり、それぞれに注解が付される。心の片隅に、「常識」に縛られない空間をつくるために、手元に置きたい一冊だ。
※カスタネダの最後の本と最近の研究書→『無限の本質』、島田裕巳『カルロス・カスタネダ』
人文・社会・ノンフィクションレジ前コーナー4月22日分より
(小林浩/人文書コーディネーター・「本」のメルマガ編集同人)

情報学の基礎 諸科学を再統合する学としての哲学
2002/06/04 17:24
従来の情報工学を超え諸学問を横断する、哲学の野心的な試み
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
「情報」という概念は、いわゆるIT(情報技術)などの枠に収まらない広がりがある。著者は、物質・生命・精神・社会とかかわりあう、秩序としての情報という概念を切り口に、学問全体を問い直し、その体系の再編と諸科学の再統合を、本書で企図している。前著『モナドロジーの美学』(1999年)での考察をさらに推し進めたもので、もともとは、著者が奉職する名古屋大学で情報文化学部が設置されたおりに開始された「知的生産論」講義とその発展形態である「社会情報学基礎論」講義のために準備した草案が土台となっている。目次は以下の通り。第一章「情報学という学問」、第二章「個別諸科学に即した科学の問い直し」、第三章「人間による創造と情報学」、第四章「情報学のモデル構築とその具体的展開のためのヒント」、第五章「テクストの未来」。アランの『諸芸術の体系』(岩波書店、絶版)の「散文論」からインスピレーションを受けたという著者は、古代から現代にいたる幅広い哲学的潮流を参照しつつ、暗黙知やKJ法、TRONプロジェクトや編集工学といった諸領域をも、本書の問題系の中軸に大胆に取り込んでいく。「人間を立て直し、解明し、再建する」(アラン)ためのひとつの方策としての情報学の未来を展望する、学際的挑戦の端緒が開かれる。
人文・社会・ノンフィクションレジ前コーナー4月22日分より
(小林浩/人文書コーディネーター・「本」のメルマガ編集同人)

論理学
2002/06/04 17:22
思考がたどる存在そのものの必然的道筋としての「論理」
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
ここ十年(1990年以後)で、ヘーゲルの著書の邦訳書は新訳のほか、再刊や復刊を含めると30点近く刊行されている(上下巻のものは1点と数える)。その数は他の哲学者の古典と比べても群を抜く多さであるが、特にヘーゲル新訳について、根気強くコンスタントに訳書を公刊しつづけてきたのが長谷川宏氏だ。本書はヘーゲルの哲学体系の根幹をなす書であり、通例『エンツュクロペディー』として知られてきたが、長谷川氏は『哲学の集大成・要綱』と訳している。ヘーゲルの意を汲んだ柔軟な翻訳は、氏が広く評価さていれる所以だ。今回邦訳されたのは、『哲学の集大成・要綱』の第一部「論理学」。ヘーゲルによれば、哲学とは概念的な思考活動の円環をなす体系であり、三つの理念にしたがってに次のように立て分けられる。すなわち「絶対的な理念の学としての論理学」「疎外された理念の学としての自然哲学」「疎外の状態を脱して自分へと還ってきた理念の学としての精神哲学」である。本書のあとには第二部「自然哲学」と第三部「精神哲学」が邦訳刊行される予定だ。論理学はさらに、思考という抽象的な場で展開する理念の学として説明され、そうした「純粋思考」を駆使する実力と熟練を要するので、「もっとも難しい学問」であるとされる。「現実的なものは理性的である」という有名な言葉は本書にある。本文には注解と口頭説明が組み込まれ、ヘーゲル独特の「論理」観が丁寧に示されている。彼の哲学体系の出発点は本書にある。
※ヘーゲルの著書およびヘーゲル研究書は→こちら
人文・社会・ノンフィクションレジ前コーナー4月22日分より
(小林浩/人文書コーディネーター・「本」のメルマガ編集同人)

暮らしの哲学 気楽にできる101の方法
2002/05/20 19:22
特別な知識の中にではなく、日常的実践の中に哲学がある
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
長年「ル・モンド」紙に定期的に寄稿している、すぐれた批評家としても著名な現代フランスの哲学者が書いた、「日常生活の中でできる簡単な哲学実践法」101例の指南書である。哲学入門書や自称「哲学」本はあまたあるが、本書のエスプリは一味違う。「寝ころんで星空を眺める」「録音した自分の声を聞く」「ひざまずいて電話帳を音読する」——すると、どうなるか? ありふれた毎日をあらためて見直し、聞き直し、触れ直すきっかけとなるヒントが本書にはぎっしり詰まっている。哲学とは古ぼけた注釈なのではなく、生きる日々の時の流れのうちに見出されるものなのだ。それをさりげなく、けっして高飛車にならず、「こんな発見ができるかもよ」と教えてくれる。感心したり、同意したり、笑いが止まらなかったりだ。それぞれに短めの解説的なエッセイが付されているほか、所要時間、用意するもの、効果、といったポイントも添えられている。例えば46番「森を散歩する」は「所要時間:2、3時間数分。用意するもの:森。効果:魂が裏返る」とある。なぜ裏返るかというと……それは解説を読んでのお楽しみ。本書を読んでふと気づかされるのは、哲学というのは自発的な行動から生まれてくるのだな、ということ。自発的な行動が思いがけない結果をもたらすことも確かにあるけれども、日常に押し流されて自分なりに「世界の意味」を実感することを見失っている現代人には、こうした自発性こそ、真新しい発見になるのではなかろうか。易しく書かれている本だが、これは自分が感受性を持っているかどうか、そして感じたものを通じて自分で考えることのできる一人前の大人であるかどうかを確認できる本でもある。
※ドロワの論考やインタビューが読める→『ミシェル・フーコー思考集成(V)』、『ヒト・クローン 未来への対話』
※近刊:ドロワの主著『虚無の信仰:西欧はなぜ仏教を怖れたか』
人文・社会・ノンフィクションレジ前コーナー5月7日分より
(小林浩/人文書コーディネーター・「本」のメルマガ編集同人)


