山田 正和さんのレビュー一覧
投稿者:山田 正和
紙の本

紙の本医療ソーシャルワーカーの仕事 現場からの提言
2000/12/28 12:17
医療・保健・福祉分野の大変革の中で転換期を迎えた医療ソーシャルワーカーの存在意義を新人向けに解説
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
医療・保健・福祉分野の大改革により,医療ソーシャルワーカー(以下,ワーカーと略)は,いま大きな転換を迫られていると言っていいだろう。介護支援専門員(ケアマネジャー)などの新たな職種も出現。ワーカーの業務内容や役割にも変化が生じ,その存在意義を問い直す必要がある。
本書はこうした現状を踏まえ,特に新人ワーカーやその指導・養成にあたる先輩ワーカーを対象にまとめられたハンドブックである。
ワーカーとして知っておくべき医療法や医学知識の概要説明にはじまり,クライアントと接する際の基本的なマナーや面接の仕方,さらにはクライアントと良好な関係を築くためにはどうすべきかといったことを,順を追って解説している。
全体的に平易な言葉でつづられてはいるが,やや理想論に傾きすぎているきらいがないではない。編著者は本書の中で,「実現までに困難があるからこそ,理想を追い求める姿勢が大切ではないか」とし,そこにワーカーとしての成長があるのではないかと説いている。ワーカーも含めた病院などの医療機関全体が「クライアント第一主義」の姿勢を貫いているかどうかも,ワーカーが能力を発揮していくうえでは大切ではないかという気がする。
ただ,全編を通じてワーカーというよりもまず,常識ある社会人としての姿勢を持つことを強く訴えている点や,クライアントに関する多くの情報収集を行うためには,行政や病院などの社会資源を有効に活用するという姿勢がワーカーには求められているなど,細部にわたってていねいなアドバイスが盛り込まれているのはありがたいことで,現場経験の豊富な編著者らの創意工夫が感じ取れる。
馴れ合いとは異なる,ワーカーにしかできない仕事も現場には多いはずであり,それが何かを学ぶうえでも参考になるだろう。
(C) ブッククレビュー社 2000
紙の本
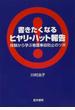
紙の本書きたくなるヒヤリ・ハット報告 体験から学ぶ看護事故防止のツボ
2000/12/28 12:17
重大な医療ミスにつながる可能性のある事例からいかに学び,看護現場に生かすべきかを解説
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
「また,医療ミスです」——こんな言葉で始まるニュースを見聞することが非常に多くなった。しかし医療ミスは決して,「また,起きた」で許されるものではない。ミスが繰り返し起こるのは,かつて起きたミスをはじめ,危うく大きな医療ミスにつながりそうだったという事例がきちんと生かされていないからではないだろうか。
本書はまさに,この危うく大きな医療ミスにつながりそうな「ヒヤッとした」ことや「ハッとした」から,看護上での事故をいかに防止するかをまとめたものである。「大きな事故につながらなかったからよかった」ですませることや,ミスにつながりかけたことを隠すことが現実にはまかりとおっているようだが,そうではなくて「ヒヤリ・ハット事例」をいかにしてスタッフ全体の教訓として活用すべきかなどについて,個々の事例も盛り込みながら解説されているのが特徴だ。
(C) ブッククレビュー社 2000
紙の本

紙の本ビジネスマンのための実践男の介護
2001/05/07 18:17
「男」が介護についてどう考え,何ができるかを実母の介護を経験した著者がわかりやすく提言する
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
この本は,国際政治学者の著者が実母の介護体験を夕刊紙に連載したのをまとめたもの。介護への意識は人によって千差万別。介護保険制度が発足して,2001年前半現在2年目を迎えたが,「介護保険というのがよくわからない」という声も多い。また「介護は女性がするもの」といった風潮も今だ払拭されておらず,「介護」を自分の問題として認識していない傾向が,特に男性に目立つのが現状だろう。
著者も,実母の介護問題が自分の身にふりかかってきて初めて,その重要さに気づいたことを強調している。実体験に基づいてのアドバイスなので,それなりの説得力がある。本書は,NPO(非営利組織)の代表をはじめ,厚生労働省幹部や元首相とも対談,介護保険や介護について,あるべき姿や公的支援などの問題を浮き彫りにしているが,タイトルにある「男の介護」という視点に立ち,「介護の問題」に男性がどう関わっていくべきかなどを,もっと具体的に提示してほしかった気がする。
(C) ブックレビュー社 2000-2001
紙の本

紙の本力強い上司になる「輝く秘訣54」 リーダーは自己を鍛え、実力を磨き、陣頭指揮する存在である!
2001/04/17 18:18
求められる「真のリーダー」になるために身に付けておくべき条件を余すところなく伝授
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
大手企業の社長交代があると,新社長の人物紹介記事が新聞に載るが,その中で「社内の評価は“バランス感覚のとれた人”というものだ」といったような一文を多く見かける。しかし,「バランス感覚を持った人」という位置付けは,曖昧といえばこれほど曖昧なものもない。どういう人物が「バランス感覚のある人」といえるのかは,人によって解釈が異なるからだが,評者の解釈は「リーダーとして人の上に立つ能力をまんべんなく身に付けた人」ということになる。
本書は,人材・組織の活性化や後継者の育成の問題などに触れながら,評者が解釈し思い浮かべるようなリーダーになるために身に付けておくべき秘訣をまとめたものである。著者が提言する1つひとつの秘訣は,ごく当たり前のことばかりで格別に目新しさはないのだが,社員教育研修に長年携わってきた著者ならではのエッセンスがそこにプラスされているので,それなりに説得力はある。
(C) ブックレビュー社 2000-2001
紙の本

紙の本個性を生かす支援ツール 知的障害のバリアフリーへの挑戦
2001/03/30 15:16
知的障害児が自立し,「生きる力」を得るための支援とはどうあるべきかを具体的に提示する
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
本書のタイトルにある「バリアフリー」という言葉は,視覚・聴覚障害者や高齢者を含めた肢体が不自由な人たちに向けて開発された製品や空間を指すものとして使われることが一般的だが,本書で扱っているのはそういった類のハード的なことではない。
その内容は,知的障害を持った子供たちの自立観に基づきながらも,彼ら彼女らが自主的・自立的に生きる力をいかに育むかという課題に焦点を当て,日常生活に生かされて「生きる力」となるための「支援の在り方」を具体的に紹介しているものである。
たとえば,問題行動をとった場合でも,それを単に叱るのではなく「望ましい行動をほめながら指導する」という本書に出てくる提言などは,必ずしも知的障害児の教育に限ったことではないもの。いまの日本の児童教育全般で再検討すべきものではないかと思わせるような提言も多く含まれており,その意味でも参考になる1冊といえよう。
(C) ブックレビュー社 2000-2001
紙の本

紙の本思春期の危機を生きる子どもたち
2001/03/08 15:16
少年犯罪の続発など,子どもたちに起きている大きな変化を検証し,大人はどう向き合うべきかを提言
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
もう旧聞に属するのかもしれないが,今年の年明け早々,各地の成人式が大荒れに荒れたというニュースを毎日のように読んだり,見たりしながら,「成人として最低限の常識もない連中は罰すればいいのだ」という怒りを抱いていたのが正直なところである。実は,近年相次いでいる少年犯罪や学級崩壊といった問題に対しても,これと同様の気持ちで傍観していたと言ってもいい。
しかし,その一方で深く心に刺さっていたのが,卒業を間近に控えながらも就職が決まらないというある女子高校生が口にした「何か社会から,自分は必要とされていないんだなって思えて,すごく悲しい」という言葉だ。
つまり,「自分たちのときはこうであったのだから」の一言で切り捨ててよいのかどうかということであり,実は本書の著者もそうした思いを散りばめながら,検証すべき課題について筆を進めている。
全体を通じて,少年少女の生き方や考えに大人の側が理解を示し,それを支援するような形が望ましいと著者は説くが,子どもたちの考え方,生き方をサポートするという「精神的な余裕」すら大人社会に欠けてきているのが実情であり,そこについての言及が乏しいのは残念なことである。
子どもたちの生き方,考え方に大人が目を向けるためには,社会なり,企業なりがそういう大人をサポートする仕組みになっていないと,個々人の力では限界があるのではないだろうか。また,現在の十代,二十代の若者の親に当たる世代がどういう思春期,青年期を送ったかにも,家庭教育のあり方などは左右されると思うのだが,そのあたりの分析も全体的に乏しい印象を受ける。
AかBかという二者択一方式で結論を記さずに,ならばどうすべきかという提案をしているだけに,ここで指摘しておいたような部分についてもカバーしてもらいたかったという気がする。
(C) ブックレビュー社 2000-2001
紙の本
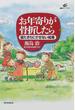
紙の本お年寄りが骨折したら 寝たきりにさせない知恵
2000/12/28 12:18
急増する高齢者の骨折を解説し,その治療法と予防についても紹介
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
「介護保険では,寝たきりにさせないようにするにはどうすべきかという理念が欠けている」。取材でよく会う,ある介護会社の社長の言葉である。最近では厚生省でもそのことに気づいたのか,「介護予防」といった寝たきりの人を増やさないようにするための施策についても力を入れるように,地方自治体にも呼びかけ始めている。
高齢者が寝たきりになる原因としては,骨折によるものが多い。しかし,本書の著者は「骨折=寝たきりではない」との考えに立ち,骨折の種類やその治療法をはじめ,骨折しないためにはどうしたらよいかをイラストや各種データもふんだんに交え,わかりやすくまとめており,勇気づけられる。
また,よい介護会社の選び方や住宅改修など,介護保険サービスの利用に関する説明も盛り込まれており,いざというときに備えて,基礎的な知識を把握しておくうえで参考になろう。
(C) ブッククレビュー社 2000
紙の本

紙の本21世紀を勝ち抜く病医院の経営ノウハウ
2000/12/28 12:15
21世紀に選ばれる病医院になるための具体的な技法・対策を満載
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
「病院関係者には院長も含め,経営にうとい人が多い」。以前,病院関係者からこんなことを聞いて意外に思ったことがあったが,その後取材をしてみると「なるほど」と納得させられるケースもいくつも見聞できた。
しかし,よく考えてみれば,病医院経営も企業経営同様に,「販売管理」や「財務管理」抜きには考えられないし,これからは「医療の効率化」といった高度な経営管理能力も求められる時代になっていくのは間違いない。
本書では「経営管理編」「財務管理編」「税務管理編」の三部にわたり,病医院が生き残るためにはどうすべきかをはじめ,節税の考え方などの問題をQ&A方式で解説しており,内容も比較的理解しやすくまとめられている。その意味では病医院関係者はもちろんのこと,企業経営も含めた幅広い意味での「経営」全般に関心ある人々にとっても一読して無駄にはならない一冊といえよう。
(C) ブッククレビュー社 2000
紙の本

紙の本介護老人保健施設サービス評価マニュアル 新版
2000/12/26 15:31
介護老人保健施設がサービス評価を自ら行うためのポイント、視点を示す
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
高齢者の寝たきり予防のリハビリに重点を置く老人保健施設は,介護保険制度では「介護老人保健施設」と名称が変わった。平成12年6月時点で,同施設は全国に2500カ所を数えるまでになっており,今後も高齢者ケアにおいて重要な役割を果たしていくことが求められていることに変わりはないだろう。
本書は同施設に求められる役割や機能,サービスのあり方などを検討するための一助となるもので,例えば食事,入浴,プライバシーの保護などの評価項目ごとに,各施設で自己評価を行う際に,どういう点に着目すべきかを盛り込んでいる。
同施設をはじめ,高齢者施設をめぐっては第三者評価の導入も始まっており,施設自らも「選ばれる施設」になるための努力を怠れば,存続の危機に直結しかねない。本書のチェック項目をクリアするのは生き残りの最低条件と言ってもよかろう。
(C) ブッククレビュー社 2000
紙の本

紙の本医者からもらった薬 2001年版
2000/12/06 15:15
薬について知っておきたいこと,知っておかなければならない情報を網羅したガイドブック
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
信じられないような医療ミスが相次いでいる。現在,明るみになっているものは手術ミスが多いが,では我々が病院からもらう薬は大丈夫なのだろうか。思うに我々は,「病院が出してくれたのだから」と疑いもせず,それを飲んでいるが,薬の成分がどういうものかや自分の病気治療にとって,なぜその薬が必要なのかといったことについて,もう少し各人が関心を持つべきではないだろうか。
本書では薬について知っておきたい基礎的な情報はもちろん,薬が入った包装容器に記された記号などからも,どういう薬かを調べることができるように解説している。また,主要な薬についてはカラー写真によるインデックスを載せており,「調べやすく見やすく」工夫されている点も感じ取ることができる。我々も病院で聞いた薬についての説明に満足せず,本書などを片手に自らの目で再確認してみるという姿勢を持ちたいものだ。
(C) ブッククレビュー社 2000
紙の本

紙の本介護サービス便利帳 首都圏版 今すぐ使える情報リスト8000件
2000/12/06 15:15
介護保険の基礎情報を網羅したほか,介護サービスの選択にも役立つ手軽なガイドブック
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
介護保険制度の導入で何が変わったのかといえば,すでに多くの識者が書籍や新聞紙上などでも答えているように,利用者である国民が保険料を納めるかわりに,自分たちで介護サービスを選択できるようになったことだ。
たとえば,ホームヘルパーを頼みたいと思えば,自分でどこの会社のヘルパーに来てほしいかを選べるわけだ。しかし,いざ会社を選ぼうと思ったり,家族の介護で困ったときにどこに相談に行けばよいかといったことなどについては,まだまだ多くの人が頭を悩ましていることを耳にする。
こうした人たちにとって,手軽なお助け本とでもいえるのが本書だ。首都圏の情報しか網羅していないうえ,掲載されているケアセンターの中にすでに統廃合されている所もあるため,細部に改善すべき点はあるが,介護サービスを利用したいという人が手元に置いて参考にするうえでは便利な一冊であるといえよう。
(C) ブッククレビュー社 2000
紙の本

紙の本生き残るための調剤薬局経営 薬価差0時代の課題と戦略
2000/11/01 12:16
急速に進む医薬分業の流れの中で,調剤薬局はいかにして生き残るべきかを解説する
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
日本では医薬分業が他国よりも遅れている。逆に言えば,医薬分業がグローバル・スタンダードとされているわけだ。グローバル・スタンダードが必ずしもよいとは言えないが,それはともかくとして,こうした状況になっている原因は,日本では医師が調剤を行ってきたことにあると,本書は指摘する。
しかし,医療制度の改革や介護保険制度の導入により,医療・調剤業界にも競争や変化が求められる時代になってきたいま,調剤薬局も病院の単なる「門前薬局」からの脱却を迫られているのは間違いない。本書では今後のあるべき調剤薬局の姿について提言する。
「薬剤師は医師の顔色を見るのではなく,患者のほうをもっと向くべきである」といった辛口の指摘も盛り込まれているが,医療ミスなどにより,医師や医薬業界への不信感は高まっている中だけに,調剤薬局の薬剤師諸氏には是非とも噛みしめながら一読してもらいたい。
(C) ブッククレビュー社 2000
紙の本

紙の本舛添要一の40代は老後の分かれ道 いまから年金・介護・お金・健康を考える
2000/11/01 12:16
老後がやってくるまでの20年間に考え,準備しておくべき課題をわかりやすく解説する
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
TVの討論番組の論客として,また,最近は実母の介護経験をもとに社会保障分野に対する提言でも知られる著者だが,今回の著書は40代になったばかりの人にはショッキングに思えるかもしれないタイトルだ。しかし,ページをめくると,40代はもちろん,それ以前の世代も少しずつでも知識を持っておいたほうがよさそうなテーマも多い。
介護保険や有料老人ホーム,あるいは年金や健康保険,退職金など,どれも人生に大きくかかわる問題だが,普段から自分なりに勉強したり考えたりしている人が少ないテーマについて,読みやすい表現でまとめているのが嬉しいところだ。まずは関心ある項目から読み始めてみるだけでも,社会保障問題が少しは身近なものに感じられてくるのではないだろうか。政府や政治家の政争の道具にされたり,党利党略で決められていいはずがない問題であることにも気づくことになるはずである。
(C) ブッククレビュー社 2000
紙の本

紙の本医療専門家のためのコミュニケーション技術
2000/10/20 21:15
豊富な実例を示しながら,医療専門家に求められるコミュニケーション技術の向上をサポートする
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
連日のように新聞やテレビで,医療ミスのニュースを見かけるようになった。正直なところ,「またか」という思いにとらわれることも多いが,病院や医師,看護婦への不信感が国民の間で高まっていくのは好ましいことではない。
医療ミスまでいかなくても,患者の疑問に答えたり,どういうことで患者が悩んでいるのかを聞き出す能力が乏しいと感じさせる医師や看護婦が多いのも気になる。高圧的とも思える態度で接したり,あからさまに「自分たちの言うことを黙って聞いていればよいのだ」という姿勢を見せる医療専門家に不愉快な思いをした人も,結構いるのではないだろうか。こうした状況の中で,医療専門家もコミュニケーション技術を身につけることがますます重要になってきているのは確かだろう。
医療専門家のためのコミュニケーションの実用書として出版された本書は,患者と医療専門家のコミュニケーションの実例とその効果を豊富に盛り込むことで,重要なコミュニケーション技術の使い方を例示している。まず,「効果的なコミュニケーションを図れることがあらゆる患者ケアの基本」と冒頭でうたい,「アセスメント面接の準備」「患者本位のアセスメント面接」「悪い知らせを伝える」などの具体的なテーマに分けて例示しているほか,各章のまとめの後には「応用問題」を出しており,理解を深めるのに役立つ。
まとめの中でも触れているように,著者はコミュニケーション技術で重要なのは,医療専門家は自分の価値を押し付けるのではなく,「あるがままに受け入れる」という姿勢を貫くことであると説いている。また,問題を解決するということよりも,問題点を明らかにすることが「コミュニケーションの目的」であるとも述べている。手術のレベルや薬の進歩以上に,コミュニケーション技術のレベルアップが医療関係者に求められる時代なのである。
(C) ブッククレビュー社 2000
紙の本

紙の本比較福祉論
2000/07/22 06:15
データにとらわれない斬新な比較の方法を追求,「福祉」とは何かをあらためて問い直す
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
「社会保障」や「社会福祉」というと,いや応なく「こうあるべきだ」とか,「正義」といったモノサシでとらえられがちなうえ,制度そのものを詳しく知っていることが研究と同義に見なされていることが多い。こうした考え方は果たして正しいのだろうかとの疑問に立ち,早稲田大学社会科学部教授の著者はデータにとらわれない斬新な方法論を展開,求められている「福祉」とは何かを検証したのが本書といえる。
各章ごとに「問題発見」,「方法論」,「具体的な試み」の3段階で問題に迫り,読者自身が比較の方法を追求し,問題意識を持つことができるように編集されたテキストだが,全編を通じて著者独特の発想や視点に慣れるまで,やや時間を要するかもしれない。ただ,「こうあるべきだ」論にとらわれがちな「福祉」について,新たな視点を持って考え直してみる一助となるのは確かだろう。
(C) ブックレビュー社 2000
