日経情報ストラテジーさんのレビュー一覧
投稿者:日経情報ストラテジー

知識経営のすすめ ナレッジマネジメントとその時代
2000/10/26 00:21
2000/3/1
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
ナレッジ・マネジメントで知られる野中郁次郎氏らによる本書は、ナレッジ・マネジメントとは単なるノウハウの共有ではなく、社内外の知を生かした「知識経営」を実践し、画期的な新商品を生むことにあると説く。
特に本書では欧米の先進事例を紹介しながら、知を活用して他社にはない新商品やサービスを創造している企業ほど、情報技術を駆使して経営を効率化していると指摘。知識経営こそが21世紀を制するグローバル企業の条件と見る。
ただし新しい知を創造するには、社員同士が対面でアイデアを交換し合う「場」が必要で、場を運営する指導力が欠かせないという。このため日本企業は、今まで無意識に備えていた対話の場を、戦略的かつグローバルに展開すべきと説く。長年、知識創造を追求してきた著者だけに論点は明確で、しかも知の創出につながる場の運営ノウハウにも触れており、ビジネスマンにも読みやすい。三田
Copyright (c)1998-2000 Nikkei Business Publications, Inc. All Rights Reserved.

グループ経営マネジメント 連結シナジー追求戦略の構築
2000/10/26 00:21
2000/3/1
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
今、日本の経営者にとってグループ連結経営は、最も大きな関心事の1つだろう。本書はそのグループ連結経営に必要な企業組織の在り方、人事や業績評価制度の改革、業績把握に必要な情報システムの整備といった9つの項目について解説している。
特に、業績評価制度の項目と企業の実例が興味深い内容になっている。
例えば前者では、ROE(株主資本利益率)やEVA(経済付加価値)といった会計的な指標だけでなく、バランスド・スコアカードなど非財務的、定性的な項目を採用した新しい経営指標も紹介している。このため自社の事情に応じて新しい経営評価指標を作る際の参考になる。
グループ連結経営の事例としては、過去にアーサーアンダーセンが手がけた凸版印刷や住友電装の内容を掲載。個別の企業戦略をグループとしての戦略にまとめるうえで、経営トップが果たすべき役割を再認識できるようになっている。安倍
Copyright (c)1998-2000 Nikkei Business Publications, Inc. All Rights Reserved.

日経インターネットイエローページ 2000
2000/10/26 00:21
2000/3/1
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
国内企業がインターネットに公開しているホームページのアドレス(URL)をまとめた1冊。上場/店頭公開企業のみならず、有限会社や個人事業主にいたるまで掲載数は約2万7000件に達する。検索エンジンなどを使っても探したいホームページがうまく見つからない場合などに役立つ。
「マスコミ」「メーカー」「商業」など大きく9つのカテゴリーに分け、さらにその中を五十音順でまとめている。上場/店頭公開企業については、ホームページの概要とおおまかな構成を紹介。さらに所在地と代表電話番号も記載する。
冒頭には、インターネットに詳しい村井純・慶応義塾大学教授のインタビュー記事を掲載しており、電子商取引など2000年のインターネットの動向を知るのに参考になる。
本書に掲載したURLの一覧に加えて、米国を中心とする主要企業のURLなどを収録したCD−ROMが付属する。川上
Copyright (c)1998-2000 Nikkei Business Publications, Inc. All Rights Reserved.

プロジェクト・マネジメント実践講座
2000/10/26 00:20
2000/1/1
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
企業組織が大変革するなか、仕事のやり方も根本的に変わってきた。最近では、ある仕事に対して社内から最適な社員を集めて一気に実行する「プロジェクト型」が注目されている。本来は、プラント建設やシステム開発などで使用される用語だが、今では「営業プロジェクト」や「業革プロジェクト」など一般のオフィスでも自然に使われるようになった。しかし、たとえ優秀なメンバーでプロジェクトチームを結成しても、会議に明け暮れるばかりで先に進まない場合もあるようだ。
本書は、プロジェクトを成功させる手法を、科学的に解説した指南書である。著者の専門分野はプラント建設などエンジニアリング関連だが、「プロジェクトの基本は立ち上げ、計画、遂行、コントロール、終結にある」と語るなど、オフィス業務でも役立ちそうな内容が記述されている。「ケーススタディ」や「チェックリスト」を設けるなど、読者の理解を助けてくれる工夫も多い。大山
Copyright (c)1998-2000 Nikkei Business Publications, Inc. All Rights Reserved.

PACE 製品開発のスピード化戦略
2000/10/26 00:20
2000/1/1
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
製品の市場投入の時間を最大で60%短縮し、開発コストは最大で80%削減—。本書で紹介する製品開発の新しい方法論、「PACE(Prod uct And Cycle−time Excellence)」を導入した企業は、軒並みこうした華々しい成果を実現したという。
だが本書には、日本の製造業が取り立てて驚くような手法が記述されているわけではない。製品開発の各プロセスで発生する無駄をいかに省くかといった基本的な課題について、体系に基づいた観点からアドバイスしている。
例えばPACEでは、組織横断的な少人数の「コアチーム」に強力な権限を与える。そして、コアチームが各プロセスごとに現状を評価し、次のプロセスに移行するか、中止するかを決めるという手法を取っている。また、計支援ツールは各プロセスの最適化を追わず、プロセス全体のバランスから選択する、といった点も重視している。
現状の製品開発プロセスをゼロから見直すのに役立つだろう。安倍
Copyright (c)1998-2000 Nikkei Business Publications, Inc. All Rights Reserved.

ブラーの時代 eコマースの新・経営戦略
2000/10/26 00:20
2000/1/1
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
企業や個人が様々なネットワークによる「コネクション」を形成することで、物的な資本よりも情報や信用、ブランドといった「無形物」の重要性が高まり、それらのすべてがものすごい「スピード」で変化していく—。
今、我々が直面している経済社会の変容のなかでは、旧来のルールや常識があっと言う間に役に立たなくなってしまう。著者はこの社会現象を「ブラー(blur)化」という言葉で説明し、そうした社会のなかで必要とされるビジネスの新しい思考法や視点を、本書で提供しようと試みている。
「ブラー」とは耳慣れない言葉だが、著者はこれを「変化が著しく速く、ものごとの境界があいまいになる世界」と定義する。
例えば売り手と買い手の関係。ブラー化した経済社会においては、「売り手」と「買い手」は従来のように明確に分けられない。アマゾン・ドット・コムは顧客に書籍を販売する一方、読者から書評を集めてウエブ上に提示し、新たな顧客を誘引している。顧客の書評が“商品”の1つになっているのだ。そこには、売り手と同じ立場にいる買い手の姿がある。
しかもブラーの時代では、モノとしての製品とそれに付属するサービスはますます不可分になり、何を売るべきかで競争優位は大きく変わる。ライバル企業は競合相手であると同時に、市場を拡大するための協力者としての側面を増しており、誰が味方で誰が敵になるか判別しにくい。
こうした変化を商品、組織、資源という3つの視点から分析し、「ビジネスをブラー化する50の方法」を提示する。副題に「eコマースの新・経営戦略」とあるように、そのなかには「買えるものは育てるな」といった持たざる経営を提唱するものが多い。時間がない読者なら、まず「50の方法」に目を通すことをお薦めする。著者のホームページ(www.blursight.com)で最新の情報発信や読者との意見交換も積極的に行っている。花澤
Copyright (c)1998-2000 Nikkei Business Publications, Inc. All Rights Reserved.

パソコンを使った実践キャッシュフロー計算書のつくり方
2000/10/26 00:20
1999/12/1
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
企業会計基準の改訂に伴い大きな注目を集めるキャッシュフロー経営。大手企業の中には、キャッシュフロー計算書を作成するため、わざわざ新し会計システムを導入するケースも少なくない。しかし中小企業にとっては、キャッシュフロー経営の重要性は理解できても、この不況下では新たな情報化投資は難しいだろう。
本書は、中小企業を対象にパソコンによるキャッシュフロー計算書の作成手法を解説したもので、著者は「高価な会計ソフトを導入しなくても、表計算ソフトでも計算書は作成できる」と語る。本書は「間接法」と呼ぶ計算方式を使い、簡単に計算書を作成する方法を述べている。
巻末には本書の計算方式を収めた体験用ソフトや「弥生会計」「勘定奉行」など市販会計ソフトのデモ版を収めたCD−ROMも添付するなど、計算方式を実践的に学べるようにした。キャッシュフロー経営の目的や意義などもやさしく説明している。大山
Copyright (c)1998-2000 Nikkei Business Publications, Inc. All Rights Reserved.

電子商取引とサイバー法
2000/10/26 00:20
1999/12/1
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
情報が取引の中心を占める「情報経済」においては、政府は介入を差し控えて、市場における自主的なルール作りや契約慣行を尊重すべきだ—。
現在の主流と言えるこの主張に、著者は疑問を呈する。“野放し”にしておけば、売り手にばかり都合のよい慣行がまかり通る危険性があるという。事実、インターネット上では消費者の個人情報やわいせつな画像が売買されるといった犯罪に事欠かない。
そこで、情報経済における法律のあるべき姿を、米国の「サイバー法」や訴訟事例から探ろうというのが本書の趣旨だ。取り上げた内容は、知的財産権や個人情報の保護から、大企業による市場の独占禁止までと幅広い。基本ソフトとWWWブラウザの関係を争点とした、いわゆる「マイクロソフト対米司法省」事件にも、ページを割いて詳しく解説している。
このケースを初めとして米国での代表的な訴訟事例を多数、掲載しており、具体的に理解しやすい。中山
Copyright (c)1998-2000 Nikkei Business Publications, Inc. All Rights Reserved.

市場をリードする「業務優位性」戦略 実践サプライチェーン
2000/10/26 00:20
1999/12/1
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
「実践」と銘打つサプライチェーン・マネジメント(SCM)の書籍を読むと、生産管理や購買、在庫といった業務プロセスや情報システムなど、主に現場に視点を置いた記述が多い。本書は同じSCMを扱いながら、「SCMでいかに経営のパフォーマンスを上げ、株主価値を向上させるか」など経営戦略の視点で語っている点が大きな特徴だ。このため、SCMをテーマにしながらも書名に「業務優位性戦略」と名付けていると思われる。
本書は「優位性が株主価値を創造する」「課題を直視する」「需要と供給を同期化させる」「業務優位性で顧客を勝ち取る」など8章で構成。トップが策定した経営戦略を製造や購買、物流など各部門レベルの計画立案にどう落とし込むかなど、戦略策定から実行段階まで一貫した流れを書いているため、SCMの全体像を理解しやすい。各章の終わりには「マネジャーへの質問」と呼ぶ記述があり、ポイントを確認できるよう工夫した。大山
Copyright (c)1998-2000 Nikkei Business Publications, Inc. All Rights Reserved.
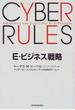
E−ビジネス戦略
2000/10/26 00:20
1999/12/1
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
CYBER RULES:Strategies for Excelling at E−Business」(サイバー・ルール=Eビジネスで成功するための戦略)が、本書の原題である。著者のトーマス・シーベル氏はSFAソフトのベンダーとして急成長中の米シーベル・システムズの創業者でCEO(最高経営責任者)、共著者のパット・ハウス氏は同社の共同設立者。Eビジネスの最先端に身を置く2人による“Eビジネス必勝の勘所”と言える内容だ。
営業とマーケティングを専門とするシーベル氏が書いた前著「バーチャル・セリング」に比べ、オートバイテル・ドット・コムやチャールズ・シュワブなどの事例も交えながらEビジネスの全体像を解説している点が特徴だ。Eビジネスの渦中にある当事者として、実に綿密かつ冷静に新たなビジネス・モデルを研究しているという印象を受ける。これからEビジネスを推進したい企業が実際に手を染める際には、本書から少なからぬ助言を得ることができるだろう。秋山
Copyright (c)1998-2000 Nikkei Business Publications, Inc. All Rights Reserved.

組織設計概論 戦略的組織制度の理論と実際
2000/10/26 00:20
1999/12/1
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
サプライチェーン・マネジメント(SCM)やエンタープライズ・リソース・プランニング(ERP)など、経営革新を支える新しい経営手法への関心は高まる一方だ。これらの実践に情報技術の活用が不可欠なことは言うまでもないが、もう1つ忘れてならないのが「人」の問題である。
いくら最新の情報システムがあっても、それを使いこなす人間系の議論が欠けていては、狙い通りの効果が上げられない。ライバルに負けないスピードとコア・コンピタンス(中核となる事業)が企業に求められる時代では、むしろ人や組織のあり方を根本から見直すことが重みを増している。
こうした経営環境のなか、情報化時代の組織論を正面から取り上げたのが本書である。カンパニー制、ネットワーク型組織、実力主義の評価制度など、日本企業が取り入れ始めた新しい手法を具体的に解説しているほか、各手法がなぜ脚光を浴びているのか、実際に導入するにはどういう手順を踏むべきかといった、総合的な視点で記述している点が特徴だ。
全体は大きく3章で構成する。「組織とは」と題する1章で組織論の基本を定義し、続く2章の「組織設計のプロセス」で、うまく機能する組織の設計と、それを定着させるノウハウを解説。最後の3章「現代の戦略的組織制度」で、実例に基づいた最新動向を詳述している。
組織論を解説した本は、理想論や机上論に終始して「勉強にはなるが現実味に乏しい」という読後感をもたらすものが少なくない。その点、本書は各社の事例を重視しているだけに説得力がある。ソニーやマツダ、リクルート、HOYA、ベネッセコーポレーションなど著名企業の先進事例をふんだんに扱っており興味深く読める。
終身雇用をはじめとする伝統的な日本企業のスタイルが変わりつつあるなかで、社員はどのようなキャリアパスを描くべきか。そのヒントを得るうえでも、役立つに違いない。川上
Copyright (c)1998-2000 Nikkei Business Publications, Inc. All Rights Reserved.

経営ビッグバン 情報活用21 経営改革のテーマに徹底的に迫る
2000/10/26 00:19
1999/10/1
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
経営革新のためのIT(情報技術)については、様々な概念や手法、仕組みが相次いで登場している。だが、実際に活用するには、システム担当者のみならず、経営トップや現場の一般社員までが理解しなければならない。そのためには、実際にITの活用に取り組んでいる企業の実例を知り、推進者の話を聞くのが一番だろう。その点で、本書は格好の一冊である。
本書のベースになっているのは、98年10月にスタートしたテレビ番組「経営ビッグバン」である。経営革新にチャレンジしている企業の最新事例を「大福帳システム」や「SCM」「コールセンター」といった12の視点で紹介、それらの事例を経営者や専門家が議論し、成功するための処方箋を導き出すという内容だ。
理論に走りがちなIT関連書籍が少なくないなかで、実際のケースを基本に置き、経営者の生の声と専門家による評価をバランスよく配したことが、わかりやすさにつながっている。花沢
Copyright (c)1998-2000 Nikkei Business Publications, Inc. All Rights Reserved.

「情報」で小さな会社も強くなる
2000/10/26 00:19
1999/11/1
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
「業績を上げるには、長時間働くことが大事。仕事の質は量についてくる」「上司の命令を聞かない部下について悩む必要はない。そうした社員はくびにすればよいからだ」。本書をわずか数ページ読んだだけで、型破りとも非常識ともつかない言葉が次々に目に飛び込んでくる。だが読み進むうちに、「なるほど、そうした考え方もあるな」と妙に納得させられる。
筆者は東京に本社を置く中堅企業、武蔵野の小山昇社長である。同社は清掃用品レンタルで知られるダスキンの第1号代理店だが、最近はボイスメール・システムなど情報機器を積極的に活用する経営手法で注目を集める。本書には中堅企業が情報化経営を推進するうえでの体験談を本音で記述しており、創業以来、売り上げ増を続ける同社の秘密が垣間見える。
本書の記述には常識外れに思えるものが多いが、「小さくとも強い会社」を作るには、こうしたバイタリティが必要だということがわかる。安倍
Copyright (c)1998-2000 Nikkei Business Publications, Inc. All Rights Reserved.

インターネット・電子商取引の法務と税務
2000/10/26 00:19
1999/11/1
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
インターネットの普及に合わせて、企業間や企業と消費者間の電子商取引(EC)市場が急成長している。通産省の調査によると、その規模は2003年に70兆円を超える見込みだという。
こうした拡大の一方で、新しい取引の場であるECには、確立したルールがないのが実情だ。これまでの法律や商慣習をそのまま当てはめられないことが多く、トラブルも少なくない。
本書は大学教授や弁護士といった法律の専門家が、現行の法律をEC向けに読み替えて取引ルールを解説したものである。顧客や取引先との情報のやり取りにインターネットを活用して、未知の取引環境に踏み込む企業にとって、心強い1冊になるだろう。
といっても、難解な法律書ではない。ECにおけるモノやカネ、データの流れから詳細に説き、既存の商取引との違いを明確にする。トラブルを避けるために必要な暗号化技術や電子署名、電子決済システムといった要素技術にも触れた。力竹
Copyright (c)1998-2000 Nikkei Business Publications, Inc. All Rights Reserved.

ソリューション・セリング 小売業の業態革命
2000/10/26 00:19
1999/11/1
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
「ソリューション・ビジネス」は、様々な業界で流行語となっている。市場の主導権が生産側から顧客側に移り、単なる「モノ」の販売ではなく、顧客の問題解決策(ソリューション)を提示できるところだけが生き残るという構造に変わってきたためだろう。
本書は、米国の小売業界で生まれつつある顧客志向型の新しい業態を紹介し、これを「ソリューション・セリング」と呼んでいる。例えば、「ホームヘルスケア」を専門とするテイク・グッド・ケア社や「食」を専門とするユークロップス社などだ。従来のような商品カテゴリーや店舗形態に縛られない新しい小売業の姿が浮かび上がってくる。実現のためには経営マインドはもちろん、コールセンターなどの活用も不可欠。本書では、そうした最新の情報技術の動向にも触れている。
日本の小売業界が消費不況を依然克服できないのは「顧客志向の業態開発を怠っているため」という主張には、一消費者として同感である。秋山
Copyright (c)1998-2000 Nikkei Business Publications, Inc. All Rights Reserved.

