さあちゃんさんのレビュー一覧
投稿者:さあちゃん

最果てアーケード
2012/08/27 23:57
この透明感が際立っているのです
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
この作品は10の短編から成り立っています。それぞれありそうでないお店ばかり。遺髪レースやらドアのぶだけのお店とか・・・主人公の私とそのアーケードに集まる人々のエピソードが淡々とそして静かに語られていきます。
小川洋子さんの作品はどれも透明感があふれていると思いますがこの作品も例外ではなく一つ一つのエピソードがまるで水底からふわりと浮きあがってくる水泡のように水面に表れて光の中にきらめいたかと思うとまた静かに沈んいく・・・そんなイメージがあります。
その透明感が素晴らしい。
そして浮遊感。このまま魂がこのアーケードにたどりつけそう気がしてくるから不思議です。
そんな中にもチラリと見えるかすかな影。それは最後に明かされるのですがそのとたんがらっとこの作品は今までと異なる顔をみせてくれます。
それぞれのエピソードが繋がり浮き上がってくるその見事さ。是非読んで味わってほしいと思います。

楽園のカンヴァス
2012/03/27 20:14
ルソーって誰?
6人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
ニューヨーク近代美術館の学芸員ティム・ブラウンは間もなく開催されるルソー展の準備に追われる日々を過ごしていた。そんな彼の元にある日一通の招待状が届く。差出人は名前は広く知られるも誰も見たこともない伝説のコレクター。彼が所有するルソーの名作の真偽を鑑定してほしいとの依頼だった。しかし内容からするとこの依頼は明らかに彼のボスであり主任キュレーターとしての名声を得ているティムとは一字違いであるトム・ブラウンにあてられたもの。しかしルソーはティムの憧れの存在であり特にその作品「夢」を観た時の衝撃が彼をこの世界に進ませたきっかけである。「これは運命なのかもしれない。」トムになりすますことを決意しティムはスイスに飛び伝説のコレクターであるバトラーの屋敷で一人の東洋人の女性と出会う。彼女の名は早川織絵。美術学会を騒がせている新進気鋭のルソー学者である。そして二人の前に現れたルソーの作品とは「夢のあと」
ティムの勤めるニューヨーク近代美術館が所有するルソーの傑作「夢」と同じ構図の作品だった。この作品の真偽を二人は7つの章からなる古書を交互に読みそれをもとに講評しなければならない。そしてどちらか優れた講評をしたものにこの作品の取り扱い権を譲るという。この意外な申し出に秘められた謎とは・・・
ルソーって誰?こんな一般常識もないような美術のことに全然興味のない私でも面白く読めた。ルソーを語っているのだがそのうんちくが専門的ではなくわかりやすい。そして作品の真偽が一つの物語を通して語られるという構成の素晴らしさがこの作品の魅力だと思う。この謎に加え主人公達が一つの作品を通して心を通わせるようになる様子もいい。上質のミステリーのように謎に引き込まれページをめくるてが止まらない。耳慣れない美術用語もでてくるが読み進むなかで苦労にはならなかった。特に監視員という美術品を鑑賞する人の為に静かな環境を見守る仕事があるということは初めて教えられた。
ルソーの「夢」私もこの作品の前に立ち作品の声に耳を傾けてみたい。作者の情熱を感じてみたい。美術音痴?の私にもこの作品は語りかけてくれるだろうか?そんな夢をみさせてくれる作品だと思う。
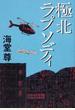
極北ラプソディ
2012/03/09 00:15
ノンフィクションに近いフィクション
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
北の果て極北市。財政破たんしたこの町唯一の総合病院である極北市民病院。市の財政破たんの一因と揶揄される赤字病院の立て直し人として市民の期待を一身に背負い登場した世良院長。彼が打ち出した方針は入院病棟の閉鎖であった。それに伴いスタッフは大幅に削減され救急外来は維持できなくなったのだ。そのためいかなる症状にも関わらず救急患者は全て受け入れを拒否し隣の雪見市の極北救命センターに送られることとなった。このタイムラグにより救える患者も救えなくなってしまったのではないだろうか・・・勤務医の今中は悩む。しかし現実には院長と二人だけの勤務体制で支えることはできないのはわかっている。しかし何かできることがあるのではないだろうか・・・そんな葛藤を抱える今中医師に下された新たな指令。それは極北救命センターへの無期限の派遣というものだった。北の大地でドクターヘリを駆使して球目う救急の雄として名を馳せる極北救命センター。噂では将軍と呼ばれる若き猛将も加わったという。そんな折診療拒否による患者死亡という新たなスキャンダルが市民病院を襲う。はたして病院再建は可能なのか・・・
極北クレイマーの続編。この作品も作者の世界観がしっかりと描かれていると思う。他の作品でお馴染みの人物もそこここに顔をだしているのでファンとしては嬉しい。一つの大きな世界の一部でおきていることを判り易くクローズアップしてみせてくれるその問題意識の鋭さにはいつも考えさせられる。医療という私達のとても身近で起こっている問題点を様々な角度から光を当てて見せてくれる。医師である作者ならではだろう。
この作品で描かれていることは自分たちの住む町にも起こりうることなのだと思う。現に私の住む隣町でも同様なことが起こっている。原因は医師不足であるという。毎年多くの人が医療を志す。私達の認識では決して医師が不足しているようには思えない。原因はどこにあるのだろう。長時間勤務と責任の重さなのか。それともお金の問題なのか。異なって見えるようだが実は背中合わせなのかもしれない。私達は自分の命を預ける時そこに信頼と責任を求める。そんな医師には万全の状態であってほしいと願う。そのためにはどうすればいいのか。救命救急とは何か。患者として医師としてなにができるのか。そんなことを考えさせる作品だと思う。

舟を編む
2012/01/28 17:10
辞書には驚きと感動が詰まっていることを教えられました。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
このタイトルからこれが辞書作りに携わる人々を描いた内容だとは想像もつかないと思います。勿論三浦しをんさんの新作なので通り一辺倒なものではないだろうとは思っていました。しかしまさかこんなにまで感動的で涙するようなものだったとは!
まさに嬉しい驚きでした。
これは15年もの間優れた辞書を世に出そうと奮闘する人々を描いた作品です。中心になるのは辞書編集部主任の馬締光也。
名前の通り真面目で少し変わっている。ぱっと見ははっきり言ってあまり関わりたくないタイプ。しかし本が好きで言葉に対する感性と情熱は飛びぬけている。そんなちょっと変わった彼を支える同僚や部下それぞれの視点から描かれています。
辞書。考えてみれば誰もが1冊はもっているはずだと思います。そう思えば大ベストセラーですよね。何だか所謂お偉い先生がつくっているというイメージを持っていました。勿論それが間違ったイメージでは無いでしょうがそれ以上に特別な勉強や知識を持たない一般の人々が仕事として関わり長い年月をかけて作り上げていくものだということを教えてもらいました。この仕事に情熱を傾けた多くの人々。ものを作り出すという仕事の素晴らしさが描きだされていると思います。
私達がこの世で生き自分のあるいは人の想いを感じるためには言葉が必要です。そんな言葉のの持つ力を大切にするために今日も名も無き人々が力を注いでくれている。そんな思いを強く感じさせてくれる作品だと思います。
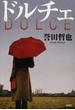
ドルチェ
2012/01/20 00:17
新しいヒロインの登場です
10人中、9人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
警視庁練馬警察署魚住久江巡査部長。42歳。独身。3日で二箱あけてしまう結構なヘビースモーカー。禁煙はしたいと思っているのだがいまだ止められない。10年前には本部捜査一課にいた。巡査部長に昇任してから所轄の強行犯係をわたり歩いている。今でも時々捜査一課に戻らないかと誘われる。この10年結婚したいと思ったことも子供が欲しいと思ったこともある。しかし戻りたいと思ったことは一度もない。それは一課が殺人捜査専門だからだ。いつしか人が殺されてから関わることに虚しさを感じるようになった。誰かが死ぬ前に事件と関わりたい。誰かが死んだ謎を解き明かすよりも誰かが生きていることに喜びを感じるようになったのだ。
こんなヒロイン魚住久江が活躍する短編が6つおさめられているのが本書である。どれも大きな事件ではない。強制わいせつや家庭内暴力・交通事故。どれも私達の身近でおきそうな事件である。一見変哲もない事実の裏側を丁寧に解き明かしていく。人間の心の奥にある気持ちの揺れや想いを声を荒げるわけでもなくでも一生懸命寄り添いながら解決していく。主人公の年齢設定も絶妙だ。気持ちはまだ30代でも体は確実に衰えてきている。でも独身生活が長いからといってわびしいわけではない。貴族とは言わないが一人の生活を楽しむすべはちゃんとある。そんなヒロインの存在感が絶妙だと思う。また脇を固める上司や同僚も個性的だ。
作者の別シリーズのヒロイン姫川玲子も好きだけどそれより少し力の抜けた感じのこちらのヒロインも凄くいい。次はいつ会えるのか待ち遠しい。

人質の朗読会
2011/05/18 23:53
語る人
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
語る人と聞く人。世の中はこの二つに分けられるのではないだろうか。そして作者は静かに語りかける。しかしその圧倒的な物語の前に私たちはただ耳を傾けるばかりだ。
ここで語られているのはどれもありふれた日常の物語。静謐だけれども奇妙な物語だ。しかしそれらの物語はどれも私たちの心の奥深くに入り込んで握りしめる。それは今は亡き者たちの声だがらか。それとも私たちの過去に観た風景だからなのか。いずれにしてもその世界に足を踏み入れたなら戻ることは許されない。ただ作者の語る声に身をゆだねるしかない。
とにかく作者の世界にただただ脱帽しそして恐れおののく。もはや語るべき言葉はない。ただ聞こう。語るべき言葉もない私達は。

シティ・マラソンズ
2010/12/02 00:09
なんだか私も走ってみようかなと思ってしまいます
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
三浦しをん・あさのあつこ・近藤史恵という当代人気の作家がマラソンをテーマに描く3つのものがたり。
「純白のライン」三浦しをん
いきなりの社長命令でニューヨークシティーマラソンに参加することになった安部。確かに学生時代には長距離選手だったけど就職して以来10年。確実に体重は増え今ではランニングさえおぼつかない。そんな彼がニューヨークで観たものは・・・
「フィニッシュ・ゲートから」あさのあつこ
学生時代将来を嘱望された長距離ランナーだった悠斗。しかし才能に限界を感じ競技から離れ今はランナーの為のシューズを作っている。「来年の東京マラソンを走る」ずっと音信不通だった湊からかかって1本の電話。学生時代はずっと控えの選手だった彼。あの日以来どうしていたのか・・・
「金色の風」近藤史恵
半年間の留学のためにパリに着いた夕は自分がパリの町に少しも馴染めないことに気がつく。ずっとバレエ一筋であったからなんとなくパリに憧れを抱きここに来れば何かが変わる思っていた。しかしただ逃げ出したかっただけかも知れない・・・
どの作品もそれぞの個性がでていて面白い。ただ走る。マラソンというのは単純なスポーツだ。ゴールを目指してひたすら前に前にと進んでいく。息があがり体が悲鳴を上げてもう駄目だと思ってもひたすら前へ前へ・・そのランナーの気持ちがよく描かれていると思う。主人公たちは走ることによって自分を見つめなおしていく。その様子がさらっと描かれていて読んでいる私もその風に吹かれて体が軽くなり走りだせそうな気持になる。マラソンコースも丁寧に描かれていて作者は実際にこのコースを走ったのかなあなんて思った。走るということに興味と共感を覚える作品集だと思う。

往復書簡
2010/11/27 23:43
そういえばもう何年手紙を書いてないだろう
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
3つの短編がおさめられている。同級生・先生と生徒・恋人達。それぞれが交わす手紙だけで物語は構成されている。そこではそれぞれ10年・20年・15年前の事件が語られている。真相は何処にあるのか・・・そして書き手たちの秘められた想いが語られていく・・・
今や一人に一台は持っているといっても過言ではない携帯電話によって私たちは今という時間を共有することが可能になっている。しかし手紙ではそうはいかない。手紙を書いてから相手から返事がくるまでの時間。この時間を意識して書くのが手紙というものではないだろうか。その時間があることによって相手の事自分の事をより深く考えるようになる。つまり相手を意識して書くということは自分の内面を掘り下げていくことなのではないだろうか。その意味においても昔の事件を手紙で語るという設定はうまいと思う。
今という時のなかでは見えないことも時間をおくと見えてくることもある。角度を変えると四角いものが丸く見える時もある。今見えていることが真実とは限らない。そういったことが往復書簡の形式でよく表現されていると思う。ラストもひねりがきいていてよかった。

暗黒街の女
2010/11/25 23:50
まるで映画を観ているみたい
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
場末の怪しげなクラブで経理の仕事をしている貧しいわたし。ビジネススクールに通いながら平凡な毎日を過ごしていた私の前にグロリアという女性が現れる。「あんな脚が欲しい」わたしにそう思わせた彼女はギャングの幹部で暗黒街でも一目置かれる存在だった。わたしの何が気に入ったのか彼女はわたしに仕事を手伝わせる。賭博の運び屋などの仕事をこなしそれなりの報酬を受け次第に彼女の信頼を勝ち取っていく。貧しい娘だったわたしをグロリアは拾い上げ鍛え暗黒街で顔を知られる女に変えていった。そんなわたしが出会ったのはろくでなしのギャンブラー。関わりあうべきではないと解っていたのにどうしようもなく溺れていってしまう。そして運命は残酷に変わっていく・・・
読んでいくとまるで映画を観ているみたいに場面場面が映像的に浮かんでくる。それも白黒。昔の映画のようにちょっとざらざらした感じ。それが私の抱くイメージだ。石畳を歩くカツカツとしたハイヒールの音まで聞こえてくるようだ。そしてグロリア。長身でエレガントな衣装を身にまとい髪は一糸乱れぬように結いあげ大きなサングラスと手袋をみにつけ背筋をのばしてゆっくりと歩くさまはまさに圧倒的存在感を醸し出す。男に頼らずに仕事で自立する女。冷静で非常な女。そんなグロリアに憧れ自分を引き立ててくれることに感謝しつつも自分を支配しようとすることに反発するわたし。そんな微妙な心の揺れや葛藤が見事に描かれている。
この作品はわたしの一人称で語られているがその語り口も見事でちょっとした心の揺れや怯え感情の揺らめきや劇場などが真っ直ぐに伝わってくる。
とにかく読んでみて欲しい作品だ。

獣の奏者 外伝 刹那
2010/11/21 01:05
刹那の意味が心にしみます
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
本編では描かれなかったエリンとイサルとエサルの物語。それぞれの視点で語られた物語はどれも心に染み入るようだ。
「人生の半ばを過ぎた人へ」あとがきで作者はこう述べている。人生というものがどれほど早くあっけなく過ぎ去ってしまうのかということを実感し始めた方たちに読んで欲しいと。これはエリンやイサルやエサルの物語であるだけでなく読者の物語でもある。彼らが感じている刹那の喜びや悲しみや人を愛したり想いやったりするその感情の揺らめきが読者の中に入り込みそして浮かびあがってくる。その刹那の積み重ねが生きることの喜びであり悲しみでもある。良きことも悪しきことも後悔もすべてが人生に織り込まれていく。選ばなかった事を後悔するよりもつまづきながらも不器用に前に進んでいく3人の物語はまさに生きていく姿を描いている。
年齢的にも一番近いエサルの物語に一番心惹かれた。その時は夢中で気がつかないことも歳を重ねると見えてくることもある。そしてその頃の自分が恥ずかしくもあり褒めてやりたくもあり叱ってやりたくもある。自分の生きて経験してきた様々な断片が浮かび上がってきて切なくなる。それぞれの物語の中に生きていくということの意味を改めて問い掛けてくるような作品だと思う。

蜜姫村
2010/11/13 00:11
もっと凄い乾ルカを読みたい
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
陸の孤島。東北の山深い瀧埜上村の中でもまだ奥深い仮巣地区はまさにそう呼ばれるのかふさわしい場所だった。一年前変種のアリを負って遭難した昆虫学者の山上一郎は一年間のフィールドワークの為新婚の妻和子を伴って再びこの地を訪れた。医師でもある和子にとって医師のいないこの村での暮らしはやりがいのあることだと感じていた。二人は一郎を助けてくれた恩人であり地区の中心的人物でもある白滝家の離れにやっかいになる。何くれと世話をやきいつもにこにこと接してくれる村人たち。だが幾日か過ぎていくうちに微妙な違和感を感じるようになる。それは老人達がみんな元気で過ごしていること。それに様子を診ようとする和子のことをみな避けているようなのだ。疑惑が膨れていく中世話になっている白滝家の男の子が高熱を発して寝込んでしまう。今度こそ診察させてほしいと申し出る和子。だが固く拒絶されてしまう。その夜二人は病気の男の子が背負われて連れて行かれるのを目撃する。行く先は村に来た時に決して立ち入ってはならないと厳命された社に通じる階段だった・・・・
人里離れた場所で親切だがうちとけない人々。そして立ち入ってはいけない秘密の場所とくればある程度の展開は予想できる。そしてこの作品は予想通りの展開をみせるのだ。連鎖的におこる悲劇。しかし作者は何を描きたかったのか。ストーリーは確かに起伏にとんでいる。だがストーリーの中にいる人々の姿がみえてこないような気がするのだ。あの昼下がりの午後に陽の光の中に舞うダストのきらめきのような作品を知っているだけに何だか肩すかしをくわされたような気がする。この作品との相性が悪かったということだけなのかな。
ストーリーは面白かったが本の帯にあるような鳥肌のたつような感動は得られなかった。何故なら乾ルカがもっと凄い作品を生み出せることを知っているからだ。

下流の宴
2010/08/04 00:18
とても身につまされました
8人中、7人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
福原由美子48歳。地方の国立大学を卒業し大手家電メーカーに努める夫とは職場結婚。東京に一軒家を構え長女の可奈は有名女子大へ通っている。早くに小児科医であった父親を亡くし母親が女で一つで苦労して育ててくれた。「あなたはお医者様の子なんだから」という母親の口癖を聞きながら努力して中流家庭を築いてきた由美子のたった一つの誤算は長男の翔だった。中高一貫高を中退しフリーターをしている翔が結婚相手に選んだ宮城珠緒は高校卒業後フリーターをしている沖縄の離島出身の不器量で下品な女。両親は離婚し母親は飲み屋をしており異母兄弟が何人もいるという。育ちが悪いから断固反対と言い放つ由美子に対して珠緒は医大に入って翔との結婚を認めさせてみせると宣言する・・・
この由美子の気持ちはよくわかる。自分が同じ立場にたたされたならきっと由美子のようになだめすかし泣き落し懇願しとあらゆる修羅場を演じるだろう。この息子の翔はやりたいことも目的もない。お金だって暮らしていけるだけあればいい。その日その日を暮らしていければいいのだ。すなわち将来の自分を想い描けないでいる。そんな翔に対して珠緒は現実的だ。結婚するということは将来の生活設計を共に描いていくということを理解している。そのうえ手結婚というものが個人の結びつきだけではなく家族がの繋がりも大事だということもちゃんと判っていて二人だけで婚姻届だしちゃおうという翔にたいしてみんなに祝福されたいからと必死にもう死に物狂いに頑張るのだ。こんな娘もったら親としては誇らしいと思う。物語が進むにつれて不器量と描かれているがだんだん綺麗に輝いて見えてくる。
対照的に翔の姉の可奈はもっと上琉の暮らしを望み金と力を持つ伴侶を求め婚活に励む。そしてその結果得たものは・・・
由美子と歳も立場も近い私としては由美子の姿に共感を覚えるとともにその滑稽さは自分が陥る姿かもしれないとも思う。何だかとても身につまされた。もし自分の息子が翔と同じ道を選んだら私はそれを認めてやれるだろうか?
育ちのよさとは学歴やお金のあるなしではなく人としての品性をもっているか否かということではないだろうか。そんなことを考えさせられた作品だ。

先生、カエルが脱皮してその皮を食べています!
2010/07/27 23:18
僕らはみんな生きている
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
本作は鳥取環境大学で教鞭をとる作者が大学の内外で出会う様々な出来事が描かれている。
カエルがシャツを脱ぐように脱皮することとか大学で飼っているヤギが柵を飛び越えて脱走することとか作者の勤める大学では日々興味深い出来事が起こるらしい。それを本書は何故そういうことが起こるのかを説明しながら同じことを人間にもあてはめて説明してくれる。そこがとても面白い。カエルやイモリなどがとる行動も私たちがとる行動もつきつめれば種を残すという同じ本能からきているということは愉快ではないか。よく狸親爺などと人は動物に例えられることがあるがあれは単に外見が似ているということだけではなくその行動を例えるものかもしれない。人間動物行動学というあまりなじみのない言葉だが本書を読めば人間もやはり動物だということを再認識させてくれる。何よりもユーモアあふれる文体なので読んでいて飽きない。知的好奇心も満足させてくれるのだ。
私は個人的にいえば作者が愛着をもって語るヘビやカエルなどは苦手だ。しかし作者の優しい視線で語られている彼らを何故か可愛く思えてくるから不思議だ。
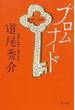
プロムナード
2010/07/23 00:00
好きな人のことはやっぱり知りたいよね
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
今最も気になる作家の一人道尾秀介の初エッセイ集。
実は作品は何点か読んだことがあるのだが作者についてはほとんど知らなかった。だからすべてのことが新鮮だった。へえこんなこと考えてるんだなんて共感したり驚いたり発見したり・・・
それは他人の部屋に入り込んだ感じかな。本棚や机の上やおいてあるものを見ている感じ。残念ながら引き出しの中まではのぞけなかったけどでもなんだか部屋の雰囲気はつかめたかな。そんな距離感が心地いい。
巻末のプロフィールだけではわからない作者の素顔がにじみ出ている一冊だと思う。
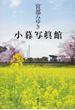
小暮写眞館
2010/07/16 23:58
宮部みゆきは期待を裏切らない
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
ちょっと変わり者の両親が購入したマイホームは古い写真館だった・・・
物語はこの古い写真館から始まる。高校生の花ちゃんこと花菱英一が彼のもとに持ち込まれたさまざまな写真の謎を紐解いていく。そこに込められていたのは様々な人の想いだった・・・
なんと700ページにも及ぶ大作。厚さは枕に匹敵する。これ何日かかるだろうという心配は全くない。本を開けばたちまちのうちにこの作品の虜になり早く読みたくて仕方なくなるだろうから。
これは少年の成長物語だ。主人公の花菱英一はごく普通の高校生だ。しかし人と出会い話を聞き考えていくうちに人には様々な顔があり色々なものを抱えていることに気がつく。そして考える。この想いはどこからきているのかということを。生者と死者についてを。
なんといっても主人公の花ちゃんがいい。親友のテンコがいい。コゲパンもいい。ピカちゃんもいい。お父さんもお母さんも登場人物の一人ひとりがみんないい。みんながこの作品のなかで生き生きしている。そう作品の中で確実に生きている。これは凄いと思う。
読後にみんなの集合写真が目に浮かぶようだった。


