ももんじゃ05号さんのレビュー一覧
投稿者:ももんじゃ05号
紙の本
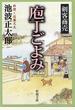
紙の本剣客商売庖丁ごよみ
2008/03/02 20:13
結構意外だったのですが、松茸って、剣客商売に出てこなかったんですね
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1 小兵衛先生は、よく旨いものをめしあがっていらっしゃる。行きつけの小料理屋、料亭、それから、自宅で愛妻の手料理など、値の張るものから、財布にやさしいものまでいろいろめしあがっていらっしゃる。
2 ただ、私があまり料理の話を知らないので、鯰のスッポン煮とか、冷やし汁とか、鮒飯とか、名前だけは出ているが(作り方もちょっと書いてはあるんだが)、中身があまり想像できないものがあった。
しかし、本書においては、これが写真付きで作り方まで解説されている。
あれ、一度、食ってみたいなあというのも出てくる。私は、「待ち伏せ」で大治郎が3杯食べたとかいう「アサリのぶっかけ」が食べたい。アサリとネギの五部切りを薄味で煮て、汁もろとも炊き立ての飯へかけて作るやつである。汁が飯に絡んでものすごく旨そうである(しかも作り方は簡単)。
3 本書を手にとって、これがあれで、あれがこれかとしみじみ眺めながら、食った気になって腹を撫すのである。腹の虫殿も、しきりに相槌を打っておられる。
4 さて、夕飯にすべえ。
紙の本

紙の本風流 江戸の蕎麦 食う、描く、詠む
2011/03/06 17:23
粋の構造 そば編
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1 本書は、江戸のそば文化について、文芸、芸能に現れた話をまとめた本である。
2 江戸時代、基本的に、流通、産地の関係から、関西はうどん、関東はそばであった。そばは、救荒作物の側面があり、低温の場合でも、2か月から3か月程度で育つ。寒冷地、山地で栽培しやすいので、関東近辺で、栽培されたんだと思う(そばの産地は、長野とか、山形とか寒いところが多い)。
しかし、切りそばが生まれ、粋な食べ物だということで(直侍がおにぎりでは絵にならんなあ)、江戸っ子にも大変好かれていく。
このため、江戸の文芸、芸能との非常に関連が深かくなっていった。
3 有名どころは、忠臣蔵。赤穂浪士が集まったのがそば屋の二階であったとか、しかし、実際には、討ち入り前に数名がそばを食べにいっただけだそうな。
また、赤穂浪士に限らず、武士のそば愛好者も多い。松尾芭蕉は、そばを俳句に詠んでいる。それまで、和歌では、そばを題材に扱うことはなかったんだが(やっぱり王朝文化だから、関西中心か、また、そばの扱いが低かったのかもねえ)、芭蕉が、旅路で読んでいるのである。
さらに、新井白石が、そばを漢詩にうたっている。これがなかなかふるっていて、楽しい。私は、新井白石は、おっかない人だと思っていたのだが、こういうお茶目な側面が意外であった。
他方、恋川春町(この人、本職は、小藩の家老級である)が、酒呑童子の話を題材に、化物大江山という話を書いている。なんでもこの話、洛中に繰り出しては、無銭飲食を繰り返すうどん童子を、源のそばこ(頼光のパロディ)が四天王(渡辺綱ならぬ渡辺のチンピとか薬味が題材)を連れて、打ちにいく(討つと掛けている)話である。かなり手が込んでいて、パロディとして大変面白い(神仏の化身が、浅草の市場で買ってきた麺棒を授けるのは、笑ってしまった)。
4 庶民の生活では、源平合戦(一の谷)をパロディにして、そば屋と客の掛け合いがあったり、小話があったりする。今でも残っているものとしては、歌舞伎で、前出の直侍がそばを食べたり、落語(ときそば、そば清)にでてきたり。そば清に関連して、そばの大食い選手権みたいな記録もあるんだけど、中に、どっかの藩の侍(しかもかなりいい年)がいて、みんな楽しんでるなあと思う。
5 そばって、手軽な食べ物でありながら、江戸っ子に親しまれ、また、文芸や芸能に取り上げられた結果、洒脱になっていったみたいである。
なお、現在のそばの関係で、こういう漫画がある。腹が減ってきたので、この辺で。
紙の本

紙の本解剖医ハンター 2
2011/01/25 18:28
常識の敵対者
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1 本書は、18世紀のロンドンを舞台に、ハンターという名前の医者が、病気を治すため、また、科学の発展のため、身を粉にして働くという話である。
2 …というと、なんだかドラマにもなった仁みたいだが、ハンター先生、もっと楽しい人である。夜な夜な墓場に現れては、死にたての死体を掘り出して、日夜解剖、病理検査に明け暮れるのである(このため本書は、臓器や治療の描写多し)。
しかも、ところはヨーロッパ、時期はまだまだ18世紀である(多分、1770年代)。教会の影響は強く、人々は迷信深く、ハンター先生の行いはキリスト教の中では、悪魔にも比肩する行為であった(死体を損壊してしまうと世界の終りに復活ができなくなるから、ものすごく嫌われた)。また、ときどき博物学のため収集した猛獣(虎とか)が逃げ出したり、かなり迷惑な人である。
しかし、ハンター先生、教会や他の学者あるいは近所の善男善女にがたがた言われたくらいでひるむタマではない。人間以外にも博物学全般に興味を示し、今日も今日とて解剖にいそしむのである。
3 なんだそんなの、気持ち悪いとおもわれる方、ごもっともである。作者も、ハンターが隣に住んでたら引っ越すと言っている。
しかし、この人、ただの迷惑なおっさんかといえばさにあらず。当時、ロンドンは、公衆衛生などと言う崇高なものはなく、民衆の栄養状態は悪く、また、有益な薬は少なかった。医者は、ほとんどがギリシアやアラビアの古典教育を受けてきいるが、やることといえば、もっぱら瀉血か、浣腸くらい。症例を見て、処方するなんてことはなかった。結局のところ、解剖なんてことは全然やっておらず、人間の体の構造なんか理解してない。まともに診療できなかったのである(年間に解剖用に供される死体は、死刑囚の死体で6人分でしかなかった)。
これでは、助かる命も助からない。そこで、ハンター先生、常識に基づく世間の批判を向こうに回し、今日も今日とて解剖に励むのである。
4 さて、本書の主人公ハンター先生だが、名前はハンターって作ったようだし、人間性もアレだし、架空の人物じゃなかろうかと思うだろうが、恐ろしいことに、実在した人物である(ジキル博士とハイド氏やドクタードリトルのモデル)。ぶっとんだ登場人物も、多くは実在の人物である。18世紀は、イギリスが坂の上にのぼる時期だったので、多彩な人材を輩出した(とんでもない人も結構いたが)。しかし、この多彩な人材は、常識にぶつかった。当時の常識は、科学的な裏打ちのないものも多かった。このため、当時の先進的な科学者は、誤った常識(ありていにいえば世間)を敵にまわさねばならなかったのである。いろいろ命懸けですなあ。
5 なお、蛇足ながら、本書の漫画を描いておられる黒釜ナオ氏は、安彦良和氏、吾妻ひでお氏のアシスタントをしていたそうな。また、濃いところを…。
紙の本

紙の本要件事実論30講 第2版
2010/12/19 09:39
要件事実入門
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1 本書は、要件事実論につき、学者と実務家が、作成した教科書である。
2 本書の偉いところは、なんといっても、答えが載っているところである。そして、ただ、答えが載っているのではなく、答えに至るまでの経緯が載っているのである。
紛争類型別(今改訂中?)は、薄い本なので、とっつきやすいと思ってうかつにかかっていく人が多いが、あれは、難しい本である。多分、遅延損害金のところで挫折するはずである(なお、実際には、あそこは二回試験に出ない)。しかし、すごくいい内容で、作った人たちの頭の良さがわかる本でもある。ある程度勉強して、話がわかるようになってから読んでみると、感動できる本である。
3 しかし、これでは「ある程度」できるようになるまでは、地獄の三丁目である。要件事実論は、わかる人は一発でわかるが、わからん人はなかなかわからん。そして、わからん人が大多数なのである。
そこで、本書である。
本書は、要件事実で問題になる一般的な項目につき、30項目を挙げて書かれている。特に、要件事実で、なんでこれをここで書くのかという理由がわかりやすく書かれており大変いい。
4 他に、要件事実の教科書としては、要件事実の考え方と実務第2版とか、要件実務マニュアルがある。前者は、割合薄い本でわかりやすいので入門向き、後者は・・・まあ、裁判官志望の修習生が読む(といわれている)本である、もうねえ、要件事実については、全部書いてあるけど、分量が非常に多いのですよ、わからなくなったときの辞書ですなあ(あと、辞書的に使うために、索引をもうちょっと何とかしてほしいなあ)。
5 要件事実は、一回わかると大体あとは何とかなる学問である。二回試験や後期修習のときの課題はかなり難しいが、結局は、技術なのでシステマティックになっており、基本さえ分かれば、なんとかなるのである。
紙の本

紙の本大江戸捕物帳の世界
2010/09/20 21:14
ゼミ旅行が東京刑場、墓地廻りだった件について
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1 本書は、明治大学中央図書館事務長様(大学と言うと学部長より事務長のほうが偉いので、事務長は事務長様と呼ぶ)の著者が書いた江戸時代の刑事裁判及びその執行に関する本である。
2 私は、学生時代法制史のゼミに所属していた。江戸幕府法とかやってたのである。そのゼミのゼミ旅行が、東京(江戸)の刑場及び刑事史跡廻りであった。小塚原、鈴が森刑場跡とか小伝馬町大牢屋跡とか腕の喜三郎の墓とか見に行ったのである。
その旅行過程に、本書の著者の勤務先である明治大学の中にある刑事博物館(現:明治大学博物館)があった。駿河台の喧噪のなか、明治大学の現代的なビル(うちの大学とは大違いであった)に、その博物館はあった。
そこには、さすまたとか袖がらみの他に(なお、現在、裁判所内にさすまたがあります。冗談ではなく)、鉄の処女とか、ギロチン、獄門台とかがあった。本書にも紹介されている獄門台に置かれている生首の写真とかもあった。
こういうのを見ても、恐怖より先に、行刑方法に興味が向くのが法制史学者というもんである。死体の写真を見ても、気持ち悪いとか思うより、証拠物として見てしまう法曹関係者に近いものがある。
3 本書では、江戸の取り締まり現場、大岡越前の裁判(とくに白子屋おくま一件)、長谷川平蔵の話、江戸の刑事裁判手続き(ちなみに、民事は全く別です)と公事方御定書について、裁判機関と刑罰の実施及び刑事史跡の話が紹介されている。最後の刑事史跡は、ゼミ旅行の旅程であった。
4 江戸幕府の法律は、適用される範囲が幕府の領内に限定される。そのため、私領(各藩の領土)には適用されない。そのため、司法権が錯綜しているんだが、中に熊本藩御刑法草書(という刑事法典がある)みたいに、恐ろしく近代的な行刑が整備されていたりすることもある。
日本法制史全般について勉強してみたい方は大学の教科書によく選定されるものだがこんなんはいかがでしょうか(新しくなっててびっくり)。
なお、最後のほうに書いてある公事方御定書の刑罰体系と刑種(何やるとどういう刑に処せられるかが書いてあります)は、結構便利である。時代劇のおともにいかがか。
紙の本

紙の本幇間探偵しゃろく 1 (ビッグコミックス)
2010/07/25 10:04
粋が沢山あった頃
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1 本書は、昭和初年ころ、東京向島に出入りする若旦那と、それに付き合う幇間(太鼓持ち)が、探偵をして、事件を解決するという話である。
2 本書の若旦那は、さる会社の次男坊、しかも、3人の兄と姉がいる末っ子である。だから、家は長男が継ぎ、親御さんも甘く、今では、向島界隈へ出入りする遊び人である(30年くらい前まで、老舗では、親御さん(父親だけでなく、母親も)が、息子の遊ぶ金を出す習慣があったそうな。年取ってからよからぬ遊び(遊びや遊ぶ相手にも上中下がある)を覚えないように、あらかじめ若いうちから遊ばせとくんだそうである。また、付き合いで、野暮なのがばれると、あんまり外聞がよろしくない。旦那は遊びも仕事だったのである)。
ただ、生来の育ちの良さか、遊びは、きれいなもんである。しかし、相当野暮天だ(こっちの方が致命傷かもねえ、遊び人としては。服の趣味はいいんだけどねえ)。
この若旦那が、事件が発生するとさっそうと現れて、事件を解決…しない。事件を解決するのは、もっぱら太鼓持ち氏であるが、どっかの眼鏡の少年探偵よろしく、太鼓持ち氏は、若旦那に手柄を渡すのである(ただ、通常、遊ぶ方より、遊ばせる方が知識も技量もうえでないといけない。太鼓持ちと芸者は馬鹿ではできない)。
3 しかし、この太鼓持ち氏、大変珍しい。太鼓持ちは、お座敷などで、旦那のご機嫌をとる商売であり、旦那や一緒に来たお客の機嫌を損ねるなど言語道断の所業である。
ところが、この太鼓持ち氏、酒癖が悪く、行儀の悪い客を見るや啖呵を切り、若旦那以外には、縁切りをされてしまったという御仁である。
若旦那も太鼓持ち氏に愛想をつかしそうになることもあるが、なかなか切れない。そのたびに、事件が起きて、太鼓持ち氏が事件を解決するのである。
4 本書は、推理だけでなく、今はほとんどなくなってしまったお座敷遊びの情緒や、昭和初年ころの洋風と着物がいい感じで混ざった東京の風俗が描かれている。
古き良き時代の良き場所の一席である。
紙の本

紙の本狼の口 1 (BEAM COMIX)
2010/03/14 10:03
黒が基調の昔話
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1 本書は、14世紀初頭のアルプス(スイス、イタリア間)の関所のお話である。
2 ときは、オーストリア公ハプスブルグ家がスイスでの権勢をふるっていたころである。ウィリアム・テル(本書にも出てくる)がゲスラー代官に喧嘩を売っていたころである。
スイス・イタリア間の要衝ザンクト・ゴットハルト峠では、オーストリアから派遣された関守の代官が、取り締まりをしていた。
しかし、この代官、優しげな顔に似合わず天魔地魎のごとき者である。その眼力は猛禽よりも鋭く、その性根は豺狼よりも恐ろしい。
密行者とみれば忽ちとらえて、拷問の上、残虐な刑を科すのである。
その密行者と代官との暗闘、悲劇を描いたのが本書である。
3 まだまだ1巻なので、代官がどういう人かよくわからない。そのうち、代官の経歴、生育過程などのも明らかになるだろう。とくに、どういう経緯で、あの眼力が備わったのか興味のわくところである。
4 おそらく本書は、歴史に即して進むだろう。そのとき、あの代官がどうなるか、スイスの夜明け前での一席である。
紙の本

紙の本国際民事手続法
2009/01/11 00:20
この分野,他に手頃な本がない
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1 本書は,国際民事手続法というあまり聞きなれない法律分野の本である。
2 法律で,国際と来ると,国際公法と国際私法である。国際公法は,国家間の取り決めのための法律であり,国際私法は,裁判においてどこの国の実体法(民法とか,商法とか,問題に実際に適用される部類の法律)を使うかという話である。後者は,結構離婚事件とかで問題になるのである(韓国民法とカ,フィリピン民法とか,ときとして北朝鮮民法とか)。
じゃあ,国際民事手続法とは何ぞやということになるが,これは,どこの国の民事訴訟法を使うかという問題なのである。
3(1) なにそれ,地味,国際私法と大して変わらないじゃないと思われるかもしれないが,これがちょっとちがう。国際私法は,どこの国の法律を使って判断するかという話で,判断するのは,日本の裁判官である。一方,国際手続法というのは,判断する裁判官が,どこの国の裁判官かまずわからないというところの話なのである。
(2) 国家というものには,主権というものがある。この主権の結構重要な部分を構成するものとして,司法権がある。そうすると,国家間をまたいで訴訟を始めると,両方の国に管轄が生ずることがある(この前提として,送達という訴状や裁判所の文書を相手に送る手続きが,かなり重要になる)。
(3) 札幌と福岡に住んでいる人が,裁判をすることになるとする,どちらの裁判所が管轄を持つかは費用や手間を考えると,結構シビアな問題だろう。これがさらに,国をまたいだりすると,まず言語がわからないし,法律だってなんだかよくわからない。ところによっては,裁判官が信用できない国もある(発展途上国だと,判例・裁判が公開されていない国もある。これは偏頗的な裁判をしても,バレないというなかなか恐ろしい効果がある)のである。皆様あんまりそうは思ってないかもしれないが,日本の裁判所って,国際的に比較すると,かなり処理が早いし,親切である。
4 この分野,あんまり触れる人がいなかったのか,長らく教科書的なものがなかった(石黒先生の本はあったけど,この本かなり癖がある)。
アルマのAdvancedというほとんど見たことないようなマニアックな分類の本であるが,興味のある方は一度手に取ってみると面白いかもしれない。
紙の本

紙の本労働法の世界 第7版
2008/04/13 19:32
分量と内容を考えると、このくらいがちょうどよいような気がする。
4人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1 本書は、労働法に関して、採用、労組、労働条件、労使間の紛争、そして、退社の順で、各点につき記載された教科書である。
2 労働法といえば、いわずもがなのことであるが、菅野労働法が金字塔である。
ただ、この本、厚いのである(厚さ800頁に迫る)。まるで鈍器の仲間である。だから、これを通読するのはしんどいと思う。
一方、本書は、400頁ちょっとと、それほどごついわけではない。しかし、なりはそれほど大きくはないが必要なことはしっかり書いてある。これを読めば、労働法に関して、大体のところは把握できると思う。
3 実際問題として、法律は一定の割合は記憶しなければならない。あまり厚い本だと、あっちを読んでいるうちにこっちを忘れ、こっちを確認したかと思ったら、あっちはどうだったっけと思うのが落ちである。
厚い本は、辞書と割り切り、比較的手軽で良質な本を何度か読んだほうがいいように思う。
4 本書を読んで、さらに突っ込んでやろうと思ったら、労働法の百選とか、前出の菅野労働法、また、演習をして勉強しようと思ったらウォッチング労働法なんかで補充するのが良いと思う。
順々に勉強していけば、だんだんとわかるようになるのである。一足飛びに難しいことをやろうとしても、よくわからんのですわ。
紙の本

紙の本判例講義民法 補訂版 1 総則・物権
2008/04/05 10:49
百選よりごちゃごちゃしていないと思う
4人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1 本書は、民法の総則物権についての判例に関する解説書である(なお、債権に関してはこちら)。
2 判例の理解が法律上重要であるということは、当然であるが、これも結局わかりやすくないといけない。最高裁の判例なんか素で読んだら結構気合いがいるもんである(というか、判例だけよんだってわからない)。百選は重要な判例解説であるが、各著者の書き方が一定していないこと、ともすれば通説とかの解説よりも自説のプッシュのほうが比重が高いことが問題である。
3 一方、本書の特徴は、第一に、書き方が一定していることである。流れとしては、(1)論点、(2)事実の要約、(3)裁判の流れ(原審、原々審の流れである)、(4)(最高裁の)判旨、(5)判例の法理、(6)判例を読むの順で構成されている。
このうち、(6)の「判例を読む」の項では、判示にかかる学説や関連する問題が記載されている。
特に、上記の(5)の「判例の法理」が独立して書かれているのは、重要だと思われる。ここで、判旨された事項のうち最高裁の見解が短くまとめられている。
これが書いてあること、また、どこに書いてあるか即座に分かることは、かなり重要である(難しい本を読んで、経験した方はわかると思うが)。
また、特徴の2点目として、見開き1ページから3ページですべての事項が記載されていることである。前に、キーワードで読む会社法の書評でも書いたが、あんまり長いことごちゃごちゃ書かれるとまずい、2ページ程度で書いていてくれるとありがたいのである(ちなみに、本書の方が百選より字が大きい)。
特徴の3点目は、自説のプッシュがどっから始まるかわかりやすいということである(笑)。自説が出てくるとすれば(6)以下である。
学者である以上、自分の書くものに自説を書かなくてなんとするということはある。しかし、学生が知りたいのは、先生の御説ではなくて、最高裁の見解とか通説だったりする。
まあ、書いている人によって多少書き方が違うのだが、(6)「判例を読む」以下では各項目の表題が太字で書かれている。通説や学説の動向が書いてある場合とか、より細かい議論や場合分けがあるような話の時も同様に表題が太字で書かれている。何を論じられているかが一目でわかる。
何より、上記のとおり、「判例法理」はしっかり把握できるため、道を踏み外すことはないと思う。
4 楽して法律はわかりませんが、わかりやすくなきゃだめですがな。まあ、頑張って勉強しましょうや。
紙の本

紙の本釣り人の「マジで死ぬかと思った」体験談 3 Accident File 45〜65
2008/02/25 20:14
道楽は、病気である。死ぬまで治らないが、死んでしまっては面白くもなんともない。
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1(題名からわかることだが)この本に出てこられる方は、みな、死にそうになっておられる。
だから、話はものすごく痛そうである。しかし、不思議と暗くならない。これは、おそらく、釣りという道楽にまつわる話だからであろう。
2 私は、ずいぶん昔にちょろちょろと釣りをしていたくらいで、もう、糸の結び方も忘れてしまったような人間である。
一方、ここに登場される方は、筋金入りである。いや、筋金どころか、全体的に形状記憶合金か何かでできているのではないかと思われる。
釣りをやっていたら(またはやろうとしたら)、やれ、滑落しただの、滝つぼに落ちただの、落雷にあっただの、無数のフナ虫に噛みつかれただの、エライ目にあっておられる。
しかし、彼らは屈しない。ひどい目にあっても、あっても、釣りに行く。一人として、「私はこれで釣りを止めました」とは、言わないのである。ある方など、釣りをしている最中に事故にあい、骨折して、血まみれになった直後、なお、「鮎マスターズの予選までに走れるようにしてください」と医者に懇請している。
まさに、何度形を変えても元へと戻る形状記憶合金である。
たぶん、嫁さんや親や、わが子にさえ呆れられているのではないか?
3 しかし、彼らはそれはそれで幸せなのだろう。釣りは、道楽である、道楽は当人が幸せならばいいのである。他人がやいやい言うのは野暮である。
だから、この話は痛い話なのだが、明るく楽しい? のである。
4 ただ、死んでしまってはもう釣りもできないんだから、皆さん十分注意してくださいと願うばかりである(まあ、楽しいことやっているときに、他のことを考えるのは難しいのですけどね、ええ、私も違う病気の患者なので、あまり難しいことは申せません)。
紙の本
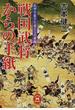
紙の本戦国武将からの手紙 乱世を生きた男たちの素顔
2008/08/02 22:34
もうちょっといろいろな手紙を読んでみたい
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1 本書は,戦国武将が出した手紙をもとに,その人となりに迫ろうとする本である。総勢18名,みんなメジャーどころである。
2(1) さて,本書は,公的な書状もあるのだが,中に家族に送った私信がある。これを見ると,なかなか楽しい。
上杉謙信は,結構養子(景勝)思いで,義父らしい手紙を書いていたり,豊臣秀吉の子供(秀頼)への愛情の注ぎ方が異常なほどだったり,伊達政宗が結構お茶目だったりする。
特に,個人的に興味深かったのは,毛利隆元と黒田官兵衛,それから,島津義弘である。
(2) 毛利隆元は,毛利元就の長男にして,吉川元春,小早川隆景の兄貴だが,他の人に比べて影がうすい。これが,手紙でも表れていて,手紙は,無常感にあふれ,後ろ向きな内容なのである。他方,親父の元就は,本当に説教魔だったらしく,書状でくどくどくどくど説教を垂れている。隆元,親父の説教が原因で,こんなに後ろ向きになってしまったのか,そういえば,この人,早くに亡くなったなあと感慨深いことしきりである。この辺の後ろ向きぶりは,徳川秀忠の手紙にも表れているので,偉大な親父をもった2代目の苦悩の表れかもしらん。
(3) また,黒田官兵衛は,巷間に流布している煮ても焼いても食えない謀略家というイメージとちょっと違う。なんか,上の者(当時は,秀吉やその甥の秀次)を大切にしろとか,善人として果てるなら後悔ないとか,人間が丸いのである(手紙を書いたときは,文禄慶長の役だそうである。あの息子(長政)にお前の左手は何をしていたとか言っていた関ヶ原より前の話である)。本当に法名のとおり(如水),淡々としているのかしら。結構意外であった。
(4) そして,最後の島津義弘は,日本はもとより,加羅唐土にも勇名が鳴り響いた猛将であるが,かなり奥様とはラブラブだったみたいである。
義弘57歳の時に妻に送った手紙だが(妻の年齢は不詳,ただし,子供の年から逆算すると,結構な年齢だった模様),これが,すごいのである。追伸の冒頭部で「今夜もまたお前の夢を見たよ」とくる! 人間50年の時代に,57歳で奥様にこう書くとはすごいな維新斎!
3 プライベートの手紙は,家のために戦国武将として書く公文書とは全く性格が違うので,いろいろと面白かった。
ただ,掲載されている手紙の量が少ないので,もうちょっといろいろほしいところ。1通や2通では,その人となりはよくわからないのである。なお,こういう本もあったが,もう売ってないかあ,惜しいなあ。
紙の本
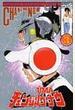
紙の本チェンジング・ナウ 3 (週刊少年マガジンKC)
2008/04/13 19:05
大体ギャグ、ところどころシリアス。ただし、シリアス展開のときには、主人公はおいてけぼりのことしばしば。
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1 本書は、突然、変態もとい変身ヒーローになってしまったふつうのお父さんが、なんだかよくわからないけど、怪人を倒しながら、日々を過ごしていく物語である。
2 このお父さん、ある日、酒を飲んだら記憶をなくし、翌朝あら不思議、ヒーローへと変貌していた。しかし、お父さんには、愛すべき家族(なお、嫁さんは美人)と会社の仕事がある。ヒーローばっかりやっているわけにはいかんのである。
ところが、日々苦悶に打ちひしがれるお父さんを尻目に(といっても、はたで見ているとあほらしいのだが)、年ごろの愛娘は、変身したお父さんをカッコワルいと毛嫌いする。あまつさえ、別のカッコいいヒーローは応援しているようだ。お父さんとしては立つ瀬がない。
3 一方、本書においては、敵方も魅力あふれるキャラクターが多い。本書の敵役の悪の秘密組織は、なんだかどっかの会社みたいに次回登場の怪人のための会議をやり、資料を作り、研究開発に取り組んでいる。福利厚生もしっかりしているようだ。あと、なんだかよくわからない部署もあって、芸能関係のプロモーターとか、食玩もやっているらしい。
特に、本書の「大佐」と呼ばれる支部長(支店長?)は、過去にいろいろあったようだ。ただ、部下にはやさしくもあり、厳しくもあり、大変いい上司である。
また、紅一点の敵方幹部が実はお父さんの…であったりなかったりする。なんかイケナイ社内恋愛である(なお、くどいようだが嫁さんは美人)。
4 残念ながら、本書は中途半端なところで終ってしまった。掲載誌が少年マガジンだったため、若年層にはなかなかわからない話だったかもしらん。私は、悪の秘密結社が社員旅行に行く話が好きだったなあ…でも、最後の怒涛のシリアス展開もよかったなあ。もうちょっと読みたかったと思う。
紙の本

紙の本軍事とロジスティクス
2011/03/20 19:22
有事の際のロジスティクス
3人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1 本書は、故江畑謙介氏が、昨今の軍事技術を、ロジスティクス方面から論じた本である。
2 ロジスティクスは、輜重とか、兵站、あるいは物流と訳されるが、軍需物資の輸送、保管にとどまらない、前線で有効な活動できるような機構、組織、設備そのものである。
だから、本書では、輸送の話もたくさんあるが、民間軍事会社の利用とかの話もある。
米軍が、民間軍事会社とコスト・プラス方式(経費支出に応じて報酬が支払われる方式だそうな)で、契約したら、無駄な支出が増大してエライコトになったとか。まあ、こんな契約で、相手に、善意を期待するのは、戦略的な誤りであろう。
この話で思い出したのは、昔、某大企業の法務部長の話で、アメリカの弁護士事務所とチャージ方式(書類作成、打ち合わせ等にかかった時間によって報酬を払う方式)で契約したら、ものすごい額の請求をされた。調査したら、昼飯の時間まで、打ち合わせと称して、報酬に計上してやがったと怒っていらっしゃった。どこの業界にも、こういうことする奴いるねえという話である。
3 さて、今般、大地震と津波が起きて、大変なことになった。
本書は、前出のとおり、軍隊の兵站の話である。したがって、輸送や保管、物品管理の話は、災害時も応用できる話である。
本書を読んでいたら、これあったら災害時便利だなあというのがあった。たとえば、ハイブリッド型飛行船である。普通の飛行船は、浮力だけで空に浮いているが、ハイブリッド型は、機械動力も利用して、揚力を稼いで空を飛ぶんだそうな。この飛行船、何がすごいかって、大きさと搭載量である。最大のものは、100万立方メートルの体積(簡単に言うと、100メートル×100メートル×100メートルの大きさ。まあ、実際は、もっとスマートな形をしているが)で、搭載量は、1000トンだそうな。しかし、元が飛行船なので、滑走路は1400メートルくらいでよく、しかも、推進機を強化すれば、垂直離着陸が可能なんだそうな。ステルス性も高く、レーダーにも映りずらいって。目下、米軍が、次世代輸送手段として研究開発中。
災害時に、これがあれば、道路事情とかに影響されず、1000トンの荷物の移動ができる(垂直離着陸式なら、場所さえ確保できれば、どこでも降りられるし、空中に浮遊したまま積み下ろし作業だってできる)。今般の交通の混乱を見ていると、これあれば大層便利だろうなあと思うことしきり。
あとは、おっかないのは、財務省である。
また、無人機の話もある(主に無人輸送機の話だが)。今般の原発の話を見ていると、ああいう危険地帯を偵察するための無人機は、空・陸問わず必要かもねえ。
4 今般の災害に際し、自衛隊が活躍しているが、今後、兵站の方面を強化するような予算の付け方をすれば、もっと改善できるのではと思った。
今回の災害に関し、関係各位のご努力には、敬意を表するところである。
紙の本

紙の本暁星記 1 (モーニングKC)
2010/12/19 09:08
巨大な森と矮小な人の話
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1 本書は、ある部族の中で生きる少年の成長譚である。
2 少年の世界では、深く大きな森の中で、神話の世界の猛獣に似た動物が跳梁跋扈し、人間なんぞ、実に、弱く小さな存在である。縄文時代か、アマゾンのジャングルかといった風情だが、部族の風習、風俗が非常に細かく書かれており、とんでもない話なんだけど、リアルに感じられる。特に、結婚関係の習俗は、今なら漏れなく人権団体が反対するところだが、このような結婚形態をとっている部族というのは、結構あった。生産性が非常に低く、人間が死に易い世界なので、父、母、子(あるいは祖父母)という役割は、個人ではなく、集団で考えないとまずいのだと思う。
3 もう、この本は、御用とお急ぎでない方は、実際、読んでくださいとしかいえませんなあ。アイアムアヒーローもそうなんだけど、詳しく書くとネタばれになってしまうのである。
4 なお、漫画の絵は当初は、なんかコミカルですが、巻数が進むに従って、だんだんとシリアス展開になるに従い、絵の方もシリアスになっていきます。ご安心を。
