ももんじゃ05号さんのレビュー一覧
投稿者:ももんじゃ05号
紙の本

紙の本信州日帰りでゆく温泉
2010/09/12 14:52
信州信濃の温泉地
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1 本書は、下記掲載の著者HPから、長野県の日帰り温泉を選集及び加筆・修正した本である。各地方ごとの温泉が掲載されている。
2 日帰り温泉とは、宿泊を伴わずに利用できる温泉で、リーズナブルな価格(500円前後)なのが特徴である。
著者は、弁護士であり、多忙な中、休日を利用するなどして、長野県内の様々な温泉へ出かけておられる。すごいのは一軒一軒ちゃんと行ったところを掲載しているところである。
なかには、接見(警察署などの刑事施設に勾留されている被疑者や被告人に面会すること、警察への接見だと、夜中に行くことが多い)に行った帰りなどに遠隔地の温泉に入っておられるみたいである(著者HP参照)。
3 法学部で温泉と言えば、富山の宇奈月温泉である(権利濫用に関する重要で古い判例があり、民法やるとかならずやるから、みんな知っている。弁護士業界の合宿は、宇奈月温泉でやることが結構多いのは、我妻先生の功徳である)。また、全国的には、伊豆やら別府やら草津やらが有名である。
しかし、一番温泉地が多いのは、静岡や大分ではなく、北海道なんだそうである、面積も広いし、有名な火山も多いのである。そして、次点になるのが、本書で紹介される長野県なのだそうな。
長野県の温泉地は、有名どころだと、諏訪、上田、野沢温泉、松本(白骨とか)などがある。もちろん地方によって、泉質は違うが、なかには、同じ地方内にあっても、源泉の場所によって、お湯の泉質が違ったりするんだそうな。
また、長野県内には、面白いところに温泉がある。長野県らしく山小屋にあったり、銭湯みたいな温泉があったり、また、中央道のサービスエリアにあるところもある(諏訪湖サービスエリア)。
4 温泉に入って外の景色をみながらぼけーっとしていると、難しいことなんぞどっかいってしまって大変よろしい。
これから秋に向かうが、温泉入って、ビール飲んで、うまいものくって、のんびりするのがこの世の極楽ですなあ。
旅のお供に本書をいかがか。
紙の本

紙の本伊達政宗の手紙
2010/06/10 20:07
独眼竜、かく書きたり
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1 本書は、戦国大名伊達政宗の手紙を集め、その人となりに迫ろうという本である。今回めでたく復刊された由。
2 伊達政宗というと、母親(義姫)や叔父(最上義光)と仲が悪く、弟を手にかけ、親父も撃ち殺し、また、ときには虐殺までしたという名うての戦国大名である。遅れてきた織田信長の感がある。また、江戸時代には、いい年をして、方々に迷惑をかける困った爺さんな側面もあった。
そうすると、なんだかとてもおっかなくて、冷徹な感じや、性格悪いんじゃないかという気がする。しかし、戦国大名は、一国の主である。主だったら冷厳なだけでは、部下はついてこない。手紙をみると、伊達政宗、実際には、結構、細かいところに気配りができて、お茶目な人だったらしい(織田信長も、お茶目だったそうだが、あと、甘党だったそうな)。
大体、人の気持ちがわからない奴に、戦争や謀略はできないのである。
3 紹介される手紙の内容はいろいろある。部下に対する命令書のような公的文書、戦死した部下の親に宛てた手紙、母親や子供への手紙(仲そんなに悪くない? )などなど、それこそいろいろあるのである(書中に秀吉に対する感想を書いたものもあって興味深い)。
ただ、部下への命令書といっても、側周りの連中に対して出すのは、茶目っ気が効いていて、ご本人も面白がって書いているような雰囲気である。
さらに、なかには、小姓(男性)へ送った浮気の弁解の手紙なんかもあって(武田信玄と高坂弾正の間にもこんなんあったが)、えらい人はこんなもんまでのこってて大変だなあと思う。
4 領主として、あるいは上司として苦悩し、子供や親を心配し、それでも豊臣、徳川の荒波を乗り切ったという伊達政宗。英雄もやはり人間である。現代人と苦労のしどころ、喜びどころはあんまり変わらないかもしれない。
紙の本

紙の本マンガ日本の古典 23 三河物語
2010/05/19 23:29
忠義の行く末
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1 本書は、大久保彦左衛門忠教が記した三河物語を漫画化したもの・・・ではない。本書のあとがきにも書いてあるが、三河物語がおもったよりつまんなかったので、大久保彦左衛門が三河物語を書くにいたった経緯と、一部原著の面白いところの抜き書き、脚色をしたものである。
2 三河物語というのは、戦国時代から江戸時代へのちょうど端境期に生きた一人の老武人の心持を記した本である。
大久保一族といえば、三河以来といわれた譜代の中でも抜群に古く、勲功多く、忠節を尽くしてきた一族である。上り藤に大の字は伊達ではない。
しかし、戦国時代が終わりに近づき、江戸時代が近づくと話が変わってきてしまった。大久保一族の嫡流は、大久保忠隣であったが、権力闘争に敗れ、改易の憂き目を見てしまう。
他方、一向一揆に参加し、家康に敵対した揚句、三河を出て行ってしまった本多正信の一族が、今度は、権力の座についた(帰参には忠隣の父、大久保忠世の世話になっている)。
大久保家からすれば、何たることかというところである。
3 また、世の中は、でかい戦がなくなり、武辺者は、次第に隅に追いやられ、文官ばかりが重用されるようになってきた。
世の中の流れの中での武辺者の地位の後退と、自身の一族の没落が一緒に来てしまったのである。
だから、原著は、基本愚痴である。一番苦しいときにお家を支え、命をかけて戦ったのに、老境に至って、遠ざけられ仕打ちを受ければやむを得ないところである。
4 ところで、本書には、太助が彦左衛門のわらじとりとして出てくる。この人は、終始なんだかんだいっても殿様を慕っている。しかし、この人の彦左衛門に対する感情は、彦左衛門個人に対する敬慕というようなものであって、忠義ではない。
他方、彦左衛門が、自身や他人に求めるのはお家に対する忠義である。この辺の違いから、太助は、魚屋になったんだと思われた。
紙の本

紙の本戦国武将兜百撰 ビジュアルガイド 伊達政宗 豊臣秀吉 織田信長 上杉謙信 徳川家康
2010/06/06 13:02
鎧兜 入門編
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1 本書は、戦国武将及びその所用する鎧兜につき、写真入りで解説した本である。
2 武将の鎧兜は、かなり奇抜である。武将の職場は、戦場である。したがって、自分の武功を喧伝するため、派手な方が目立つのである。
また、生死のかかるところなので神仏の加護を受けるため、宗教的な兜を着用したり(有名どころだと片倉小十郎の「愛宕山大権現守護所」との護符が前立になっている兜)、縁起のいい動植物をあしらったり(熊、兎、ナマズ、ときには毛虫など。佐竹義重、義宣の前立て、モップみたいだと思ってたが毛虫だったんだ)、不退転、死を覚悟して戦うことを示すため死を連想させる模様もある(ドクロ。SSみたいである)。中には自分の孫の名前を書いた前立(本多富正所用)なんかもある。
3 本書は、織田、豊臣、徳川などの有名どころやその配下のあんまり有名でない武将も含め、武将の鎧兜をまとめている。鎧兜の種類、用語等についても若干の説明もあり、つらつらみるものとしてはおもしろい。
4 ただ本の主題からして兜中心なのでしょうがないのかもしれないが、鎧については全部写っている写真が少ない。あと、どうしても織豊、徳川の武将の鎧が多く、それ以外の地方は少な目である。
まあ、本体価格571円である。入門編としていかがでしょうか。
紙の本

紙の本捜査不能 沈め屋と引揚げ屋
2008/03/17 23:31
実録! 手形訴訟
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1 本書を知ったのは、この本に書かれていたからである。そう、捜査(推理小説)だからたって、刑事訴訟じゃないのである、主題は民事訴訟である(詐欺事件なので刑事も関係あり、警察も出てくるが)。
著者は、知っている人は知っていると思うが、弁護士さんである。だから、ここらの法律の話は正確である。
2 事件は、京都の老舗お香屋さん(株式会社)のボンボン(専務取締役)が、競馬のための金欲しさに自社の手形をちょろまかし、これを金融屋に流してしまったことから起こる。
この手形債務が、当該会社ではとても払えない量。そこで、父親である社長が、出入りのコンサルタントと一計を案じたことから話がややこしくなってきた…。それではと、満を持して主人公の弁護士の登場である。
弁護士先生はいろいろ手を尽くす、手形の満期はじりじり迫る、不渡り出したら倒産である。一方、これを妨害しようとする輩も現れる。社長は困り、捜査は進まず、金貸し、詐欺師に、ヤクザも動く、そして、ついに人も死ぬ。話はだんだん佳境に入っていくのである。
3 最近、手形をそんなに使わなくなってきたが(使う人は使うが)、この手形、便利なのだが(手元に現金を持っていなくてもよい等)、その便利さの反面危険もある。その危険性が現れた話。
普段の生活からはなじみがない話なので、若干とっつきにくいかもしれないが、特に法学部の学生の人とかだったら、手形訴訟で何をしなければならないか、また、裁判における手続きの流れもわかってその面からも面白いかと思う。
なお、出てくる法律は古い。民訴も旧民訴、会社法じゃなくて旧商法である。
4 法律は、かわいそうな人を守るものではなく、法律を守った人を守るものである。桑原桑原。
紙の本

紙の本令状請求の実際101問 改訂
2011/07/02 10:25
判例・通説 令状請求
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1 本書は、検察庁の偉い人が、警察官向けに書いた令状請求(現行犯逮捕とかも含むが)に関する本である(立花書房だしな)。
2 本書の特徴は、警察官向けに書かれたというところである。これ、何が言いたいかというと、内容は、判例通説べったりなのである。令状請求段階でポカやって、あとあと違法収集証拠排除とか、毒樹の果実とかいわれるとこまるので、判例・通説に沿って書かれている。したがって、初めて刑訴を勉強したりするのに丁度いいのである(まあ、実務やり始めてから、調べ物にもいいんだけど)。
分量も、1つの論点あたり2頁くらいで適量である。
しかも、論点になりそうなところは、たぶん全部書いてあるという優れもので、これ一通り読めば、令状請求関係は、おさえたことになるであろう。
3 元はといえば、この本は修習中に、検察起案の勉強のために推奨された本であった。法律の知識というのは、司法試験の論文が終わった直後が、一番あるといわれている。修習にいくと,別の勉強が必要になったり(自賠法とか、破産法の知識が結構必要になるし、実務上の手続きは、実体法の勉強とは全然別である)、開放感から遊び出したりするので、法知識がだんだん減退してくる。そして、後記修習になって、各試験の起案をするときに、はたと困るのである。
その際、記憶を喚起するのに、本書は非常に役立ったため、この書評を書くところである。
4 初学者から修習生まで、結構お世話になれる本である。価格も、1300円(税別)である。公判前の話がよくわからんという人は、どうぞ。
紙の本

紙の本世界ファシスト列伝
2010/05/27 22:53
悪魔が来たりて、ピ~ヒョロロ
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1 本書は、第一次大戦後から第二次大戦にいたるまで世界のいたるところにいたファシストの紹介をした本である。
2 ファシストは、大まかにいえば、独裁主義で、統制経済を目指し、対外膨張論をとる連中である。第二次大戦でいえば、日独伊である。
しかし、世界にはいっぱいファシストがいた。スペインやポルトガルは結構有名(フランコ、サラザール)だが、自由の国アメリカにもいたし、戦勝国のフランスにもいた。さらに、東欧にも、北欧にもいた。南米にだっていて、しまいには政権までとってしまった。
3 西欧列強、第一次大戦が終わり、ようやく助かったと思ったら、世界恐慌が襲ってきた、これは、戦勝国、敗戦国構わず襲ってきた。命をかけて戦った兵士や困難に耐えた銃後の生活を苦しめた。しかも、第一次大戦後は、民族自決が流行り、帝国主義に対して疑問投げかけられ、さらには、共産主義が流布し、財閥や地主の権益を脅かすようになった。上も下も天変地異のごときである。
4 そこで出てきたのが、ファシストである。強い政府を標榜し、帝国の瓦解を防いだり、また、失った自尊心を取り戻そうとしたり、果ては、ブロック経済を打開するため、戦争起こした(ドイツの旧領土回復、イタリアのアビシニア占領、日本の満州事変。ただ、この手の国は、植民地をあんまり持ってなかった国(新興の帝国主義国ないし第一次大戦で大損した国)であり、大型の帝国主義国(英米仏あとロシアの遺産を継いだソ連)が、善良だったわけではない。第二次大戦は、現状維持組と現状打破組の争い…と国際政治史の授業で習った)。
5 人間、つらい時に悪魔が神に見えてしまうときがある(まあ、共産主義もおんなじようなもんだったが)。
試験中に、パッとひらめいて、俺って頭いいと思って書いた答案は、大概間違いである。
その間違いが、世界中で起きていたというお話である。桑原、桑原。
紙の本
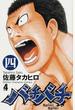
紙の本バチバチ 4
2010/05/03 23:50
ギラギラでバチバチでボコボコ
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1 本書は、元大関の父親を持つ主人公が、角界に入り、横綱を目指し、戦っていくという話である。
本書の主人公の父は、悪たれ大関と渾名され、強いが素行が悪かったため、広くお茶の間の皆様、角界関係者の方々に毛嫌いされたり、尊敬されたりした人であった。最終的には、暴行事件を起こし、角界を追放されてしまうのである・・・って、なんかどっかで聞いた話だが、こちらの漫画のほうが先である。
2 さて、相撲漫画というとああ播磨灘とか、ごっちゃんとか、力人伝説(作画は小畑健氏)とかがあった。このうち、ごっちゃんと、力人伝説は、少年ジャンプで連載していたのだが、少年誌で相撲漫画というのいうのは、なかなかしんどいものがあるらしく、両方ともそんなに連載しなかった。
でも、面白いんですよ、相撲って。昔は、何が面白いのかよくわからなかったんですが、年取ると、面白くなりますな、あれは。
3 本書は、単にスポコンだけに終始せず(そういう要素も多分にあるが)、相撲の技術的なところにも話が及んでおり、楽しい。
武道武術の類は、基本的に技術である。力ばっかりでは、なかなか思うようにいかん。初代若乃花だったと思うが、「頭で考えているうちはだめ、体が勝手に動くようになるってようやく武芸」と言っておられたが、これは他の武道武術でもいえるところである(昔、イギリスのSASのナイフ訓練の映像を見たことがあるが、型稽古だった。急場に、体を反射的に動かすためには反復練習が必須である)。
4 現在のところ、一番の男前はアゴンの兄さんである(私見)。空流部屋の親方もかっこいい。まだまだ序の口だが(番付的に)、長期連載していただき、横綱になるところまでやってもらいたいところである。
