Yoshさんのレビュー一覧
投稿者:Yosh

空飛ぶ広報室
2013/03/02 11:01
何という清廉な人たち
18人中、18人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
電子書籍サイト「E★エブリスタ」連載(2010年6月~2011年5月)分に、書下ろしの「あの日の松島」を併せ、単行本として刊行。
デビュー作『塩の街』に始まり『空の中』『海の底』と続く「自衛隊三部作」、自衛隊員を主役にした大甘ベタベタの「自衛隊ラブコメシリーズ」(『クジラの彼』『ラブコメ今昔』)、そして御存じ「図書館戦争シリーズ」と、自衛隊を素材にして快作を次々とものにしてきた有川浩が、またも目も覚める様な――勿論致死量一歩手前のベタ甘満載の――自衛隊員群像純愛ドラマの秀作を生み出した。
今回の舞台は航空自衛隊広報室。不慮の怪我でパイロットの職を断念せざるを得ず、失意のまま空自広報室に配属された空井が主人公である。そもそも、空井の上司鷺坂のモデルとなった人に、空自の取材を誘われたことが執筆の発端になったそうだ。
航空自衛隊という存在を認知してもらい親しみを覚えてもらうため、「商品」としていかに売り込み広報するか?取材に2年もかけただけあって、広報官として活躍する自衛隊員の描写は、臨場感に溢れリアルそのもの。
本書は、元々は2011年夏に刊行される予定だった。ところが、「3.11」による自衛隊災害出動を目の当たりにして、著者は刊行延期を出版社に申し入れる。結果、刊行は一年延びたけれども、最終章「あの日の松島」が加わることで、美しく感動的な――涙無しには読めない――フィナーレが誕生した。後は読んで、有川ワールドに骨の髄まで浸ればいいだけである。
蛇足を二つほど。
ラブコメ度を期待している方々へ――P98「頭にぽんと細い手が乗った。あやすようになでる」という一行が、P419「わたしがなでたいのでなでます」という台詞に結びついた時の甘酸っぱい、されど清冽な感動を堪能して下さい。そして更に、P452の台詞が加わった時、目頭が熱くなる――人によっては号泣?――ことを保証します。
自衛隊という組織の存在に、イデオロギー的観点から批判的な方々へ――自衛隊の肯定否定はひとまず保留し、P452「そこまで見知らぬ他人に尽くせるものだろうか」という言葉に刮目して下さい。著者が、小説主人公のモデルとなった人々に対し、真摯に感謝と尊敬の念を表明していることが伝わってきます。

社会を変えるには
2012/11/10 17:32
アンガージュマン
12人中、12人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
気鋭の社会学者小熊英二(おぐま えいじ)氏が書き下ろした、読み応え十分の「新書」である(「 」をつけたのは本書が500頁を超える大作だからで、優に単行本で出せる分量なのに敢えて新書で出したのは、価格を抑える為だろうか)。「3.11」以降脱原発のデモが数多く行われていることを受け、デモで社会は変わるのか?もし無理なら、変えるにはどうしたらいいのか?そもそも社会を変えるとはどういうことなのか?といった極めて素朴で、根源的で、重要な問いについて考えてみよう、というのが本書の趣旨である。
話し言葉で書かれているから読み易いが、中身はこの上なく濃い。まず第1章で日本社会の現状を概観するが、この章が実に素晴らしい。大学の先生とはとても思えないほど、平易な語り口で大きな問題を分かり易く解説していて、この章だけでも本書を買う価値あり。第2・3章では社会運動の歴史を、第4~6章は民主主義の歴史を振り返り、第7章で視点をもう一度現代日本に戻す。
読み終えて、何故本書が通常の社会学の本より遥かにとっつき易いかを考えてみた。語り口の易しさも勿論一つの理由だが、最大の理由は、筆者が市井の人々の姿勢・視点で書いているからだと思う。大学のセンセ方は、自分の為に、学会ムラという内輪・サークルの為に書くことが主目的となり、自分の研究が社会や市民とどう関わるのか、どのような形で社会・市民に還元できるのかを考慮しないことが往々にしてある。小熊氏は違う。自分も一市民であり、共に今日本で起きていることを考えていきましょう、どういうことが起きていてどう対応すればいいのかを一緒に議論していきましょう、という姿勢が一貫しているのである。反原発運動に積極的に参加――単なる支持ではない――する行動性からしても、「アンガージュマン」という懐かしい言葉を使いたくもなる。
「もし本書の内容がいいと思ったら、私を講演に呼ぶより、読書会を開いて討論するほうが、本書で私が言いたかった趣旨に沿うと思います」とあとがきにあるように、今の日本社会を理解するための「思考や討論のたたき台」として、大きな示唆を与えられた書物である。

別冊図書館戦争 2
2011/10/10 12:41
<図書館戦争>サーガ外伝 其の弐 A
10人中、10人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
『戦争』『内乱』『危機』『革命』全4巻で図書館戦争シリーズは目出度く完結したが、『別冊』2巻は番外編として、4巻の流れの合間に図書館内外で起こった様々なエピソードを収録している。
本を開くと、本文が始まる前のカラー・イラストにこんな文章が引用してある--「終わった恋に望むとすれば--君に幸あれ。ただそれだけを。/二人の未来が真っ白だった頃のように、君が幸せであればいい。願わくば君の隣に優しい誰かがいて、君の夢を見守ってくれていることを。そしてどうか俺がここで君の本も守ることを許してくれますように」
はっきり言って、これだけ読めば歯の浮くような文言である。この甘ったるさに辟易する人も少なからずいるだろう(筆者もしかり)。ところが、である。第1話「もしもタイムマシンがあったなら」を読み進め、終盤近く(P57)にこの一文を再度見つけた時は、胸にグッとくる。古今東西恋愛物語の構造は至ってシンプルで、ハードルが高ければ高いほど走者にとっても観客にとっても盛り上がる、謂わば障害物競争のようなものだ。問題は、この実に単純な物語構造(骨格)にどう肉付けするかなのだが、その肉付けの過程で有川浩が見せる表現力の深さとテクニックの卓越さは只事ではない。冒頭の引用文に見られる、一見陳腐なロマンス設定を、どう活性化しどう血肉化するか--それが抜群に上手い作家である。
加えて、登場人物は皆真っ直ぐである。生きることにも、勿論恋することにもひたむきに、真剣に向かっていく。変に斜に構えたり、ゲージュツっぽく難解な言辞を垂れ流したり、単なる風俗小説的に表面をなぞって生きるのではなく、読み手の心に正攻法で立ち向かってくる。だから、例え作りものではあっても、作り話の中で息づいている主人公たちの(ひいては、そこに込められた作家の)真摯な姿勢と思いを本能的に感知して、素直に感情移入できる。本書の後半は、筆者の御贔屓柴崎が主人公となる。そこで柴崎が置かれる状況の過酷さは、そこまで描かなくてもと思うほどだが、その艱難辛苦を克服していく過程は、真っ直ぐに生きる人たちのみが成しうる高貴さと輝きに満ちている。
辛いことの多い人生を生き抜くには、有形無形の絆が不可欠である。郁と堂上、郁と柴崎、柴崎と手塚を始めとして、このシリーズに生きている人達は、その「絆」が生み出す力と素晴らしさを読み手に再認識させてくれる。しかも、極上のエンタテインメントという形で。

図書館戦争
2011/07/10 17:31
<図書館戦争>サーガ エピソード1
11人中、9人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
有川浩の人気を一気に爆発させた『図書館戦争』シリーズが文庫化されたので、これを機にこのシリーズを一冊ずつレヴューしてみよう。
「文庫本あとがき」で著者は記す――“(本書の企画を渡された)担当さんは電話のむこうでしばらく考え込み、「…ごめん。これ、面白さが私にはちょっと分からないんだけど」/図書館で戦争。月9連ドラ風で一発GO!と実質二行のプロットを受け取ればまともな人の反応はこんなもんでしょう”
例えば、“サメが海水浴場を襲う。男3人組が退治しに行く”とプロットをまとめたところで、スピルバーグ『JAWS』の手に汗握るスリリングな面白さと興奮が全く伝わらないのと一緒で、「担当」氏の反応はゴクゴク全うである。では、この「二行のプロット」を血肉化するため、有川氏はどういう戦略をとったか。
まず凝りに凝った会話を武器にしたことである。プロットの骨格だけ取り出せば相当大甘の月9風ラブロマンスだが、著者はこれをキャラ達の絶妙の遣り取りで一気に読ませてしまう。月9が、“俳優が口にする言葉を、音声として視聴者が聞き取ることを前提として書かれた(活字で読めば相当ベタな)セリフ”であるのに対し、本書は、“読者が活字として読み取る際、微妙なニュアンスや言葉の端々に込められた感情の見え隠れ、意外性等々を頭の中で咀嚼して初めて面白さを堪能できる台詞”として書かれている。従って、会話が内包しているこの面白みは、そこに込められた感情の吐露や、諧謔味、知的ヒネリ等々を読者が理解した後――一瞬のタイムラグを置いて――読者の心中に沸きあがってくる。月9など及びもつかない相当高度な技を駆使して、会話を成立させているのである。
このキャラなら、こういう内容を、こういう言葉にのせて、こんな口調で語るだろうという読者の予想を、様々な形でフェイントをかけて裏切りながら物語を進行させる手腕は、大したものだ。ぼく自身、単行本で刊行されて読んだ時よりも今回再読した時の方が大笑いし、時には胸熱くさせられた。
もう一つの戦略は、「図書館」を舞台に設定したことである。朗読CDではなく電子書籍でもなく、わざわざ単行本なり文庫本なりを手にとって読むのだから、消費者(=読者)がある水準以上に本好きであることは自明の理である。この自明の理のど真ん中を著者は意図的に撃ち抜いた。音楽ではなく、映画でもなく、スポーツでもなく、わざわざ書物を読むために相応の時間を費してくれる人間は、皆基本的に本好きである。そして本好きならば、生涯のどこかの時点で図書館のご厄介になっている公算が高い。娯楽が山ほどあるこのご時勢においてわざわざ本に時間を費やそうという人間にとって、「本」と「図書館」を守ろうというプロットが琴線に触れないわけが無いではないか。
これが地球だったり、男女の愛だったり、正義だったりすると異論百出だが、「本」「図書館」を素材にした時点で、読者はこの物語に素直に感情移入させられる。図書特殊部隊および図書館員の全員に対し、無条件でエールを送る。この大前提に読者を無条件降伏させたうえで、男女の愛や正義まで注入するのだから、読者は著者のなすがままに、感動と興奮を増幅していくだけだ--。まことにもって周到な戦略である。
本を愛する全ての人間に手にとって読んで欲しい、実に愛おしい一冊。

あの日からのマンガ (BEAM COMIX)
2011/12/13 19:50
「あの日からの日本」を生きる全ての人へ
7人中、7人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
「3・11」以後、著者が「朝日新聞」(夕刊連載『地球防衛軍のヒトビト』3月15日~5月21日掲載分)、「コミック・ビーム」(5月号~8月号掲載の短編4話)、「小説宝石」(『川下り双子のオヤジ』5月号~7月号掲載の短編3話)、「TV Bros.」(『はなくそ時評』4~6月掲載の6篇)に発表した、東日本大震災および福島第一原子力発電所事故をテーマにした漫画を収録。
或る女性作家が、3・11直後にこんなことを書いていた。医者や消防士、自衛隊のような手に技術を持つ人達は、被災地に行っても即戦力としてすぐ活躍し、貢献することが出来る。それに引き換え、そういう特殊技能を持ち合わせていない作家などは何の役にも立たず、せいぜい本の朗読くらいしか出来ることがない――。
別に作家に限らず、これは震災後に殆どの日本人が共通して抱いていた悔しさ/切なさだと思う。未曾有の大惨事を目の当たりにし、自分に何が出来るのかどんな風にお役にたてるのかと自問自答してみても、その答えが見出せずただ途方に暮れるだけ。募金をしたり救援物資を提供するだけでいいのかと、己の無力さ/非力さに歯軋りするくらい情けない思いをした人は多い筈だ(少なくとも、ぼくは強い無力感に打ちひしがれた)。
しかし、作家や音楽家といった「表現者」は普通の市井の人々は異なり、直接的/一次的救援活動こそ出来ないが、被災された人々を始めとする多くの人々を励ます間接的/二次的(精神的)支援をすることは出来る。そして場合によっては、この災害――特に原発事故――の本質を分析して世に問うたり、意見を広く表明することが可能である。しりあがり氏の凄いのは、「3・11」に真正面から向き合って作品を描き始めた時期の早さと、量と、アプローチの多様さである。今となってはどうとでも言えるが、地震直後に――大多数の「表現者」が、何を、どう表現していいか分からず茫然自失・躊躇している間に――猛然と創作活動を始め、しかも極めて質の高い作品を連打したことに目を見張る。
ぼくも愛読している『地球防衛軍のヒトビト』は脱力系半歩手前のゆる~いユーモアとペーソスを基調としている四コママンガである。震災以降の掲載作でも基本テイストは変わっておらず、著者自ら4月上旬現地へボランティアに赴く経緯を描いた一連の作品も、「珍道中」的興趣に溢れていて、その変わらなさぶりにどこかホッとさせられる。しかし、であるからこそ、5月2日、6日、7日掲載分(本書P53~P54)は極めてショッキングである。ゆるいテイストを貫いていたしりあがり氏ですら、その手法を放棄せざるを得なくなった事実に、読者は、生半可な想像では及びもつかない現実の過酷さを否応無く知らされたのである。
『地球防衛軍のヒトビト』が日常ユーモアスケッチであるのに対して、「コミック・ビーム」掲載の四篇は、しりあがり氏のもう一つの側面――『真夜中の弥次さん喜多さん』や『メメント・モリ』がその典型だが――シリアスでシュールでブラックな思索と方法論が一気に炸裂する。中でも『×希望』は、「表現者」ならではの想像力を駆使した一つの成果で、とりわけラストカットが衝撃的だ。その一方で、3・11後の日本の未来をSF的に描いた『海辺の村』、東京を捨て東北で子供を生むことを決意する女性の物語『震える街』、台詞が全く無い『そらとみず』の三篇は、過酷な現実を描きつつも、それを乗り越えんとする作者の真摯な祈りが、赤裸々に、顕わになっている。特に『そらとみず』は、無辜なる民への鎮魂歌(レクイエム)とでも呼びたい荘厳かつ哀切な作品で、自然と敬虔な想いにさせられる傑作である(宮崎駿『風の谷のナウシカ』を連想した人もいるだろう)。
本書『あの日からのマンガ』は、「あの日からの日本」を決して忘れることのなきよう、日本内外で暮らし日本を愛する全ての人々が、今読むべき一冊である。

図書館革命
2011/08/21 08:30
<図書館戦争>サーガ エピソード4
9人中、7人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
有川浩の人気を一気に爆発させた『図書館戦争』シリーズが文庫化されたので、これを機にこのシリーズを一冊ずつレヴューしてみよう。
第1巻『図書館戦争』・第2巻『内乱』で図書館支持派vs.反対派の物語を、第3巻『危機』で表現の自由という問題を描き、問題の対象を次第に包括的に拡大していった筆者は、シリーズ最終巻である本書で<検閲>問題に真正面から向き合っている。
物語はまず、福井県の敦賀原子力発電所がテロリストに襲撃されたところから始まる(本書が刊行されたのは2007年だが、3・11の後ではこの設定を絵空事と気楽に読み飛ばせなくなってしまった)。この原発テロの状況が人気作家のベストセラー小説に酷似していたことから、メディア良化委員会は作家の身柄を拘束し、ひいては<作家狩り>が可能になるよう企む。著者の安全を確保すべく図書隊は出来る限りの手を打つが、状況は刻一刻と悪化。窮地に陥った図書隊は、起死回生の大胆な策を打つことになる・・・。
一冊の書物が原発テロの教科書になった可能性があるという「特殊性」を建前にして良化委員会が作家狩りの「最初の事例」を作ってしまうと--そして一般市民もこの事例の場合は表現の自由の規制もやむなしと納得してしまうと--あとはTV・映画・雑誌・書籍等の全メディアはメディア良化委員会の思うがままに屈伏させられる。そうはさせじと、図書隊が必死で抵抗するわけだが、フォーサイスやクランシーのような所詮対岸の火事の謀略小説と違って、この問題は他人事ではなく、しかも現実に起こる可能性が充分あることから、生々しく切実な問題を読者に突き付けてくる。成程、著者が最終的に切り込みたかったテーマはこれだったのかと、此処に至る過程と物語の組みたての緻密さに改めて舌を巻く。
されど、ガチガチの硬派エスピオナージュかというと勿論そうではないわけで、「月9連ドラ風で一発GO!」のノリは加速度を増し、いよいよクライマックスへと突入する。郁が堅い謀略物を読んでいることを堂上に意外がられて、「難しいことは全部飛ばし読みです。完全にキャラ読みですが何か?」(文庫版28頁)と応答する場面があるが、これなどちょっぴり自虐めいた著者の内情晴らしではないかと思う。
堂上との××シーン(249頁)には思わず胸が熱くなるし、物語最大の山場である二人の逃避行(第4章)は、著者の実体験を重ねただけあって迫力満点。加えて、個人的御贔屓の柴崎は本書でも大活躍で、検閲を巡るハードボイルドな遣り取り(76頁~)など痺れるくらいカッコイイ!
番外編はあれど、シリーズがここで終ってしまうのは本当に寂しいが、稀にみる「立った」キャラ達のその後およびスピンオフを読者一人一人が想像することで、このシリーズを末永く楽しみたいと思う。

阪急電車
2012/03/09 15:47
電車が奏でる「ディヴェルトメント」
6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
幻冬舎の隔月刊雑誌「パピルス」11号~16号に掲載されたものに、折り返し分を書き下ろして単行本として刊行。
西宮北口と宝塚を結ぶ、片道15分わずか8駅しかない阪急今津線。実際に今津線沿線に住んでいるという著者は、この路線を舞台にして長編を書いた。複数の事件が同時進行するミステリーをモジュラー型と呼ぶが、本作は更に手が込んでいて、電車が一駅ずつ進むにつれて(空間移動)、様々な人物が乗り降りし(複数の物語の同時展開)、登場人物が内包する物語が語られ(現在と過去のフラッシュバック)、登場人物がふとした偶然で触れ合う様を視点を変えながら語っていく(エピソードの重層化)。
こんな風にしたり顔で分析しても面白くもなんともないが(苦笑)、実際読んでいくとその物語展開は唖然とするほど緻密で、その水際立った上手さに唸らされる。連作短編のように一話読み切りではなく、小さなエピソードが少しずつ重なり合い、次第に大きな物語世界に結実していく様は、様々な主題が重なり変奏されるシンフォニー、いや、そこまで仰々しくはなくもっと軽やかな楽しさに溢れているので、ディヴェルトメント(嬉遊曲)と呼ぶに相応しい。本好きが縁で知り合った征志とユキ、彼氏を寝取られ「討ち入り」を果たした翔子、イケメンの彼氏のDVに苦しむミサ、年上の彼氏の「アホ」さ加減をあっけらかんとネタにするえっちゃん、軍オタの圭一と美帆の初々しい恋心等々、「乗客たちがどんな物語を抱えているか――それは乗客たちそれぞれしか知らない。人数分の物語を乗せて、電車はどこまでもは続かない線路を走っていく」のである。
正直、西宮北口から宝塚までの物語だけでも充分読みごたえはあった。ところが、何とも嬉しい事に、筆者はその半年後の彼/彼女たちの姿を、今度は宝塚から西宮北口に向かう電車の中で展開してみせてくれる。この「折り返し」によって、本書は秀作から傑作の域へと昇華した。元来有川氏は、『クジラの彼』や『別冊図書館戦争』が如実に示すように、前日譚・後日譚に抜群の冴えを見せる作家である。本書も、この後半部の展開において、前半で紹介した人物やエピソードをさらに掘り下げ、しみじみした人生の機微を味わわせてくれる。思うに、有川氏は、物語に出てくる各々のキャラクターを相当深くかつ細かく設定しているので、物語中ではその断片しか読者は垣間見る事が出来なくとも、断片が断片にとどまらず、断片からその人物の全体像と真の姿を読者は感じ取ることが出来るのであろう。
ちなみに、武庫川の中州に作られたオブジェの話が、物語の冒頭と結末に出てくるが、これがまた実に心地よい余韻を残すコーダとなっている。そう、本書は正に、電車に揺られ窓の外の変わりゆく風景を眺めながら聞く、「ディヴェルトメント」なのである。
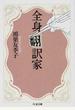
全身翻訳家
2011/09/23 21:11
名翻訳家の名エッセイ集
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
『嵐が丘』『灯台へ』の新訳等で知られる鴻巣友季子氏のエッセイ集。2007年刊『やみくも』(筑摩書房)に加筆・訂正し、多数のエッセイを追加収録した<リミックス>版。
一般読書人には余り知られていなかったであろう「Mainichi Weekly」連載エッセイ(毎日新聞さん、御免なさい!)も熟読玩味していた自称鴻巣ファンからすると、この半・新刊は美味しいエキスが充満した(自称他称)読書通が舌なめずりする一冊である。
まず、文章が上手い。これ見よがしの技巧過多のそれではなく、日夜横文字を縦文字にすることに腐心されていることで到達されたであろう、くどくなくサラっと読めてスッと頭に入ってくる達意の文体で書かれている。一例を挙げると、『真夜中のしめきり』中、娘さんが通っている保育園の「連絡ノート」を書く件:先日は、「お風呂で子どもが急に『ママ、お顔が汚れているからふいてあげるね』と言って、タオルでごしごしやってくれました。ただ、それは汚れではなく肌のシミだったのです…」という自虐ネタを書いたのに、先生から反応のコメントがなく、密かに傷ついた(『真夜中のしめきり』)。こういう文章は書けそうで書けない。今谷崎が生きていたら「新文章読本」に引用するんじゃないかと思える程。
次にネタが豊富。勿論翻訳に絡む話題は多いが、それだけにとどまらず、日常生活や食べ物・お酒等々、身辺雑記として池波正太郎や向田邦子に充分肩を並べる多彩さとそれに見合ったクオィリティの高さに唸る(左党の筆者は、幾つかのエッセイでもう喉が鳴ってたまらなかった)。
この面白さは実際読んでいただくしかないのだが、筆者が最も共鳴した作品を二つ挙げておく。一つは『なにもないことの恵み』--子どもを持つ親からすると、最後の4行に涙がこぼれそうになった。もう一つは『他者のことばを生きる』--翻訳家としての決意と矜持がさりげなく、されど明確に示されている。
ああ、自分ももっと言葉を磨かねば!

レインツリーの国 World of delight
2012/02/13 20:36
<図書館戦争>スピンオフから生まれた<純愛物語>
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
『図書館戦争』シリーズ第2弾『図書館内乱』(2006年、メディアワークス)に、図書隊員の小牧が幼馴染である毬江に『レインツリーの国』という本を勧めるエピソードが登場する。実は、この本が『内乱』では物語に重要な役割を――図らずも――果たすことになるのだが、その架空の本を、こうして現実の本として書き下ろしたのが本書である。
ある小説の感想を主人公がネットで見つけた事をきっかけにして、若い二人の男女が知り合う。最初はチャットだけだったが、男性の方が果敢にアプローチして実際に会うところまで漕ぎつけると、実は女性にはある秘密があった・・・。
出来れば一切の予備知識を持たずに読んで欲しいので、ネタバレを避けるため物語も極力ボカして書くが、人が人を愛するとはどういうことなのか、本当の愛情とは何なのかを深いところまで掘り下げた秀作である。有川浩の凄いのは、プロット的にはベタ甘の典型的ラノベであっても、かなり重いテーマを素材にしている事もあって、どんどん読者を引っ張り込み、その感銘の深さは純文学的の域にまで達している筆力である。
それと有川浩は会話が抜群に上手い。会話の巧さというと、向田邦子や山田太一の書いたTVドラマを筆者は真っ先に連想するが、今風のラブストーリーで、こんな風に鋭さと切なさとボケとツッコミをちゃんと同居させて読者を唸らせる作家は他にはいない。物語の発端がネットでの遣り取りというのも、後々重要な伏線として効いてくるし、「傷つけた埋め合わせに自信持たせてやろうなんて本当に親切で優しくてありがとう」などという鋭い怖いイタい台詞があるかと思えば、「今度は誰も見てないところがいいです」というごくごく平凡な台詞でジ~ンと痺れさせてくれるなんて、もうお見事!というしかない。そして最後に、ある言葉の意味が明らかになる。音楽でいえば、それまでの展開ですっかり満たされていたのに、追いうちをかけるように極上のコーダでさらに酔わされたような気分。
繰り返しますが、一切の予備知識無しでお読み頂きたい。
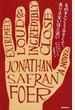
ものすごくうるさくて、ありえないほど近い
2012/01/08 11:27
「9・11」以降の世界を生きるということ
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
ニューヨークに暮す9歳の少年オスカーは、9・11テロで父を亡くし母と二人暮らし。偶然、父の遺品の中に謎の鍵を見つけた彼は、この鍵に合う「鍵穴」を見つけるべく、ニューヨークのアパートを訪れ始めるのだが――。
2002年のデビュー作“Everything Is Illuminated”(『エブリシング・イズ・イルミネイテッド』ソニー・マガジンズ、2004年)で一躍脚光を浴びたJonathan Safran Foer待望の第2作。前作は、ウクライナでルーツ探しをする米人青年の珍道中をオフビートのユーモア感覚で巧みに描いていて面白かったが、本作ではその語り口の巧さはますます冴え、「鍵穴を探すオスカーの物語」「オスカーの祖父から息子(=オスカーの父)への手紙」「祖母からオスカーへの手紙」――この三つの物語と時空間が、並行して進んでいく。作品主題としては、理不尽かつ無慈悲に人間を翻弄する歴史(の悲劇)ということになるだろうが、それをことさら厳めしく深刻に描くのではなく、さりげなくさらりと語っていくのがフォアの真骨頂である。三つの話しは各々語り口をがらりと変えている事に加え、視覚的仕掛けも相当手が込んでいる(タイポグラフィーや写真がふんだんに挿入される)。とはいえ、実験的過ぎて難解頭でっかちになることはなく、いい意味での軽みを失わない。
主人公オスカーの語りを現代版『ライ麦畑』に準える批評も多いが、確かに、他者とコミュニケーションが上手く取れず一人称で饒舌に語るオスカーは、もしホールデンが9・11以後のニューヨークに暮していればこんな風かも、というイメージにぴったり合う。しかしフォアは――21世紀に「9・11」以降を生きる人間として――サリンジャー以上に現代世界に生きる代償としての苦痛・過酷さを抱え、それを作品世界に投影することを余儀なくされる。或る意味、自分なりのやり方でイノセンスを求めていたホールデンが存在していた時代は、まだ大らかで幸せだったのだ。
KYで他者とコミュニケーションを取れないオスカーは、鍵穴を探し続けた結果、自分が用いるべき言葉を回復する。第二次大戦のドレスデン爆撃とヒロシマ原爆投下、9・11という「大きな物語」を背景に、オスカーや祖父母の「私の物語」をピンポイント的に描くことで、歴史が観念的なものでなく血肉化され、生き生きした形で読者に提示されていく様は見事である。
近年のアメリカ文学の大きな収穫と言える秀作。

クリスマス・エクスプレスの頃
2010/11/10 21:50
時代を超越した名作CM
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1987年春の国鉄民営化で設立されたJR東海は、88年12月にある一本のテレビCMを流した。83年に山下達郎が発表したアルバム『メロディーズ』に収録され、コアなファンからは高い支持を得ていたものの一般的には全く知られていなかった楽曲「クリスマス・イブ」。撮影当時15歳で、まだ全くの無名だった深津絵里。この二人のコラボレーションを主体にして、今や伝説となった「シンデレラ・エクスプレス」という素晴らしいCMが生み出された。
それから20年余。このCMの生みの親である三浦武彦氏と早川和良氏のお二人が語り合った『クリスマス・エクスプレスの頃』という本が出版された。本には、お二人が製作したCMも何本か収録され、「クリスマス・エクスプレス」は1作目と2作目(牧瀬里穂篇)が入っている。
まずは、DVDでこの2本の「クリスマス・エクスプレス」を観た。恥ずかしながら涙が流れた。20年前のこの頃、自分は何をしていたのだろうと、年甲斐も無く回顧的で感傷的な気分に溺れた。幾度も幾度も続けて映像を見た後、本も一気に読んだ。そして、このCMの成功は単なる偶然でなく、優秀なクリエーター達の苦労の産物、叡智の結集であることに感銘を受けた。でも、それだけでは、一本のCMが伝説となり、映画ならいざしらず、20年も経ってからわざわざ本のタイトルに冠せられるはずがない。
では何故このCMが「伝説」となり、社会現象にまでなったのか?何故今見直しても、当時見た時の新鮮な衝撃が蘇るのか?「時代の真空状態を埋めた」と三浦氏は語る。バブル絶頂期で日本中が浮かれていたあの時代も、一皮向けば不安と空虚感が支配していた。そういう虚飾の中に潜む孤独感を、このCMは見事に撃った。最後に人が拠り所とするのは、富でも名声でもなく、人と人の触れ合いから生まれるぬくもりであることを見事に証明(映像化)してみせたのだ。だから、今でもこのCMの魅力は褪せない。
当時このCMに心動かされた人も、名のみ知っている人も、この60秒のドラマを改めて体験して下さい。

タブーの正体! マスコミが「あのこと」に触れない理由
2012/05/17 20:53
タブーは密かに、されど着実に増殖中
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
月間総合雑誌として『文藝春秋』に次ぐ実売部数を誇り、黒字経営のまま皆に惜しまれて2005年に休刊した『噂の眞相』というアングラ的月刊誌が、かつて存在した。
『噂の眞相』(以下『ウワシン』)は、週刊誌『朝日ジャーナル』が休刊する際(1992年5月)その終刊号に一ページ広告を出し、『ジャーナル』にエールを送って終焉を惜しむと同時に、「しかし、まだ『噂の眞相』がある!」と怪気炎を上げていた。実は筆者はこの一頁広告で『ウワシン』の存在を初めて知り、早速一冊試し買いしてから熱烈な愛読者となった。スクープ記事を連発し、メジャー・マガジンへと躍進していった過程をリアルタイムで体験し、毎月最も発売日が待ち遠しい雑誌の一つだった。その『ウワシン』を陣頭指揮していたのがかの有名な岡留安則(おかどめやすのり)編集長、その女房役が川端幹人副編集長で、本書はその川端氏の新著である。『ウワシン』は、マスコミが絶対書かない/書けない「タブー」に数多く果敢に挑戦し、時には「タブー」側から激しい攻撃を受けてきたが、そういう修羅場を副編集長として数多く乗り切ってきた、いわば百戦錬磨のジャーナリストが著した本から、面白くない筈がない。
ここで取り上げられている「タブー」は、政治家や官僚をはじめ、電力会社、ユダヤ、宗教、AKB48等々多岐にわたっている。マスメディア内でタブーが増殖している現状を、「暴力」「権力」「経済」という三つの要因を軸に逐一具体的に検証していくと同時に、肝心かなめのメディア内の人間にタブー強化の自覚が無い事に、強く警鐘を鳴らしている。学者や評論家の分析と異なり、長年「現場」で身体を張ってタブーと闘ってきた川端氏が記す具体的事例には事実の重みがあり、思っている以上にタブーが肥大化・増殖している現代日本の姿が浮かび上がり、愕然とさせられる。
「あとがき」で川端氏が記している「へっぴり腰の闘い」という言葉が持つ意味は、限りなく重い。

壜の中の手記
2012/01/23 19:38
究極の<物語>、あるいは<物語>の究極
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
北村薫編の傑作アンソロジー『謎のギャラリー こわい部屋』(新潮文庫)に収められていた短編「豚の島の女王」で、ジェラルド・カーシュというとてつもない作家の存在を知った人は(筆者を含め)多数いると思う。そのカーシュの短編集が、晶文社ミステリの一冊として刊行された。
とにかく、<物語>の面白さ――着想の奇抜さといい、語り口の巧みさといい、オチのつけかたの見事さといい――を骨の隋まで味わわせてくれる。一時一世を風靡したラテンアメリカ文学のマジック・リアリズムで書かれた最上の作品--これに匹敵する極上の奇譚が、此処にはひしめいている。ブラック・ユーモア、シニシズム、ファンタジー等々、読む人によって名称は異なるかもしれないが、<物語>が持つ力を信じていた作家の気迫に押し切られるかのような、一種異様な力に満ちているのは確か。
ちまちましたリアリズムと縁を切り、暫しの間途方もない「作り話」に身を浸し、<物語>の面白さにとことん翻弄されたい読者には必読の書。

キケン
2012/06/25 19:55
「本気」であることの楽しさ
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
有川浩は故伊丹十三監督に似ているなと、感じたことがある。誰もが思いつきそうで誰にでも思いつけないコロンブスの卵的着想を作品化する、着眼点/発想の妙だ。しかし、似ているのは此処まで。伊丹作品が、こうすれば観客に受けるだろうというあざとさと計算高さがしばしば鼻についたのとは正反対に、有川作品の登場人物はいつも懸命で、ひたむきで、清々しい。
「ほどほどの都市部に所在し、ほどほどの偏差値で入学でき、理系の宿命として課題が鬼のように多い、ごく一般的な工科大学」である成南工科電気大学を舞台に、「機械制御研究部」(略称【機研】)に所属する部員たちの活動を描く物語――。大学の部・サークル活動を素材にした青春小説というのは、今までありそうで余り無かった。しかし、この長編小説が面白いのは、単に発想の新鮮さのみに因るものではなく、此処に描かれている人間群像が極めて生き生きしているからだ。つまり、個々のエピソードや情報を単なる素材として提示するのではなく、それを見事に血肉化し、作品世界内で自由闊達に動き回るキャラクターを造形する有川浩の筆力が、図抜けているからだ。
まあ、女性の視点で描いた部活動だから、野郎オンリーで構成される人間集団にしてはちょっと綺麗ごと過ぎるきらいはある。されど、例えば第3話・第4話「三倍にしろ!」(前・後編)で、彼らが取組む学祭ラーメン屋台の獅子奮迅の活躍ぶりには、読んでいて素直に胸が熱くなる。そう、大学生にとっては、学祭模擬店はたかが「遊び」ではない。「遊び」ではあるが、人生でここまで全身全霊で取り組んだことがないような、真剣勝負の対象なのだ。
主人公の元山高彦も、同級生の池谷悟も、二人を無理やり「キケン」に引きずり込んだ部長の上野直也――「成南のユナ・ボマー」と呼ばれる超キケン超個性派――も、副部長大神宏明も、皆「本気」である。社会人との違いは、それが生計を立てる手段なのか、その過程自体が目的であるかの差に過ぎない。
加えて、話術のテクニック。面白おかしく語られる大学生活の外枠に、もう一つ仕掛けられた物語。この枠組みが、最後の最後で効いてくる。これがあるから、264~265頁がかくも感動的に映えるのだ。
毎度のことながら、有川浩の筆遣いの上手さに言いように翻弄され、心地よく酔い、ゲラゲラ笑い、最後は胸熱くなる。「本気」であることの楽しさが、眩しい限り。

シアター! 1
2012/06/10 12:35
メタ演劇小説の秀作
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
小劇団シアターフラッグを主宰する春川巧(はるかわ たくみ)は、300万円の累積負債を抱え、劇団存続の危機に直面していた。幼い頃から陰になり日向になり、時には庇い時には支えてくれた兄の司(つかさ)に融資を泣きついたところ、兄は劇団員の前でこう宣言する――「今日から俺が債権者でシアターフラッグが債務団体だ。今から二年で返せ。劇団が上げた収益しか認めない。――返せなかったらシアターフラッグを潰せ」。皆が舞台に立って楽しく演劇活動を続けられれば是とし、サークル活動の延長のノリでやってきたシアターフラッグは、これを機に演劇で食っていく「プロ」としての道を歩むことを否応なく促される・・・。
とまあ、設定は前作『フリーター、家を買う。』同様幾分シビアだが、一旦物語が動き出した後は、有川浩ワールドのめくるめく展開に心地よく身を委ねていればいい。芝居に関わること以外はまるで不器用で世間知らずな巧と、劇団員から「鉄血宰相」と恐れられる司の関係に、『図書館戦争』の郁と堂上を重ね合わることも可能だ。
モラトリアム人間が困難に直面し、それを克服することで大きく成長する「ビルドゥングス・ロマン」。個性とアクの強い人間集団が、幾多の衝突と融和を経ながら有機体のように育っていく「群像劇」。そして、実在する小劇団に取材することで、演劇の現場をリアルに描き出した「メタ演劇小説」。本作は、かくも多彩な要素が多層的に重なり合い、と同時に主役は無論のこと脇役も実に生き生きと楽しそうに飛び回っている。
勿論、会話の上手さは言わずもがな。脚本の上りが遅い巧が司に詰られ、巧が切羽詰まって井上ひさし(本文中では「井上ヒトシ」となっている)を引き合いに出して遅筆を正当化しようとすると、司は巧をこう罵倒する――「よりにもよって業界のてっぺん持ってきて言い訳する奴があるか!向こうが神だとしたらお前なんか脊椎発生以前の昆虫だろが!」(P117)。イヤ~、何とも凄まじい台詞。でも、思わず吹き出してしまった程上手く、実際に舞台の上で役者に言わせてみたくなる、キメ台詞ではなかろうか。
その逆もある。司が土曜夜公演完売を告げた時の劇団員の欣喜雀躍ぶりを見て、司はこう心で思う――「圧倒的な歓喜の表情は最後は涙にたどり着くのか。たった一人でそれを傍観しながらそんなことを思った。テレビの中なら見たことがある、しかしその光景は多くの人間にとってフィクションだ。テレビで見たことがあるから知っている、という程度の。関わった全員で驚喜し、はしゃぎ、泣き出すようなことを、一体どれだけの人間が死ぬまでに経験するだろう」(P218)
演劇という未知の分野を手掛けても、まるで以前からこういう素材を手掛けていたかのように手練れの筆致を見せる有川浩。彼女の才能には瞠目するのみ。


