コラム
丸善ジュンク堂のPR誌 書標(ほんのしるべ) 2016年12月号
今月の特集は
『音楽と科学の共鳴』
『ささやかな暮らしを考える』
丸善ジュンク堂のPR誌 書標(ほんのしるべ)。今月の特集ページで紹介された書籍を一部ご紹介致します。
気になった書籍はネットストアでご注文も可能です。
(※品切れ・絶版の書籍が掲載されている場合もございます。)
すべての内容を、WEB上でお読み頂けます。
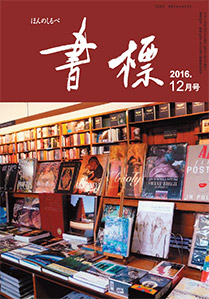

今月の特集(一部抜粋)
「数学と音楽よ! 人間の思考の中で考えられるかぎりもっとも明白な反対物よ! であるにもかかわらず手を結び、互いに支え合っている!」
――ヘルムホルツ「音楽の和声の生理学的原因について」(一八五七)
十九世紀の大科学者ヘルムホルツの右の言葉に導かれるかのように書かれた、興味深い本が出ました。
ピーター・ペジック/竹田円訳『近代科学の形成と音楽』(NTT出版・五〇〇 〇円)
本書は、音楽が数学、天文学、物理学、生理学など、科学の幅広い分野に与えた影響を、歴史の流れに沿って検討しています。
太陽系の惑星がメロディを奏でているというケプラーの「天体の音楽」はわりと有名かもしれませんが、本書によると、無理数の概念、光の波動説、電磁気学、そして量子物理学の誕生にまで音楽が関与していたというのだから驚きです。十四世紀フランスの自然哲学者オレームにはじまり、教科書でおなじみのガリレオ、ケプラー、デカルト、ニュートン、オイラー、ヤング、ファラデー、ヘルムホルツ、リーマン、プランクといった錚々たる科学者たちが登場します。一風変わった科学史というだけにとどまらず、音楽や人文思想に関心のある人にもとても興味深い本だと思います。
著者のペジックはもともと物理学を専攻した科学史家で、これまでにもたくさん本を書いていますが、じつは彼はプロのピアニストでもあるそうで、さらにフッサール、ベンヤミンといった「人文系」の教養も豊か。そうした文・理・音楽が融合したユニークな個性が生んだユニークな本です。
というわけで、今回の「愛書家の楽園」は、この本にかこつけて「音楽と科学の共鳴」といえる本を集めてみました。

近代科学の形成と音楽
著者 ピーター・ペジック(著)
竹田 円(訳)
NTT出版
5,400円(税込)
【内容紹介】
音楽が、天文学、数学、物理学、生物学などの自然科学分野に与えた影響を、古代から現代に至る壮大なスケールで明らかにする画期的な著作。ケプラーの法則に音楽が影響を与えたのは有名だが、本書はさらに、無理数、光の波動説、電磁気学、電信、そして量子力学の誕生にまで音楽が関与していたことを明らかにする。また、科学史を科学革命やパラダイムシフトという観点ではなく、連続的にとらえ直そうとする野心的な本でもある。
青の物理学 空色の謎をめぐる思索
ピーター・ペジック(著)
青木 薫(訳)
岩波書店
2,808円(税込)
【内容紹介】
「空はなぜ青いの?」 子どもも抱くこの素朴な疑問は、知の巨人たちを悩ませ、科学者による謎解明への試みは、芸術家たちを虜にした。背景にある文化史や美術史にも目を向けながら、1000年に及ぶミステリーの行方を追う。
ピュタゴラスの音楽
キティ・ファーガソン(著)
柴田 裕之(訳)
白水社
3,672円(税込)
【内容紹介】
「ピュタゴラスの定理」で知られる、紀元前6世紀のギリシアの賢人・ピュタゴラス。その数奇に満ちた生涯と、現在に至るまでの思想の継承史を明らかにする。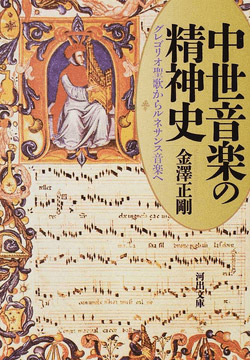
中世音楽の精神史 グレゴリオ聖歌からルネサンス音楽へ(河出文庫)
金澤 正剛 (著)
河出書房新社
1,188円(税込)
【内容紹介】
祈りの表現から誕生・発展したポリフォニー音楽、聖歌を広く伝えるために進められた理論の構築と音楽教育の展開…。キリスト教と密接に結び付きながら開花し、西洋音楽の礎となった中世音楽の謎に迫る。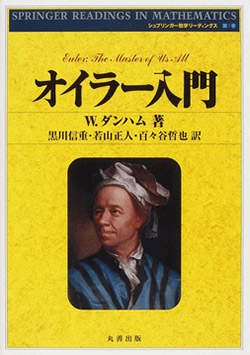
オイラー入門(シュプリンガー数学リーディングス)
W.ダンハム(著),黒川 信重(訳),
若山 正人(訳),百々谷 哲也(訳)
丸善出版
2,916円(税込)
【内容紹介】
760本もの論文を遺し、数学および数学者に多大な影響を与え続けるオイラー。彼がどのような問題に直面し、いかに解決したかを、原論文に沿って解説したテキスト。18世紀、驚異の天才が成し遂げたことが明らかになる!2016/12/05 掲載


