ジュンク堂書店 書店員レビュー一覧
ジュンク堂書店 書店員レビューを100件掲載しています。1~20件目をご紹介します。
書店員:「ジュンク堂書店福岡店スタッフ」のレビュー
- ジュンク堂書店
- ジュンク堂書店|福岡店/MARUZEN 福岡店(文具)
たんぱく質 飴屋 法水 (著)

他者の命
体をかたちづくっているタンパク質についての考察がなされた小説といえばいいでしょうか。
そうは言えど、本の形も色も、普通の小説のようではありません。本当に本なのかな?というくらい。写真集のようでもあるし詩集みたいでもあるしオブジェのようでもある。おみくじのようでもあるし教会のようでもある。
飴屋さんの書かれる文章から流れるタンパク質、栄養についての考察はとりとめがなく、読んでいると気が遠くなってきます。それは、もしかしたら私をかたちづくっているいつか何処かで拾った栄養が、こうして力を持ち文字を読み込むに至った。そうして文字を読み込むのに疲れ、栄養として再度流れ出そうとしている、そう思えてくるからなのかもしれません。
小説の中でなぜ栄養は種によって吸収できるものと出来ないものがあるのか問われます。多種の体を喰らわねば生きていけない、その残酷な仕組みを誰が設けたのか?と。
体の終わりについて考えることはまだ生きているからこそできること。それを考えているのが私なのか他者の命なのか、読んでいるとわからなくなってくるのです。
書店員:「ジュンク堂書店福岡店スタッフ」のレビュー
- ジュンク堂書店
- ジュンク堂書店|福岡店/MARUZEN 福岡店(文具)
凶笑面 (角川文庫) 北森 鴻 (著)

民俗学とミステリを楽しめる人気シリーズ復刊です
何者にもとらわれず我が道をゆく異端の民俗学者・蓮丈那智(れんじょうなち)と事件に巻き込まれがちな助手の内藤三國(ないとうみくに)の二人が調査に赴いた先で遭遇する数奇な事件。その真相は時に凄惨で風化されることを望まれるような過去も絡み研究結果として発表できないこともある。蓮丈那智フィールドファイルシリーズはそんな世に出せなかった言わば裏のフィールドファイルをまとめた作品。
著者の北森鴻は短編の名手とも云われ、とりわけ連作短編集で読者を魅了してきた。本シリーズも民俗学への興味と事件の謎解きの好奇心を満たしてくれる読み応えある作品揃い、北森鴻の代表作として人気のシリーズで長らく入手困難な状況だったが、角川文庫からシリーズ全作が復刊する。ぜひこの機会に北森鴻の作品にふれてほしい。
孤高の天才・蓮丈と時に鋭いひらめきを見せる助手の三國の相棒ものとしても楽しめるシリーズ。
書店員:「ジュンク堂書店福岡店スタッフ」のレビュー
- ジュンク堂書店
- ジュンク堂書店|福岡店/MARUZEN 福岡店(文具)
29歳、今日から私が家長です。 イ・スラ (著)

ささやかで新しい小さな革命
主人公であるスラは、父ウンイと母ボラの雇用主。
スラは運転手であるウンイに好きなお昼ご飯を食べるよう
気前よくクレジットカードを渡し、
それまでの家長が一度も払ってなかった家事への対価を
きちんとボラに支払う理想の女家長だ。
しっかり者のように見えるスラだが、
原稿の締切が終われば変な踊りを踊るし、
デートのために貴重な睡眠を削り、
数字が苦手でケタを間違えて大変な失敗をしたりもする。
掃除がうまくておちゃめなウンイ。
料理上手で布団の上でお菓子を食べるのが大好きなボラ。
3人のことを好きになるのにそんなに時間はかからない。
ここで紡がれるのは、私たちがまだ読んだことのない家族の日常。
ずっと読みたかった新しくてフラットな家族の物語。
クスッと笑わされたかと思えば、何気ない会話のやりとりで
ぼたぼたと涙を流したり、心が忙しい。
3人の日常にこんなにも励まされている自分がいて驚く。
本の持つ力を改めて感じさせてくれる1冊。
書店員:「ジュンク堂書店福岡店スタッフ」のレビュー
- ジュンク堂書店
- ジュンク堂書店|福岡店/MARUZEN 福岡店(文具)
僕の神さま (角川文庫) 芦沢 央 (著)

水谷君は人生一体何回目
亡くなった祖母が作った桜茶の瓶を落としてしまった少年。
絵具の水が入ったバケツを同級生にかけてしまった少女。
騎馬戦に勝つための作戦に隠されたある秘密。
父親に殺されたと噂される少女。
図書室にあらわれた「呪いの本」。
物語の主役は小学生。
彼らが困ったとき相談するのは親でも先生でもなく「神さま」と呼ばれる同級生の水谷くんという1人の少年だ。
誰も気が付かない、大きなニュースにもならないかもしれない、
けれどその時の自分にとっては世界のすべてと思えるような悩みごとに、水谷君はスマートに向き合って答えを導き出してくれる。
そこまでしたなら「解決編」といわんばかりに披露してもいいのに、水谷君は導き出した答えをけして得意げにひけらかしたりしない。
謎解きが目的ではなく、その謎の底にある悩みに気が付き、慮ってくれるからきっとみんな水谷くんを頼り「神さま」と呼ぶのだろう。
帯には「ホームズに出会ってしまったワトソンの話です」とある。
あのシリーズのように、ぜひこの物語も続きが読みたい。
書店員:「ジュンク堂書店福岡店スタッフ」のレビュー
- ジュンク堂書店
- ジュンク堂書店|福岡店/MARUZEN 福岡店(文具)
別れを告げない ハン ガン (著)

すべてのものに重さがある
作家のキョンハは、虐殺に関する小説を執筆中に、何かを暗示するような悪夢を見るようになります。ひどい虐殺事件が過去に起こった済州島出身のインソンは10代の頃、毎晩悪夢にうなされる母の姿を見ています。自分が経験したことでもないのに、繰り返される悪夢。それは、戦争を知らない私たちが、広島や長崎の映像を見た後で悪夢を見ることにも似ています。
雪のように軽く、鳥のように軽くても、すべてのものに重さがあり、肩に降りかかったときからそれは始まっているのです。
話の終盤、インソンはキョンハにある道を示しながら「私が歩いたところだけ踏んできて。」と、言います。過去の人たちの足跡を現在の私たちがたどることは、あまりにも不確かで、それが真実なのかは永遠にわからないままなのかもしれません。 しかしこうして本で読むこと、想像することさえもなくなってしまったら、どれだけ怖ろしいことが起こっても、その重さに気づかないまま、過ごしてしまうような気がするのです。
書店員:「ジュンク堂書店福岡店スタッフ」のレビュー
- ジュンク堂書店
- ジュンク堂書店|福岡店/MARUZEN 福岡店(文具)
老虎残夢 (講談社文庫) 桃野 雑派 (著)

武侠小説とミステリを楽しめる一冊
中国を舞台にした武侠小説をご存知だろうか。武術家たちがおのれの信念に則って義理を重んじ、とんでもない身体能力と驚きの技を繰りひろげる冒険譚。
本作はさらに孤絶の楼閣(館)で起きた事件の謎を解く密室ミステリでもある。
紫苑(しおん)は女武侠、武術の達人・泰隆(たいりゅう)に師事し長年修行を積んでいた。だが師匠の泰隆は奥義を弟子の紫苑ではなく名だたる武人を集めその中から選んだ一人に伝えるという。集められたのは師匠とかつて縁のあった三人、武侠小説ならではの強烈な個性の面々。
三人がそろったその翌朝、湖に浮かぶ孤島の楼閣で泰隆が遺体となって発見される。泰隆以外の人物が足を踏み入れた形跡のない状況はまさに密室ミステリ。紫苑は師匠の死の真相を追う。
武侠小説の世界で密室ミステリを紐解くとどうなるのか。その身体能力があれば、その武術の技があれば可能では、と武侠ならではの選択肢があるのがとてもおもしろい。
武侠小説には義理と人情があってほしいもの。本作の登場人物たちの背景や命を懸けた行いは信念と義理と人情があり胸があつくなる。読後タイトルに思いを馳せてしまう寂しさとあたたかさの余韻ある一冊。
書店員:「ジュンク堂書店福岡店スタッフ」のレビュー
- ジュンク堂書店
- ジュンク堂書店|福岡店/MARUZEN 福岡店(文具)
私の「結婚」について勝手に語らないでください。 クァク・ミンジ (著)

ここにいるよ、と旗をたてること
韓国で話題の非婚ライフ可視化ポッドキャスト
「ビホンセ(非婚世)」制作兼進行役のクァク・ミンジさんによるエッセイ。
いつまでたっても結婚しない人にあれこれ言ってくるのは、おとなり韓国も同じ。
結婚する意志はないと伝えると、
「そう言いながらいつかは結婚するんだろう」と
うんざりするような言葉を投げかけられながらも
非婚を貫く彼女の日常が綴られている。
自分と仲良くすることは、自分の取扱いを知ること。
意見は違っていても誰かを愛することはできること、
そしてこんなふうにここにいるよ、と伝えてくれる彼女の言葉に
自然と勇気をもらえます。
あれこれ詮索してくるお節介な人たちも、本当はみな、
作者の祖母のように「しあわせかい?」「そういう道もえらべるのかい?」と
ききたいだけなのかもしれません。
いろんなバリエーションを見ることで、それを見た人は
好きに選択していいんだと知ることができるから。
書店員:「ジュンク堂書店福岡店スタッフ」のレビュー
- ジュンク堂書店
- ジュンク堂書店|福岡店/MARUZEN 福岡店(文具)
山亭ミアキス (角川文庫) 古内 一絵 (著)
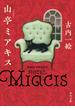
誰かのための9つの命
意図せずに人々がたどり着くのは不思議なホテル、山亭ミアキス。
そこで働くスタッフはいささか個性が強すぎる節はあれども、心にしっくりくる美味しい食事に、疲れをとかすような温泉はまぎれもなく極上のもの。
ふかふかのベッドで眠り、朝は青い湖のまわりをゆっくり散歩すれば、日常のしがらみや苦しみから抜け出せる・・・・!なんてこともあるのでしょうか。
この山亭ミアキスに迷い込む人々は、まるで選ばれたように誰もが重たい何かを肩や胃の腑に抱えこんでいます。
すごく良い人でもなく、すごく悪い人でもない、でもどこか自分勝手なずるさを持っているな、と思うような人間たち。彼らに既視感を持ってしまうのは、自分も彼らと同様にそういったずるさや弱さを持って生きているからにちがいありません。
けして現実逃避はさせてくれない山亭ミアキス。
ここを訪れれば、傷みとともに、何かを得て帰ることができるのかもしれません。
書店員:「ジュンク堂書店福岡店スタッフ」のレビュー
- ジュンク堂書店
- ジュンク堂書店|福岡店/MARUZEN 福岡店(文具)
みどりいせき 大田 ステファニー歓人 (著)

すべることばたち
「読みにくい」「びっくりした」そんなイメージの小説を想像していました。
実際は真逆でした。
確かに、若者の話し言葉が多用されています。しかし、そこにあふれる言葉たちを読んでいると、ずっとそこにいたい感覚がたちのぼってきます。自分が幼児だった頃のことを思い出します。
「ごめんかった、まじ」「ゆーれいの貸し車」「なんか、思考がめくれてく感じ。たまねぎみたい」
ひらがなの羅列。見たものを隣の子にそのままいう感じ。頬をすべってゆく風、虫や雲をみんなで見たこと。
【ひかるは、きゅうじゅうくらいまでながいきするきしかせん】
登場人物たちが常に話題の根底に置いているものが「死」です。そのイメージについてみんなで話すとき、「死」という言葉でさえも、様々な色たちによって彩られている気がしてきます。小さい子供たちが話しているみたいなのに、逆にすごい年寄りが話しているような気もする。言葉と言葉がざわめく。ひらがなになっただけなのに、あいだに空白を持たせただけなのに、言葉が、本に載っているものではなくなろうとしている。
上手く消化しようとするけれど、なかなか、できません。ただ言葉たちが目の中をすべるのを眺める心地よさにあふれている、そんな小説です。
書店員:「ジュンク堂書店福岡店スタッフ」のレビュー
- ジュンク堂書店
- ジュンク堂書店|福岡店/MARUZEN 福岡店(文具)
小さな町・日日の麵麭 (ちくま文庫) 小山 清 (著)

人々のささやかな日常が集められた短編集
はじめて小山清の作品にふれた時、ただ日々を生きる人々を描いているだけだと思っていたのに気づけば最後まで読んでしまっている自分にびっくりしてしまったことを覚えている。日常の描写にこんなにも引き込まれた読書体験は初めてで、それまでは手を出すことのなかった作家の作品も「読めば面白いのかもしれない」と読むようになり新しい本と出会うきっかけを作ってくれた。
「小さな町」は戦時下に下谷の竜泉寺町で新聞配達をして過ごしていた主人公の日常が綴られている。新聞配達の管轄に住まう人々はじめ付き合いのあった人々との日々のやりとりが目に浮かぶ描写は思い出話を聞いているような心地よさで読み進めてしまう。
小山清は太宰治のもとに原稿を持ち込んだことがある。「風貌」で語られる太宰治との交流で語られた小山の作品を読んだ太宰が送った葉書に書かれていた一節「周囲を愛して御生活下さい」。小山清の作品に引かれた身にはあまりにも腑に落ちる言葉で、そんな小山の目を通して描かれる日常を読めるよろこびを噛みしめてしまった。
書店員:「ジュンク堂書店福岡店スタッフ」のレビュー
- ジュンク堂書店
- ジュンク堂書店|福岡店/MARUZEN 福岡店(文具)
棚からつぶ貝 (文春文庫) イモト アヤコ (著)

つぶ貝に愛をこめて
コモドドラゴンと競争したことはあるだろうか?
このエッセイの著者は競争したことがある。
太い眉毛とセーラー服がトレードマークで、芸人・女優・そして母として活躍するイモトアヤコさん。
本著では自身が成し遂げた様々な実績よりも、彼女が大切にしている人々への愛がひたすらにつづられている。
自分のずるさも弱さもさらけだし、人からもらった優しさを自覚でき、そしてその人への愛を力いっぱいに叫ぶことができるイモトさん。
読み終わったとき、自分もいつもそばにいてくれる人たちをちゃんと大切にしよう、そう改めて思えた。
書店員:「ジュンク堂書店福岡店スタッフ」のレビュー
- ジュンク堂書店
- ジュンク堂書店|福岡店/MARUZEN 福岡店(文具)
続きと始まり 柴崎 友香 (著)

人がいなくなった場所で
震災やパンデミックの間で、生きていく人々を描いた小説です。
本の中に、学校が好きだった、なぜなら誰かいるから、今日話せなくてもまた明日でいいかって、というような描写があります。ずっと人がいるのって、貴重だよね、ということ。
学校だけに限らず、人が常にいる職場やお店も、そうだと思います。
非日常になったとき、人がいないことの重みを私達は感じる。
小説のラストで、はちみつの入った飴をなめるシーンがあります。そのはちみつは、ウクライナでとれたはちみつでした。このはちみつを採取した人も、今もうその場所にはいないのかもしれない。
生きている限り過去には戻ることができないし、未来にも行けない。私達にできるのは常に思い出すこと、想像することだけです。その軌道を、何回も描写した小説です。
書店員:「ジュンク堂書店福岡店スタッフ」のレビュー
- ジュンク堂書店
- ジュンク堂書店|福岡店/MARUZEN 福岡店(文具)
世にもあいまいなことばの秘密 (ちくまプリマー新書) 川添愛 (著)

あいまいな言葉を理解することで日本語が面白く思える本である
私たちの生活の中で、あいまいな言葉は多く存在し、
その曖昧さによって言葉のすれ違いが起きている。
筆者は、あいまいな言葉に対し、
異なった解釈をすることで生じる言葉のすれ違いを対処できるようになるには、
言葉を「多面的に見る」ことが必要であり、
その際に役立つのは、曖昧さがどういうときに起こるかについての知識であると述べている。
つまりは、曖昧さの要因がわかっていれば、
相手が何を言いたいのか推察でき、あいまいな言葉によるすれ違いを防げるということである。
本書は、なぜ異なる解釈が起こるのか、
あいまいな言葉を9つの特徴に分け、詳しく、面白く解説されている。
それぞれの特徴は例題を用いて説明しており、
よく私達が生活の中で耳にしたり、自ら言ったり、見たりする会話や文章が多く使われている。
また、例題の解説後には問題も設けられており、より理解しやすい内容となっている。
書店員:「ジュンク堂書店福岡店スタッフ」のレビュー
- ジュンク堂書店
- ジュンク堂書店|福岡店/MARUZEN 福岡店(文具)
カッコの多い手紙 イ ラン (著)

つかずはなれずの距離感
韓国の京畿道九里市生まれのラッパー、スリークと
韓国のソウル生まれのアーティスト、イ・ラン。
手紙を書くとどうしてもカッコが多くなってしまうのふたりの往復書簡。
銭湯でのタトゥーの話、同居している猫の話から、
フェミニズム、ジェンダー、ヴィーガン、創作についてなどなど、
交わされる話題は多岐に渡り、コロナ禍で寄る辺ない気持ちのなか
出会ったふたりのあかりを探すようなやりとりにこちらもはげまされる。
手紙に出てくる人物(猫も)たちは会ったこともないはずなのに
古くからの知り合いのような気持ちになるのは不思議。
どうかともに暮らす猫たちがしあわせでありますようにと
気づけば祈りながら読みすすめていた。
手紙の中でイ・ランも触れているスリークの曲「私のもの」はいろんな人にきいて欲しいです。
読み終わった頃にはきっと久しぶりに誰かに手紙をかきたくなっていることでしょう。(もちろんカッコの多い手紙を)
書店員:「ジュンク堂書店福岡店スタッフ」のレビュー
- ジュンク堂書店
- ジュンク堂書店|福岡店/MARUZEN 福岡店(文具)
幸せな家族 そしてその頃はやった唄 (中公文庫) 鈴木悦夫 (著)

もはやホラーなジュブナイルミステリ
あるところに幸せな家族がいました。
お父さんは有名な写真家です。
お母さんはいつも優しいです。
長女は美しく聡明です。
長男はいばりんぼうです。
そして末っ子の僕は、たいくつが苦手です。
保険会社のテレビCMのモデルに選ばれた「幸せな家族」のもとに撮影隊がやってきたのは、雪のふるひな祭りの日のことでした。
そこからはまるで嘘のようです。
ひとり、またひとりと人が死んでいくのです。
それはもう坂道を転げ落ちるように、誰もがこんなことはおかしいと思いながらも、不可思議な死の連鎖はとまりません。
主人公である小学六年生の少年の目線で描かれた「幸せな家族」の崩壊を、不気味で不謹慎な「その頃はやった唄」がはやしたてます。
完璧なひとつの円だったものはぐしゃぐしゃとほどかれ、それが元あったなにかに戻ることはきっともうないでしょう。
私はこの幸せな家族の心に深く潜ることは叶わず、終わっていく姿をファインダー越しにただ眺めることしかできませんでしたが、最後まで目を離すことはできませんでした。
書店員:「ジュンク堂書店福岡店スタッフ」のレビュー
- ジュンク堂書店
- ジュンク堂書店|福岡店/MARUZEN 福岡店(文具)
トゥデイズ 長嶋 有 (著)

明日のフレーズ
長嶋有さんの小説で、とても好きな部分があります。それは、登場人物が体験した日常のささいなことがフレーズ化され、自分の日常の中でも、大きく輝きを増すところ。
今回新作を読んでみて、「あっ、ふえている」と思いました。
家族の輝きが、フレーズ化が、ふえている。
今までは働くOLであったり、主婦であったり、アルバイターの輝きであったりしました。でも今回の『トゥデイズ』では、生活する夫婦に加え、成長していくちいさなこどもの輝きが折り重なっている。
そのことに気づいたとき、すごいなあ、と思ったのです。
壁や柱にできる小さな虹。ヘッドフォンのバッテリー残量を知らせる小さな女の人の音声「バッテリーレベイズロウ」。反対のメニューを答える子どものために、両親が考える「目玉焼きか卵焼きか」の質問。
マンションの中で毎日同じように見えながらも、変わっていく「フレーズ」。
自分の小さい頃にも、そのような「フレーズ」が、あったのかもしれません。
親は、もしかしたら今も、覚えているかもしれません。妹がうまれて、初めて病院から家にやって来たとき、いつも薄い色の食べ物しか買わなかった母がなぜか買ってきたゼリーのおやつの毒々しい色。(自分のためのゼリーだったのかもしれません)。寒かったマラソン大会のときに見た飛んでいる鳩、両親が喧嘩したあとに子どもたちに買ってきた、クレヨンとスケッチブック。
「フレーズ」はとめどなくあふれて、でもいざ思い出そうとするとなかなか出てこず、いつか死ぬときに走馬灯としてそれを見るのかもしれません。
「フレーズ」は人生でいつか失われこそすれ、自分が新しい「フレーズ」を、つくっていくのかもしれません。そのことを考えると、この小説の登場人物のように、「明日」についてぼんやりと、考えてしまいます。
書店員:「ジュンク堂書店福岡店スタッフ」のレビュー
- ジュンク堂書店
- ジュンク堂書店|福岡店/MARUZEN 福岡店(文具)
青天 包判官事件簿 (中公文庫) 井上祐美子 (著)

中国時代物、ミステリがお好きな方に
中国・宋の時代を舞台に描かれるミステリ短編集。
謎を解くのは清廉潔白、裁きは公平、晴れ渡った空の如し。「包青天」と謳われる名判官。中国では庶民の味方として長く親しまれている。日本でいう水戸黄門や遠山の金さんのような人物。
宋の国土の南端に位置する端州(たんしゅう)に赴任したばかりの知事・包拯(ほうじょう)、字を希仁(きじん)という。三十代半ばとまだ若く、身につける服も質素、言葉遣いも丁重で威厳には欠けるが仕事ぶりは真面目。時々不注意から墨で書類を汚したり仕事の合間にぼんやりしているのはご愛敬。そんな評価をしていた役所での世話係・孫懐徳(そんかいとく)だが「生きた牛の舌が切り取られる」事件をきっかけに新しい知事の厄介な一面も知ることになる。
舞台は宋代の中国なれど、その時代や地方の特色も分かりやすく描かれている。古代中国の知識に不安があっても楽しめるので中国時代物がお好きな方はもちろんミステリ好きな方にもおすすめの一冊。
書店員:「ジュンク堂書店福岡店スタッフ」のレビュー
- ジュンク堂書店
- ジュンク堂書店|福岡店/MARUZEN 福岡店(文具)
八重歯が見たい チョン・セラン (著)

嫌な予感はあたるもの
『ジェファはヨンギを九回も殺した。』
頁をめくると強烈な出だしにギョッとする。ジェファは一度見たら忘れられない特徴的な八重歯を持つ作家。ヨンギはその元恋人。
もちろん実際に殺しているわけではなく、自分の書いた小説の中で何度も何度もヨンギを殺している。
あるときは龍のしっぽに押しつぶされて、またあるときは宇宙の時空間の接着面に挟まれて。もちろんヨンギはそのことは知らない。
ある日、ヨンギの身体に不思議な現象が起きる。ジェファの書いた文章がタトゥーのように浮き出るのだ。
付き合っていた時も、別れたあともすれ違ってばかりだった二人が交錯するとき、事件は起きる。
テンポ良く進む文章の中に潜む不協和音に気づいた時、その正体にゾッとする。
恋愛は絶望とあきらめだらけの、まるで貸し借りの契約のようなものかもしれない。
でもひざを突き合わせてお互い向き合った時、少しずつ良い方に変わっていくのかも
しれないなと、そんな気持ちにさせてくれるかなりパンチの効いたラブストーリーだ。
書店員:「ジュンク堂書店福岡店スタッフ」のレビュー
- ジュンク堂書店
- ジュンク堂書店|福岡店/MARUZEN 福岡店(文具)
分断を乗り越えるためのイスラム入門 (幻冬舎新書) 内藤 正典 (著)

読めばムスリムへのイメージが変わる本である
新型コロナのパンデミック、ロシアのウクライナ侵攻という世界規模の災厄の中で
ムスリムはどう動いてきたか、どう考えてきたかを取り上げなから、
イスラムについてわかりやすく説明している。
一見、厳しくも怖いイメージのイスラムだが、代表的な教えは、
「アッラー以外に神はいない」と信じ、一日5回の礼拝、弱者のために喜捨をすること、
ラマダン月に断食すること、一生に一度メッカに巡礼することとなっている。
もちろん戒律を破るとそれなりの罰はあるが、それは私達が法律を破ったときと同じことだ。
ムスリムはこれらの教えを異教徒へ強要しない。
逆に、西欧文明が悪いというのではないが、
西欧は、自分たちの思い込みや、絶対的な優位性を持つ自分たちの規範性を異教徒へ押しつけ、従わせようとしてきた。
そうしたことで、今日のムスリムとの共存が難しくなってきたのである。
その分断を、イスラムを正しく知ることで乗り越えようと筆者は説いている。
書店員:「ジュンク堂書店福岡店スタッフ」のレビュー
- ジュンク堂書店
- ジュンク堂書店|福岡店/MARUZEN 福岡店(文具)
ブキの物語 シュザンヌ・コメール=シルヴァン (著)

もやがかかったもの
民話の本です。カリブ海の島国で収録された多くの民話。
小さい頃から昔話を読む時、なぜでしょう、祖母の家の、使い古された毛布がいつも頭に浮かびました。毛布にはたくさんの外国の動物が描かれており、なんの動物だったかはもう忘れましたが、多くの外国昔話を知った時、いつもその外国の情景ではなく、毛布の模様が頭に浮かびました。
載っているたくさんの民話は、かなりの悲劇もありますがどこか明るく、不思議です。ハイチではものごとがすぐに忘れ去られるんだ!という、それを言って良いのかしらんという記述も堂々とあります。面白いのは、民話に出てくる人たちのうち、「何者だかわからない」人がいるということ。コンペ・アンヴォワジュテなる人物がそうです。彼は、カニを探しに穴に手を突っ込んだ人物に、自分が「コンペ・アンヴォワジュテ」だと告げますが、「コンペ・アンヴォワジュテ」が動物なのか植物なのか人間なのかは、最後まではっきりとしません。ただ、彼の「当然さ」というせりふで、なんだかカニを探しに来た人物よりももっと強烈な存在がいるとわかるだけです。
いつからか、物事には起承転結があって、謎の人物の正体は最後には明かされるものなのだと思っていました。動物の顔や性質も、昔話の最後には判明するのだと思い込みました。でも、そうではないおはなしがずっと昔からあったことを、この本は教えてくれます。私が見た毛布の動物たちの顔もぼやけたものでなく、最初からもやがかかっているものだったのかもしれません。


