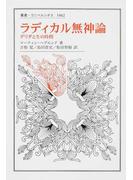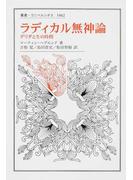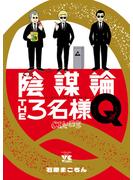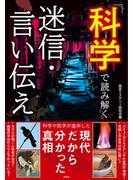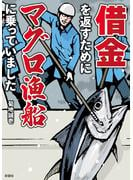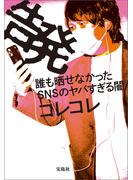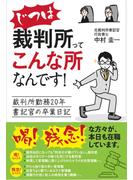ブックツリー
Myブックツリーを見る本の専門家が独自のテーマで集めた数千の本を、あなたの”関心・興味”や”読んでなりたい気分”に沿ってご紹介。
あなたにオススメのブックツリーは、ログイン後、hontoトップに表示されます。
進化論の光と影。進化という考えが社会に与えた影響を知る本
- お気に入り
- 10
- 閲覧数
- 1016
環境変化に適応した者が生き残る「適者生存」。国際標準から取り残された「ガラパゴス化」など、進化論に関係した表現は日々よく使われます。「進化したね」と言われると、知識やスキルが向上したと喜ぶ人が大半です。しかし、こうした理解は誤りだと聞くとどうでしょう。虚実さまざまに浸透した進化論を問い直す本を紹介します。





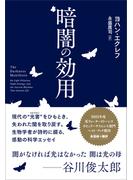
作家の視点で作家を語る。観察眼が光る秀逸な作家論が読める名著
- お気に入り
- 2
- 閲覧数
- 3147
著者自身が作家であり、おなじ文学界の作家を論じることは古今東西でありました。その範囲は顔見知りから昔の異国人まで含み、時代も国境も越え、文芸評論として現代に根づいています。ここでは「作家による作家論」と題して、数々の作品を書き残してきた作家の人物像と文学観を考察するとともに、その実体を浮かび上がらせる名著を紹介します。




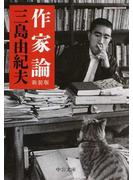

「第二の皮膚」としての衣服。身体論の視点で衣服を読み解くための本
- お気に入り
- 1
- 閲覧数
- 1741
「衣服は人間の皮膚に次ぐ第二の皮膚である」というように、マーシャル・マクルーハンのメディア論では、衣服は皮膚を拡張する記号として捉えられていました。今では「第二の皮膚」は記号としてだけではなく、身体に影響を与えるものとして哲学や社会学で考えられています。保温や清潔以上の意味について、衣服を身体論の視点からひも解くための本を紹介します。




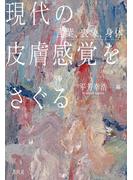

人はなぜ音楽に惹かれるのか。哲学や科学から見るユニークな音楽論の本
- お気に入り
- 19
- 閲覧数
- 2121
つらいときや悲しいとき、音楽に癒されたという人は多いでしょう。スポーツ選手が集中力を高めるために、競技の前に音楽を聴く姿も珍しくありません。人間には音楽が必要だ、というのは誰もが賛成すると思われますが、その理由をはっきりと知る人は少ないかもしれません。音楽が持つ力の源に哲学や科学の視点から迫る本を紹介します。



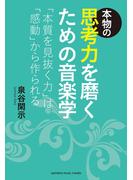


知っているようで知らない不思議に挑戦!空と地上の自然現象を解説した本
- お気に入り
- 1
- 閲覧数
- 532
空を見上げているとき「なぜ色が青いのだろう?」と疑問に思ったことはありませんか。私たちの身近な空や地上には、知っているようで知らない不思議にあふれています。なかには地震や噴火など、災害対策として知っておくべき事柄もあります。ここでは、空と地上の自然現象を解説した本をピックアップしました。
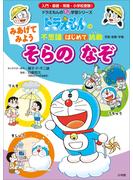
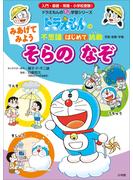
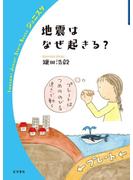


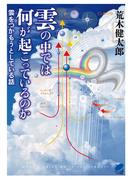
常識や一般論では語れない。「規格外の愛しい関係」を描いた物語
- お気に入り
- 69
- 閲覧数
- 4468
血縁のない家族、禁断の間柄、立場を超えた愛、不毛な恋、人間以外との結びつきなど・・・。非常識だとか普通じゃないとか言われようと、当人にはかけがえのない愛しい関わりというものが確かに存在します。そんな規格外ともいえるまっすぐな想いや愛しいつながりを繊細に綴った物語を集めました。どの関係にも胸打たれるはずです。
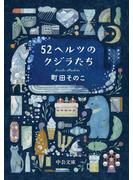
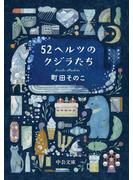

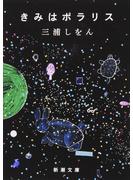
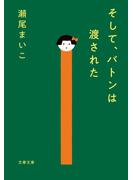
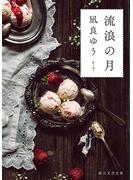
都市伝説ではなく陰謀論!
- お気に入り
- 8
- 閲覧数
- 11034
都市伝説と陰謀論って同じだと思っていたら違うということが最近になってわかった。陰謀論者の中で話題になってるのが「アドレノクロム」という子供の内臓で作るドラッグ。全ての陰謀論にはアドレノクロムが関わってるらしい。これは都市伝説とは違うらしい。
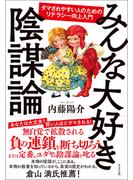
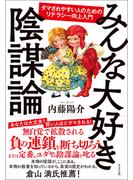


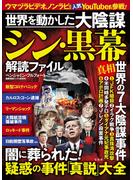
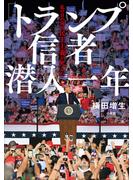
すべての人をやさしく包む込む。はじめての吉本ばなな
- お気に入り
- 3
- 閲覧数
- 794
語りかけるような自然な文体で、人の心の動きを繊細に捉える吉本ばなな。そこには、どんな人生も肯定して包み込んでくれるような温かさがあります。大切な誰かを亡くしたとき、つらいときや苦しいとき。傷ついた心を癒し、もう一度歩き出せるようにそっと背中を押してくれる。そんなやさしさに満ちた小説を集めました。
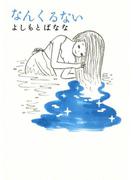
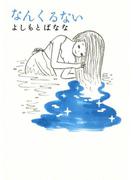
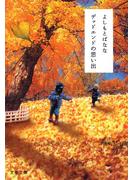
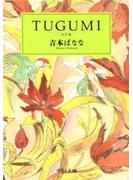
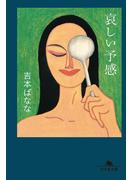

ネットだけでは得られない深みへ。読書の必要性を知り、読み方を学ぶ本
- お気に入り
- 18
- 閲覧数
- 1320
「ネットで調べれば十分」「読むのに時間がかかる」など、さまざまな考え方や理由で読書から遠ざかっている方もいるでしょう。しかし、読書にはネットメディアにはない魅力があります。また、難しいことを考えずしても、効果的かつ気軽に読書を楽しむ方法もあります。読書の必要性、そして読書の方法が学べる本を紹介します。


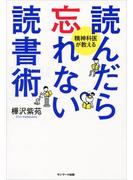
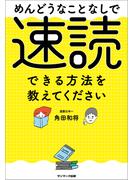
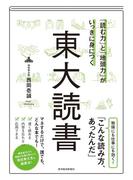
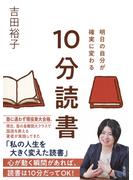
幸福論が苦手な理論派、必読!科学的な視点から幸福になる方法を学べる本
- お気に入り
- 16
- 閲覧数
- 2531
神経科学や脳科学などの見地に立って、幸福になるための具体的なメソッドをまとめた本を紹介します。「巷で流布される幸福論は、科学的根拠がなくて信じられない」「『結局は心の持ちよう』というあいまいな結論に帰着しがち」そんなことを一度でも考えたことがある方にこそ読んでほしい本を集めています。科学的に幸せを掴みましょう。
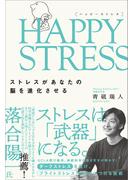
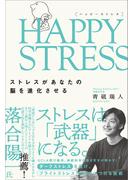
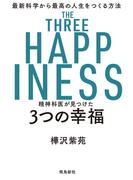
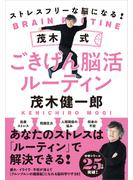

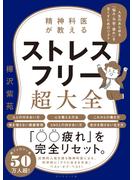
中学生でも大丈夫!進化論を学べる読み物
- お気に入り
- 31
- 閲覧数
- 4733
地球上には、人間をはじめさまざまな生物が生息しています。今の生き物の姿はこれまでの進化の結果であり、未来に向かう途中の姿でもありますが、ダーウィンをはじめとする研究者たちによって、進化の過程は次々と解明されています。そこで、中学生から学べる進化論の本を集めました。多様な生物たちから見る進化の世界をご堪能ください。



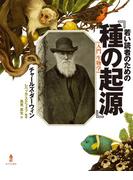
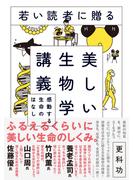
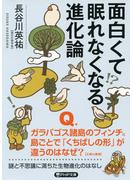
陰謀論といえばこの5冊!
- お気に入り
- 7
- 閲覧数
- 13219
「フリーメイソン」「イルミナティ」など誰もが好きな都市伝説。その中でも陰謀論はかなり人気が高い!世界の陰謀ネタやら闇社会ネタの本はかなり多い。そんな陰謀ネタ最新本がこれ。


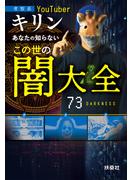
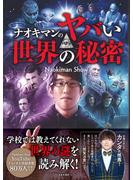
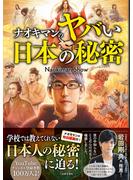
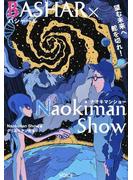
本の読み方・選び方に悩める人に!いろんな本との付き合い方が学べる本
- お気に入り
- 7
- 閲覧数
- 802
「今の本の読み方でいいのかな」「自分に合った本の選び方を知りたい」といったお悩みを抱えている方にオススメの本を集めました。読書の達人たちが、独自の読書法や本の楽しみ方を紹介しています。ひとり静かに読書を楽しみたい方も、SNSなどで感想を発信している方も、読めばブックライフを盛り上げてくれるヒントが見つかるはずです。
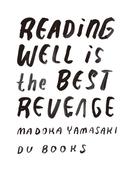
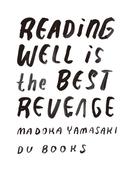



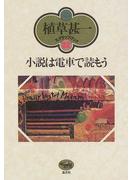
自分らしく生きたい人の背中を押す、吉本ばなな珠玉のエッセイ
- お気に入り
- 23
- 閲覧数
- 9349
自分のことが嫌い。人生がつらい。毎日が楽しくない。そんな方に読んでほしいのが、小説家・吉本ばななのエッセイです。彼女の文章には「自分らしく生きることが大切」という一貫したメッセージがあります。粒ぞろいのエッセイの中から、明日を生きる活力になる本を集めました。読後、「自分の人生も悪くないかも」と思えるようになるはずです。


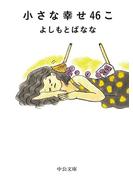
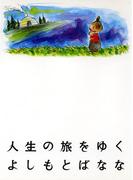


私たちはなぜ物語に惹かれてしまうのか?はじめての「ナラトロジー(物語論)」
- お気に入り
- 86
- 閲覧数
- 9582
物語は、私たちの心にいろんな感情を生み出します。文字を追うだけの行為になぜここまで心が揺さぶられるのか、冷静に考えるとちょっと不思議なものです。そんな疑問を解き明かす学問が「物語論(ナラトロジー)」。「何それ?」という方にもわかりやすい基礎的な手引書を精選しました。物語論を学べば、物語をより深く味わえるようになるはずです。



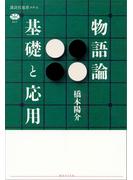


次々に起こる心霊現象と不可解な殺人・・・オカルト×ミステリーの世界
- お気に入り
- 89
- 閲覧数
- 12398
ホラーとミステリーは相性が抜群。不可解な状況にオカルト的な要素を加えれば、「心霊現象」のできあがりです。そんな心霊現象を作為あるトリックとするものもあれば、一部実際に起きた心霊現象を取り入れたり、いろいろなパターンや作例があります。ここではオカルト要素満載でありながらロジカルな本格ミステリーを紹介します。
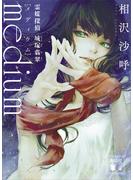
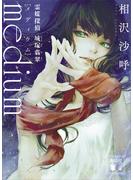
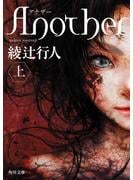
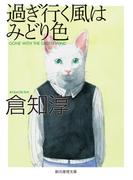
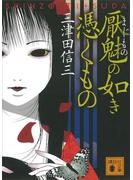
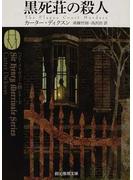
深く考えるための思考法とは?その方法論やヒントが書かれた本
- お気に入り
- 37
- 閲覧数
- 3640
学生でも社会人でも、自分なりに考えた答えを求められるシーンはあるものです。そこでじっくりと考えたからといって、納得させられる結果が残せるものではありません。深く考えるには、その方法を身につける必要があるのです。ここではそのヒントや方法論を知ることができる本をピックアップしました。



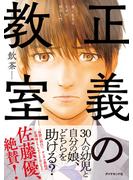


贈与論を通してどう資本主義を突き抜けていくか
- お気に入り
- 79
- 閲覧数
- 8555
行き過ぎた資本主義は、自然の搾取、無縁社会、貧富の差をもたらしている。贈与の思想は資本主義を問い直し、人間関係、自然との関係を新たに創造する可能性をもっている。旧来の贈与の慣習だけでなく、臓器移植、コモンズの利用、自然の恵み、動物本能を含めて贈与を考えていこう。【選者:岩野卓司(いわの・たくじ:1959-:明治大学教授)、赤羽健(あかはね・けん:1991-:編集者)】






吉本芸人の頭の中を覗きたい!と思った人が読むべき本
- お気に入り
- 2
- 閲覧数
- 2912
テレビで吉本興業の芸人を見ない日はありません。吉本芸人に一度も笑わされたことがない日本人って、なかなか珍しい人かもしれません。考えてみればこれはすごいこと。しかし一方で、私たちは吉本芸人たちの素顔をよく知りません。いったい彼らは何を考えて日々笑いを生み出しているのでしょう。吉本芸人の頭の中を覗ける、そんな本を紹介します。
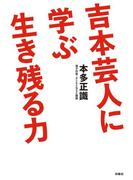
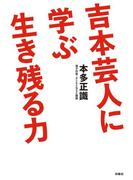
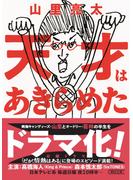

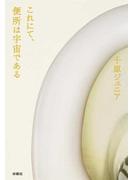

フランスにおける動物論の展開
- お気に入り
- 36
- 閲覧数
- 5006
1970年代に英米圏で「動物の権利」運動が開始され、人間と動物の倫理的・社会的関係が問われてきた。フランスでも思想や文学の領域で、動物の概念の再定義がなされたり、哲学的な動物論が展開されたりしている。動物のまなざしに曝されて新たに開かれた世界で、人間中心主義的な思考はいかに変容するだろうか。【選者:西山雄二(にしやま・ゆうじ:1971-:首都大学東京准教授)】
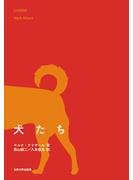
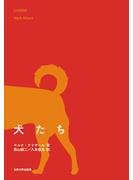



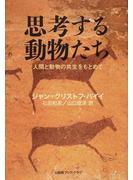
映画論で見る表象の権力と対抗文化
- お気に入り
- 27
- 閲覧数
- 5096
現代世界史を通じて映画やテレビ番組などの映像メディアは、大衆文化・国民文化・対抗文化として、圧倒的な影響力をもってきた。その人種/ジェンダー/階級の表象は資本主義を広め強化してきた一方で、被支配者・マイノリティの側もまた映像メディアを用いて別様の表象を試みてきた。【選者:早尾貴紀(はやお・たかのり:1973-:社会思想史)】




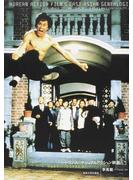

「読書」の意味を一から問い直す!?新しい本の読み方が発見できる本
- お気に入り
- 65
- 閲覧数
- 5025
黙っていても情報が押し寄せてくる現代社会においては、「読書」がどんな意味を持つのかを改めて考えてみる必要があるのかもしれません。読書への新しい視点や新たな本の読み方に気づかせてくれる本を読むことで、今まで想像していなかった読書の魅力を発見することができるでしょう。速読などの技術的側面ではなく、読書の新たな側面を提示してくれる本をセレクトしました。



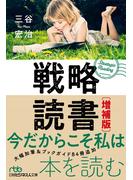
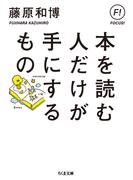
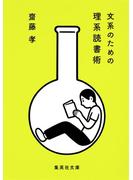
現象学とはどのような哲学か?日常の経験から哲学を始めるための本
- お気に入り
- 62
- 閲覧数
- 11952
「現象学とは何か?」という問いに対して、現象学者から共通の見解が返ってくることは期待できないでしょう。それほど現象学は多種多様に拡散し、展開されてきました。では「現象学的」と評される方法論のうちには何かしらの共通点はあるのか?ここでは現象学について学び、考えるための一歩を踏み出すことのできる本を紹介します。


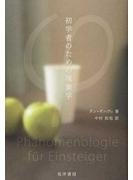



東京の転機を見いだすために読みたい都市論
- お気に入り
- 9
- 閲覧数
- 1139
「日本橋をかつての姿に戻す」なんてことがいわれるけど、どの時代に戻すのが正解かは難しくないですか。江戸なの明治なの?震災?空襲?どこが近代東京の分かれ目?バブル前後とかでも変わってない?などなど。東京についての本も、どこの時代と接続させるのかによって大きく見方は変わります。以下に取り上げるのは、ある時代との比較によって語られる東京本です。
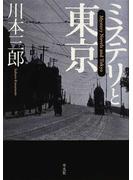
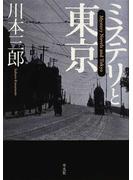
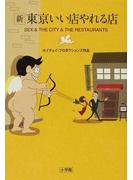

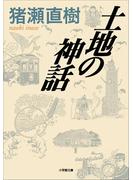
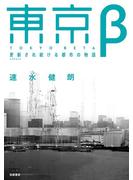
ファンタジーとは何か?その書き手たちによるファンタジー論
- お気に入り
- 9
- 閲覧数
- 7931
ファンタジー文学を好きな人は大勢いますが、では「ファンタジーとは何か?」という問いにすぐさま答えられる人はどれほどいるでしょう。ファンタジーを数多く生み出してきた作家たちもその問いについて考え、さまざまな形で自らの考え持論を述べてきました。国や宗教、生い立ちの異なる5人の作家たちによるファンタジーについての本を紹介します。
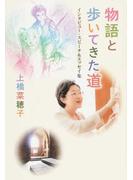
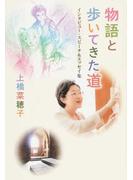
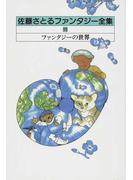


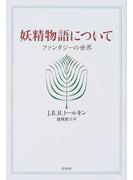
夜中のトイレが怖くなる・・・身近な怪現象に背筋が凍りゾクゾクする本
- お気に入り
- 37
- 閲覧数
- 4776
実話を元にした怪談、マンション、町中など日常で関わる場所が舞台になることで、本を読み終わった後も持続する怖さを体験できる本を紹介します。巨大なお化け、モンスターなどが登場する派手な怖さとは一味違い、常に誰かに見られているような、静かでまとわりつくような恐怖を体感できます。思い出すと夜中にトイレに行くのが怖くなる話ばかりです。
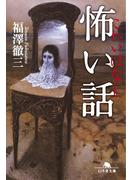
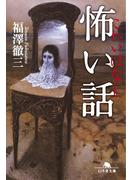


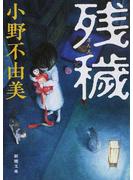
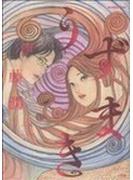
人生を支えてくれる本との出会い方とは?読書家たちの「読み方」がわかる本
- お気に入り
- 37
- 閲覧数
- 11067
友人に勧められて、本屋で表紙に惹かれて、SNSで知らない誰かの感想をみて・・・など、世の中にはさまざまな本との出会い方があります。では、読書家の人たちはどのように本と出会い、その本の滋味を味わい、日々を乗り越えてきたのでしょうか。読書がささやかな楽しい営み以上のものになるかもしれない、そんな本を紹介します。
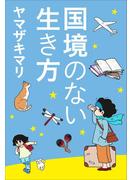
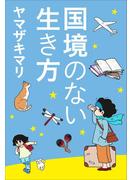
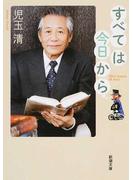
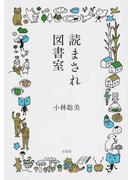


運命論から『ジョジョの奇妙な冒険』を読む
- お気に入り
- 36
- 閲覧数
- 10932
人間には自由意志があるのか?全ては神や環境によって決定されているのか?それは哲学や宗教のテーマでもありますが、近年のウェブ社会化や脳科学・神経科学・行動経済学などの発達によってあらためて身近な問いにもなってきました。『ジョジョ』の運命論を読み解くために役立つ著作を紹介します。【選者:杉田俊介(すぎた・しゅんすけ:1975-:批評家)】



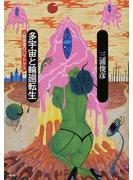

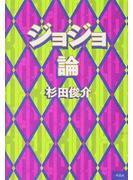
ラディカル無神論をめぐる思想的布置
- お気に入り
- 70
- 閲覧数
- 7943
「神の記憶を持つラディカルな無神論」という言葉を基本線にデリダを読解したヘグルンドの『ラディカル無神論』の翻訳が出版されました。それにあたり、同書といくつかの本を紹介することで、「ラディカル無神論」を巡る布置の概形を描くことを試みました。【選者:吉松覚(よしまつ・さとる:1987-:パリ西大学博士課程)】