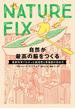投稿元:
レビューを見る
自然は人間をリラックスさせる。自然を欲する本能を満たすからこそ、行動を起こす意欲が湧き上がってくるのが脳のシステム
マルチタスク以外の脳の部位がはたらくin自然
マルチタスクを続けているとエネルギーが使い果たされてしまう。
注意回復理論(しせん
極めてシンプルな結論→できるだけ外に出ること。時には雄大な自然が広がる場所に出かけて畏怖の念を感じること。深々と自然の空気を吸うこと
嗅覚→自然の匂い(アロマも効果あり)
視覚→フラクタルが知覚に優しい
聴覚→小鳥のさえずり。なるべく人工の音がない場所が良い
気持ち→畏怖の念、リラックス効果。
1ヶ月に5時間自然の中にいるだけです認知能力が改善する。この際、携帯電話は必ずオフで
人生でやるべき自然に触れるリスト(ネイチャーピラミッド)は以下
毎年:大自然に畏敬の念を抱く
毎月:ハイキングや森林浴に出かける
毎週:緑豊かな大きな公園、川辺でリラックス
毎日:庭、観葉植物、街中の公園で一息つく
今は都市に人口が大量流入する時代。よって、都市に緑を取り戻す仕組み作らなければならないだろう
投稿元:
レビューを見る
内容紹介
戸外で過ごせば過ごすほど、あなたの頭は冴え渡る!
「森林浴は気持ちがいい」「ハイキングしたら元気になった」それは単に気分が変わるからではなく、実際に自然がストレスを激減させ、脳機能を高めるためであることを科学的に解明。日本をはじめ、各国の最新の研究とその取り組みを紹介する。今日から脳力アップのために、まずは15分間、近くの公園でのんびりしてみよう!
内容(「BOOK」データベースより)
水と緑に触れるだけで、あなたの脳はこんなにも変化する!日本、アメリカ、フィンランドなど、世界中の最新研究をもとに徹底解明。都会でも15分で実感!!
投稿元:
レビューを見る
外に出たくて仕方ない。
大阪への日帰り出張で読んだから、余計にそう思うのかもしれない。
明日から能登旅行。のんびり緑を求めてさまよってみたい。
投稿元:
レビューを見る
おそらくは多くの人が直感的には知っているであろう、"自然の中で過ごすことは心身にとっていいことである"、という実感を、エヴィデンスを紹介することによって確かな事実であると示している本であるわけだが、ヴォリュームが多い割に全体の構成が単調過ぎて、中盤以降はヘタってくる。
舞台となる国や状況は変えながらも、一般的に見れば似たような研究結果を延々と羅列されるのは読み物としてはなかなか辛い。
この手の書籍を流行らせる旗手の1人となった、ジョン J.レイティ氏の著作等とは完成度において比べるべくもなく、期待が外れた。
日本人による研究もいくつか紹介されているが、日本で森林セラピー等にまつわる研究がこれほど為されているとは知らず、勉強になった。
投稿元:
レビューを見る
最新の研究を紹介する書籍では理解を促すためにエピソードを多用するのは当然だが、この本ではそれが冗長すぎる。
投稿元:
レビューを見る
自然は体に良い影響を及ぼす。誰でも同意してくれそうなことであるが、それは科学的に解明されているわけではない。それを科学的に解明しようとしている研究者を著者自身がその研究に参加し、その研究に参加している人の声や自分自身に起こった変化を記述することで自然の効果を明らかにしようとするユニークな一冊。
投稿元:
レビューを見る
何が幸福にしているかのデータをマッピネスというアプリを利用して集めているらしい。今時のデータの集め方に驚いた。結果がどうでるか興味津々です。
都会にいると脳は景色の構造を読み解こうとするらしい、そりゃ疲れるわけだ。ところが、自然の中にいると、脳の中に天然のアヘンが放出され癒され、網膜にもドーパミンを放出し、眼球が楕円形になりにくくしているそうだ。
都会の中に少しでもホッおとできる緑の場所を増やしてほしい。「緑の不平等」といわれるようになるのも近い気がします。
投稿元:
レビューを見る
なぜ私は自然が好きで、走ることや園芸が好きなのか、その理由がわかった。
本から
Nature Fix
「どこにいるか」が幸福度を左右する
予測誤差
人間の細胞が環境を敏感に察知するのを知っていた
人はどんな文化であれ時代であれ「見晴らしが良く、かつ安全に身を隠せる」自分の城が欲しいと思っている
自然には人間を元気にする力がある
「自然欠乏症」
「ネイチャー・ニューロン(自然の神経細胞)
自然こそが人のふるさと
芳香性揮発物質、フィトンチッド
土から採取したカビの胞子からペニシリンをはじめ重要な抗生物質を人工的に作ることが出来る。土には人間を癒す力があるのだ。
マインドフルネス その時の自分の内面的・外的経験にフルに注意を向け、あるがまま受け入れること。
スマイスによれば、ごく短時間でも自然に触れるようにすれば、いま脚光を浴びている瞑想などのストレス解消法より大きな効果が得られるそうだ。
ジョン・ワッツラスキン
「静寂なる大気は甘美にあらず。音ともつかぬほどのものがあたりに息ずくとき初めて心地良さが生まれるー鳥が奏でる三連音符、低く高く鳴く虫の音があってこその静寂である」
「聴力は、僕たちのて天賦の才だ。積極的に外に出て、繊細で美しい音を聞き逃さないように努力しなければ、宝の持ち腐れになる」
緑がある環境にいると向社会的行動をとりやすくなり、地域社会との連携感も強まる。
「低木、木立、岩々を眺めていると、人間が欲する共鳴がつ伝わってくる」
べートーベン
新奇性効果
目新しい新鮮な経験をしていると気分が明るくなる
歩き始めると私たちの足はひとりでに草原や森に向かいます。もし庭園や木陰のある散歩道しか歩かないとしたら、どうなるでしょうか。
ソロー
「歩くことで解決する」 聖アウグスティヌス
「真に偉大なる思想は散策の賜物だった」 ニーチェ
「黙想できるのは歩いている時のみである。足を止めると、思考も停止する。私の頭が働くのは、足を動かしている時だけだ。」 ルソー
自然はカフェインのようなものだ。いや、ヘロインのようなものか。もっと、もっと欲しくなる。
一日に四十分間、ゆったりとしたペースでウォーキングを続ければ、加齢による脳の認知機能の衰えを防げるうえ、実行機能と記憶力が向上し、判断力と行動力のスピードが増す。 クレイマー
「賭けてもいい、自然に囲まれていれば前頭前野に負荷がかかり過ぎることなどありえない」 ストレイヤー
スピリチュアルな感覚は信仰心のみから生じるものではない。自然の中での超越的な経験からも生じるのだ。
スウェーデンの研究によれば、自然の多い環境では男子と女子の運動量のさgあ縮まるという。運動量の男女差を、自然が詰めると言ってもいい。森の幼稚園に通う子どもは、室内で過ごす時間が多い園児に比べて病気になりにくく、より多様でより健康的な細菌叢が体内に大量に宿っている。
ADHDの子どもたちはいわば前衛部隊だ。環境をその子どもたちの脳に順応させる方法がわかれば、ADHDでない者にも道が開ける。ひとつだけ、明確なことがある。人間の脳はそれなりの時間を戸外ですごしているときにもっとも成長する、ということだ。
脳は水が好きだ。ゆえに、川などを都市計画の中心に据えるのは理にかなっている。
投稿元:
レビューを見る
公園へ行こう。森へ行こう。山へ海へ、自然に親しもう。運動も大事だけど自然も大事。若かりし頃にはケッと思っていたけど、雰囲気や気分の問題じゃなくて、数値化して突きつけられるとなあ…。今まさに旬なシンガポール、頑張ってるなー。
投稿元:
レビューを見る
読書の動機→自然が心身に良い影響を及ぼすのではないかという仮説を持ち、その検証のために読んだ。
人類が誕生してきてから自然に囲まれ、守られ、自然と共生してきたのにも関わらず、現代は自然との繋がりが希薄になっているのは奇妙ではないか?
この疑問から始まる本書は、自然が心身に良い影響を与えることを証明する(証明しようとしている)研究を紹介する。
驚いたこと
・森林浴は日本発祥
・都心部を歩いている時と比べて森林を歩いている時では、ストレスホルモンと呼ばれているコルチゾールの値が下がる
・森林で過ごすことでNK細胞が増大し、それは持続する
・樹木が発するフィトンチッドがNK細胞に影響を与える
・実行、空間知覚、デフォルトネットワーク
・血圧が正常値に近ずく
・自然界にある幾何学的パターンのフラクタルは、視覚野にも見られる
・フィンランド国土の74%が森、人口500万人でコテージは200万個
・畏敬の念を覚えるには、「はてしない広がり」が必須、簡単には分類理解ができず、好奇心がかきたてられる、恐怖と謎と美が一体になった時に、記憶に焼きつく
・シンガポールの取り組みーバイオフィリックシティ、国土の緑地は年々増えている(2007年で47%)
その他
・研究の信頼性や妥当性を保つのが難しそう
投稿元:
レビューを見る
自然は人間の心身にどういった影響を与えるのか
ということを科学的に実証しようとしている。
ワシントンに住む著者が世界中を駆け巡り
自然を利用したプログラムの実施者や
研究者に会いにいく。
さらに実験に参加し、ときに批判的な目を持ち
コミニケートして、データと実感をもって
人間はいかに生きていくかを提案している。
世界各地の賢者に会い、知恵を授かり、修行を積みレベルアップしていく·····
まるでRPGのようでワクワクして
学術的な記述も多々あったが
読み飽くことはなかった。
投稿元:
レビューを見る
自然が人にもたらす影響に関する最新の、世界中の論文ごった煮、面白く語ってくれる一冊。読んだ後にすぐさま外に出たくなる。
外に出ることだけでなく、室内でも自然の好影響を受ける方法諸々がある。ので、室内でできる健康法、について関心がある人も良いかも。精神疾患と自然の関係についての話も多くあって、とても身になった。ヒノキのアロマオイル購入。
帯文とかで、チープな印象になって損してると思う。
投稿元:
レビューを見る
自然の中にいるとリフレッシュする感覚。
自然がこのような人の気分やウェルビーイングだけではなく、思考力にも及ぼす影響を数値で示そうとしている。
記憶し、計画を立て、創造性を発揮し、集中する力、社交能力までもが自然によって左右される。
自然の中で15分過ごせば血圧とストレスが低下して気分がよくなり、45分過ごせば認知機能や活力、熟考する力が増し、3日間過ごせば創造性が50%向上するという実験結果もある。
バイオフィリアとは
人間が他の生きた有機体と情緒の面で生まれつき密接な関係をもっていること
注意回復理論(ART)カプラン夫妻
自然の風景の写真をみた後や実際に戸外で過ごしたあとには被験者の思考が明晰になり、不安感が減る
自然には脳を回復させる力がある。それはトップダウン処理を行う部分が解放されて、そのあいだにじっくり時間をかけて回復できるから。
自然は視覚だけではなく、五感に作用する。
森の香りや鳥のさえずりもリラックスさせる効果がある。
フラクタルパターンとは(数学者マンデルブロ)
一見複雑で混沌としている膨大な配列のなかに単純な幾何学的ルールがあること
荒削りな自然の中によく見られる。
フラクタルパターンが脳を活性化させる
視覚系のフラクタル構造が、視野に入ったフラクタル映像と適合すると、生理学的な共鳴が起こり、ストレスがやわらぐ
うつうつとした気分を改善するには、1ヶ月に5時間自然の中で過ごす。一回あたり30分程度を週に二回過ごせばよい。
スウェーデン、デンマーク、フィンランドは世界幸福度は高いが、自殺率も高い。(長く暗い冬が原因か?)
電話で話しながら歩く人たちは、トップダウン処理を行っている注意ネットワークが休まず動き続けている。歩く、聞く、話すというマルチタスクを行っている。特に話す行為は多大な注意を向けなければならない。
自然の中で過ごすと、反芻思考(うつや不安につながる)が改善される
発達過程にある子供の脳には自然が必要
自然の中で遊ぶと、子供の認知機能と情緒的発達において、運動と探検遊びが強化される。
4才から18才のこどもが体を動かすと、脳内物質の働きが活性化し、知覚能力、IQ、言語能力、数学的能力が向上するうえ、学習に向けた下地もできる。
思春期のこどもの前頭前野は、環境刺激によって形成される
都市部で活かす方法は、身近な場所に自然があること。
都会の隅々まで緑で埋め尽くすには、政府の確固としたビジョンが必要(シンガポールの例)
ところどころに少し野性味を加えると、都会の自然は最大の効果を発揮する。
ネイチャーピラミッド(ビートリー)
毎日;庭、観葉植物、街中の公園で一息つく
毎週;緑豊かな大きな公園、川辺などでリラックスする
毎月;ハイキングや森林浴に出かける
毎年;大自然に畏敬の念を抱く
準備、エネルギー、感性がこの本の源泉
樹木は地球のお役に立つべく、す��に気をつけの姿勢で立っている
投稿元:
レビューを見る
都市化が進む現代において現代人は自然より人工物に囲まれて暮らすようになった。しかし、自然の中にいることが人間にとってとても良いことであると、科学的に示している。
私はあまり実感が湧かない。
冷房の風の方が気持ちが良いし、紫外線にあたることも進んでしたいと思わない。
だが本書の通り自然が良い効果を生まない人もいるようだから私はその1人なんだろう。
投稿元:
レビューを見る
自然の木や川や鳥のさえずり、水のせせらぎがどれだけ私たちに心と体の治癒とストレス解消の効果を与え、自然のない都会(特に低所得者層の地域)は心と体にデメリットが多く鬱病や統合失調症になるリスクがあるのかがわかった。この本の影響で私はすぐに部屋に観葉植物をたくさん置いてヒノキの香りがするスプレーを部屋中にかけたりして擬似森体験をして癒されてる。
科学的根拠のある自然の効果がわかりとても勉強になったがアメリカ人作家特有の私情や感想も途中で何度か出てくるから個人的に読むのにすごく時間がかかった。(シュガードーナツが食べたい!みたいは)