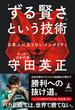0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちゃこさくら - この投稿者のレビュー一覧を見る
サッカーをしている中学生の息子が、サッカー関連の本が欲しいと、書店で実際に吟味し、他とも比べて最終的に選んだ本です。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:なつめ - この投稿者のレビュー一覧を見る
日本人に足りないメンタリティについて、面白く読むことができました。ずる賢さを上手く使う技術が、わかりやすかったです。
投稿元:
レビューを見る
【守田英正をさらけ出した本】
惜しげもなく、自らの頭の中をクリアにさらけ出している。自らの這い上がり方、パスのもらい方、代表にはヒエラルキーがあるとか…わかりやすい言葉でポンポンとバスが飛んでくる。
いや、もしかしたら、すでにさらにその先に守田自身はいるのかもしれない。あえて、分かった気にさせられているだけなのかもしれない。
ずる賢いというより、抜け目がない、捉えどころがない。変化し続けられるのが守田英正の強みだとわかった。
ワールドカップで、守田が躍動する日が、世界を驚かせる日が楽しみだ。怪我だけはしませんように。カフェイン飲んで、最高のコンディションで本番の日を迎えて欲しい。
投稿元:
レビューを見る
通底していると感じたのは、「自分で考える」ということ。監督の教えも、先輩の助言も聞きながら、じゃあ自分はどうするか、何が自分に合ってるかは自分で選択して決めていくことの大事さね。
あと自らに対する自信。「このプレーは得意」「自分は完全に止められる」やっぱり自信は大事だしそれがないと闘えないしこんな本も書けないよな。
大好きになりました。
さあ決戦だ。出てこいよ守田。
投稿元:
レビューを見る
守田選手の考え方がわかる本。当たり前の基準が高いところに身を置いて基礎レベルを上げて、自分の公式の数を増やしていく考え方をサッカー現役時代に知れたらよかったと思いつつ、これはサッカーに限らないと思った。
投稿元:
レビューを見る
なんとなく謎キャラだった守田の人間性がよくわかる。マリーシアのようなズル賢いプレーというよりは正統派な戦術論も多かった。W杯を観てから読むことをオススメする。
投稿元:
レビューを見る
表題につられて購入。そこまでサッカーに詳しくない人には難しいところもあったけど、全体を通してわかりやすい内容でした。ずる賢いをスキルとして認識、使用する考え方は確かに必要だなと思います。
投稿元:
レビューを見る
https://www.gentosha.co.jp/book/detail/9784344040540/
投稿元:
レビューを見る
題名の様な狡賢さについてはあまり書かれていないが、守田選手のものの考え方、取り組み方が書かれていた。
投稿元:
レビューを見る
サッカー経験者ではない私にも読みやすい内容。戦術の部分は少し難しかった。子供にもずる賢く考えることについて伝えたい。
投稿元:
レビューを見る
サッカー日本代表の守田選手の自伝的サッカー本。
ユース年代で特段、代表にも選ばれることのなかった
守田選手がどのようにしてプロや日本代表にまで
昇り詰めていったのか、その秘密が明かされています。
そのポイントは、守田流に言えば、
「ずる賢さ」にあるとのこと。
他の選手から隠れて練習する、
大学4年間は彼女を作らないと自分で決める、
など、自分なりの決め事をしっかりと全うしたことが
プロになれた原点のようです。
一方で、大学時代はタバコを吸っていたり、
あまり食事面には気を使っていなかったりと、
矛盾するユルさを持ち合わせているのが、
守田流というか、オリジナリティなのでしょう。
独特の考えを持った守田選手ですが、
プロを目指す人にとっては興味深い内容だと思います。
投稿元:
レビューを見る
「自分ツッコミ」はめちゃくちゃ使えるテクニックだなと気づきを得た。
客観的に俯瞰的に、どこか他人事のように自分を外からツッコんでイジってみる。
それだけで、心が軽くなったり打開策が浮かんできたりすることは結構あるんじゃないだろうか。
また、「ずるがしこく競争して勝つ」という姿勢からも学びを得た。
「正々堂々」とか「真っ向勝負」とかも、もちろん結構なことなのだが、現実問題としてやっぱり勝たなければ楽しくない。
なんとなく今の日本は「勝敗をつけない」教育をしているように思うが、社会に出ればそこがバッチバチのの競争社会である。
勝ち負けには2つある。
まず身内の中で勝つこと。次に、外集団に勝つことだ。
まず身内の中で勝ち、メンバーに入らなければ、そもそも勝負の土俵に上がれないという厳しい現実がある。
厳しい体育会系の部活を経験している人間は自然とこの感覚を体得しているので、社会に出ても比較的適応できるような気がしている。
もっとふてぶてしくずる賢くクレバーに、ときにはグレーな手段を使ってでも上に登り詰めようと思える一冊でした。