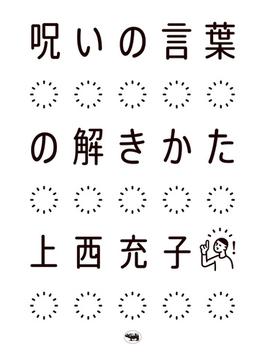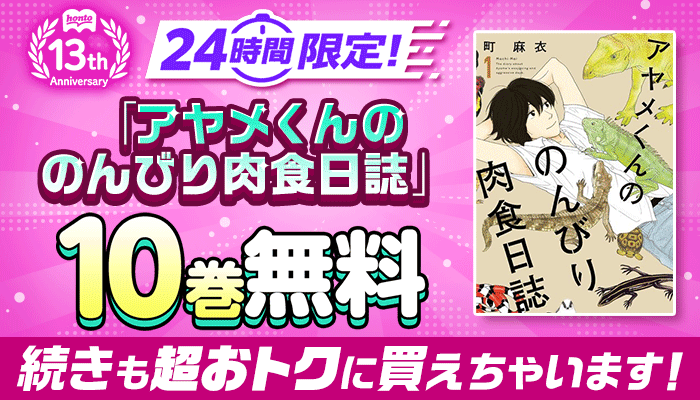- みんなの評価
 7件
7件
呪いの言葉の解きかた
著者 上西充子
政権の欺瞞から日常のハラスメント問題まで、隠された「呪いの言葉」を
2018年度新語・流行語大賞ノミネート「ご飯論法」や
「国会PV(パブリックビューイング)」でも大注目の著者が
「あっ、そうか!」になるまで徹底的に解く!
「私たちの思考と行動は、無意識のうちに「呪いの言葉」に
縛られている。そのことに気づき、意識的に「呪いの言葉」
の呪縛の外に出よう。
思考の枠組みを縛ろうとする、そのような呪縛の外に出よう。
のびやかに呼吸ができる場所に、たどりつこう。
――それが、本書で伝えたいことだ。」(本文より)
呪いの言葉の解きかた
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
呪いの言葉の解きかた
2019/08/17 11:25
分断を乗り越えて団結しなければならない。そんなことも教えてくれる
6人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:くりくり - この投稿者のレビュー一覧を見る
「働き方改革」関連法の審議において、裁量労働制を行っている労働者のほうが通常の労働者より労働時間が短いとした政府提出資料の誤りを指摘し、裁量労働制の拡大を意図した改正法案の国会提出をストップさせた法政大学教授上西允子さん。「呪いの言葉の解き方」は上西さんが「ものの見方・考え方」を指南するものだ。
「働き方改革」関連法の国会での議論において、上西さんは、政府が言い逃れや論点のすり替えを行う答弁を行う中、政府の答弁を「ご飯論法」と自身のTwitterで糾弾した。ご飯論法とは、たとえば、「朝ご飯は食べたか」という質問の「ご飯」を故意に狭い意味にとらえ、「ご飯(米)は食べていない(が、パンは食べたかもしれない)」と答えるもので、追及をかわすために( )内は説明せず、論点をずらしたり、ごまかそうとすることを言う。
的確で絶妙な言葉だ。流行後大賞にもノミネートされた。
「呪いの言葉の解き方」は上西さんが「ものの見方・考え方」を指南するものだ。
言葉は、大切だ。しかし、日常はいつのまにか「常識」とされる言葉に縛られてしまっている。その「常識」はいったい誰が作ったのか?そのことを見極めれば、私たちの思考を縛ろうとする呪縛から解き放たれる。私たちを縛る言葉を上西さんが斬る。
上西氏は、法政大学キャリアデザイン学部で教鞭を執っている。学生が社会や労働の現場に放たれても困らないようにワークルールなどを教えている。呪いの言葉の解き方は学生達へのエールでもあるし、現役の労働者としても「働きづらさ」から解き放たれる視点が得られる。また、ジェンダーをめぐる呪いについては、女性のみならず男性を縛る呪いについても言及される。
特に「労働をめぐる呪いの言葉」の章は、働く中で度々繰り出される呪い「文句を言うと職場の雰囲気を壊す」「会社員である以上どうしようもない」「成果で評価」「ダラダラ残業」など聞き覚えのある言葉が斬られていく。斬られた後は「すっきり」だ。
「逃げるは恥だが役に立つ」「ダンダリン」「しんきらり」等のコミック、映画「サンドラの週末」「わたしは、ダニエル・ブレイク」などのシーンを例に取りこんで、上西さんの呪いの言葉を解くメッセージが語られるのも、理解の幅を広げる。しかし、コミック、映画を見たことのない人には、ちょっと辛いかも知れない。とても考えさせるコミック、映画なので、この本をきっかけにして一読してもらいたい。
安倍首相の答弁撤回をひきだした前述の統計偽装問題によって、与党側から嫌がらせが繰り出される。このときの上西教授を守った法政大学総長の田中優子のメッセージが全文掲載されているが、感動だ。呪いの言葉を解くことは一人でできるものではなく、分断を乗り越えて団結しなければならない。そんなことも教えてくれる。
呪いの言葉の解きかた
2019/07/08 18:48
面白い
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:おどおどさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
私が嫌いな言葉であり、縛られてもいる言葉に「普通は…」というのがあるけれど、それを聞いていちいちイライラするのではなく、流したり、普通だと信じている普通ではない人がなんか言ってるわ!くらい受け止め方を変えれたら楽しいな。
呪いの言葉の解きかた
2019/11/21 15:02
気づかされること・考えること・自分にできることは、まだまだある…
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:misuke - この投稿者のレビュー一覧を見る
この本を手に取り、まず付録を読みました
うわ、きついなぁこれ…が第一印象です
でもでも、本編を読み進めていくと、自身がいかに浅く、
テレビやネット等のマスコミ報道、そして『世の中こうあるべきの決めつけ』に、
埋もれて日々過ごしているのかもしれないと、
少し恐ろしい気分になりました
文中で引用されている研究者・活動家・著者・著書…等々にも、
心惹かれています
行動を起こすことはまだできないかもしれないのですが、
凝り固まった思考回路にかなり刺激的に突き刺さる感覚を受けた1冊でした