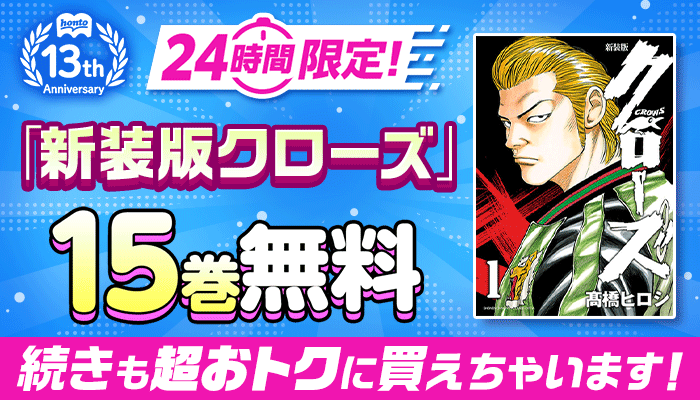- みんなの評価
 2件
2件
「おふくろの味」幻想~誰が郷愁の味をつくったのか~
著者 湯澤規子
肉じゃが、ポテトサラダ、オムライス……? 男女の性別によって、あるいは世代によって、「おふくろの味」という言葉に対する認識や意識は異なる。なぜその味は男性にとってはノスタルジーになり、女性にとっては恋や喧嘩の導火線となり得るのか。わかりそうでわからない、正体不明のこの味について、本書は、個人の事情や嗜好というよりもむしろ、社会と時代を丹念に読み解き、その誕生の経緯と実体が何であるかを探る。
「おふくろの味」幻想~誰が郷愁の味をつくったのか~
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
「おふくろの味」幻想 誰が郷愁の味をつくったのか
2024/03/13 23:44
「おふくろの 味」の変遷 たどった本
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:清高 - この投稿者のレビュー一覧を見る
1.内容
そもそも料理というのは女性が作るものとは決まっておらず、場所によっては男性が作ることもあったが(p.39「女は機織り、男はかしき」)、家庭料理は「おふくろの味」とされている。その変遷をたどった本。第2次世界大戦後の日本における集団就職のような大都市への移動、農村部を起こすビジネス、核家族化、マスメディアの影響、これらが絡み合って「おふくろの味」が作られたが、それは、日本において、親から子へ受け継がれたというものではない。
2.評価
書かれてみればその通りで、筆者にとっての「おふくろの味」も、母が祖母から教わったものではない。筆者の個人的体験を真実とするわけにはいかないが、本書に書かれたことに共感する人が多いと勝手に思っている。
筆者はp.274-277の付録から読んだからか、「おふくろの味」の文献がたくさんあり、時代によって傾向が違う(主に第5章)ことが説明されているのがなるほどと思った。
そのほか、都市部、農村部、核家族と言った、多方面からの検討がなされているのも面白かったので、5点とする。
「おふくろの味」幻想 誰が郷愁の味をつくったのか
2023/03/02 20:09
おふくろの味は母の味ではなかった。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:nekodanshaku - この投稿者のレビュー一覧を見る
「おふくろの味」は、言葉として生まれたのは戦後しばらくしてからであるという。団塊の世代が社会に働きに出、それと共に「おふくろの味」は様々な形を持ちながら、社会に浸透していった。家庭料理でもあり、故郷の料理でもあり、必ずしも母から娘に継承されるものではなかった。多面的な、いろいろな持ち味がある料理であったようだ。その言葉にあまりこだわらなくてもいいのかもしれない、と思う。美味しいっものを食べたいとして料理し、口に入れれば、美味しかった、それでいいと思う。