nekodanshakuさんのレビュー一覧
投稿者:nekodanshaku

三千円の使いかた
2021/11/28 16:55
お金の使い方は、ひとそれぞれ
15人中、15人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
人生を振り返ってみて、またこれからの短い先のことを見つめて、いい物語だなと思う。お金の使い方には、その人の生き方が詰まっている。人それぞれだけれど、使い方を考えていくことは、幸福の追求とどうぎなのだろう。理不尽なことが多すぎるならば、それを見越して、うまく生き抜いてみたい。

同志少女よ、敵を撃て
2022/01/10 16:28
武勇伝ではない。
11人中、11人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
第二次世界大戦、ドイツのソビエトへの侵攻に対する反攻中に、狙撃兵となった少女が親しい人々を失いながら、何かを得る物語である。戦争にはいかなる正義もないが、理不尽さが当然のことであるように覆う戦場で、女性同士の連帯が描かれ、それがとても胸を熱くする。戦争には、人間を悪魔にする性質があり、非戦時下では犯罪であることも大義名分をこじつけられる場面に、主人公は強く憤り、戦争が終わった未来に、希望を見出そうとしていた。よい物語でした。

13歳からのアート思考 「自分だけの答え」が見つかる
2020/04/24 12:17
アート思考について考察
11人中、11人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
絵画や彫刻などの作品を、時として漫然と見ていた。気分転換というか、心の癒しをもたらすものとして、鑑賞していた。しかし、この書を読み、最初の一歩を踏み間違えていたことに気づかされる。自分だけのモノの見方、考え方を喪失していることに気づいてすらいなかったのだ。アート思考とは、自分の内側にある興味をもとに、自分のモノの見方で世界をとらえ、自分なりの探求をし続けること。自分なりの答えを生み出すこと。自分なりの問いを持つことにより、自分だけの答えが見つかる。

流浪の月
2020/02/08 17:29
一緒にいたい人がいる
12人中、11人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
言葉にできない想いを、文字にして伝えようとした物語。切ないような、哀しいような、そして結末は、心を優しく包む。人は、一人の方がずっと楽に生きられる。それでも、やっぱりひとりは怖い。恋でも愛でも性愛でもなく、二人でいると心安らぐ主人公たちの生き方は、自分の住む街にもあるかもしれないなあ。新しいかもしれないこんな人間関係を、言葉を尽くして書いた素晴らしい小説でした。
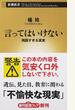
言ってはいけない 残酷すぎる真実
2016/05/30 19:37
不愉快なことに真実があるのかも
12人中、11人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
誰も不快にしない表現の自由は自由とは言わない。不愉快なものこそ語るべき価値があると著者はいう。努力は遺伝に勝てない。「見た目」で人生は決まる。子育てや教育は子どもの成長に関係ない。なんという残酷な事実だろう。最終章で、ハリスの集団社会化論を紹介しているが、子供の人格は、遺伝的な要素を土台にして、友達関係の中で作られていく。子どもはなぜ親の言うことを聞かないかといえば、ヒトは社会的な動物で、集団から排除されれば一人で生きていけず、アイデンティティというのは集団・共同体への帰属意識のことだから。親は無力だというのではなく、親が与える環境(友達関係)が子供の人生に決定的な影響を及ぼす。幾度が驚きながら、しかし納得した。

認知症世界の歩き方 認知症のある人の頭の中をのぞいてみたら?
2021/12/10 12:27
認知症を知る
9人中、9人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
認知症を医療の立場から理解しようとすることは多い。一方、認知症と思われる人の立場、視点から、生活するこの社会がどのように見え、感じ、動いていけるのかを記したものは少ないのだろう。本書はそういう視点を持っているからこそ貴重なのだが、それ以上に読みやすく理解しやすい。物忘れや思い違い、記憶違い、手順の忘れが複合すれば、それは認知障害につながる。自分自身が、これおから徐々に認知症世界に足を踏み入れ、生きていくことを自覚するうえで、役立つ書籍だ。

汝、星のごとく
2023/02/13 18:38
自由に生きること
8人中、7人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
人は生きていく上で、知らず知らず、この社会には生き方の正しい基準や標準というものがあると思い、日々生活していく、そんな思いを揺るがすことができる物語だった。恋とか愛とかは、必ずしも結婚という形式に必要されず、生きる上での互助会だと教えてくれる物語でもある。自分の人生を生きることを誰かに許されて行うものか、そんなことはない、誰もその人生の責任は取ってくれないのに。自分がどうありたいかの選択権は、自分の中にしかないのに、知らないうちに、他に委ねてしまっている自分に気づいた。

Think CIVILITY 「礼儀正しさ」こそ最強の生存戦略である
2019/10/29 11:34
自分を見つめなおす
6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
礼儀正しさ、すなわち礼節を弁えることが、仕事を遂行する上で、重要であると訴える。礼節は人間関係の基礎となる。他人に対する態度、ふるまいに常に敬意があれば、自分自身を前進させることにつながるし、キャリアにも影響を与える。一方、無礼な人間、無礼な言動は、組織に大きな損害をもたらす。礼儀正しくあるために、「与える人になる」「成果を共有する」「褒め上手な人になる」「フィードバック上手になる」「意義を共有する」が必要である。自分の残す功績は、自分が他人に与えるものの事である。自分を見つめなおす、良い機会をくれました。

夜が明ける
2021/10/25 19:03
生きづらい世界
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
この世界には、それほどの生活苦を味わずに過ごしている人が知らない不幸があることが、この物語で示される。自己責任などと言われて、助けられることを求めることが出来ずに生きてきた男たちの友情は、読む者の心を切なくさせる。助けてもらうとは思わせない援助の網が、きちんと世の中で働くといいのに、その網を使いもしない人たちが破り捨てようとしているのが、現代社会なのか。作者の想いは、多くの人々に伝わると思う。

人は、なぜ他人を許せないのか?
2020/03/18 11:05
知らないうちに正義中毒
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
我こそは正義と思ってしまうと、他人に正義の制裁を加える。そして脳の快楽中枢が刺激され、ドーパミンが放出されると、正義に溺水しまった中毒状態に陥るという。それが他人を許せなくなる脳のしぐさなのだ。正義中毒は、彼に伴う脳の保守化が関与するのかもしれない。正義中毒から自分を解放するためには、自分をいつも見つめ直し、そして自分にも他人にも、一貫性はないということを認識しなくてはいけない。明確な解決方法はないかもしれないが、答えがないからこそ考え続けなくてはいけない。

通い猫アルフィーの奇跡
2016/08/19 12:54
ほっこり猫物語
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
物事がうまく進まないように思うことが多いこの世界、それが人に喜怒哀楽をもたらす一因なのだが、哀しみの気持ちを抱いたときに、なにかそれを和らげてくれればと思う。猫好きの私は、そのなにかを猫の存在だと思いたい。「通い猫アルフィー」のような猫がいればいうことはないのだが。物語を読み進めるうちに、こころはゆったり温かくなり、膝の上に猫が眠っているような気がする。誰ともつながっていないと思う時、この物語は、愛ある通い猫アルフィーを呼び寄せてくれる。

極楽征夷大将軍
2023/06/26 21:57
足利尊氏を主人公とした一代記
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
足利尊氏を主人公とした一代記であるが、主人公を取り巻く弟・直義、足利氏家宰・高師直らの視点から主人公を描く形になっている。茫洋としたとらえようのない人物であったようだ。世間の欲望の上にぽっかりと浮かび上がる化身のようなものだという表現が作中にあるが、鎌倉幕府執権北条一門を滅ぼし、幕府を起こすために、直義や師直らにより神輿として担ぎ上げる人物としての主人公は、担ぎ上げてくれた人々を、内ゲバのような戦いの中で失い、自らは遅ればせながら自立していったようだ。室町幕府成立前後の世の流れが、よく理解できた。

傲慢と善良
2022/10/02 21:25
自分自身の傲慢さを知る
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
重い主題を抱え込んでいる小説を読んでしまった。ひとつの結婚に至る男女の想いが物語の流れだ。、それぞれの心の温度で、日常的に自分隊が抱くちょっとした違和感のようなものが、炙り出されていく。親兄弟の当事者たちに向ける視線、友人たちの心も模様、そして世間体という空気が、自分の意志が分からないという状況を、中途半端に安定させてしまうのだ。自分で選択しているようで、心の渦は、周囲の影響を受け続け、時に善良な人になり、時に傲慢に行動してしまうのかもしれない。読む者の心を一筋のメスの切開線が入り込むようだった。

物語ウクライナの歴史 ヨーロッパ最後の大国
2022/03/05 15:47
ロシアのウクライナへの侵攻という時期
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
ロシアのウクライナへの侵攻という時期に、本書を読むことが出来た。ウクライナの歴史を知り、その地政学的な意義を理解することは、この時代の動きにより正しく対応するために重要だと思う。ウクライナは面積、人口においてヨーロッパ第二の大国であり、大穀倉地帯を有する点でも、重要な地域となっている。1654年ウクライナ・フメリニッキーがモスクワ公国と締結したペレヤスラフ協定を、ロシヤがウクライナに介入する根拠の一つにとらえているようだが、原本は紛失し、怪しい複写しか残っていない事実が、ロシアのうさん臭さを示している。

一汁一菜でよいという提案
2022/02/18 09:57
食事により生活を整える
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
日本の食文化を見つめると、こういう提案ができるのかと感心した。食べるという行為は、生きていくうえで必須の行為であるが、食事をする、料理をするということになると、身構え、別の意味合いを持つようになる。美味しいものが巷にあふれ、宣伝されるが、毎日が美味しいものを口に入れる必要はなく、一生懸命に丁寧に生活するために、食事をするというスタイルには、一汁一菜がふさわしい。食材を集め、下ごしらえをし、調理して、器に入れ、「さあ召し上がれ」と提供し、調理された汁物とご飯を食すという一連の行為が食事だと初めて知った。

