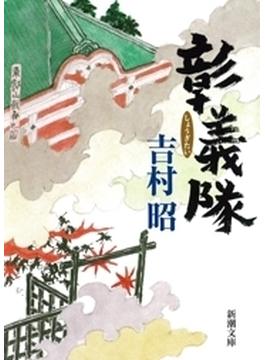- みんなの評価
 5件
5件
彰義隊
著者 吉村昭
皇族でありながら、戊辰戦争で朝敵となった人物がいた──上野寛永寺山主・輪王寺宮能久親王は、鳥羽伏見での敗戦後、寛永寺で謹慎する徳川慶喜の恭順の意を朝廷に伝えるために奔走する。しかし、彰義隊に守護された宮は朝敵となり、さらには会津、米沢、仙台と諸国を落ちのびる。その数奇な人生を通して描かれる江戸時代の終焉。吉村文学が描いてきた幕末史の掉尾を飾る畢生の長篇。
彰義隊
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
彰義隊
2009/10/04 19:15
天皇になるか天下のお尋ね者になるかは紙一重
7人中、7人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:あまでうす - この投稿者のレビュー一覧を見る
徳川幕府に最後まで忠誠を誓い、上野の森に立てこもって薩長の朝廷軍と戦った彰義隊は新撰組と並んで江戸が最期に咲かせたささやかな玉砕の2輪の華でしょう。
しかし著者がこの本で精細に描いているのは、その彰義隊本体ではなくて、彼らの精神的支柱と仰がれ、後に奥羽列藩同盟の盟主に担ぎあげられた寛永寺門主の輪王寺宮の波乱に満ちた生涯の軌跡です。
輪王寺宮は名は能久、法名を公現と称し、弘化4年1847年伏見宮邦家親王の第9子として生まれ、12歳で勅命により輪王寺宮を襲名し、元治元年1864年には親王の位の第1位をさずけられて天台宗の最高責任者として比叡山、東叡山、日光の3山を管領するようになりました。
輪王寺宮は慶応4年1867年1月の戊辰戦争で敗北した一橋慶喜の一命を救助しようとして箱根を下り、朝廷軍の東征大総督であった有栖川宮の慈悲を乞うたのですが、にべもなく拒否されてしまいます。有栖川宮は自分の婚約者であった和宮を奪った徳川家を憎み、その一族である慶喜に味方する輪王寺宮に冷酷に対応したのです。
同じ皇族のよしみを心頼みとし、交渉に楽観的であった輪王寺宮の自負と矜持はむざんに打ち砕かれ、あまつさえ有栖川宮率いる官軍は彰義隊を討伐すると称してなんの断りもなく輪王寺宮が居住する寛永寺を砲撃します。
この時のトラウマが彼の運命を一変させてしまいました。朝廷を代表する一員であり、明治天皇の伯父でありながら、輪王寺宮は有栖川宮への敵意と対抗意識から官軍に反旗を翻し、賊軍である幕府の側に立つのです。
しかし東北雄藩の奮戦むなしく奥羽列藩同盟はあっという間に崩壊し、輪王寺宮はまたしても一敗地にまみれてしまいます。朝廷軍に降伏して京に呼び戻された輪王寺宮は、東征のみならず佐賀の乱や西南戦争の鎮圧にも勲功をあげた有栖川宮に激しいライバル意識をいだき、兄の小松宮の力を借りてドイツに留学して軍事技術を修得し、勃発したばかりの日清戦争に従軍して国恩に報いようと望んだのですが、その切なる願いを握りつぶしたまま宿敵の有栖川宮は61歳で逝去してしまいます。
けれども明治23年5月、ついに宿願が果たされる日が到来しました。兄の小松宮によって近衛師団長に任じられた輪王寺宮は、清国と通じた台湾の不穏な動きを鎮圧することを命じられたのです。かつての朝敵としての汚名をそそごうと勇躍した輪王寺宮は、兵士の先頭に立って清国軍と激戦を繰り広げたのですが、ちょうどその頃台湾で大流行していたマラリアに感染し、同年10月28日48歳で病没しました。
もしかすると明治天皇に代わって天皇になっていたかもしれない一人の男が高僧となり、反乱軍の長となり、天下の朝敵となり、ついには大日本帝国の軍人として異国の地に斃れる。著者はその波乱万丈の生涯と彼を最後まで突き動かした強烈な心的機制を慈愛の目で丁寧に描きつくしています。
彰義隊
2021/10/06 15:25
吉村昭の最後の歴史小説
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:夏の雨 - この投稿者のレビュー一覧を見る
この作品は多くの歴史小説を書いてきた吉村昭が2005年11月に刊行した作品で、2006年に亡くなる彼にとっては最後の歴史小説になった。
吉村昭という作家を見た場合、純文学的な作品でもそうだが、彼が生まれ育った日暮里あたりの下町を愛し続けていたかがよくわかる。
それは井の頭公園そばに終の棲家を構えてからも変わらなかったのではないだろうか。
そんな吉村だったゆえに、彰義隊の旗印に祭り上げられた上野寛永寺の山主であったこの物語の主人公輪王寺宮が逃亡の過程で吉村ゆかりの土地土地をめぐった姿を追体験した時、どのような思いであったろう。
吉村はこの作品の「あとがき」で「敗れた彰義隊員が私の町にものがれてきたという話などを、断片的に耳にしたりした」ことがあると語っている。
時代を超えて、逃げていく輪王寺宮たちの姿を見つめている吉村少年の姿を見るようだ。
輪王寺宮というのは、皇族の一人ながら幼児の時に出家し、幕末の争乱の際に寛永寺の山主であった人物である。
その立場でなければ、あるいは官軍の将であったかもしれず、人の人生というのはわからないものだ。
作中にも「時代の大きな流れの前で、人間は無に等しい」という言葉が出てくるが、それでもこの時代であれば岩倉具視のようにしぶとく勝ち抜いた人物もいるだから、なんともいえない。
輪王寺宮の生涯もまた同じで、最後には国葬になったことを思えば、この人の人生もいかばかりのものだったのだろう。
彰義隊
2019/06/03 00:28
吉村氏最後の歴史小説として合点がいく
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ニック - この投稿者のレビュー一覧を見る
吉村昭最後の歴史小説。「桜田門外ノ変」「天狗争乱」などの著作で水戸藩士が幕末の変動に与えた影響を描いてきた著作の流れからして、戊辰戦争を描く本作は題材としてとても合点がいく。主人公である輪王寺宮が上野から日暮里、根岸、三河島へと落ちのびていく行程は、そのエリアで生まれ育った吉村氏こそが描く必然性に充ちている。