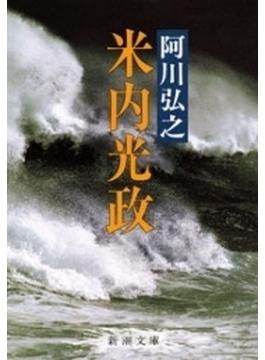- みんなの評価
 1件
1件
米内光政(新潮文庫)
著者 阿川弘之
「米内光政は国に事がなければ、或いは全く世人の眼につかないままで終る人であったかも知れない」(小泉信三)。海軍兵学校の席次は中以下、無口で鈍重と言われた人間が、日本の存亡のときに当り、自らの手で帝国海軍七十余年の栄光を葬り去った。一億玉砕よりも、未来ある敗戦に賭けて……。最後の海相の人物と識見を描いて、危機に際しての真の指導者とは何かを問う、感動の記録文学。
米内光政(新潮文庫)
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
米内光政 改版
2007/04/08 21:54
この芒洋から何を汲み出せるか
6人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:SlowBird - この投稿者のレビュー一覧を見る
軍部特に海軍にも開戦反対の動きはあったという引き合いによく出されるのが米内光政。昭和12年から14年に海軍大臣。翌年総理大臣となるが半年で総辞職。それから間を置いて、小磯、鈴木貫太郎、東久邇宮、幣原内閣で海軍大臣。三国同盟に反対、開戦に反対、それで内閣は引きづり降ろされる。終戦のために動くが捗々しく進まずに、結局は無条件降伏。敗戦処理に働く。
見識としては、ベルリン滞在などの経験もあるが、山本五十六、井上成美などと足並みを揃えて協調したことを考えると、海軍の人材育成からはある程度当たり前のようでもある。ただ当時の陸軍の独走、強硬な論調、それに引きずられた世論になびかなかったのは、特異とも言える。結局日本を戦争から救ったかというと、破滅へ向かう道に相当に水を差した。これは相当に戦略的に行動しなければ難事だ。米内がいなければ相応の人物が代役をしたかもしれないが、まずは大きな功績ではある。分かりやすさから言えば、ある種つかみ所の無い人物のようでもあり、そういう人物像を資料を丹念にあたって、淡々と、しかし歴史上の位置付けを明確に照らしだしたのが本書だ。
乱世が来るべき時に、必要な、是非にいてもらいたい人物ではある。では我々の社会は再度このような人物(山本でも井上でも)を輩出することができるかというと、正直のところ自信が無い。あるいは生まれうるとしても、当時よりさらに強い世論(メディア)の力で圧殺されるのではないかという危惧もある。
一方では、米内のような人物の育て方、これは難題。美丈夫で女によくもてたという。自己実現のために、権力や愛国心を依りどころにする必要が少なかったとは言える。しかしそれは人間に取っては如何ともしがたい才能である。せめてそのような人物、あるいはその対極のような人物(玉音盤を奪おうとした陸軍軍人のような)を見分ける目も、我々は育てていない。
だからもう一方の、このような人材を活かす(殺さない)社会でありうるか、それにも自信を持てない。
もう八方塞がりである。一つの解は、一人の英雄に頼らない成熟した社会。実は戦後の(戦前も)日本はこれに近かったとは思うが、暴走するカリスマに対しては極めて脆弱でもあるのも現代史が示す通り(それは日本に限った話では無いが)。歴史を繰り返して、いつかは何かしら教訓を得る日が来るのだろうと、なんかそんな妄想を呼び起こされました。