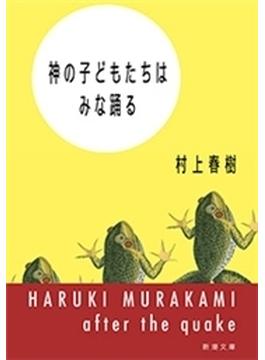- みんなの評価
 16件
16件
神の子どもたちはみな踊る(新潮文庫)
著者 村上春樹
1995年1月、地震はすべてを一瞬のうちに壊滅させた。そして2月、流木が燃える冬の海岸で、あるいは、小箱を携えた男が向かった釧路で、かえるくんが地底でみみずくんと闘う東京で、世界はしずかに共振をはじめる……。大地は裂けた。神は、いないのかもしれない。でも、おそらく、あの震災のずっと前から、ぼくたちは内なる廃墟を抱えていた――。深い闇の中に光を放つ6つの黙示録。
神の子どもたちはみな踊る(新潮文庫)
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
神の子どもたちはみな踊る
2011/05/26 07:54
作家の役割
8人中、8人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:K・I - この投稿者のレビュー一覧を見る
『神の子どもたちはみな踊る』には6つの短編が収められていて、
それらはすべて1995年2月に舞台が設定されている。
これは1995年1月の阪神・淡路大震災と3月の「オウム真理教」による地下鉄サリン事件の2つが戦後日本の大きな転換点だと村上が考えるからである。
田中康夫は阪神・淡路大震災後、印税を寄付しなかった(少なくともそう表明しなかった)村上春樹を激しく批判したが、はたして、大きな災害があったときに作家にできることは、お金を送ることだけなのだろうか?
2011年3月の東日本大震災に直接の影響を受けた小説というものは主だったところではまだ見られていない。
しかし、村上のように作家として大災害にフィクションで答えること、それも作家の一つのあり方なのではないか?と思う。
1.地震のニュースばかり見ていた妻が突然家を出て行く話。
2.流木で焚き火をする初老の男と若くない女の心の交流。
3.新興宗教の信者の母をもつ若者の「父親探し」。
4.タイで休暇を取っている女医の体験。
5.かえるくんが東京に大地震をおこそうとしているみみずくんとたたかう話。
6.淳平という短編作家の日常を描く村上春樹唯一の「家族小説」。
読み直して、ここにはたしかに「フィクションの力」があることが分かる。
作家の役割は一義的ではない。
それぞれがそれぞれできることを、
やればいいのだ。
神の子どもたちはみな踊る
2010/02/05 21:28
阪神大震災から15年、節目に読むことによってより感慨深いクオリティの高い作品集だと言えそうです。切ない話ばかりですが、読み終えるとなぜか勇気を少し分けて貰った気がするところが素敵なのでしょう。全6篇でどれもいいのですがなんといっても「蜂蜜パイ」が秀逸。ラストに持ってきたところが心憎くいです。
6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:トラキチ - この投稿者のレビュー一覧を見る
阪神大震災を題材というか間接的なテーマとした短篇集。
1995年という年は阪神大震災と地下鉄サリン事件の両方が勃発します。戦後の日本の歴史を変えたといっても過言ではない1995年。
今年で15年となりますが、この作品は読者にとってはまるで阪神大震災のようにいつまでも記憶に残る作品集だと言えそう。
そしてこの作品集は日本という国が決して安全ではないという警告を促しているのですね。
それは何も震災の当事者だけではありません、なぜなら作品に出てくる地域は神戸以外の地域ばかりなのですから。
全6篇からなりますが、それぞれの構成及び内容が素晴らしいと思います。
まずは妻が震災後家出をする「UFOが釧路に降りる」からラストの「蜂蜜パイ」まで。
それぞれ悩みを持った人たちが闇に包まれる生活を送っています。
読者は1篇1篇読み進めるごとに救いを見出すことができるのですね。
とりわけラストの2篇は強い救いが感じられ、明るい光明が差している印象が強く感じられました。
かえるくんやくまきちは読者に希望と勇気、そして感動を与えずにいられません。
それ以外の他の篇もすべて素晴らしく読者によって好みは分かれそうですが。
なかなか村上さんの描く世界を言葉で表すのは困難なのですが、どうなんだろう、手元に置いていつでも読み返せるような状態にしておきたい作品ですね。
読めば読むほど味わい深いものだと思われます。
読み終えた後におぼろげながら“全体像”を感じ取ることが出来るのですが、繰り返し読むことによってよりくっきりすることだと思います。
だから私の感想も初読時の感想ということでご容赦くださいね(笑)
本作を読む限りの村上さんの特徴として強く感じたところを書きます。
やはり誰もが持っている寂しさを認識しつつ、希望を読者に見出す指針を与えてくれるところでしょうか。
その希望の大きさの大小は読者によって違うと思いますが。
読者としたらどうなんだろう、“なぜ自分は生きているのだろう”ということを再考せざるをえないのですね、否応なしに。
それは他の作家にはなかなか真似が出来ない芸当だと思います、次元が違うというかなんというか。
少し余談ですが、たくさん海外小説の話題が作中に出てきます。
たとえばほとんど英語圏の作品しか読んだことのない読者の私は作中のかえるくんの次のセリフに読書意欲を掻き立てられました(笑)
もし読んでいたらもっと村上ワールドを理解できていたのにという悔しさを噛みしめながら・・・
“ぼくが一人であいつに勝てる確率は、アンナ・カレーニナが驀進してくる機関車に勝てる確率より、少しましな程度でしょう。片桐さんは『アンナ・カレーニナ』はお読みになりましたか?”
(「かえるくん、東京を救う」より引用)
人生、何事も勉強ですね(笑)
神の子どもたちはみな踊る
2011/05/09 18:19
空虚さと向き合い、新しい方向へ。
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:きゃべつちょうちょ - この投稿者のレビュー一覧を見る
この短編集に登場する主人公たちは、
阪神・淡路大震災をきっかけに
自分がからっぽであることを再認識してしまう。
地震の前から、彼らは崩れそうなものを抱えていて、
それが崩れてしまうのは時間の問題だったのかもしれない。
あまりにも大きな崩壊が起きると、
なにをやっても無駄なんじゃないかと
おそろしい無力感につきまとわれる。
いまの力ではどうにもならないこと、
理由づけのできない悲劇の前には
自分があまりにも小さいことを思い知らされる。
地震という大きな外的要因と、自己の内的要因がリンクして
登場人物たちは崩れ落ちた自分の中の空虚さを知る。
しかし彼らは、おそいかかってくる無力感の中から足を踏み出す。
物語に終わりはくるけれど、彼らの人生は続いていく。
続いていくという予感に(そこにきちんと人生が存在することに)
救われる思いがする。不思議な癒し効果がある。
なぜかわたしは、最後の話から読んでしまったのだが、
この本はちゃんと順番どおりに読んでいくことをお薦めする。
巻末の書き下ろし、エンディングの感動を満喫するために。
ハルキニストではないけれど、
村上作品で偏愛しているものがいくつかある。
それらは、あるときどうしようもなく読みたくなり、
ページを捲ると、喉の渇きを潤すがごとく、一気に読んでしまう。
この本も、そういう一冊になるかもしれない。