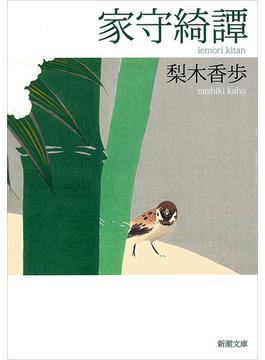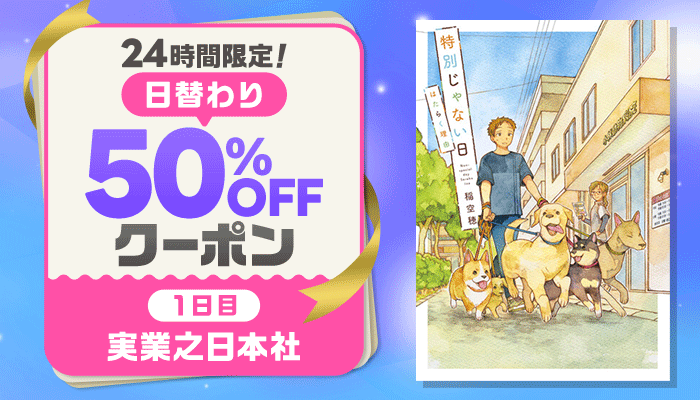- みんなの評価
 25件
25件
家守綺譚(新潮文庫)
著者 梨木香歩
庭・池・電燈付二階屋。汽車駅・銭湯近接。四季折々、草・花・鳥・獣・仔竜・小鬼・河童・人魚・竹精・桜鬼・聖母・亡友等々々出没数多……本書は、百年まえ、天地自然の「気」たちと、文明の進歩とやらに今ひとつ棹さしかねてる新米精神労働者の「私」=綿貫征四郎と、庭つき池つき電燈つき二階屋との、のびやかな交歓の記録である。――綿貫征四郎の随筆「烏〓苺記(やぶがらしのき)」を巻末に収録。
家守綺譚(新潮文庫)
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
家守綺譚
2018/11/11 00:23
剣も魔法もないファンタジー。正統派日本文学。
9人中、9人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:たけぞう - この投稿者のレビュー一覧を見る
文庫本の表紙で,雀が竹やぶから顔を覗かせている。
竹には六十年に一回という花が咲いている。
カバー装画は神坂雪佳「雪中竹」という作品だそうだ。
描き下ろしではないのに,これほど雄弁に内容を表している
表紙にはなかなかお目にかかれない。
竹取物語。舌切り雀。
家守綺譚は日本の伝統の系譜に根ざした作品だと思う。
目次を見ると二十八種類の植物の名前が並ぶ。
総数197ページなので,一話あたり七ページ前後の
掌編小説集ともいえる。
明治の頃,電燈が灯り始めた頃が舞台。文明開化とともに
失われていった古き良き日本の土着風俗が描き出されている。
綿貫征四郎という売れない作家がいる。
亡くなった親友の高堂の父親から,娘の近くに隠居することに
なったので高堂の家の守をしてくれないかとお願いされる。
その高堂の家に住むようになった所から話が始まる。
一話目はサルスベリ。夕方から風雨が激しくなり夜半に収まる。
それと同時にキイキイという音が掛け軸から聞こえ始める。
掛け軸を見ると雨の風景になっており,死んだはずの高堂が
ボートを漕いで近づいてくる。
綿貫は「どうした高堂」と声をかけ,高堂は
「なに,雨に紛れて漕いできたのだ」と答える。
なんでも,庭のサルスベリが綿貫に懸想をしているので
伝えに来たとのこと。
考えてみると掛け軸の中の親友と話をするなんて
あり得ないのだが,なぜかとても自然だ。
私は「懸想をしている」なんて言葉遣いにもまいってしまった。
全編こんな調子だ。サルスベリに惚れられた綿貫は,
木陰で本を読んでやるようになる。
河童や人魚,小鬼もそれぞれの掌編に登場する。楽しいなあ。
梨木さんはイギリスにしばらく住んで現地の童話作家に
師事していた。その影響か初期の作品はイギリス人が出てきたり,
古びれた洋館が舞台になったりしていたが,
日本の伝統を見つめる作品も徐々に増えてきている。
伝統的だからいいというつもりはないが,剣と魔法の物語で
登場人物が日本人の名前だったりする時の違和感は,
やはり事実として感じるのである。
お互いのいいところを取入れ,新たな日本ならではの
物語を読みたい。梨木さんに答えを一つ見せてもらった気だする。
自分の体は,やっぱり味噌としょう油でできているんだなあと
強く実感したのであった。自分の足元は大切にしないとね。
家守綺譚
2010/07/23 21:48
「此方」と「彼方」を分かつもの
10人中、9人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:wildcat - この投稿者のレビュー一覧を見る
綿貫征四郎は、学生時代に亡くなった親友・高堂の実家に住んでいる。
高堂の父親から、年老いたので嫁に行った娘の近くに隠居するから、
この家の守をしてくれないかと頼まれたからである。
綿貫は、文筆家だが、決して売れているわけではない。
非常勤で働いていた英語学校正職員の話があっても、
本文は物書きだから、そちらの方に精を出したくないと思ってしまうような性分。
住まっていることで月々のものがもらえる家守の話は、渡りに船だったのだ。
ここは、「此方」と「彼方」の境界線が実にあいまいにして、
それでもやはり境界はある、という世界。
『西の魔女が死んだ』を読んだ時も、
「異なる考えをどれも包み込むように共存させているような
穏やかな力が作品世界全体を支えている」と感じたのだが、
この家守綺譚にも同様のものが流れている。
学生時代ボート部だった高堂は、山を一つ越えたところにある湖で
ボートを漕いでいる最中に行方不明になっていた。
その高堂が、掛け軸の中から現れる。
ボートを漕いでやってくる。
―どうした高堂。
―逝ってしまったのではなかったのか。
―なに、雨に紛れて漕いできたのだ。
―会いに来てくれたんだな。
―そうだ、会いに来たのだ。
高堂はこともなげに云うが、綿貫も自然とこの出来事を受け入れている。
本書は、すべて植物や鳥の名前で章題が立てられており、
全体で、綿貫が家守を始めてからちょうど1年の季節がめぐる。
サルスベリに懸想されたり、犬のゴローに懐かれたり、
ヒツジグサが「けけけっ」と鳴くと思ったら河童が迷い込んでいて
それをゴローが滝壺まで送り届けたり。
不思議なことが淡々と起こる。
綿貫の受け入れ方が淡々としているから、
その不思議な出来事が日常として起こっていても
全くおかしくないように思えてくる。
それらの出来事を普通に受け止めるのは、綿貫だけではない。
綿貫に季節のものを持ってきたり、おすそ分けをしてくれたりと
なにくれなく面倒見てくれる隣の奥さん。
(実は、犬のゴローのことを気に入っていて、
綿貫の方がゴローのついでだという説もある。)
彼女は、ゴローが持ってきた、綿貫には何だかわからないものを見て、
河童の抜け殻に決まってますと自信満々に、一目見ればわかるというような人。
「おかみさんの論理は、机上で組み立てたものではなく、
すべて生活実感から出てくるものであるので、
非常な説得力と迫力を持つ」
と綿貫は思っている。
このお話の世界が「生活実感で出てくるもの」である不思議。
でも、読んでいるうちに、こちらも意識をふっとずらせば
この物語の世界は実感のある出来事になるんじゃないかと思えてくる不思議。
綿貫のところに原稿を取りに来る後輩の山内も、
そういったことを当たり前に思い、説明までしてくれる。
山内は、綿貫がサルスベリに懸想されていることも自然に受け止め、
サルスベリを入れ替えてリサベルと女性の名前を付けて
呼んであげたらどうだなんて言ってきたりする始末。
高堂が此の方にボートでやってくることを知ると、
先輩に湖の底のことを聞いて、ぜひにもそれを書くようにと頼むくらいである。
高堂は、掛け軸の中からだけではなく、いきなりふっと現れたり、
しばらく来なかったりするが、現れて綿貫と言葉を交わすたびに、
高堂自身のことを、読者もだんだんわかってくる。
綿貫は、山内から頼まれた湖の底のことを、高堂に訪ねる。
高堂は、それはやはり自分の目で見るのが一番だろうという。
綿貫はそれができるのかと半信半疑で訊くが、
お前の覚悟次第だと言われるのみだった。
高堂の存在は、「此方」と「彼方」は
それほど遠いものではないのではないかと思わせる。
だが、確かに綿貫は「此方」の者で、高堂は「彼方」の者なのだ。
かたや肉体を持って今を生きる者、かたや肉体を手放した者。
高堂は語れないものについては、
「おまえにそれを語る言葉を、俺は持たない。人の世の言葉では語れない。」
と説明をしないが、
綿貫は、高堂に無粋だと言われても、
「しかし俺はそれを言葉で表したいものだと思う。」
綿貫は、これが高堂と自分との決定的な差異なのだと悟る。
高堂と綿貫の違いをはっきりと示すのが、
最終章の葡萄に登場するエピソードだ。
綿貫は、「私は与えられる理想より、
刻苦して自力でつかむ理想を求めているのだ」と気づく。
そして、同時に、それでも彼方に憧れる気持ちもあることも認めている。
これは、『西の魔女が死んだ』で、
おばあちゃんが語っていた、魂の本質の話ともつながる。
魂は身体を持つことによってしか物事を体験できないし、
体験によってしか、魂は成長できないんですよ。
ですから、この世に生を受けるっていうのは魂にとっては願ってもない
ビッグチャンスというわけです。成長の機会が与えられたわけですから。
そして・・・。
いちばん大事なことは自分で見ようとしたり、聞こうとする意志の力ですよ。
こんなおばあちゃんの声が、どこかから聞こえてきそうである。
最後に、綿貫を此方に留めたものは、いかにも綿貫らしい。
「私には、まだここに来るわけにはいかない事情が、他にもあるのです。」のあと、
彼がなんと言ったのか、ぜひ読んでみていただきたい。
不思議な者たちに見入られながら、
彼方の者と言葉を交わしながら、
それでも、確かに綿貫が此方の者である理由が
この葡萄の章に集約されている。
本書の綿貫の気づき、そして、『西の魔女が死んだ』で
おばあちゃんからまいが学んだことは、
「魂と身体の合体であるわたし」を味わって生きることの大切さであろう。
それは、常に梨木香歩作品の根っこに存在するものに思えた。
家守綺譚
2011/09/27 09:17
静謐な、水墨画のような世界。四季折々の花と共に、河童も鬼も犬も人も調和を保って静かに暮らしている。
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:道楽猫 - この投稿者のレビュー一覧を見る
しんとした、静謐な世界。
水墨画のような風景の中、風がさわさわと庭を通り抜け、池でとぷんと小さく水が跳ねて波紋が拡がる。
そこではサルスベリの木が人に懸想をし、河童がしばし逗留し、もちろん狸は人を化かす。
そして座敷の掛け軸の中から、湖で行方不明になったはずの友人が、何気にボートを漕いでやってくる。
一見すると怪談かとも思われるような物語が、ここではごく当たり前の情景として静かに語られるのだ。
昔、少し生け花を習っていたことがある。
そこの先生がおっしゃられていたのだが、植物にはどうも
「手を嫌う」
ということがあるらしい。人参などは、蒔き手によっては全く芽を出さないそうな。
嘘か本当かわからないが、相性、というものは、確かに植物と人の間にもあるのだろう。
そしてそれはもちろん、動物と人の間にも存在する。
ゴローが何を思って綿貫の家に居つくことにしたのか、それは常人には知り得ぬことだけれど、ゴローはたいへん偉大な犬であるので、綿貫の中にある無防備なまでの率直さ、柔軟さを直感で嗅ぎ取ったのだろう。
実際、綿貫は大した人物だと思う。
諸々の不思議を不思議のまま、「そんなものか」と素直に受け容れる。
そしてそのような柔軟さを保ちながらも、安逸とした生活への心惹かれるいざないを良しとせず
「こういう生活は、わたしの精神を養わない」
と言い切る凛とした潔さも同時に持っている。
確かに彼は立派に「家守」なのだ。
精神の高みを目指しつつも、 少欲知足の生活を守る。
欲しいものは何でも望めば簡単に手に入る、便利な生活に慣れた今の私たち日本人が
少し昔に置いてきてしまった"慎ましさ"に、ここで出会う。
すっと喉を過ぎ、いつのまにか身体中に染み渡る
清浄な水のような、そんなしずかな文章に心満たされた。
そのすべてに圧倒されつつ、身を任せるのがこの物語を読む幸せ。