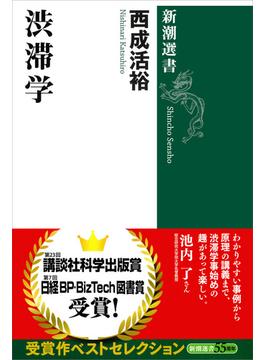- みんなの評価
 8件
8件
渋滞学(新潮選書)
著者 西成活裕
人混み、車、インターネット……世の中、渋滞だらけである。新しく生まれた研究「渋滞学」により、その原因と問題解決の糸口が見えてきた。高速道路の設計のコツから混雑した場所での通路の作り方、動く歩道の新利用法まで。一方で、駅張り広告やお金、森林火災など停滞が望ましいケースでのヒントにも論及。渋滞は、面白い!
渋滞学(新潮選書)
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
渋滞学
2007/10/08 19:28
役立つ視点をあなたに
8人中、8人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:GTO - この投稿者のレビュー一覧を見る
あとがきにもあるように、これは専門書ではない。啓蒙書である。とにかく分かりやすいのが素晴らしい。世に最新の学問を分かりやすく説明するとした本が多数あるが、本当に分かりやすいものはまれである。この本は実感に即した例を用いてうまく説明していて、すんなり納得できるものばかり、講談社科学出版賞受賞もうなずける。
この本で扱われているASEP「非対称単純排除過程」とセルオートマトン法の視点(手法)は、他の学問分野はもちろん日常生活での行動決定にも応用がきく。現在社会のストレス軽減に、緊急時のパニック回避に、学問的にも、個人として行動する上でも役に立つ。渋滞はもちろん、通勤・通学でイラっとしたことがある人、必読です。
そしてまた、コンピュータが万能であると思っている人には、「パイこね変換」の結果を知るだけでもためになる。どんな道具も何ができて、何ができないか。何に向いていて、何は向いていないか。限界は?それをしらないと大きな落とし穴に陥ることになる。それを知るにも、必読です。
渋滞学
2006/12/27 22:43
渋滞という視点からとらえた世界
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:コーチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る
高速道路などで、ある地点から渋滞がすっと消え、その後はビュンビュン飛ばせるようなことがよくある。べつに分岐点や事故があるわけでもないのに、突然渋滞がなくなるのである。そんなとき、実に不思議な気分になり、どうしてこんなに急に空くのだろうと悩んでしまう。この理由について今までいろいろ考えてみたが、どうしてもわからなかった。
「事故もないのに自然渋滞ってなぜ起きるんだろう?」という宣伝文句を読んだとき、この問題についての答えをあたえてくれる気がして、手にとったのが、この『渋滞学』という本だった。実際に、答えはクルマの渋滞に関する最初の章であたえられた。その鍵となったのは、ASEPという近年、数学や物理学で使われるようになった理論であった。
ASEP理論を使って渋滞を単純なモデルに変換することにより、不可思議な謎は、まったく納得のゆく現象へと姿を変える。この理論において、道路は一列に並べられたいくつもの箱に、クルマはその箱に入ったボールに見立てられる。クルマの進行は前の箱にボールを移す行為と見なされる。そして、直前の箱にボールがあって前に進めない状態が「渋滞」と定義される。何のことはない、渋滞とは単純に自分のすぐ前にクルマが存在している状態であり、直前からクルマが消えたとき、渋滞は消えるのである。渋滞の終点において、クルマは前の箱に何も入っていないことを見、スピードをあげて走り出すのだ。次の瞬間、その次のクルマも同じように走り出す。...ASEPの理論とその応用について読みながら、このことにハタと思い当たった瞬間、私の中で件の謎は氷解していった。
かくして私の積年の謎も冒頭で解決したのであるが、筆者の西成活裕氏は、このような渋滞の概念をクルマだけでなく、人やアリさらにはインターネット等さまざまな領域に応用してゆく。私は、世界を渋滞という視点からとらえることのユニークさと分析の鋭さにひきつけられ、結局最後まで読んでしまった。ASEP理論を使った分析にもとづくこの新たな学問を渋滞学といい、その応用範囲は医療、都市計画、IT産業などさまざまな分野におよぶと期待されている。物理学者が本業の筆者の記述はなるほど、どの分野においても、専門的な知識と深い洞察力が感じられるものばかりだ。
ただ「お金の渋滞」と称して、財産相続が社会にあたえるマイナス面を指摘し、相続税率100パーセントを推奨するかのような記述には、首をかしげたくなった。子供の生活や将来を考える親心というものは、人が一生懸命に働き、財をたくわえようとする際の非常に大きな動機である。親が子供に何も残してやれない世の中がどんなに暗いものであるか、普通に考えればわかりそうなことなのに、どうしてこんな主張をするのだろう。ひょっとしたら、著者は自然科学の概念だけで人間や社会を測ろうとしているのでは、あるいは単純に、この人は社会科学的思考に疎いのではないかと感じ、残念であった。
このように疑問点はあるものの、自然・社会現象におけるさまざまな渋滞を扱う渋滞学は、これからもどんどん発展し、その成果は社会に多大な利益をもたらすだろう。著者自身も述べているように、渋滞学は基礎科学と応用科学の融合というこれからの大学がめざすべき方向の、具体例でもある。渋滞学をめぐる科学界の状況は、新しい時代の新しい科学のあり方を示しているのかもしれない。
渋滞学
2022/09/17 17:42
日常ありふれている現象を
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Koukun - この投稿者のレビュー一覧を見る
道路の渋滞のように日常ありふれている現象を理論的に解明すればどの様になるか 身の回りにいくらでも例があるせいで、とてもわかり易くしかも有用な解説となっている。交通渋滞のみならずインターネットや電話の輻輳、スーパーマーケットのレジの待ち行列など、いくらでも応用範囲が広がるのが多白い。