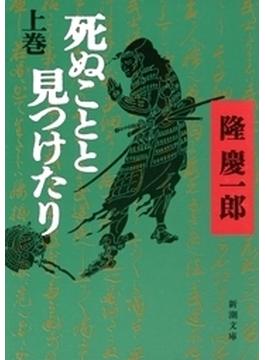- みんなの評価
 1件
1件
死ぬことと見つけたり
常住坐臥、死と隣合せに生きる葉隠武士たち。佐賀鍋島藩の斎藤杢之助は、「死人」として生きる典型的な「葉隠」武士である。「死人」ゆえに奔放苛烈な「いくさ人」であり、島原の乱では、莫逆の友、中野求馬と敵陣一番乗りを果たす。だが、鍋島藩を天領としたい老中松平信綱は、彼らの武功を抜駆けとみなし、鍋島藩弾圧を策す。杢之助ら葉隠武士三人衆の己の威信を賭けた闘いが始まった。
死ぬことと見つけたり(下)
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
死ぬことと見つけたり 改版 上巻
2009/09/17 01:20
隆慶一郎の本も、小学生の日記「にあんちゃん」も、その深さとやさしさは、はかり知れないものがある。そして両者は同じなのだ。
3人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:みどりのひかり - この投稿者のレビュー一覧を見る
隆慶一郎は野放図で頑なで一瞬先に何をしでかすかわからない魅力的な男を描く。その野放図な男があるとき、また次のようなる。
[杢之助は望楼に備えつけられた遠目鏡をとった。四郎に向け、遠目鏡の胴体をひき伸ばしていった。
不意に四郎が眼の前にいた。手を伸ばせば届きそうな場所にいた。
四郎は微笑していた。なんとも倖せそうに微笑っていた。口が僅かに動いている。老人と同じ唄おらしょを口ずさんでいるようだった。
今はな 涙の谷なるやなあ
先はな 助かる道であるぞやなあ
そこのところだけ、四郎は二度繰り返した。
突然、そう、全く突然、杢之助は理解した。
今までの謎が一気に解けた。
何故どこまでも孤立無援のいくさを戦わなければならなかったのか。それは勝つためではなかったのだ。生存のためのいくさではなかったのだ。それは死のためのいくさだった。それも只の死ではいけない。まるちる(殉教)でなければならない。原城に集まる切支丹三万七千という。ならば三万七千のまるちるがなければいけない。三万七千ことごとくが輝かしいまるちりす(殉教者)にならなければいけないのである。
じぇろにも四郎時貞は、そのための総大将だったのだ。合戦のための総大将ではない。そんなものである筈がない。あの、いつも天を仰いでいるような眼は、まるちるの時の眼だった。己れ一人がまるちりすになることはたやすいだろう。だが三万七千のまるちりすを引きつれてぱらいぞに参るのは至難の業である。
四郎は今ようやくその至難の業をやりとげようとしているのだ。(中略)だから今、微笑っている。晴晴と微笑っているのだ。そして、いえじし・まりあも御照覧あれ、四郎には確かに微笑う資格がある・・・・・・
杢之助はいつか泣いていた。どうしようもなく、声を殺して泣いていた。]
野放図な男が描かれて来ていたのが、ここへ来て慟哭させられる。隆慶一郎の深さに言葉もない。
隆慶一郎のこの深さとやさしさが何処から来ているのか知らないが、これに最も近い本がある。いや同じといった方が良い。「にあんちゃん」だ。隆慶一郎の本も「にあんちゃん」も同じなのだ。隆慶一郎は小学生の日記「にあんちゃん」をもとに、映画「にあんちゃん」のシナリオを書いた。
死ぬことと見つけたり 改版 上巻
2009/08/25 21:15
『葉隠れ』は面白くてはいけないのか?
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:いちろう - この投稿者のレビュー一覧を見る
隆慶一郎の、最初の葉隠れとの出会い。
学徒動員で軍隊にとられる際、読みたい本を密かに持ち込むために、葉隠れの本の中ほどを切り取り、そこへ望みのものをいれてカムフラージュしたわけだ。で、葉隠れの思想などどうでもよかった。陸軍の軍人が共鳴する思想など隆慶一郎にとっては嫌忌の対象以外の何物でもなかった。
しかし、軍隊ではみんな活字に飢えていた。それで葉隠れを読み始めたわけだ。
[(意外におもしろいな) それが読後感である。以後二度、三度、五度と繰り返し読んでいるうちに、この面白さは確定的になった。何より人間が素晴らしい。野放図で、そのくせ頑なで、一瞬先に何をしでかすか全くわからない、そうした人間像がひどく魅力的だった。]
[ 何をすべきだとか、何をしてはいけないとかいう部分は、いい加減に読みとばし、誰それが何をしたという、いわばエピソードの部分ばかり読んだわけである。]
『葉隠れ』は面白くてはいけないのか? という思いがこの作品へと繋がったいきさつが、読者を引き込み、読む前からわくわくさせる。
初めから思わず笑ってしまう。
斎藤杢右衛門、用之助親子は米がなくなるとお城へ運ぶ年貢を盗りに行く、堂々と、悪びれることも無く。
隆慶一郎の作品て、こんなに笑えるんだとあらためて思った。
最近「不落樽号の旅」という小説を読んで、その作者が隆慶一郎が好きというのであらためて作品を手にして見ました。隆慶一郎描くところの登場人物たちのそれぞれの性格がそれぞれに面白い。
初めて読んだときは何が何だかよく分からずに読んでいたのだけど、10年経って読み返してみると実に面白い。
死ぬことと見つけたり 改版 上巻
2007/09/24 11:23
最後のいくさ人として生き様
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Yostos - この投稿者のレビュー一覧を見る
隆 慶一郎の遺作『死ぬことと見つけたり』を久しぶりに読んだ。
あの『葉隠』から、よくもまぁこんな痛快な物語を編み出したものだと今さらながら感心する。葉隠をベースに江戸初期の鍋島藩を舞台に浪人斉藤杢之助の活躍を描いた物である。
隆 慶一郎といえば、『影武者徳川家康』などで代表されるよう網野史学を下敷きに自由民、職能民(道々の者)と体制、権力者との戦いを描くというのが得意とする作風である。
この作品もやはりこれから本格的に江戸幕府の体制に移行する時期に、戦国時代が終わり活躍の場を失いつつあるある種の職能民「いくさ人」である斉藤杢之助、中野一馬、鍋島直茂らが、体制側である鍋島勝茂、老中松平信綱らとの戦いが描かれている。そして、彼らのいくさ人としての苛烈さが姑息な体制側との対比で鮮明となり隆慶一郎の本領である痛快な時代劇に仕上がっている。
ただ、どの作品においても、最初は痛快であるが後半は必然として時代が体制側へと流れていき、主人公たちはある種の悲しみを纏うことになる。どの主人公もその悲しみを笑い飛ばす奔放さを持つため、爽やかな読後の印象につながる。残念ながら、この作品は作者の逝去により未完に終わっているが、解説に示されてる斉藤杢之助などの最後を読むと、『影武者徳川家康』などと同様素晴らしい作品に仕上がっていただろうと思わせる。