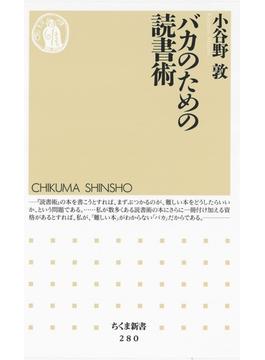- みんなの評価
 17件
17件
バカのための読書術
著者 小谷野敦 (著)
学校は出たけれどもっと勉強したい人、抽象的な議論がどうも苦手だという人。そういう「バカ」たちのために、本書はひたすら「事実」に就くことを指針とし、インチキ現代思想やオカルト学問、一時の流行に惑わされず、本を読み勉強するための羅針盤となるべき一冊である。本邦初「読んではいけない」リスト付き。
バカのための読書術
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
バカのための読書術
2009/05/13 22:34
本当は「蓮實重彦よ、一番の馬鹿はお前だよ」と言いたかったんじゃないのかなあ、ねえ、小谷野先生?
17人中、13人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:塩津計 - この投稿者のレビュー一覧を見る
昔なら「読書案内」「本の読み方入門」とでも名付けられたんだろうが、そこは小谷野先生、いきなり「バカのための読書術」だもんなあ。
まず、この「バカ」が何を意味するのかが問題である。本書の序言には「当面、哲学とか数学とか、抽象的なことが苦手な人のこと」などと、当たり障りの無い定義が提供されているが、どうも私には、これは先輩後輩から後ろ指を指されないようにするための偽りの定義のように思えてならない。と、いうのは、本書ではポストモダン以降、特に激しさを増している自称知識人による「難解ごっこ」が猖獗を極め(俺はこんな難解で晦渋な文章が読めるし書けるんだぞ。お前ら「バカ」にはわからんだろう)、それが「アラン・ソーカル事件」でピークアウトしたことが、きちんと踏まえられているし、あの東京大学のキャンパス風景を破壊した蓮實重彦による「あなたがバカだからです事件(中沢新一を東大教授に迎えようと西部邁が運動したが否決され、西部がそれに抗議して東大を辞職したことを巡り、東大駒場キャンパスで中沢賛成派の蓮實らと中沢反対派の杉本が公開討論を行った。その際、討論会を傍聴していた学生から「なんで大学の先生の言葉遣いというのは、こんなに難しいのですか」という問いかけがあったのに対し、蓮實が「なぜ難しいか。それはあなたがバカだからです」と答えた事件)」が序文の直後に引用されているからである。本文中ではあたかも著者はこの蓮實による「あなたがバカだからです」発言を支持しているかのごとき姿勢をとっているが、これは東大内で孤立しないための演技であって、本書を読めば、著者の姿勢はこういう傲慢な姿勢をとる蓮實に対しかなり批判的のようにも思えるのだが。。。
タイトルは刺激的だが、中身は相当踏み込んだ非常に良心的な読書案内となっている。そもそも戦前は大学に進学し教養を身につけられるのは日本国民のうちのごくごく一部の特権階級に許された贅沢であった。大学生=エリートであり、それを一番良く知っているのが大学生じしんであった。そして少なくとも戦前は「教養」は、一般大衆とエリートとを峻別する差別化の道具でもあった。目的が差別であるから、庶民でも理解できる平易な言葉で「教養」を語ることは、場合によっては「バカに見える」忌むべき行為であり、難解・晦渋な表現が珍重された。しかるに、戦後、大学の大衆化が進むにつれ、大学生の基礎体力が低下するようになり、こうした晦渋の砦にエリートが蟠踞する贅沢が、だんだん困難になっていく。昔は旧制高校や帝大内ではかろうじて通じた晦渋語がだんだん通じなくなってきたのだ。
そもそもギリシャの昔、ソクラテスやプラトンは哲学を日常の平易な言葉で語っていた。平易な言葉で難しい問題を論じたから、議論に参加するにあたっての間口は広く開放されていたと見てよいだろう。ところが日本では、だんだん言葉のみが難解・晦渋になって中身が空疎になる傾向が顕著になっていった。蓮実や浅田彰は、こうしたゴシック化した哲学のグロテスクな標本みたいな存在だろう。彼らに連なる系譜は、自分を大きく見せるため、賢そうにみせるため(バカでないように見せるため)、わざと難しい本を読み、晦渋な文章を書き、難解な書物を書評で取り上げるので、初学者は益々教養から離れていくという悪循環が起きている。これを何とかしなければというのが、どうも著者の本書を執筆した動機のようである。
初学者は「難解な本」に出くわすと、すぐ「僕は頭が悪いんだ」と思い込み自信喪失に陥りがちだ。しかし、著者は「読んで分からない本は読むな」と、まず初学者に救いの手を差し伸べる。そして返す刀で、「なぜその本が難しいか」といえば、そもそも文章が意味もなく難しい場合(それはその本を書いた人間にかなりの責任があることが多い)もあるし、また読書にはステップがあるのであって、まずその本に書いてあることを理解するために必要な基礎知識が不十分なのにいきなり上級な議論の本を読んだって分かるわけが無いと噛み砕くように教えてくれるのである(プロ野球を見たことも無いし、野球のルールを知らない人に阪神の金本とマリナーズのイチローの比較論を読ませても理解できるはずが無い)。だから、基礎的な知識も無い読者層に対し、基礎知識がなければ分かるはずのない本を薦める人間にも、相当な責任があると著者は言う。
そして著者は更に踏み込んで、最近の学生の歴史知識が低下している理由のひとつに英雄譚、ヒーローの物語を否定し、民衆史を提唱したマルクス主義歴史学者の罪を指摘する。顔の見えない民衆の歴史なんか幾ら読んでも歴史に興味が沸くはずが無いし、歴史に興味がわかなければ、そもそも歴史を読まなくなり、歴史に関する基礎知識が欠如するという悪循環に陥ると著者は警告する。今、民衆史を書いているマルクス主義歴史学者が少年だった自分は、庶民含めろくな娯楽がなかったから人々は講談芝居その他で歴史に関する基礎知識を自然に身につけていたが、今やアニメ、インターネット、テレビ、ラジオ、DVD、ゲームと娯楽は巷間に溢れており、子供たちは放っておくと牛若丸弁慶の話も知らずに成人するようになっているのである(ついでながら、これは日本のみの減少ではなく海外でも似たような現象は起きているそうだ)。そこで著者が推奨するのが司馬遼太郎、海音寺潮五郎らが書いた歴史小説である。こういうものをまず読んで、歴史の大まかな流れを頭に入れないと、大学で習うような歴史学が身につくわけがないという著者の指摘には私も大いにうなづける。それにしても司馬の著作が動機がアカデミアで大手を振っていた唯物史観への当て付けであったとは知らなかったなあ。
面白い指摘も多い。前述の中沢新一の著作は「いんちき」だから読むなとか、ユングの哲学は学問ではなくオカルト(だから読むな)だとか。しかし何と言っても新鮮だったのはNHKに訳知り顔で出てきてはサンクトペテルブルグのエルミタージュ美術館の案内を得々と行う五木寛之がとんでもない食わせ物で、要するにソヴィエト政府御用達(のスパイみたいな)作家という指摘には大笑いした(詳しくは126ページ参照)。なぜNHKが五木を案内役に選ぶのか私はその理由が良く分からなかったがこれでその理由が氷解した。やっぱりNHKにはソヴィエトのスパイみたいな連中が相当入り込んでいるのではないか。そうでないと(五木の直木賞受賞作)「蒼ざめた馬を見よ」のような低レベルの作品(ソヴィエト政府は人権を蹂躙する抑圧的な政府かもしれないが、西側(特にアメリカ)はソ連以上に悪辣だというのがこの本の趣旨)を書いた作家を重用する理由がないからだ。
あらゆる意味において、本書は良心的で良質な読書案内といえよう。
ついでながら裏表紙にある著者の写真(熊谷武二撮影)は何時の写真だろうか。「もてない男」の著者の写真(前田博史撮影)とどっちが近影なのだろうか。ひょっとすると先に出た「もてない男」のほうが最近の写真で、本書の写真は著者の学生時代の写真なのではないか。非常に気になるところではある。
バカのための読書術
2005/11/07 21:31
ここでのバカとは、なにがインチキ現代思想やオカルト学問か分からない人という意味である。
12人中、12人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:GTO - この投稿者のレビュー一覧を見る
なかなかよくできた読書案内である。
蔵書派とカード派については、私も蔵書派がよいと思う。古典の直筆本とかは高価でもあり手に入れることはできないが、これはという本は、新刊のうちに手に入れておかないといけない。書店で必要になってから本を探してももう見つからないことが多い。古書店でもなかなか見つからない。だから、すぐに読むかどうかは別として買って手元に置いておくことが必要となる。
読むべき本に関しては、私と意見が異なるものもあるが、この本の売りは、『「読んではいけない本」ブックガイド』で、「小林秀雄のほとんどすべて」とあるのに同感である。途中のインターミッションもそれなりにおもしろい。
私も「国語」が苦手だった。だから、第6章の『特に「作文」というのが私は苦手で、要するに作文というのは本当のことを書かねばならず、私の周囲や日常に、書くに値するような面白い出来事というのはなかったのである。』に、「そうだ、その通り」と叫びそうになった。書くに値するものを持てるまでには、人生をしばらく生きなくてはいけない。
著者は、『もてない男』で有名なようだが、もう1冊読むならば、『すばらしき愚民社会』を推薦する。
バカのための読書術
2001/02/03 18:24
インテリに騙されないために
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちーたま - この投稿者のレビュー一覧を見る
「抽象的な思考が苦手なら、インテリには知識で対抗。そのためには本当の入門書を」と主張する、実践的ブックガイド。学会の通説に捕らわれず、一般人が読んで役立つもの、読んで面白いものを多数取り上げている。
あまたの名著(と言われているもの)を「専門家以外読む必要なし」「いんちき」と切り捨てる筆は痛快。