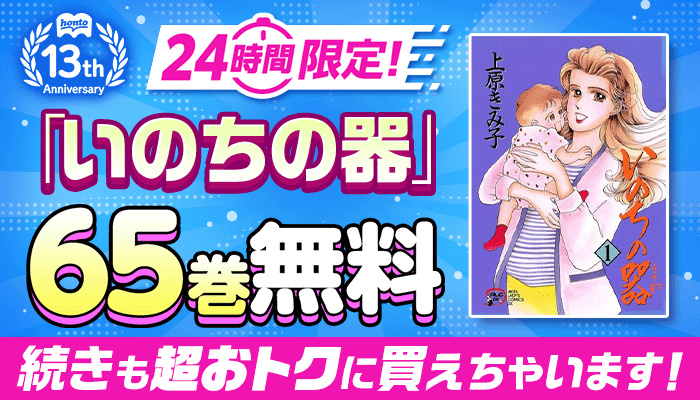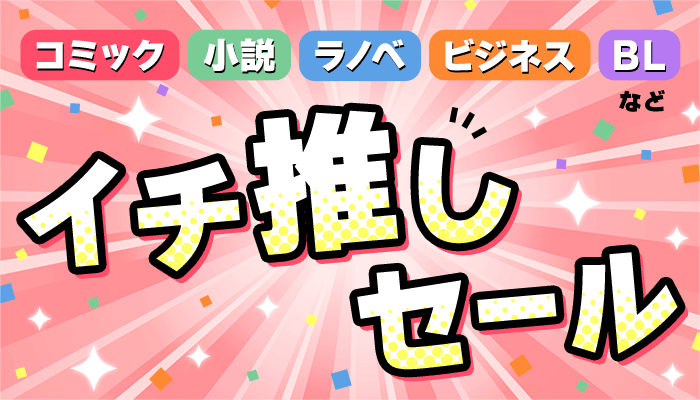- みんなの評価
 3件
3件
ことばの発達の謎を解く
著者 今井むつみ
単語も文法も知らない赤ちゃんが、なぜ母語を使いこなせるようになるのか。ことばの意味とは何か、思考の道具としてどのように身につけていくのか。子どもを対象にした実験の結果をひもとき、発達心理学・認知科学の視点から考えていく。
ことばの発達の謎を解く
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
ことばの発達の謎を解く
2023/09/07 23:01
赤ちゃんすごい
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:qima - この投稿者のレビュー一覧を見る
言葉を知らない赤ちゃんは、まっさらな状態で言葉を覚えるのではなくて、ある程度の予備知識をもって習得していくというお話。こういう研究が進んでいること事態すごい。
ことばの発達の謎を解く
2022/05/03 16:13
ことばの発達と思考
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:だい - この投稿者のレビュー一覧を見る
○単語の発見
赤ちゃんが最初に学習するのは母語のリズムとイントネーションの特徴
“音素”が単語をつくる音の単位となる
単語は“それ自体で意味を持つ”
機能語は“助詞等独立した意味を持たない”
リズムやイントネーションは音声を区切る手がかりになる
赤ちゃんは連続した音声の中から切り出した同じパターンの音声を記憶しストックしていくことで単語を理解していく
○ことばの世界
“言葉”を学習すること
モノや動作と音の結びつきを覚えるだけでは不十分で、伝えたいことを単語を組み合わせて表現することができるということである
一般化の問題
言葉の意味は、その言葉が指す一つの特定の例だけから確定することは可能性が多すぎて不可能なことである
“同じカテゴリーに属する他のモノ”を子供はどうやって判断できるのか
二歳以下では“形が似ている”ことが拠りどころとなっている
子供は試行錯誤の中で言葉と意味の結び付き方の規則性や仕組みを発見していく
発見した規則性を使って言葉の意味を推察し、急速に言葉の数を増やして行く(語彙爆発)
○動詞の意味
赤ちゃんは“モノの名前”と明らかに違う形態の言葉があることに気づく
三歳児は初めて聞く動詞を“この特定のモノでするこの動作”と考える
“あげる”“もらう”“くれる”
動詞の意味を考える場合、文の構造が大事な手がかりになる
主語・目的語、行為動作をする人、受け手やモノとの関係性が分からないと動詞の意味を推察できない
日本語で動詞の型(自他)を見極めるのには“が“”を”等の助詞の役割りが大きい
動詞は“同じ”とみなした動作や行為に名前をつけるわけだが、どの範囲を“同じ動作・行為”とみなすかは言語によって異なる
○名詞・動詞以外
モノの特徴
形、色、模様、触感、重さ・・・
子供はモノのどの特徴を言っているのかをつつかまなくてはならない
比較対象がある
形容詞は対になる言葉を持ち、相対的に決まる
大きい・小さい、高い・低い、高い・安い(何に対して?)
色
古代の日本には赤・青・白・黒の四色のみであった
前後左右の位置
“前”を使うには二つの視点があり、どの状況でどの視点が使われるかの理解が必要
単語の意味は単体では決まらず、語彙のシステムの中で他の単語との関係で決まる
一つ一つの単語の意味を他の単語との兼ね合いで学ばなければならない
○言葉の発達
“心の中の語彙辞書”を作りあげる
・発見
言葉全体を学習するために要素一つ一つの学習が必要
子供は要素間に共通するパターンを分析し、システムの存在を見つけようとする
・創造
あるパターンを暫定的に発見すると、その知識を使って知っている言葉を新しい状況で使い、新しい言葉の意味を推測するのに使う
この創造にオノマトペが使われる
・修正
子供は新しい言葉を覚えると、すでに“知っていた”言葉の意味を同時に修正し、言葉の意味を深化させている
○言葉と思考
目に見えない概念を表すのも言葉であり、抽象概念をシステムの中で理解していく
言葉は、大人が持つ膨大な知識体系の基礎を推論することを助け、知識構築をすることを可能にしている
赤ちゃんの数の概念は、4より大きい数ん大まかな量として扱っている
やがて、各々の数の言葉がモノの数に対応することを理解する
科学者の思考
ある仮説をもって、システムの仕組みや働きを発見する
説明したい現象をシステムと捉え、構成している要素どうしの関係を考え、その構造と働きを探求する
このプロセスは、言語の発達の過程と同じである
ことばの発達の謎を解く
2022/03/05 01:35
太本
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:イシカミハサミ - この投稿者のレビュー一覧を見る
始まりから終わりまで
「ほー」となる良本。
専門的な内容を
優しく易しい調子で教えてくれる。
普段何気なく使っている言葉を見直す時に。
これから小さい子を育てるという時に。
一度読んでおくといい本。