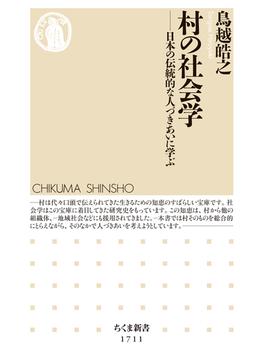- みんなの評価
 3件
3件
村の社会学 ──日本の伝統的な人づきあいに学ぶ
著者 鳥越皓之
日本の村々は、長い歴史のなかで工夫に工夫を重ね、それぞれの風土に根ざした独自の生活パターンと人づきあいのあり方をかたちづくってきた。そのしくみや特徴をつぶさに観察してみると、村を閉鎖的で前近代的なものとみなすステレオタイプこそ、むしろ古びたものにみえてくる。コミュニティの危機が叫ばれる今日、その伝統を見つめなおすことは私たちに多くの示唆を与えてくれるのだ。日本の村に息づくさまざまな工夫をたどり、そのコミュニティの知恵を未来に活かす必読書。
村の社会学 ──日本の伝統的な人づきあいに学ぶ
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
村の社会学 日本の伝統的な人づきあいに学ぶ
2023/10/24 10:05
読む側にゆだねた感じ
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:とらとら - この投稿者のレビュー一覧を見る
社会学、という書名なので、もう少し学術的な本かと思ったけど、わりと軽めの読みものという感じの本だった。村イコール古い封建的なもの、というのではなく、生活者のコミュニティとしての基盤や知恵があるんだよ、ということ。現在、そういったものがなくなってきていること、行政へ頼るしかないようなところなどを、ちょっと憂いている感じだけども激しく批判しているわけでもなく。いろんなことを読む側にゆだねたような文章が多かった。本文のなかにあるお坊さんのような役割なのだろうか。
村の社会学 日本の伝統的な人づきあいに学ぶ
2023/03/28 21:07
村は、日本の伝統的な人付き合いの場。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:おじゃもんくん - この投稿者のレビュー一覧を見る
親の実家が農村部なのだが。
子供の頃から街に住んでいる私にとっては、不思議な空間だった。
ドラマ等の物語によく出てくる、封建的閉鎖空間では無く。
田んぼやはたりが広がり、お祭りがあり夜は真っ暗で。
虫やメダカを観察して、楽しんでいたなぁ。
筆者は、日本の村落を長く研究し観察していて。
この本も、日本の隅々の農村・漁村を巡り巡ってたどり着いた結論が書かれていて。
村々が、長い歴史の中で工夫に工夫を重ねて。
それぞれの風土に根ざした、独自の生活の中の人付き合いのあり方。
それを詳細に観察して行くと、村は閉鎖的でも無く古いものでも無いと定義。
村を前近代的なものとみなす、社会のステレオタイプな部分が古びて見える。
村の作り上げたコミュニティーこそ、今の私達に必要なものを示している。
なかなか、目から鱗な事例が多くてびっくりでした。
本書は、村の知恵やコミュニティー・そしてローカルルール等仕組みについて解説して。
中頃で、村の働きや人間関係・思想について。
後半は、村の意図的消滅論や過疎化の危機について書き。
自由主義と共和主義は、個人主義と村社会として。
村は共和主義で、その村の持つ知恵を活かす時代に来ていると締めくくっている。
なかなか奥が深い「村の社会学」でした。
村の社会学 日本の伝統的な人づきあいに学ぶ
2023/04/11 16:00
たわけ者
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:とめ - この投稿者のレビュー一覧を見る
村=田舎と侮るなかれ。都会の砂漠の一粒の砂として生きる気楽さと束になって対応するという生き残り策との対比などから、生きるための知恵のうちの日本人の伝統的な人づきあいを考えている。