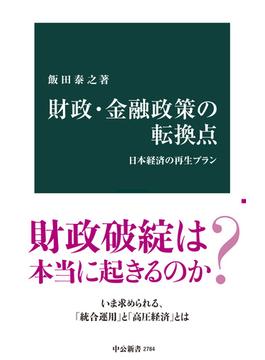- みんなの評価
 4件
4件
財政・金融政策の転換点 日本経済の再生プラン
著者 飯田泰之 著
世界の経済政策が大きく転換しようとしている。これまで財政政策は抑制的に、金融政策は独立して行うことを常識としてきたが、昨今、その実効性が疑問視されるようになったのだ。巨額の政府債務と長期の低金利政策で財政破綻さえ囁かれる日本。この苦境はどのように打開すべきなのか。本書は財政・金融政策の理解を整理し、両政策の現代的な意義と機能を考察。日本再生の第一歩として必要な新たな経済政策を提言する。
財政・金融政策の転換点 日本経済の再生プラン
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
2024/02/11 15:50
からめ手はない
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:象太郎 - この投稿者のレビュー一覧を見る
財政・金融政策は難しい言葉が多く、とっつきにくいが、本書は最近話題のテーマをよく整理していて、丹念に読んでいくと相当勉強になる。電子書籍なら検索機能が便利だろうから、辞書代わりに手元に置きたいと思った本だ。
本書が論を進めて向かうのは「高圧経済」をもたらす財政・金融政策の在り方だ。供給能力を上回る需要の圧力によって労働力の移動や投資を促し経済成長につなげる。そういう経済循環を目指す上で、政府・日銀は具体的にどこに資金を流し込んでやればいいのか。論を辿る私の関心は、もっぱらそこに向かった。歴史の教訓として、政府が産業を選ぶと失敗することだけは確かで、難しい問題だ。
本書は「政府が使途を指示せず、民間の自己判断による支出を促す方法として代表的なものが減税と給付金支給だ」と指摘した。貯蓄にまわらず消費につながりやすい減税・給付として、若年層・低所得者向けの給付、未就業時の国民健康保険料の減免拡大を挙げる。ただ、これに関しては、需要を力強く担う主体として、若年層・低所得者はちょっと弱すぎるような気がした。もうちょっと元気のある人たちに引っ張ってもらわないと、日本経済はすぐに腰折れしてしまうような気がしないでもない、と。
続けて「社会的価値の探究、安全保障、国土保全などの事業には、一時的に多額の資金・資源を必要とするものが少なくない」とも記すのだが、それ以上詳しく書いていなかった。無理もない。日本経済のけん引役として、この辺りで何か出てくることを期待したいが、まだ見えないのが多くの人の正直なところだろう。
本書は高圧経済に向かうカギとして、やっぱりと言うか、社会保障分野に目を向けた。直接的な人的サービスを多く利用する公的医療・介護サービスの縮小、機械化・合理化による労働量の減少、医療・介護事業が生み出す付加価値の向上が必要だ、と。日本経済の癌である社会保障分野の手術は、どうしたって避けられない、という結論になる。
経済の長期停滞、巨額の政府債務といった難問に対し、私は最新の財政・金融論ならからめ手を提示するのかもしれないとどこか期待していたが、それは逃げようとしていたというだけで、核心をまっすぐ突くべきなのだと改めて思った。
財政・金融政策の転換点 日本経済の再生プラン
2024/02/08 11:21
日本経済
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:なつめ - この投稿者のレビュー一覧を見る
日本経済の今後について、興味深く読むことができました。アベノミクスからの再生への転換点に、なってほしいです。
財政・金融政策の転換点 日本経済の再生プラン
2024/01/30 20:33
多額の国債が積み上がった時代の財政・金融政策はどうすればいいのだろう
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:雑多な本読み - この投稿者のレビュー一覧を見る
財政政策と金融政策の役割分担が意識されたのは1980年代という。リーマンショック後には非伝統的金融政策が採用されていく。それでも、世界の経済成長率は高いといえず、特に日本は低いままで30年余りが経過した。本書は、この難解な財政政策と金融政策の両方を新書というコンパクトなものにまとめ上げている。当然、財政政策や金融政策のすべてを網羅されているわけでない。財政政策では安定化機能を中心に、金融政策はマネタリー・ポリシーをメインテーマに扱っている。目次を見ると、
まえがき
第1章 財政をめぐる危機論と楽観論
1 財政の「今」を知る
2 公債は誰にとっての負担なのか
3 GDPギャップと財政政策の効果
第2章 金融政策の可能性と不可能性
1 金融政策の論理
2 金融政策の波及経路と非伝統的金融政策
3 長期停滞論と定常的不況の可能性
第3章 一体化する財政・金融政策
1 国債と貨幣に違いがあるのか
2 財政政策・金融政策の依存関係
3 財政の維持可能性をめぐって
第4章 需要が供給を喚起するー求められる長期的総需要管理への転換
1 高圧経済論とマクロ経済政策
2 需要主導政策にむけての重要な注意点
謝辞、註記 となっている。
以上のように展開される。日本の国債発行は1000兆円を超え、自治体分を合わせると驚くほどになっている。国民一人当たりと表現されているが、あくまで政府の借金であり、半分は日銀引き受け、残りの多くは国内で引き受けられているので、国民は債権者となる説明から始まる。政府の多額の借金となると、悲観的になるか楽観的なのかとなり、冷静な議論ができていない指摘が出てくる。いくつかの考え方や議論が紹介され、勉強するにはちょうどいい。通貨と国債の違い、租税と公債との違いなどは面白く読めるだろう。経済学での議論も紹介され、多くの面から学ぶことができる。この2つの政策の統合的運用と高圧経済への移行という提案もある。統合的と言っても、行政府が中央銀行を子会社のごとく扱うことは想定されていないだろう。ただ、1回読んだだけで理解するのは難しいが、一読してほしい本である。