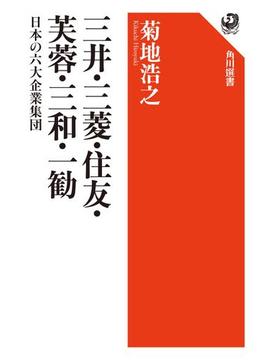- みんなの評価
 2件
2件
三井・三菱・住友・芙蓉・三和・一勧 日本の六大企業集団
著者 著者:菊地 浩之
日本には、財閥を基盤とする6つの企業集団が存在していた。三井・三菱・住友・芙蓉・一勧・三和である。これらの企業集団の誕生から、その後合併・再編を繰り返し、現在どのような状況にあるのかを明らかにする。
はじめに
第1部 企業集団とは何か
第一章 企業集団の概念規定
第二章 歴史的な経緯
第三章 六つのグループ
第2部 社長会
第一章 社長会に対する評価
第二章 企業集団形成のために社長会を結成したのか
第三章 社長会メンバー=企業集団なのか
第四章 本当に大株主会だったのか
第五章 メガバンク再編後の社長会
第六章 企業集団にとって社長会とは何か
第3部 株式持ち合い
第一章 終戦直後の乗っ取り防止
第二章 資本の自由化対策
第三章 持合い崩れ
小括 企業集団から見た日本企業の株式所有構造
第4部 系列融資、集団内取引、包括的な産業体系と共同投資会社
第一章 四つの標識の概要
第二章 都市銀行の融資戦略
第三章 総合商社による集団内取引
第四章 共同投資会社による新規事業の進出
小括 企業集団は単なる株主安定化の装置ではない
第5部 メガバンク再編後の企業集団
第一章 メンバー救済の限界
第二章 メガバンク再編
第三章 六大企業集団は三つになるのか
第四章 六つの標識から見たメガバンク再編後の企業集団
小括 六大企業集団は四つになった
あとがきと主要参考文献
三井・三菱・住友・芙蓉・三和・一勧 日本の六大企業集団
05/08まで通常1,408円
税込 704 円 6ptワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
三井・三菱・住友・芙蓉・三和・一勧 日本の六大企業集団
2019/04/26 10:40
日本の企業集団の歴史的な変遷と現状がこれ一冊でよく分かります!
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、日本の企業集団の歴史と現状をコンパクトに一冊にまとめた非常に価値ある書です。日本の企業集団は、戦前の三大財閥が再編されてできた三井、三菱、住友と、戦後さまざまな企業が集合してできた芙蓉、三和、一勧がありますが、高度経済成長期にこうした企業集団を超えた銀行の統廃合が起こり、それを契機に、「最適モデル」と謳われた芙蓉、三和、一勧が低迷してしまいました。この背景にはどのような理由が隠されているのでしょうか?企業集団の歴史からいろいろな事実が見えてきます。
三井・三菱・住友・芙蓉・三和・一勧 日本の六大企業集団
2017/08/21 17:16
企業集団の歴史と現状
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:melon - この投稿者のレビュー一覧を見る
財閥を起源に持つ三井・三菱・住友と非財閥系の銀行が主導した芙蓉・三和・一勧という6つの企業集団。その歴史を紐解き、都市銀行再編後の現状を考えている本書。まずあとがきにあるように本書の著者の経歴が面白い。大学の研究者ではなく、本業はサラリーマンでありながら、研究に打ち込み論文を仕上げ、さらに学会に所属する異色の経歴である。
社長会、株式持ち合い、集団内取引の3つの観点から企業集団を考察しているが、第1の社長会についてはほとんど意味を成していないように感じる。社長会が集団の重要事項を決定して各員に守らせるといったことができていないようで、親睦会や情報交換会のようなものであれば、それほど大きな役割はなさそうである。株式持ち合いについては、株主安定化を実現するために他の会社に株を持ってもらうに際して、事業会社には商取引に応じた分を持ってもらうものの資金力の面からさほど大量には保有してもらえないことから、金融機関が多く株を持つことになった。さらに事業会社とは逆で、金融機関が株を保有する分に合わせて保険契約を結ぶという生保方式によって株式持ち合いがなされていたようである。そして集団内取引について、ブロック経済のような排他的な系列融資と集団内取引によって、自グループが得をするようにしていったようだ。ただそれは資金需要が旺盛で金の足りなかった高度経済成長期の話であり、オイルショック以後の低成長時代に突入するとその意味は薄れていったようである。
旧三和銀行は結果的に旧三菱銀行に呑みこまれてしまったわけだが、これは旧さくら銀行を旧住友銀行に取られてしまったからであろう。旧富士銀行と旧第一勧業銀行が旧日本興業銀行と共に合併したことによって、旧三和銀行からすると合併相手は旧さくら銀行しかあり得なかった。しかし財閥の垣根を越えて旧住友銀行が旧さくら銀行を手にしたことによって旧三和銀行は敗北が決定付けられてしまったのだろう。