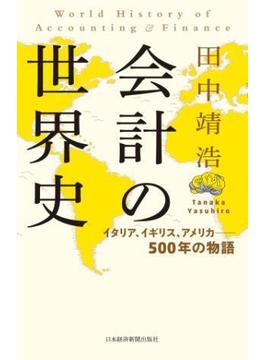- みんなの評価
 12件
12件
会計の世界史 イタリア、イギリス、アメリカ――500年の物語
著者 著:田中靖浩
数字のウラに隠された、驚くべき人間ドラマ。
誰にも書けなかった
「会計エンタテインメント」爆誕!
【本書の特徴】
その1 ダ・ヴィンチ、レンブラント、スティーブンソン、フォード、
ケネディ、エジソン、マッキンゼー、プレスリー、ビートルズ
……意外な「有名人」たちが続々登場!
その2 冒険、成功、対立、陰謀、裏切り、愛情、喜びと悲しみ、
栄光と挫折、芸術、発明、起業と買収
……波乱万丈、たくさんの「知られざる物語」が展開します
その3 簿記、決算書、財務会計、管理会計、ファイナンス、IFRS
……物語を楽しく読み進めるだけで、これらの仕組みが驚くほどよくわかります
その4 イラストと写真、ひと目でわかるイメージ図が満載。
会計の本なのに、細かい数字はいっさい出てきません!
「私はこれまで数々のビジネススクールや企業研修で
会計分野の講師を務めてきました。
会計を『大局的に・楽しく』学んでもらうのはとても難しい作業ですが、
講義で『歴史』をもちいる手法はかなり効果的でした。
会計ルールの誕生エピソードや人物秘話を少々大げさな講談調で語ると、
受講者たちが身を乗り出してきます。
本書はそんな経験をもとにしています。
皆さんにも『好奇心とともに会計を理解する』経験をしてもらえれば
嬉しいです。」
──「旅のはじめに」より
【「9つの革命」で全体像がわかる】
第1部 簿記と会社の誕生
「3枚の絵画」
15世紀イタリアから17世紀オランダへ
銀行革命/簿記革命/会社革命
第2部 財務会計の歴史
「3つの発明」
19世紀イギリスから20世紀アメリカ、21世紀グローバルへ
利益革命/投資家革命/国際革命
第3部 管理会計とファイナンス
「3つの名曲」
19世紀から21世紀・アメリカ
標準革命/管理革命/価値革命
会計の世界史 イタリア、イギリス、アメリカ――500年の物語
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
会計の世界史 イタリア、イギリス、アメリカ−500年の物語
2018/09/28 17:17
これまでに見たことがない画期的な書です!
8人中、7人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、表題には「会計の世界史」とありますが、本文には難しい会計用語や数字はほとんど出てきません。また、覚えにくい外国人のカタカナの名前もほとんど出てきません。本文は、だれにでもわかる非常にわかりやすい文章で書かれ、それでいて会計学や簿記、財務、ファイナンスについて非常によくわかるのには驚きです。ぜひ、一度手にとって見てください。きっと驚かれること間違いなしです。
会計の世界史 イタリア、イギリス、アメリカ−500年の物語
2021/07/08 18:19
時空を超えて世界を旅したような気分になりました。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ぷぷ - この投稿者のレビュー一覧を見る
簿記の勉強を始めてすぐに挫折しそうになり、気分転換に読みました。
会計の歴史が幅広く、面白く紹介されていて、会計が人類の生活と共に少しずつ形を変え、今日に至るのだなぁと、とても興味深く、簿記などの知識が全くなくても楽しく読むことが出来ました。
簿記のテキストを読む際につまらなく感じていたものが、人間の生活の一部なんだなぁと思えるようになり、楽しく学ぶきっかけにもなりました。
会計の世界史 イタリア、イギリス、アメリカ――500年の物語
2021/03/19 22:58
政治史ではない歴史
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:忍 - この投稿者のレビュー一覧を見る
NHKラジオで、この本をもとにして作者が講義をされており、それが面白かったので読んでみたところ、本もとても面白かったです。
会計の本は初めてだったのですが、たぶんかなり斬新なつくりではないかと思います。
会計の始まりから、現代まで続く流れを追っているのですが、決して会計が主役になるのではなく、世界の流れから必然的に会計が発生し、発達していった経緯を、会計とは別の切り口から語っています。
このため、メインのテーマ以上にサブ的な内容が面白く、アラビア数字や紙が世界に及ぼした影響というようなエピソードが非常に興味深かったです。
まさに歴史(History)を物語(Story)として読むという感じで、学校で使う教科書もこういうスタイルであってほしいと思いました。
また、教科書に書かれているのは政治史がメインであり、それはその時代の権力者が自身の正当性を主張するために作り出したものにすぎないことに気づかされました。なぜ政治家の歴史ばかりを教わらなければいけないのか、この本のように会計や経済から見た歴史、あるいは科学技術や工業技術から見た歴史というような観点を重視してもよいのではないか、むしろそのほうが世界の流れをよく知ることができるのではないか、と強く感じました。