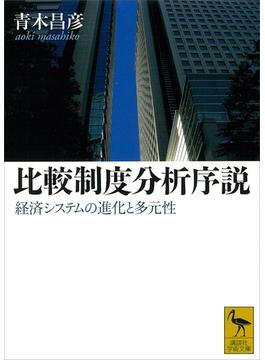- みんなの評価
 2件
2件
比較制度分析序説 経済システムの進化と多元性
著者 青木昌彦
アングロ・アメリカン型の経済システムは本当に普遍的なのか? 多様なシステムの共存が経済利益を生むような「進化」とは? そして日本はどう変革すべきか? 企業組織から国際関係まで、ゲーム理論、情報理論等を駆使して「多様性の経済利益」を追究する新しい経済学=「比較制度分析」の考え方を第一人者がわかりやすく解説する、最適の入門書。(講談社学術文庫)
比較制度分析序説 経済システムの進化と多元性
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
比較制度分析序説 経済システムの進化と多元性
2020/03/28 11:38
今注目を集めている経済学の新しい分野、「比較制度分析」の入門書です!
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、新しい経済学分野として注目を集めている「比較制度分析」の基本的な考え方を丁寧に教示してくれる入門書です。「比較制度分析」とは簡単に言えば、企業組織から国際関係といった広範囲にわたって、ゲーム理論や情報理論などを駆使しながら、多様性の経済利益を追究することを目的とした経済学の一分野です。同書では、こうした「比較制度分析」の手始めとして、アメリカ型の経済システムが本当に普遍的なのか?多様なシステムの共存が経済利益を生むようなシステムにはどのようなものが考えられるか?日本の経済システムはどう変革していくべきか?などの課題について丁寧に考察していきます。
比較制度分析序説 経済システムの進化と多元性
2009/09/05 20:22
経済=社会ではない。必要性は認めても、経済学は「万能の学問」ではない。
10人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:K・I - この投稿者のレビュー一覧を見る
僕は大学の経済学部を卒業した。ただ、経済学者がこの本を読んで100を理解したとするならば、たぶん40くらいしか理解できてないだろう。この文章はこの本への「書評」といえるものではなく、ただ、この本を読んで感じたことである。
経済学の中で比較制度分析というのは比較的新しい分野だ。
もしこの本を教科書としてテストを行ったら、僕は「可」をとるだろうが、比較制度分析という経済学の分野がどういうことを議論しているのかといったことはおおよそ分かる。
しかし個人的な感想を加えれば、この本では日本経済といった場合、企業組織について多くのページが費やされていて、社会保障、社会政策といった事柄は扱われていない。
また、最終章の著者の「改革対既得権益」といった図式は、そのまま完全に首肯できるものではない。著者は、「今の日本で、構造改革に反対だ、と公に表明する政治家はほとんどいないといっても良いだろう」(280ページ)という。「しかし、必要な構造改革とは何か、それはいかなる道筋で達成されうるのか、という肝心なことになると、同意はほとんどない」(同ページ)。
しかし著者のいう「構造改革」というのは政治経済に対する「改革」であり、もっと大きな社会一般をどうするか、といった問題にまで、筆は及んでいない。本書を読んでいて、思うのだが、おそらく現実的に現実の「制度」(それは法律や組織だけではない)に変化を加えようと考えることのできる人は、現実のあまり大きいとはいえない物事から、つまり、現実に変化の可能性のある現実的な提言を行うのだろう。そして、そこに経済学という学問の裏づけがあると、政財界の人間も真摯に話を聞くのだろう。
また、何が「既得権益」であり、それに対する何が「改革」なのか、そんなに白黒はっきり区別できるのだろうか?
たぶん、僕の上の文章は的外れなのだろう。しかし僕の関心が経済学とはズレているという認識は新たにすることができた。