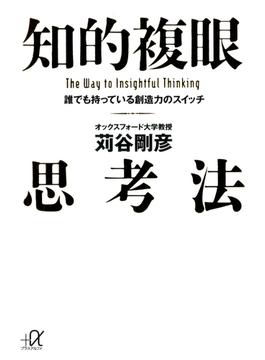- みんなの評価
 7件
7件
知的複眼思考法 誰でも持っている創造力のスイッチ
著者 著:苅谷剛彦
常識にとらわれた単眼思考を行っていては、いつまでたっても「自分の頭で考える」ことはできない。自分自身の視点からものごとを多角的に捉えて考え抜く、それが知的複眼思考法だ。情報を正確に読みとる力。ものごとの筋道を追う力。受け取った情報をもとに自分の論理をきちんと組み立てられる力。こうした基本的な考える力を基礎にしてこそ、自分の頭で考えていくことができる。ベストティーチャーの奥義!!
知的複眼思考法 誰でも持っている創造力のスイッチ
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
知的複眼思考法 誰でも持っている創造力のスイッチ
2010/04/23 13:34
現代社会に生きるわれわれにとっての知恵とは、いいかえれば「知的複眼思考」というマインドセットのことだ
11人中、11人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:サトケン - この投稿者のレビュー一覧を見る
「複眼思考」を自分自身の「ものの考え方」として身につけて使いこなす方法を、著者自身による教育実践を踏まえて、具体的な方法論として紹介してくれた、日本語では初めて出版された本である。自学自習用のテキストとしても活用できる、「自分のアタマで考える」ための基礎をつくる必読書といってよい。
本書は、基本的に1996年以前の6年間に当時の大学生(・・それも著者が教えていたのは東大生だ!)に「ものの考え方・・」を教える経験をつうじて生まれた本であり、大学生を主要な読者として設定している。東大生ですら、いや東大生だからこそ、受験勉強でアタマがコチコチになって、思考の柔軟性がなくなっていたようだ。「複眼思考」とは、思考に幅広さと柔軟性をもたらし、創造力の基盤となる「ものの考え方」でもある。
とはいえ、もちろんビジネスパーソンも読める本であることはいうまでもない。日本の大学教育では、なぜか「ものの考え方」が、方法論として教育されてこなかった。その意味では、大学生だけでなく、ロジカルシンキングを身につけたいビジネスパーソンにとっても必読書といってよいのだ。
著者による問いかけを自問自答しながら、順番に読み進めてゆくうちに、おのずから「複眼思考」のなんたるかが体得できる、ムリのない構成になっている。
序章 知的複眼思考法とは何か(知的複眼思考への招待、「常識」にしばられたものの見かた、知ることと考えること)
第1章 創造的読書で思考力を鍛える(著者の立場、読者の立場;知識の受容から知識の創造へ)
第2章 考えるための作文技法(論理的に文章を書く、批判的に書く)
第3章 問いの立てかたと展開のしかた-考える筋道としての問い(問いを立てる、「なぜ」という問いからの展開、概念レベルで考える)
第4章 複眼思考を身につける(関係論的なものの見かた、逆説の発見、「問題を問うこと」を問う)
1996年に単行本初版がでてからすでに15年近く、2002年に文庫化されてからもロングセラーをつづけている本書だが、著者が「あとがき」にも書いているように、1995年のオウム事件に際して「複数の視点からものごとをとらえていくことの重要性、そしてまたそれをなるべく広く読者に伝えることの大切さを、あらためて感じた」(P.375)という。
著者も本書のなかで指摘しているように、とかくビッグワードやマジックワードが一人歩きして、ものを考える手間を省略したがる傾向のある日本では、「複眼思考」をしっかりと身につけて、あふれかえる知識を自分なりに制御して生きてゆくことは、サバイバルのツールとして不可欠といってよい。
「知識社会」が到来したさかんにいわれているが、インターネットの存在によって知識量そのもので勝負がつく時代は完全に終わっている。本当に必要なのは知識そのものではなく、知識を使いこなす知恵である。現代社会に生きるわれわれにとっての知恵とは、いいかえれば「知的複眼思考」というマインドセットのことだと言い換えてもいいだろう。
本書には、著者が米国の大学院で鍛えられた、いい意味でのアングロサクソン的思考法が全編を貫いている。
現代人にとっての必読のテキストとして、あらためて推奨しておきたい。
知的複眼思考法 誰でも持っている創造力のスイッチ
2020/03/08 12:40
納得のいく且つ具体性に富んだ手法
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:岩波文庫愛好家 - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、視野が狭い、多角的な或いは俯瞰的な見方に欠けている、という私に対して処方されるべき良薬でした。
特に複眼的に見る為の具体的なやり方として、様々な立場の人達から見た意見を自分なりに考えてみるとか、『何故?』を幾つか挙げてみるとか、ハウツー本にありがちな理論提唱に終始せず、何を実践したら良いかを豊富な例示を基に、平易に紹介してあります。
本書の1章から4章の構成もよく練られた形となっており、1章から順を追って4章で最終的に『複眼思考』を身につけるには?へ到達します。
少しでも『複眼思考』を身に染み込ませる事が出来る様、日々意識していきます。
知的複眼思考法 誰でも持っている創造力のスイッチ
2017/03/19 16:44
どうすれば「自分の頭で考える」視点を得ることができるのか?
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:とある地方の公務員 - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、主として大学生を対象に、「本の読みかたを通じて、自分で考えるための基礎力を養う方法」(第1章)、「文章を書くことを通じて、どのようにすれば自分の考えを論理的に表現できるのか」(第2章)、「問いの立て方と展開のしかた」(第3章)、「複数の視点からものごとをとらえるには、どうしたらよいのか」(第4章)について、著者の研究・教育経験を踏まえ、具体的に、かつ分かりやすく解説した本。
「経営コンサルタントが、企業経営を題材に、ビジネスマン向けに書いた問題解決等のハウツー本にはあまり馴染めなかった。」という社会人の方に、本書を一読することをお勧めします。