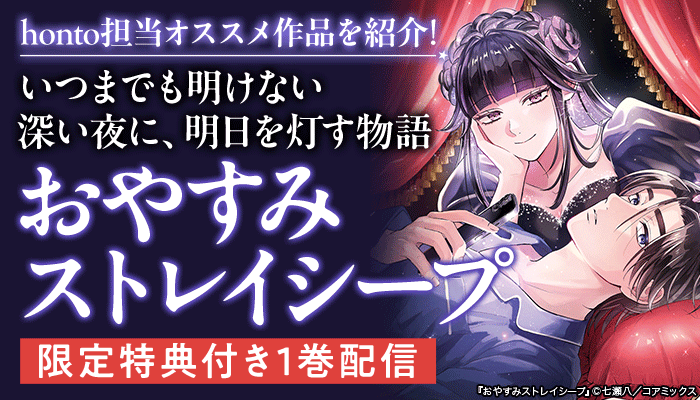- みんなの評価
 2件
2件
京都学派
著者 菅原 潤
西田幾多郎に始まる「京都学派」の思想は、西洋哲学にも匹敵するオリジナルな哲学として、高く評価されています。しかし一方、戦前日本の海外侵略的姿勢に思想面からのお墨付きを与えたとして、厳しい批判にもさらされています。本書では、いったん彼らの「政治的な誤り」はカッコに入れた上で、客観的なその哲学的評価を試みます。その上で、なぜ彼らは過ちを犯すことになったのか、その深い理由に迫ります。
京都学派
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
2024/07/15 00:55
戦争協力と哲学
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:y0a - この投稿者のレビュー一覧を見る
たまたま東京都現代美術館で、Ho Tzu Nyen(ホー・ツーニェン、シンガポールのアーチスト)の展示(2024年4月6日〜7月7日)の中で、CG映像を使った気になるインスタレーションを見た。和室の中で男たち四人が、座卓を囲みながら難しい言葉で何か話し合っている。作品の題名や解説、字幕に現れる会話などを追いかけているうちに、京都学派が戦時中行った座談会「世界史的立場と日本」が、3DのCGで描かれているということが分かった。
前から気になっていたのだが、西田哲学を継承するいわゆる京大四天王と呼ばれる論客が、この座談会で戦争協力の旗色を明確にしたことが、敗戦後の公職追放その他、彼らの立場を不利にする要因となったとは聞いている。シンガポールの現代アーチストが、わざわざ作品の素材に選んだということは、この時の四人の語りを日本以外のアジアの人が、今も時々参照しているということになる。
ハイデガーとナチスとの関係とかも少し聞いたことがあるので、哲学と戦争との関係も容易ではないことは分かるけれど、日本人としてどう考えたら良いものか知りたくなって、この本を選んでみた。私の興味にズバリ答えてくれたわけではないけれど、まったくハズレというわけでもなく、西田哲学や京都学派がどのように迷走したのか、ある程度詳しく理解することができた。中でも、京都学派が特攻に赴く青年たちの背中を強く押した可能性についてきちんと語られており、逃げずに論証すべきポイントを押さえてくれていると感じた。
筆者も書いているが、「自局に便乗した知識人や文化人は京都学派の哲学者だけではなく、(中略)戦争責任を京都学派だけに押し付けるのは適当ではない」のだが、それを前提にしながらも、ではどう過去を捉えれば良いのか、本書は一定の方向性までは提示している。日本のあちこち、たとえば文学界、映画界その他でも似たようなこと(誰かに責任をおっつけ他はほっかむりしてしまう)が起きたようだが、問題なのは、今もその検証や反省が未だに十分行われていないことだろう。本書は、西田哲学前後の流れも群像として捉えており、哲学周りでもいろんな人の協力や争いがからんでいたことが分かる。その意味では良くも悪くも普通の人たちだ。だが、哲学はある種の普遍性を求める学問だと思うから、話はそれで終わらない。西洋(欧米)とどう付き合うかという問いも、もちろんアジアでの態度も含めて、常に問われなければならないし。
「ネトウヨのように過去から目をそむけて自文化礼賛に邁進するのではなく、かかる過失を犯した愚かさも含めて日本を直視する気概を持てば」道は開ける、というか、捻じ曲がったナショナリズムに陥らずに済むのだろうと思う。だが、先は長い。
京都学派
2018/05/23 18:52
哲学
6人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:七無齋 - この投稿者のレビュー一覧を見る
京都学派の実態やら戦争加担の原因などを解説するための処置だろうが専門的記述が多く、信書という形態にも関わらず理解を困難にさせている。