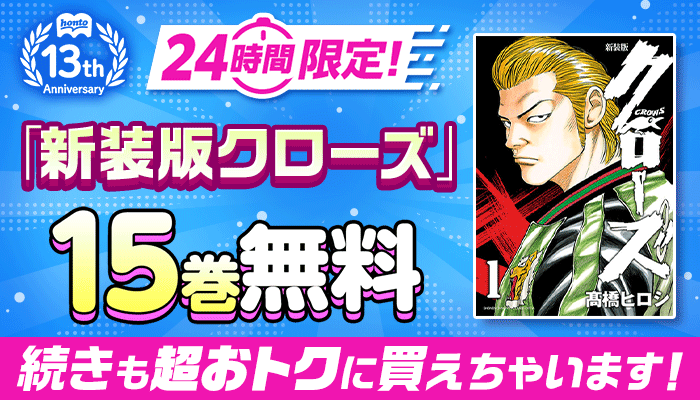- みんなの評価
 2件
2件
大学論 いかに教え、いかに学ぶか
著者 著:大塚英志
大学というのは思いの外、可能性に満ちている場所ではないか。大学全入時代のいま、世間から関心が集まるのは「就職に有利かどうか」一辺倒。学び・教えが軽視されてしまった。でも、大学ならではの「学びの本質」があるのではないだろうか。まんが原作、小説、批評など他ジャンルで活躍する人気筆者が、みずからの体験と実践を紹介しながら、大学の役割を考え直す。(講談社現代新書)
大学論 いかに教え、いかに学ぶか
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは


この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
大学論 いかに教え、いかに学ぶか
2010/05/14 16:43
世の中の、全ての「教えている」人たちに読んで欲しい「大学論」というか「教育論」。漫画技術論としても面白い。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:銀の皿 - この投稿者のレビュー一覧を見る
漫画原作者であり、大学の「まんが表現学科」の教授である著者の「大学論」に、正直そんなに期待していなかったのだが、浅見だった。「教えること、学ぶこと」についてとても核心を突いていて、真剣に読んでしまったのだ。私としては「拾い物」の一冊である。
著者の自分史的な部分やまんが学科での授業のドキュメンタリー的な部分などが混在している、読み物(エッセー)風の体裁のなかに「大学論」としての著者の意見が随所に散りばめられている。著者自身の受けた教育の話、表現論、そして具体的な「漫画論」の中にも、教育について普遍的に考えさせるものがたくさんあった。
例えば、まず方法・技術を徹底的に叩き込むのは「思ったことを制御して描くためにはそれなりの力量が必要だ」という考えからであるという主張から、現代の(ネット上などの)発言場所は広がっても発言のしかたの力量がついていっていない現状批判も出てくる。
「大学生の質が落ちた」という大学教育者の言葉に「教える側の質はどうなのだ」と自分も含めて反省を促し、「近ごろの新書って「あいつはバカだ」と名指しすることで成り立っている本が少なからずある気がしてならない。P106」というところに「書評にもあるかも」と共感する。
「教えられたようにしか教えることができない」などの、教育というものの深さへの言及もあった。
などなど、数えればきりがない。「教える」ことが必要な人(と、いうと全ての大人になるのかもしれないが)に一読してもらいたい本である。漫画技術論としてでも充分面白く読めるので、そちらの興味だけで読んでも満足できると思う。学生たちの集団作品作成風景は締め切りに追われる臨場感もある。
漫画について言えば、そういえばちょっと前「日本のアニメーション文化奨励」と称して箱物建設の話題があがったこともあった。それよりもこういう「つくり手」を養成する活動、「つくり手をつくる」活動を支援するほうがよほど長期的な効果があるのではないかとも思ったことも、付け加えておきたい。
大学論 いかに教え、いかに学ぶか
2012/02/25 09:23
共感できる大学論
3人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Kana - この投稿者のレビュー一覧を見る
著者が大学でおしえているのはマンガであり,おしえる内容も方法も 「大学論」 というタイトルから読者が普通に想像するのとはだいぶちがっている. マンガが大学でおしえるべきものなのかどうかは,読みおわってもなお,わからない. しかし,著者がいいたいのはこれが現在の大学のすがただということだろう. あとがきに著者はつぎのように書いている. 「大学でこの 4 年間,ぼくが行ったことは若いときからずっとものを書きながら考えてきたことを 「教える」 という目的の中で再構築する,ということだ. それは自分の思考を 「批評」 ではなく 「方法」 として徹底してつくりかえることであった.」 このことばには深く共感する.

実施中のおすすめキャンペーン