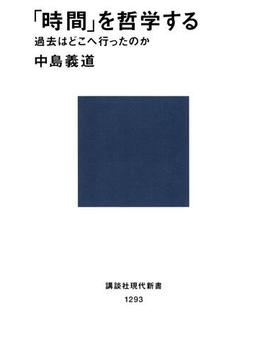- みんなの評価
 4件
4件
「時間」を哲学する 過去はどこへ行ったのか
著者 著:中島義道
超難問「過去はどこへ行ったのか」を考える。過去体験はどこか空間的な場所に消えたのか。未来は彼方から今ここへと到来するのか。過去―現在―未来という認識の文法を疑い、過去が発生する場を見きわめる。(講談社現代新書)
「時間」を哲学する 過去はどこへ行ったのか
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
「時間」を哲学する 過去はどこへ行ったのか
2009/08/19 19:59
中島義道にしては、異色な本。過去の「時間論」をメッタ斬り。
12人中、11人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:反形而上学者 - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書が出てからもう10年以上経つが、こういう「時間」をテーマにした著作というものは、やはり古びない。
「時間論」というと、一般的にはハイデガーの『存在と時間』や、ベルクソンの一連の著作が最も有名で影響力もあることだろう。
本書では、ハイデガーやベルクソンは勿論、カント、ヘーゲル、シェリング、ショーペンハウアー、フッサール、ハンス・ケルゼン、カミュ、トーマス・マン、ジャネーの法則、ゲーテ、アウグスティヌス、メルロ=ポンティ、フロイト、ユング、デモクリトス、ルクレチウス、プラトン、ジェームズ、ロック、ラッセル、マクタガート、デカルト、アリストテレス、レヴィナス、波多野精一、ブーバー、(以上、出て来る順)その他・仏教などについてどんどんと中島氏は斬っていく。
これらの批判に対して、いちいち説明していくと大変なことになってしまうので、それは諦めることにするが、中島氏が言っていることはおおよそこういうことであろう。「時間を論じる時、どんな学者も今までの議論や伝統に知らず知らずの内に引き込まれていて、中々新しいことを説明するにまでは至っていない。中でも、自分自身の思い込みを捨てきれていない学者が多いから、ある種のドグマへへと陥ってしまっている。そういう時間論は役に立たない。」とでもいったところであろうか。
個別の哲学者・思想家に対する批判は、本書を読んでもらって、楽しむ他ないが、昔からあって、しかも答えが出ていない「根源的な問い」であるだけに、本書を読むことの意義は大きいと言えよう。
当然ながら、中島氏の意見に全く賛成できない人もいるであろうし、そういう人は中島氏のどこがおかしいのかを考えてみることに価値がある。
私は、基本的には中島氏には賛成寄りの考え方であるので、ハイデガーに対する批判などは、大いに納得した。
「未来・現在・過去」というように時間を並べた時、一番掴めないのは実は「現在」ではないであろうか。過ぎ去った出来事はどれだけ新しくても、古くても「過去」であるし、まだ起こっていない将来を把握することはできないが、地球から打ち上げた火星探査機が惑星や太陽などの引力を受けて楕円軌道でいつ火星の軌道にのることができるかということは、正確に計算して時間を割りだすことができる。これは間違いなく「未来」の予測であろう。そういう例外はあるものの、「現在には」逐一の「いま」を捉えることは出来ない。「時間」について考える際には、この「掴めない今この時」を中心に据えなければ、本質的な議論の俎上には載らないのではないだろうか・・・。
「時間」を哲学する 過去はどこへ行ったのか
2002/09/24 20:50
時間が流れない世界では、過去も未来も、現在さえも消えていく
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:みーちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
時間のことを考え始めると、きりが無くなる。それこそ、時間が止まってしまう。だから嫌かというと、年に何回かは決まってその手の本を読みたくなる。結局は時間つぶしに終るのだけど、だからと言って発見が無いわけでもない。たとえば、この本で言う「時間を流れとして考えない」というのはとても新鮮だった。それが最近の「記憶は書き換えられる」といった認識に関係し、時間を記憶との関連で捉えるとなると、どういうことになるのか興味津々で読み始めた。
時間を流れとして考えない。そうすると過去も未来も消え、「今」という概念もなくなる。それが最終章の「現在という謎」になる。何とも魅力的な時間論だが、ここで、気になる点がある。著者が自分の「今」の哲学的な定義と、私たちが日常使う「今」という言葉の多義的な意味をあえて混同して、論を展開しているとしか思えないことだ。
中村は自分の時間論の定義を正として、私たちが日常使う「今」の曖昧さをつく。しかし、私たちは敢えて「今」を多義的に解釈することで、人生を送り易くしている。それが人間の知恵というものだろう。その普通の人間たちのしたたかな企みを無視した、大衆は愚かであるという決め付けでの時間論は空しい。
哲学特有の言葉の迷路に入り込むために、哲学者の多くが精神を病む。大衆は彼らの言葉の遊びに飽いて、「また始まったか」とそっぽを向く。それを「頭が悪い」としか定義できない哲学が、人々の心を捉えるはずがない。この本は、文章も親切で例も分りやすく、楽しいけれど最後の章でミスを犯した気がする。読者は著者の想像以上に賢明なのだ。大衆を侮蔑する哲学を、大衆が支えるはずがない。
「時間」を哲学する 過去はどこへ行ったのか
2001/02/18 20:44
これは紛れもない「哲学」の書だ
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:オリオン - この投稿者のレビュー一覧を見る
著者は、「心身問題」とは現在と過去の関係の問題だという。
《いきなり宣誓しますが、私は知覚ではなくむしろ想起こそ「心身問題」のモデルだと思っております。それをみな知覚の場面で論ずるから、答えられないことになる。心身問題の原型は想起、すなわち「刻印」というブラック・ボックスにおける現在と過去との関係なのですが、知覚をモデルにしたとたんに心身問題を引き起こす張本人である「時間」は消去されてしまい、大脳の〈ウチ〉に想起の「場所」を求めるというあたかも空間論のようなかたちをとってしまうのです。》
中島氏よれば、人間とは〈今ここ〉から離脱しつつ〈今ここ〉にとどまっている二重存在なのであり、眼前の知覚風景を見るとき、いつも「見えないもの」としての想起風景との関連で見ているのであって、したがって現在と過去の二元論を「克服」することはけっしてできない。そして、過去はどこへ「行った」のでもなく、「もはやない」ものとして〈今ここ〉にある。
《つまり、現在と過去との両立不可能な関係を必死に「解決」しようとするのではなく、むしろこの矛盾的関係こそ、「ここから」すべての現象が説明されるような根源的関係なのではないか、と思われます。大脳のある状態Gを過去の痕跡とみなす関係は、ほかのところからは説明不可能な根源的関係なのです。(略)「心身問題」のモデルが過去と現在との時間関係であり、具体的には過去の出来事を現在想起することであるという私の見解の根拠はここにあります。「痕跡」というブラック・ボックスの中を探っても現在と過去との関係を示すような証拠物件は何も出てこないでしょう。すべて順序が逆だからです。われわれは現在と過去との根源的関係から出発して、それを適用して大脳の中に「痕跡」というものを読みこんだのですから。》
スリリングな議論が展開された、これは紛れもない「哲学」の書だ。