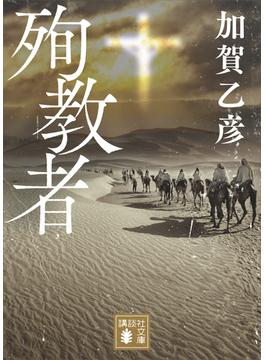- みんなの評価
 1件
1件
殉教者
著者 加賀 乙彦
1614年、2代将軍徳川秀忠がキリシタン禁教令を発布した。キリシタンへの迫害、拷問、殺戮が頻発し、岐部は殉教者の記録を集める。翌年、28歳の岐部はエスパニア人修道士と共に長崎から船出、40日の航海の後にマニラ港に着く。そこで入手した地図には、双六のように、マニラを振り出しに、マカオ、マラッカ、コーチン、ゴア、ポルトガルの要塞のあるホルムズ島、さらにペルシャ砂漠、シリア砂漠、遂にはエルサレムに到達する道筋がこまかく描かれていた。岐部は自らの信仰を強くすることと、イエスの苦難を追体験することを思い、胸を躍らせた。
ペトロ岐部は1587年に豊後の国東半島で生まれ、熱心なキリシタンの父母の元で育つ。13歳の時に一家は長崎に移り、岐部はセミナリオに入学を許される。ここでラテン語を習得し、聖地エルサレムと大都ローマを訪れることを強く決意する。
次に訪れたマカオでは差別に耐えながら志を貫き、何とか旅費を工面して、ミゲルと小西という二人の日本人とともに海路、インドのゴアに向かう。ゴアからローマに向かう船に乗る二人と別れた岐部は、水夫として働きながらホルムズ島に向い、そこからは駱駝の隊商で働き砂漠を通ってエルサレムを目指す。
1619年、岐部はついに聖地エルサレムの地を踏む。そこから徒歩で、イスタンブール、ベオグラード、ザグレブを経て、ヴェネツィアに。祖国を出て5年、岐部はついにローマにたどり着いた。海路で1万4500キロ、徒歩で3万8000キロ。乞食のような身なりの岐部に施しをしようとした神父が、流暢なラテン語で話す岐部に驚き、イエズス会の宿泊所に案内される。そこで岐部は、4日間にわたる試験を受け合格、イエズス会への入会を許された。
ローマとリスボンで2年間の修練を経て、帰国の許可を得た岐部は、キリシタン弾圧の荒れ狂う日本に向けて殉教の旅路についた。
信仰に生きた男の苛酷な生涯が荒廃した現代を照らす、著者渾身の書下ろし長篇小説。
殉教者
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
殉教者
2023/01/17 14:24
よく調べたなぁと思う。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:トッツアン - この投稿者のレビュー一覧を見る
福者となったペトロカスイ岐部の生涯を小説にしたもの。資料の少ない中で、よく調べ上げ、まとめたなぁというのが正直な感想。
師牧者となって日本にもどり、残されたキリスト教徒を支えることを胸にエルサレム、アッシジを経てローマに至るまでの苦難がサラリと著されている。
ところどころに、気づきや分かち合いに似たものを感じさせられた。
ただ、小説として発表された頃の聖書では『癩病』という表現はなくなっている。実際のところ、訳せる言葉がなくこの病気に当てはめたというのが実情なことを考えると、医者でもある著者がこの言葉を使うことは勉強不足ではないか。特に、ハンセン病患者と共に歩む師牧者からは言葉の変更が強く求められ続けている。ユダヤ教の中で、病気そのものが汚らわしいものとして扱われているが、この言葉を使う限り当の患者の方々は神から厭われた人となってしまう。神がそんなことをするわけがない。ここは原文とおり『ツァラト(またはツァラート)』として扱って欲しかった。
資料としてよく調べ上げてまとめた割には、ペトロ岐部の情熱や悲壮感が感じられない。どこか気楽な男に感じられてしまい、突っ込みが足りないと思う。
ペトロ岐部については、『守教』という小説でも描かれているが、やはり突っ込みがたりないと感じた。
ペトロ岐部については、遠藤守作の『銃と十字架』が一番切実なものとして迫ってくると感じた。
そういう意味で、この小説は浅いと思う。