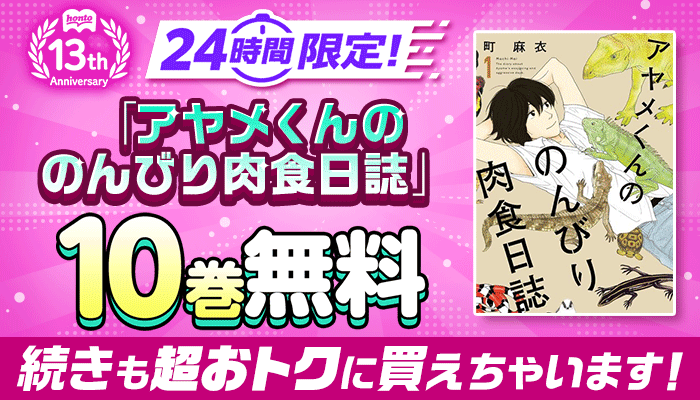- みんなの評価
 5件
5件
メノン
「徳は教えられうるか」というメノンの問は,ソクラテスによって,その前に把握されるべき「徳とはそもそも何であるか」という問に置きかえられ,「徳」の定義への試みがはじまる…….「哲人政治家の教育」という,主著『国家』の中心テーゼであり,プラトンが生涯をかけて追求した実践的課題につながる重要な短篇.
メノン
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
メノン
2003/07/13 17:49
「国家」の前に
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:照葉樹 - この投稿者のレビュー一覧を見る
プラトンの著作の中では最も取っつきやすい入門書。しかし、哲学の専門家からしても「想起説」や「知識」に関する概念が先駆けて登場するため、プラトンの理解には書かせない短編であり、評価も高い。「国家」を読む前に手にするべき一冊。
メノン
2016/06/25 09:14
プラトンが生涯をかけて追及した課題の集大成!
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、プラトンが生涯をかけて追及した実践的な課題を集めたもので、プラトン哲学の入門書とも言われる図書です。プラトンの他の著作に比べると、比較的読みやすく、プラトンを学ぼうと思われている方々にはうってつけの書だと思います。ぜひとも、本書をまず手にとられることをお勧めします。この後、かの有名な『国家』に移っていかれるとより理解が深まるのではないでしょうか。
メノン
2017/04/03 10:00
想起されるべきもの
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:コーチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る
プラトンは、師ソクラテスがアテナイの街かどで、人びととおこなった対話の模様を書き残した。最初は実際の対話を忠実に書き写したかのような書きぶりだったが、いつしかそれはソクラテスの口を借りたプラトン自身の哲学という様相を呈するようになった。徳は教えることができるのかという問題が議論される本書は、解説によると、ソクラテス的な対話篇と、プラトン哲学の両方が展開されているという。ここでいうプラトン哲学の典型は、いわゆる「想起説」である。
対話者メノンは、知識の探求に関するつぎのような議論をソクラテスにふっかける。人間は、すでに知っているものについては、これを探求する必要はなく、また知らないものについては、何を探求すべきかも知らないはずだから、何についてであれ、人間は知識を探求することはできないと。」それに対してソクラテスは、次のように答える。人間の魂は不滅であり、永遠であるから、魂はすでにあらゆる知識をもっている。しかし、現在の人間としての生においては、それらが忘れられている状態である。知識を探求するとは、この忘れているものを想起することにほかならない。ソクラテスはこう述べて、召使の少年に、自らの力で数学の問題を解くよう導く。このように、すでに知識が彼自身のうちにあることを明らかにすることによって、ソクラテスは想起説を根拠づける。
ここで私には、ある疑問が浮かぶ。知識とはいっても、いろいろとある。たとえばある日会社に行くと、見知らぬ人がいる。私はその人を知らないが、人には名前や素性というものがあるのを知っている。だから、私は同僚にあれは誰かとたずね、あれは取引先のSさんだと同僚から教えられ、納得する。
この場合、私がもともともっていたものは、「S」という名や「取引先の人間」という素性などではなく、「名前」や「素性」という、それらを容れるいわば知識の枠組みであった。私は、Sという名前や取引先の人間という情報を度忘れしていたというわけではない。単にそれを知らなかったが、今はそれを知っているというだけである。それを想起と呼ぶのはどうも腑に落ちない。ここでいう想起される知識とはいったい何だろう。
プラトンが探求したのは、真理そのものであった。それは他と境界を接することによって存在を示し、名づけられることによって、整理・分類されるたぐいの情報ではなく、あらゆる個別物の背後にある唯一絶対の真理にほかならない。それは、感覚にとらわれたわれわれ人間には、知覚できないが、しかしそれでも、存在すると私たち自身が信じている、いや少なくとも、そう感じている何かである。そのような信念はどこから生まれるのかというと、かつてわれわれが冥界にいたときに真理そのものをいだいていたという記憶からである。
それゆえ、プラトンがここでいう想起の対象とは、感覚があたえてくれるあれやこれやの知識ではなく、それらの根底にある、より根源的な真理そのものとみるべきであろう。そしてこれこそ、人間の魂が求めてやまない真の知識なのだ。