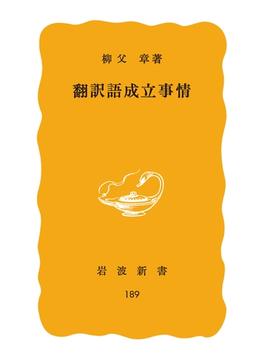- みんなの評価
 3件
3件
翻訳語成立事情
著者 柳父章
かつて、この国に「恋愛」はなかった。「色」や「恋」と区別される“高尚なる感情”を指してLoveの翻訳語がつくられたのは、ほんの一世紀前にすぎない。社会、個人、自然、権利、自由、彼・彼女などの基本語が、幕末―明治期の人びとのどのような知的格闘の中から生まれ、日本人のものの見方をどう導いてきたかを明らかにする。
翻訳語成立事情
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
翻訳語成立事情
2001/04/11 09:36
翻訳語成立事情
6人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:紅の豚 - この投稿者のレビュー一覧を見る
名著である。日本人がどのように外国語に立ち向かってきたかを知ることができるばかりではなく、現代もまだその時の迷いをそのまんま背負って生きていることを実感できる。
また、この著に取り上げられている「コトバ」の迷いを感じることなく、現代の日本人はそれらの「コトバ」を使い続けている。現代の論客とよばれる人たちの中にも翻訳を多用して話す人たちがいる。翻訳語を使えば使うほど、話の内容はすばらしく聞こえてしまうが、この著を読んでいれば、そんなことを感じなくて済むことになる。
翻訳語を意識して使用しなければ、まず持って、そのすばらしく聞こえてくることの内容は稀薄であることを知る。この著を読むことで、翻訳語に圧倒されない判断力を養うことができる。
翻訳語成立事情
2023/03/31 23:18
翻訳語成立事情
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:雄ヤギ - この投稿者のレビュー一覧を見る
中国と西洋という二つの文化圏から言葉や思想を輸入してきた日本には、その言葉をどのように日本人にわかりやすく伝えるか、という問題があった。これに伴う翻訳の際の意味のずれをわかりやすく解説している。
西洋中心の考え方ではなく、日本語を中心にしっかりと考えていると思った。
翻訳語成立事情
2020/06/01 22:53
意味が先か、言葉が先か
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:トリコ - この投稿者のレビュー一覧を見る
幕末から明治時代にかけて、翻訳のために造られた新造語の中から10の言葉を章に立てて述べていく。
「社会」「個人」「近代」「自然」「自由」など。いずれも二文字の、小学校で習う漢字である。
だが、どの言葉も、分かっているようでよくわからない。
著者の、
「ことばは、いったんつくり出されると、意味の乏しい言葉としては扱われない。(略)使っている当人はよく分らなくても、ことばじたいが深遠な意味を本来持っているかのごとくみなされる」
という主張は、重たい気もするし、逆に心持が楽になるような気もする。
良い本だと思う。