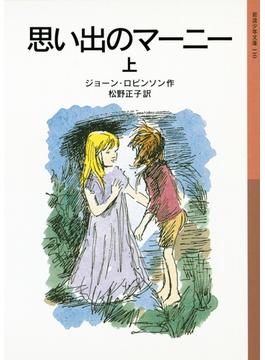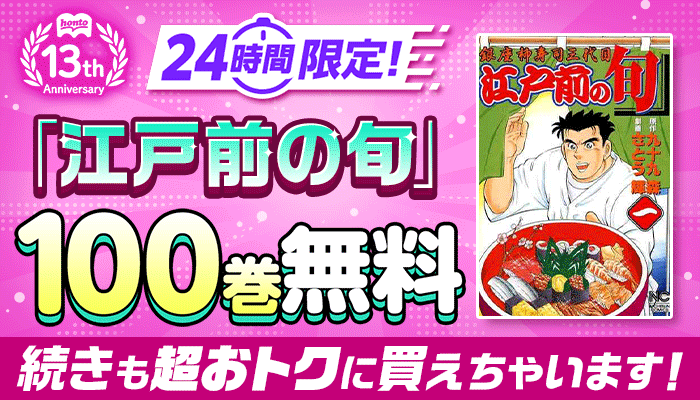- みんなの評価
 5件
5件
思い出のマーニー
著者 ジョーン・ロビンソン (作) , 松野正子 (訳)
養い親のもとを離れ,転地のため海辺の村の老夫婦にあずけられた少女アンナ.孤独なアンナは,同い年の不思議な少女マーニーと友だちになり,毎日二人で遊びます.ところが,村人はだれもマーニーのことを知らないのでした.
思い出のマーニー 下
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
思い出のマーニー 新版 上
2008/11/30 22:23
10代、20代、30代で、三度読み返した一冊
8人中、7人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:wildcat - この投稿者のレビュー一覧を見る
少女時代に私の本好きを決定づけた本が3冊ある。
いずれも人生においてはじめてできた親友が薦めてくれたものだった。
『モモ』、『はてしない物語』そして、この『思い出のマーニー』である。
なんと言われて貸してもらったんだったか正確なところは記憶していない。
たしか、きっとはまると思う・・・だったような気がする。
あるいは、主人公が私に似ているとはっきり言われたのかもしれない。
そして、案の定、見事に、はまった。
この本を最初に読んだのが11歳の頃、
そして、大学の児童室で再読したのが22歳、
そして、やっと本を買ったのが先日。
10代、20代、30代と3回読んだことになる。
そして、今は、英語のブッククラブで借りてきた
原書"When Marnie was there"にも挑戦中である。
この本とはずいぶんと付き合いが長くなったものである。
主人公のアンナは、孤児である。
実の母親も祖母も亡くなってしまい、
プレンストン夫妻に育てられている。
アンナは「おばちゃん」が嫌いなわけではないが、
うまく愛情を表現できないタイプの女の子。
学校でも、できないわけではないのにやろうとさえしない
態度のことを注意されてばかりいる。
人とは距離をとっていたいがために、
「普通の顔」をしてやり過ごす。
心にある秘密は、「おばちゃん」が養育費をもらって
自分を育てていることをとっくに知っているのに、
それを自分に隠していることが許せないこと。
彼女を誘う友達は誰も居ない。
しばらくは学校を休み、転地のために訪れた海辺の村、ノーフォークで、
アンナはマーニーと出会う。
はじめての友達ができたアンナは、少しずつ変わっていくのだが・・・。
ある日マーニーは、無人のさびしい風車小屋にアンナを置き去りにして、
エドワードとともに先に去っていってしまう。
アンナはなかなかマーニーを許せなかった。
ところが、ある日、マーニーは屋敷から去ることになり、
ふたりはもう会えないことが分かる。
そのときアンナは風車小屋先に行ってしまったマーニーを
許してあげることができた。
そのあとアンナとマーニーは会うことができなかった。
だが、ここで許したということは非常に象徴的な
大きな出来事だったのである。
さて、ここでなぜこの許しが象徴的で大きな出来事だったのか
一気にオチまで持ち込みたいところなのだが、
答えを言えないがために、これ以上は語れない。
マーニーがアンナにとってどういう存在だったのかを知ったときは、
きっと私がここに書いた意味を分かってくださるだろうと思う。
時間は、その人がそのように認識しているときが「今」なのだ。
一期一会であるかもしれないから、
許しのタイミングは逃してはいけないのだとだけは言っておこう。
思い出のマーニー 新版 下
2010/04/27 22:12
お互いがお互いでなければならない相手
7人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:wildcat - この投稿者のレビュー一覧を見る
私が本書の上巻に書評をつけたのは2008年11月30日。
今日は、いつもに増して自分語りになってしまい恐縮なのだが、
私は、2008年4月に大切な人を亡くしている。
旅立った人は病を得ていたこともあり、
2008年2月から会うことができないでいた。
書評も2008年2月から2008年10月中旬まで1本も書けなかった。
本書の上巻への書評を書いていた頃は、読書も復活していて、
文章も書けるようにはなっていたものの、
読むものも書くものもどこかで彼のことを思い出させるものばかりだったように思う。
本書も少女時代の自分と非常に縁の深い本だったこともあり、再々読し、
重ねて原書にもチャレンジしたのだった。
彼は、少女時代の自分と縁のある存在で、再会後の1年半の間に
自分に自信のなかった私が自己肯定感をもてるように助けてくれた存在だったからである。
上下巻ある本書の書評は、上巻に集約させて終わらせるつもりでいた。
ところが、1年半が経ち、もう一度本書を読み返した今、
前回の書評で書ききれなかった分をさらに書いてみたいと思うに至ったのである。
そして、それを書く日は今日をおいて他にないと思っている。
原書である"When Marnie Was There"は、入手しづらい状態になっており、
前回チャレンジした原書はブッククラブで借りたものだった。
先日、やっと中古で見つけたそれが、本日届いたのである。
まるで、誰かが今だと背中を押してくれたような気がした。
前回の書評は、アンナがどういう子であるか、
そして、風車小屋に自分を置き去りにしたマーニーを許したことには
大きな意味があったということについて書いた。
だが、上巻と下巻をまとめて1本で書くつもりでいたため、
あらすじについてはきちんと書けてはいなかった。
上巻のストーリーの要約は、marekuro氏の書評に詳しい。
また、marekuro氏の書評では、「あんたの通りに見える」とサンドラに言われて、
アンナが大変傷ついたというエピソードを引いて、彼女が自己肯定感が低かったことに触れている。
受け取る方がどうとも思わなければ、どうともない言葉。
だが、自分のことが好きになれない存在にとっては、これほど痛い言葉はない。
そして、発した相手もそれをわかっていて突いてきているのだ。
悪口か否かは、言葉ではなく、投げ手、そして、受け取り手が決める。
リンゼー家のアンドルーに「やぶにらみの妖精」と
言われてもアンナが怒らないのが好対照な例である。
アンナの心理描写は痛いくらいに当時の私であり、
今も時おり顔を出す、私、である。
大好きなお友だちを独り占めにしていたい気持ち。
似ているところがあるからこそ惹かれあい、
似ていないところは羨ましくて、
でも、本当は相手の奥底にある他の誰もが触れないような淋しさに気づいていて、
だからこそ、その根っこの部分で惹かれあったのだということわかっている。
それでこんなことを言ってしまったりする。
あたしは、あなたにいてほしいの。
あなたがあたしにいてほしいより、
もっと、ずっと、あなたにいてほしいの。
マーニーに言い返されるように、
むちゃくちゃナンセンスなのだけど、
この言葉、自分の言葉として痛いほどにわかる。
上巻で展開されるのは、アンナとマーニーの物語である。
マーニーがアンナを風車小屋に置き去りにし、
エドワードと帰ってしまうのは、
下巻の最初のエピソードである。
そして、マーニーはしめっ地やしきから去り、
アンナとはもう会うことはない。
下巻は、アンナとリンゼー家の物語である。
リンゼー家の人々は、新しく修繕されたしめっ地やしきにやってきた人たちで、
アンナは、マーニーに会うずっと前にリンゼー家の5人兄弟を目撃している。
だが、そのときに村の人は誰も彼らを知らないと言ったため、
アンナは彼らを自分の想像の中の人たちだと思っていたのだ。
マーニーと会っていた頃のアンナは、しめっ地やしきの裏側である海側から訪問していたのであるが、
リンゼー家に訪問するときは、しめっ地やしきの表側から訪問する。
リンゼー家の人たちと知り合ってから、アンナの世界は急展開する。
一見、マーニーのエピソードとリンゼー家のエピソードは、違う物語のように見えるのだが・・・。
自分に自信がなく、周りの人たちとの関係をうまく築けなかったアンナは、
マーニーと友だちになり、その関係を経た後、成長を遂げている。
アンナはマーニーとの出会いを経ていたからこそ、
リンゼー家の子どもたちと友だちになれたのではないか。
これはマーニーの置き土産であったといっていいだろう。
リンゼー家の5人兄弟の中で、もっともアンナと仲良くなるのが
プリシラなのだが、そのことは、
プリシラをプリシラと知る前からアンナにもわかっていて、
遠くからアンナを見つけていたプリシラにもわかっていた。
つかまえてほしいけど、そう簡単にはつかまえてほしくなくて、
続けてしまう追いかけっこ。
そんな気持ちも自分のことのようにわかった。
お互いにお互いではなければない相手というのはわかるものである。
アンナにとってのマーニー、マーニーにとってのアンナ、
アンナにとってのプリシラ、プリシラにとってのアンナ。
そして、アンナはなぜマーニーと出会ったのか、
出会わなければなからなかったのか。
そのすべてをここで語ることはできないのだが、
ひとつだけ前回の書評から展開させておきたい。
自分を風車小屋に置き去りにしたマーニーを許すことができたのは、
アンナにとって大きな意味があったということについて。
風車小屋の事件が起こる前に、アンナは、マーニーに
今まで他の誰にも言うことができなかった秘密を、悲しみや怒りを語っているのだが、
そのひとつに、自分を置いて亡くなってしまった母や祖母に対する怒りの心がある。
自分をひとりぼっちにして旅立ってしまったことへの怒り。
マーニーはそんな怒りを表出したアンナにいくつもの意味で深い答えを返している。
その言葉の深い深い意味は、すべてがわかったときにつながるのだが。
アンナがマーニーを許したことの意味のひとつは、
自分を置いて行ってしまった者への許しであり、
それは母や祖母に対する許しにもつながるのだ。
そして、それは、出会いが一瞬でもう会えなくても、
その相手を愛することであり、感謝するということなのだ。
思い出のマーニー 新版 上
2009/12/29 22:48
少女同士の心の交流を描いた傑作。
6人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:marekuro - この投稿者のレビュー一覧を見る
本好きの友人からのおすすめで読みました。
結論から述べると、非常に面白い作品でした。
この手の時間軸の揺らぎがある作品は大好きだと
いうのもありますが、児童文学の範囲内でそれを
思春期の少女の心と重ね合わせているのが魅力的でも
ありました。
本書は児童文学になりますが、本来読むべき年齢で
読めなかったのが残念でなりません。
少しだけ作品の周辺事情を調べたのですが
どうやら臨床心理学者の河合隼雄氏の著書
『子どもの本を読む』でも取り上げられています。
そして、長らく絶版で入手困難な状況が続いていた
ようで、復刊を希望する書き込みがネット上に残って
ました。
奥付を見ると、ようやく復刊したのが2003年だった
ようです。
上巻におけるストーリーは以下のようになります。
************************************************
両親・祖母を幼少期に亡くし里親の所で暮らすアンナ。
とても優しくしてくれている里親だったが、アンナは
感情面で難しいものを抱えています。
ある夏。ノーフォークという所に療養に出かけることに
なりました。
滞在先の土地で“しめっ地”と“しめっ地屋敷”
というお気に入りの場所を見つけたアンナ。
そこで、アンナがしめっ地屋敷と呼んでいる所に住んでい
るマーニーという女の子と知り合い、仲良くなります。
元々が感情面に若干の問題があり、人と接するのが
苦手なアンナでしたが、マーニーに対しては
一生のお友達だと言える間柄になります。
アンナもマーニーも育った家庭環境こそ違いますが
根本にある“寂しさ”を共有することで心を通じ合わせる
ことが出来ました。
お互いがお互いに与える影響から、少しずつ心を開き
はじめるアンナとマーニーですが‥
**************************************************
上巻のストーリーはこのような流れになっています。
下巻ではびっくりする展開が待っているのですが
上巻においては、淡々とアンナの心理描写やマーニーと
の交流が描かれています。
印象的だったのは以下の場面。
アンナがサンドラという女の子と言い合いをする箇所です。
「あんたはね、あんたは、“あんたのとおりに”
見えてんのよ。やーいだ!」
(p87)
この稚拙な、あまりに稚拙な悪口に対して驚くほど
動揺するアンナ。
たいした気にも留めないで読んでいたのですが
「“あんたのとおりに”見える」
意外と深いなと思います。
アンナは非常にセルフイメージの低い女の子です。
そして心理的に感情的に問題を抱えて療養しています。
そのようなアンナにとって“あんたのとおりに”見える。
のは辛い事なのでしょう。
思春期の子どもに見られる感情のほつれ。気難しさ。
理由なき苛立ち。それらの諸々をアンナとマーニーの
それぞれが持っており、そして淡々と続いていきます。
それらに対して河合先生のように
臨床心理学的に色々と解釈を加えることも
可能でしょう。
しかし。まずは純粋に物語を楽しむことを
おすすめします。
かつて思春期だった人は当時の自分を思い出すようで
ちょっと恥ずかしいかもしれません。
評者は男性であり、アンナやマーニーの気持ち。
いわゆる思春期の少女にありがちな気持ち。を
捕らえ切れていないかもしれません。
しかし、その点を含めた上で読んでも素敵な作品でした。
なお、下巻においては上巻以上に「時間」を意識
させられるストーリーになっています。
そして、上巻における淡々としたストーリー展開が
一転して、ドラマティックなものに変わっていきます。
ちょっと調べてみると多くの方が「児童文学の傑作」
と評していますが、まさにその通りの作品だと
思います。
「何年かしたらもう一度、読み返そう」
素直にそう思える物語でした。
きっと読むたびに色々な発見や気づきが
あるのではないかと思います。