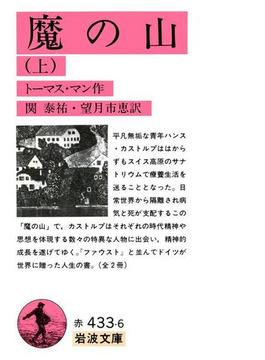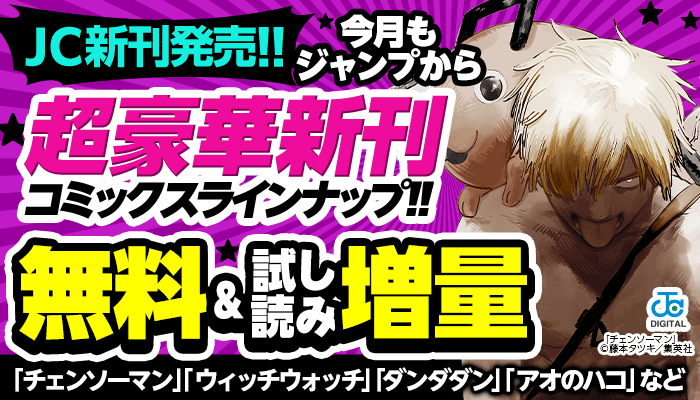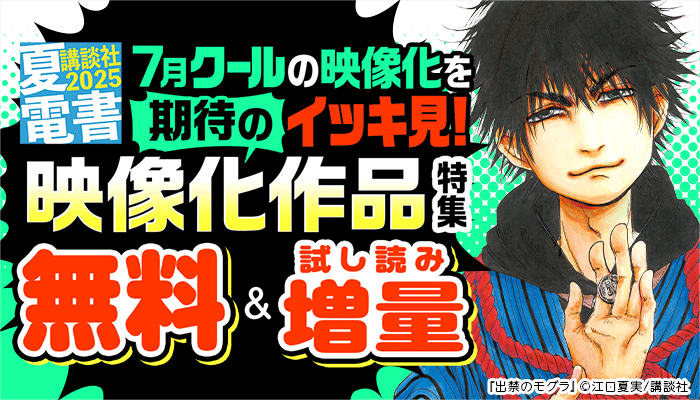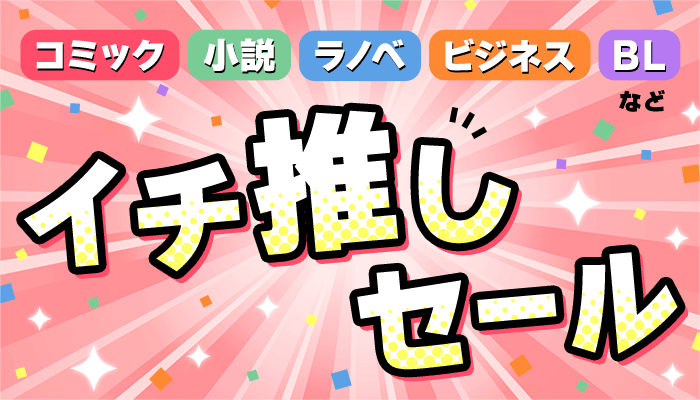- みんなの評価
 2件
2件
魔の山
平凡無垢な青年ハンス・カストルプははからずもスイス高原のサナトリウムで療養生活を送ることとなった.日常世界から隔離され,病気と死が支配するこの「魔の山」で,カストルプはそれぞれの時代精神や思想を体現する特異な人物たちに出会い,精神的成長を遂げてゆく.『ファウスト』と並んでドイツが世界に贈った人生の書.
魔の山 下
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは


この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
魔の山 改版 上
2001/06/19 14:36
魔の山上
7人中、7人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:55555 - この投稿者のレビュー一覧を見る
ドイツには古くから教養小説という伝統的な分野がある。それはどのようなものかというと、主人公が色々な人に出会ったり、色々な体験を経て大人に成長するというものである。
そんな、ドイツの教養小説の枠をトーマス・マンは「魔の山」で破壊した。
何故かというとこれまでの教養小説は少なくとも主人公が遍歴を経て成長するというストーリーであったが、「魔の山」の主人公ハンス・カストルプは移動することなく療養所に何年間も居ることによって肉体的に精神的に成長するのである。
ドイツ教養小説の新たな地平線を切り開いた傑作。
魔の山 改版 上
2017/02/28 23:29
病気と死、そして生と愛
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:コーチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る
長いながい小説である。どちらかというと、変化に乏しく、つまらない内容である。それでも、読んでいる途中でいろいろな箇所に引き込まれ、読後もいろいろ考えさせられるのは、名作の名作たるゆえんだろうか。
青年技師ハンス=カストルプは、数週間の予定でやってきたアルプス山ダボスにあるサナトリウム(療養所)で、結核にかかっていることが判明し、そのまま入院が決まる。彼は、さまざまな人びととの出会いと別れを繰り返しながら、結果的に7年間山上で過ごすことになる。ハンス=カストルプの従兄で、彼が来る前からそこで治療を続けていたヨーアヒム。ともにクセのある、しかし憎めない二人の医師、ベーレンス顧問官と代診のクロコフスキー。進歩思想の擁護者で人文主義者のセテムブリーニ。彼の対立者でイエズス会士のナフタ。そしてハンスが思いを寄せるロシア人女性ショーシャ夫人。その愛人のオランダ人ペーペルコルン...
セテムブリーニ、ナフタが繰り広げる政治談議は、現代の日本でも見られそうな左翼と右翼の不毛なやりとりを彷彿とさせる。語彙が稚拙で、話に論理性に欠けるが、鷹揚な親分肌のペーペルコルンもまた、わが社会に見出すことのできる人物の典型である。後半ではオカルトにはまる療養所内の興奮が描かれるなど、まさに現代社会に共通する事象にあふれている。
しかし本書における最も重要で根本的なテーマは、病気と死であり、それらが襲いかかる肉体と魂の問題である。また病気や死によって浮き彫りにされるのは、生であり愛である。
だから、上巻最後に描かれるハンス=カストルプのショーシャ夫人への愛の告白と、後半の佳境で描かれるヨーアヒムの死とが、最も人間的かつ最も劇的な場面として私の心に残ったとしても不思議ではあるまい。前者は、フランス語を交えながら語られる魂と魂の美しい交流であり、ハンス=カストルプにとっては決して実ることのない、しかし最も満ち足りた、最も幸せな瞬間である。感極まったハンス=カストルプがフランス語で叫ぶのが次のせりふだ。
「アア、愛ハ、君...。肉体、愛、死、コノ三ツハ一ツノモノナンダ。ナゼナラ、肉体ハ病気ト快楽デアッテ、肉体ガ死ヲ招クノダカラ。愛ト死、コノ二ツハドチラモ肉体的デアッテ、ソコニコノ二ツノオソロシサト偉大ナ魔術トガアルノダ。シカシ、死ハ…金モウケシ、腹ヅツミヲ打チ、笑イ興ジテイル生ヨリモズット高貴ナモノナンダ...同ジヨウニ肉体モマタミダラデイマワシイ性質ノモノデ...同時ニ肉体ハマタ偉大ナ尊敬スベキ光輝デアッテ...ソレヘノ愛ハ...世界ノスベテノ教育学ヨリモ教育的な力ナンダ...」
後者のヨーアヒムの死においては、物理現象についてのごとく淡々とした死の記述が、妙に涙を誘う。その涙だが、ハンス=カストルプが流したそれについては、こう述べられる。
「それは、世界のいたるところでどんな時間にも惜しみなくさめざめと流されていて、詩人にこの世を涙の谷とうたわせた透明な液体であり、心身のどちらかが激しい苦痛をあたえられたときに、神経の衝撃で肉体からしぼりだされる塩分をふくんだアルカリ性の腺分泌物であった。ハンス=カストルプは、粘液素と蛋白も少量含まれていることを知っていた。」
2024/07/23 14:47
時間そして生と死と
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:カブタロウ - この投稿者のレビュー一覧を見る
同じようなパターンの繰り返しの毎日に嫌気がさし、やはり同じような繰り返しの日常を題材にした小説があったなあということで魔の山のことをふと思い出した。
確かに20代のころに一度読んでいるはずだが、サナトリュームでの日常が淡々と描写されているだけの小説だったなという印象だった。本書を楽しむには人生経験というよりある程度の知的素養が必要かもしれない。
今回読み返してみて劇的なドラマのないこの小説の濃密さに驚いた。
マン自身が 「千二百ページに渡って繰り広げられる観念構図の夢幻的結合」 と評したように観念の嵐が吹きすさぶ観念の一大絵巻物のような小説だ。この場合の観念とは思考であり、哲学であり、感情であり、意志であり、欲望である。
この小説の主題の一つが時間観念についてだろう。マンの時間に関する見解が織り込まれながら物語は展開してゆく。
絶対的基準となる時間軸など無い世界、何しろここは一年が一日、去年が昨日のように感じる秘境魔の山なのだから。この魔の山の中にあるサナトリュームは相対的時間感覚が極めて強く支配し、全体基調において死や病気への親近感・親愛感が色濃い。
魔の山そこは死の香りが強く漂い、義務と束縛のない無秩序な魔境。
その中で繰り広げられる様々な登場人物の観念の反目と錯綜。例えばセテムブリーニとナフタの論理とペーペルコルンの感情。そんな中で当初単純な精神の持ち主であった青年ハンス・カストルプの精神は複雑さを増し発展してゆく。
「死への親近感から出発して生への意志でおわる変化」、マンが最も親しみ深いとするこの変化はハンス・カストルプの中に体現されたのであろうか。
死と病気の世界から生への意志を戦火の中に飛び込むという行為によって昇華させたハンスの中に。

実施中のおすすめキャンペーン