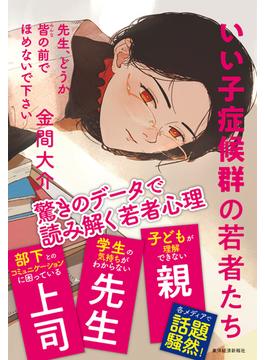- みんなの評価
 10件
10件
先生、どうか皆の前でほめないで下さい
著者 金間大介
ほめられたくない、目立ちたくない、埋もれていたい……。今、こんな若者が激増している。
・「成功した人もしない人も平等にしてください」
・選択の決め手はインフルエンサー
・「浮いたらどうしようといつも考えてます」
・LINEグループで育まれた世界観
・もう「意識高い系」とすら言わない
・上司からの質問を同期に相談する
・自分に自信はないけど社会貢献はしたい
令和の時代の重大異変を、イノベーションとモチベーションの研究家が徹底分析!
先生、どうか皆の前でほめないで下さい
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
2022/08/24 09:29
衝撃的で、考えさせられるタイトルだ。挑発的でもある。大学の教員として青年たちに接する著者が、現場での実体験と、豊富な資料から、その理由をわかりやすく語りかける。
9人中、9人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:mitu - この投稿者のレビュー一覧を見る
衝撃的で、考えさせられるタイトルだ。挑発的でもある。
良いことをしたら、褒める。
そうしたら、喜ばれるのではないか?
大学の教員として青年たちに接する著者が、現場での実体験と、豊富な資料から、その理由をわかりやすく語りかける。
講義では、後ろの方に並んで固まって座る。
物事を決めるために「あみだくじアプリ」はスマホに必須。
「成功した人も、しない人も、平等にして下さい」
「自分の提案が、採用されるのが怖いです」
「浮いたらどうしようと、いつも考えています」
と、多くの若者がそう思っている。
でも、著者は冒頭から断言する。
「若者からは、本当に多くのことを教わる。そして、もし変わる必要があるとしたら、それは彼らではなく大人が作った社会のほうだと、強く感じさせられる」(「はじめに」より)
「挑戦が成長につながることを実感できないのは大人であり、一度失敗すると這い上がれないと思っているのも大人であり、既得権信者もやはり大人である。
大人たちがそう思っているからこそ、それが子どもたち、若者たちに空気感染する。
私からすれば、そんな因果応報を棚に上げて、『まったく、今の若者は覇気がなくてダメだ』なんて言っているのは滑稽ですらある。何のことはない、若者たちはこの30年間、日本の大人たちがやってきたことをコピーしているにすぎない」(P198~9)
「私が知る限り、若者は『現役選手』しか尊敬しない。(中略)若者が変化を好まず、挑戦を避け、守り一辺倒の内向き志向となっているのは、若者が育ってきた日本社会がそうだからだ」
「したがって、本書の提言は1つ。大人のあなたがやるべきだ。まずはあなたが挑戦するべきだ」(P225~226)
当事者である若者たちには、具体的な2つのアドバイスを送っている。
「質問力を鍛えること」
意見を述べるのではなく、単なる質問でいい。
そして、質問のあとの感情を確かめる。
すごく緊張したなら、その分だけ心が成長した証拠。
なにも感じていなかったなら、それは質問する素質があるということ。
「メモの取り方を変える」
資料の気になったところに丸をつけて、横にクエスチョンマークを付けるだけでいい。
話し手の言葉ではなく、自分の頭によぎったことをメモする。
たったこれだけの行為だが、効果は大きい。
読み進めていくと、急所を突かれすぎて痛みすら感じる。
それは、本書の主張が正確なのだからだろう。
まずは、自分自身がどうなのか。
他人と比較するのではない。
昨日の自分より、一歩でも成長しているのか。
「われ以外みなわが師」(吉川英治)
昭和の大文豪の言葉を思い出す。
人生100年の時代。
「生涯青年」の心意気で、死ぬまで学び続けなければならない。
先生、どうか皆の前でほめないで下さい いい子症候群の若者たち
2022/07/20 14:11
ほんとうに
5人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:紫苑 - この投稿者のレビュー一覧を見る
ドンピシャの20代ですが、全てを書かれたような典型的な若者となってしまいました。年が上の方は理解できないとおっしゃるかもしれませんが、自分も周りもこんな感じです。むしろ、これ以外の人を見つけるのが難しいくらい。
先生、どうか皆の前でほめないで下さい いい子症候群の若者たち
2022/08/22 13:23
今の若者はと嘆く前に、自分自身に問おう。 成長していますか、現役選手であり続けられますか、と。 「われ以外みなわが師」(吉川英治)との言葉が思い出した。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:mitu - この投稿者のレビュー一覧を見る
新聞の著者インタビューを読んで手に取った。
衝撃的で、考えさせられるタイトルだ。挑発的でもある。
良いことをしたら、褒める。
そうしたら、喜ばれるのではないか?
大学の教員として青年たちに接する著者が、現場での実体験と、豊富な資料から、その理由をわかりやすく語りかける。
講義では、後ろの方に並んで固まって座る。
物事を決めるために「あみだくじアプリ」はスマホに必須。
「成功した人も、しない人も、平等にして下さい」
「自分の提案が、採用されるのが怖いです」
「浮いたらどうしようと、いつも考えています」
と、多くの若者がそう思っている。
でも、著者は冒頭から断言する。
「若者からは、本当に多くのことを教わる。そして、もし変わる必要があるとしたら、それは彼らではなく大人が作った社会のほうだと、強く感じさせられる」(「はじめに」より)
「挑戦が成長につながることを実感できないのは大人であり、一度失敗すると這い上がれないと思っているのも大人であり、既得権信者もやはり大人である。
大人たちがそう思っているからこそ、それが子どもたち、若者たちに空気感染する。
私からすれば、そんな因果応報を棚に上げて、『まったく、今の若者は覇気がなくてダメだ』なんて言っているのは滑稽ですらある。何のことはない、若者たちはこの30年間、日本の大人たちがやってきたことをコピーしているにすぎない」(P198~9)
「私が知る限り、若者は『現役選手』しか尊敬しない。(中略)若者が変化を好まず、挑戦を避け、守り一辺倒の内向き志向となっているのは、若者が育ってきた日本社会がそうだからだ」
「したがって、本書の提言は1つ。大人のあなたがやるべきだ。まずはあなたが挑戦するべきだ」(P225~226)
当事者である若者たちには、具体的な2つのアドバイスを送っている。
「質問力を鍛えること」
意見を述べるのではなく、単なる質問でいい。
そして、質問のあとの感情を確かめる。
すごく緊張したなら、その分だけ心が成長した証拠。
なにも感じていなかったなら、それは質問する素質があるということ。
「メモの取り方を変える」
資料の気になったところに丸をつけて、横にクエスチョンマークを付けるだけでいい。
話し手の言葉ではなく、自分の頭によぎったことをメモする。
たったこれだけの行為だが、効果は大きい。
読み進めていくと、急所を突かれすぎて痛みすら感じる。
それは、本書の主張が正確なのだからだろう。
まずは、自分自身がどうなのか。
他人と比較するのではない。
昨日の自分より、一歩でも成長しているのか。
「われ以外みなわが師」(吉川英治)
昭和の大文豪の言葉を思い出す。
人生100年の時代。
「生涯青年」の心意気で、死ぬまで学び続けなければならない。