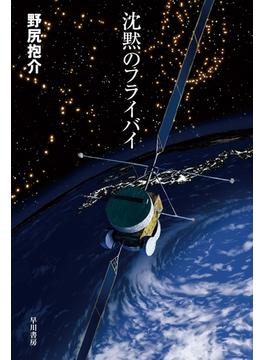- みんなの評価
 5件
5件
沈黙のフライバイ
著者 野尻抱介 (著)
アンドロメダ方面を発信源とする謎の有意信号が発見された。分析の結果、JAXAの野嶋と弥生はそれが恒星間測位システムの信号であり、異星人の探査機が地球に向かっていることを確信する――静かなるファーストコンタクトがもたらした壮大なビジョンを描く表題作、一人の女子大生の思いつきが大気圏外への道を拓く「大風呂敷と蜘蛛の糸」ほか全5篇を収録。宇宙開発の現状と真正面から斬り結んだ、野尻宇宙SFの精髄。
沈黙のフライバイ
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
沈黙のフライバイ
2008/05/12 00:09
傑作です、日本ハードSFの到達点
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:読み人 - この投稿者のレビュー一覧を見る
日本のハードSFの第一人者、野尻抱介さんの短編集です。
これどの作品も、ほんとアイデアが素晴らしくて、傑作です。
それもそのはず、収録作品の発表時期に物凄い間隔があいており
ほとんど、著者のベスト本といってもいいぐらいなのですから、
アイデアは、ぎゅーっと凝縮されております。
元々、SFはアイデア一発勝負みたいな側面もあり
一つのアイデアでとりあえず、手探りというか、ツカミというか、
短編を仕上げ、そこから書き込んでいって長編にするなんて
欧米、国内問わず、よく用いられております。
それは、おいといて、
野尻さんの作品の主要登場人物は、みんな
SFなので、理性的で、論理的な思考の持ち主なのは、
言うまでもないのですが、過激というか、リスクを恐れないというか、
兎に角前へ進もう進もうというフロンティア精神、パイオニア精神の塊です。
それが、理論的でややもすれば、停滞気味なガチガチのハードSFに対し
強力なドライブ力というか、物語の駆動力を与えております。
このパイオニア精神が顕著に表れているのが、
文字通り、「片道切符」という題名の作品と「大風呂敷と蜘蛛の糸」 。
この辺の精神が実際の著者の言動に出ていると、巻末の解説にありました。
引用させていただくと、
「どうして、帰ってこないといけないんですかね、、」という野尻さんのお言葉、、。
これに、全てが、集められています。
「大風呂敷と蜘蛛の糸」は、若い女の子が高高度の成層圏の上、中間層で凧に乗って飛ぶという
ネタなのですが、けっこう危機的な状況なのにこの女の子の爽快感の伴う、さわやかな
心境は、なんなんだ!?。
ここに、プロットとあらすじだけでは、表現しきれません。
ハードSFは、ガチガチの考証にセンス・オブ・ワンダー、と
著者の素晴らしいアイデアで一瞬のそのガチガチの考証を切り開いた時に
鮮やかに輝くものを読む感じなのですが、
今回は、勿論そのハードSFの持つ、輝きにも圧倒されましたが、
なにより、野尻さんの前に進もうというドライブ感、ポジティブさに
圧倒されました。
ほんと、傑作です。読んでください。
沈黙のフライバイ
2016/05/09 22:31
短編5つ
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:はぎ - この投稿者のレビュー一覧を見る
どれも、宇宙への進出・探索を現実的に考察した作品ばかりです。
特に気に入ったのが表題作でもある「沈黙のフライバイ」です。
実際に検討されたこともあるらしい「サーモンエッグ計画」という、恒星間探索のアイディアを基にした作品です。結構現実的で、もう数年もすれば実現できそうな技術のような気がします。
しかし、この作品で実際にそれを実行するのは人間ではなく異星人の側です。人間はそれをただ見るだけです。淡々として特に盛り上がるわけでもありませんが、それがかえってよかったのかなと思います。
その他の作品もなかなかの良作揃いで、満足できる一冊でした。
沈黙のフライバイ
2007/10/05 23:21
前へ進め!僕ら。宇宙へ
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:SlowBird - この投稿者のレビュー一覧を見る
フライバイ、孤独な言葉だ。通過。太陽系を通過するマイクロマシンの艦隊、それは霧のように来たりて過ぎ去る。それが人工物だと分かっていても、コミュニケーションは不可能なのか。然り。まったく異なる文明間のそれは必ず限界があることはS.レムの諸作に示される通りと思う。だが哲学、観念の世界と、現実にはまた違う様相がある。例えば電波を探知し、コード化し、解読できるものとできないものに分ける。それだけ。まずやりたいこと、出来ることをやってみる。多くは望まなくていい。たったそれだけで、新しい世界が拡がり始め、孤独はいくらかの共感に取って代われる。考えるのはそれからでも遅くない。理屈は手を動かしてから言え、寝言は寝て言え。技術者という立場での一つの倫理基盤であり、プラトン、アリストテレス的なものとはまったく異なる思想。独自性においても、現実の成果においても日本が世界に誇るべき思想だろう。それを小説という形でもっともよく表現し得ているのが、この野尻抱介だ。
表題作は、宇宙航空研究開発機構の一介の研究員がその担い手として、地道に淡々と、内心は熱く滾りながらそれを表現してくれる。「大風呂敷と蜘蛛の糸」ではそれは大学院生と研究チームが主役。こちらは凧で宇宙(といっても成層圏の少し上の中間圏まで)を目指すという、斬新だが、おそらくほんの少しの技術的飛躍と、予算獲得によって実現可能な夢のプロジェクト。巨大ロケットによる月や火星への旅に比べればささやかな冒険だが、最高の叡智と勇気が詰まっている。
「ゆりかごから墓場まで」では、生化学で人間の生存環境を培う新技術の開発者はタイのベンチャー企業、それを活用する主人公はインド人技術者というのも、近未来の世界のあり様を示唆している。この技術は宇宙とむちゃくちゃ相性がいいわけだが、それゆえにかえってインドの火星移住プロジェクトの悲惨さは目を覆うばかり、いや、ここは笑うところだろうか。とにかくプロジェクトはうまく進んでいるのだから。もちろん試練はある。技術者魂爆発の展開は快感。
「轍の先にあるもの」は一転、老境にあるSF作家の小惑星の地表を写したたった一枚の写真に対する懐古、そして時代は変わり、彼自らがその地に赴くことになる。時代の進歩の速度とともに、ノスタルジーの形も変っていくというところが興味深いのでおじゃる。
こういった作品で、テーマがみな宇宙開発に関わるものなのは、そりゃ作者も僕らも宇宙が好きだから。ガガーリンの時代なら、大人になったら宇宙飛行士になりたいというのは、人類でたった一人しか選ばれない、文字通りの夢と言える夢とだったけど、半世紀が過ぎて、今や努力でいくらでも叶えられる現実的な目標になっている。1000人でも1万人でも宇宙は受け入れてくれる。ちょっとしたブレイクスルーで、辿り着ける距離はどんどん伸びる。そういう移り変わりのリアルを映し出している希有な作品集だ。そして観念の世界では近くても、生身の人間にとっては広大無辺な太陽系世界の最良の案内人でもある。