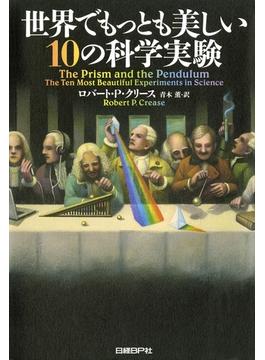- みんなの評価
 3件
3件
世界でもっとも美しい10の科学実験
著者 ロバート・P.クリース (著) , 青木薫 (訳)
実験で知る科学史です。科学史(特に物理学)に残る著名な実験のうち、物理学誌の読者投票で選ばれたもっとも美しい実験のベスト10を式なしで説明し、美しさのポイントを絵画の鑑賞のようにやさしく解説します。実験の背景となる理論、実験の概要を説明した後、著者が美しいと感じた理由やトリビア的な知識を開陳します。扱っているテーマは、エラトステネスの地球の外周の長さを求める実験、ガリレオがピサの斜塔で落下の法則を確認した実験、ガリレオが慣性の法則を確認した実験、ニュートンがプリズムで確認した光の分散の実験、キャヴェンディッシュの万有引力定数を求める実験、ヤングの光の干渉に関する実験、フーコーの振り子による地球自転を確認する実験、ミリカンが電気素量を求めた油滴実験、ラザフォードが原子核を発見したα線の散乱実験、ファインマンの量子力学に関する2重スリットの思考実験。
世界でもっとも美しい10の科学実験
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
世界でもっとも美しい10の科学実験
2008/08/26 16:41
二重スリット実験の映像に感動した。そして,あなたもそうだといいなと思ってる。
11人中、11人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:SnakeHole - この投稿者のレビュー一覧を見る
ケネス・W. フォードの「不思議な量子」に「電子は原子内の3次元空間に波として広がっている」という話が出てくる。「ああそうですか」と納得しちゃうヒトには簡単なのだが,これが以下のような実験をして導き出されたと聞けばどうだろう。
電子銃から一度に一個の電子を放出する。その行く先には放出された電子を受け止める検出システムがあるのだが,両者の間には壁が一枚設けられており,その壁には二つ,縦長のスリットが開いている……。たとえばこれをピッチャーとキャッチャー,それにマウンドとホームベースの中間に置かれた壁とすれば,キャッチャーが受け止めたボールは必ずどちらかのスリットをくぐり抜けて来たことになる。常識ですよね?
ところがこれが電子では常識ではなくなる。この実験器具を実際に作り一個ずつ電子を何個も検出システムにぶつけてみると,そこには典型的な干渉波のパタンが現れるのだ。意味解りませんか? つまり一個の電子は二つのスリットの両方を同時に通り抜けるのだ。そして互いに干渉し,また一個の電子として検出システムに到達する。おお,大リーグボール4号ですな,あれ5号かな?
本書は,この実験(二重スリット実験という)をはじめとして,科学雑誌「フィジックス・ワールド」の読者が選んだ「美しい科学実験トップ10」を解説したものだ。エラトステネスによる地球外周の計算や,ガリレオが行ったというピサの斜塔から重さの違う球を落とす実験,ニュートンの太陽光分解,地球の自転を証明するフーコーの振り子……。
果たして科学実験を「美しい」と呼べるのか,という哲学的な疑問に逐次答えつつ,著者は「科学する」ことの楽しさを余すところなく伝えている。もし時間がおありなら是非,
「Electron Waves Unveil The Microcosmos」にあるムービーをご覧あれ。これは日立製作所基礎研究所の外村彰さんがロンドンの王立研究所で1994年にやった講演のフィルムで,二重スリット実験で電子が干渉波を描くさまをその目で見ることができる。オレはこれを美しいと思った,正直言って感動した。そして,あなたもそうだといいなと思ってる。
2022/03/17 11:08
特にエラトステネスが
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Koukun - この投稿者のレビュー一覧を見る
自然科学の世界で言う「美しい」という形容詞を、豊富な具体例で持って明らかにした好著である。著者は「美しい」を 基本的、効率的、決定的 と端的 明快に定義づけているが、本書を読めばその様な定義に照らし合わせなくても「美しい」という印象を受けることができる。特にエラトステネスの話が印象的である。地球の大きさを測る という行為 精度以上に、2000年前に「科学的思考」を行う という行為に感服した。
世界でもっとも美しい10の科学実験
2007/03/25 16:39
「美しい化学実験」の実例集
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:萬寿生 - この投稿者のレビュー一覧を見る
「美しい化学実験」とは何か?。著者はその条件として、深さ(基本的であること)、経済性(効率的であること)、決定的であること、の三つを挙げている。その代表としてこの本にとりあげられている、10の物理学の実験は感動的ですばらしい。特に、紀元前三世紀、ギリシャのエラトステネスが日時計の針の影を使って、地球の円周の長さを、現在の測定値にたいし数%の誤差で測定した第一章と、油滴を使って電子の電荷を測定した第8章のミリカンの実験が、私には印象的であった。
理科離れや数学離れが問題になっている現状では、この本を読んでも科学実験の美しさというものは、理解できない人が多いかもしれない。だからこそ、高校生や教養課程の大学生に読んでもらいたい。科学者たちの失敗と挫折と、試行錯誤の工夫でそれを乗り越え、後になれば誰でも納得できる明瞭な方法で、決定的な結果を示す、その過程を追体験すれば、何故これらの実験が美しいのかが、解ってこよう。10のうち1つ2つは、美しい、感動的だ、と感じる実験があるであろう。