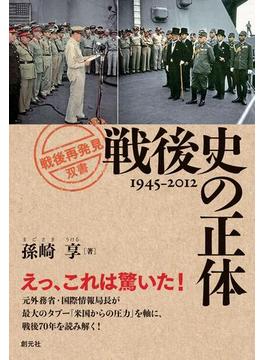- みんなの評価
 8件
8件
戦後史の正体
著者 孫崎享
日本の戦後史は、アメリカからの圧力を前提に考察しなければ、その本質が見えてこない。元外務省・国際情報局長という日本のインテリジェンス(諜報)部門のトップで、「日本の外務省が生んだ唯一の国家戦略家」と呼ばれる著者が、これまでのタブーを破り、日米関係と戦後70年の真実について語る。
戦後史の正体
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
戦後史の正体 1945−2012
2012/11/19 10:59
アメリカからの圧力・・・という観点からひも解く戦後史
23人中、18人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Fukusuke55 - この投稿者のレビュー一覧を見る
著者によれば、「高校生が読める戦後史の本」・・・というのが、出版社のお題だったそうです。高校生どころか、今を生きるわれわれ日本のオトナに取っても大変分かりやすいことに加えて、内容がなんとも衝撃的。いや、衝撃を通り越して、過激の域に突入しています。
「読んでびっくり!」
なぜ、「読んでびっくり!」かというと、本書が徹頭徹尾「アメリカからの圧力」という視点で貫かれている戦後史だからです。
少なくとも50歳未満の日本人が知らなかったこと(知ろうとしなかったこと)、学校で教わったことと違うこと、日々新聞やニュースで取りあげられている内容と異なっていることが、これでもか!というくらい登場します。
どうもこれは、現代日本にとって、タブー中のタブーだそう。
例えば、どれだけの総理大臣が「自主独立」のスタンスを示したことで、退任に追い込まれて行ったか・・・。
一応、大人なので、孫崎さんのこの主張をひとつの意見として認識し、同様に反対の立場を取る政治家、役人、経済・政治学者の主張も同様に理解する必要があるなと思いました。バランスを取ることへの強い欲求とでも言いましょうか、そんな感覚を覚えます。そのバランスを自身で咀嚼した上で、自ら判断することに尽きるのではないでしょうか。
純粋で真っ白な高校生には、本書が「すーっ」と入るんだろうなぁ。そして少しずつ歴史観というものが刷り込まれて行くんだろうなぁ。比較するのは申し訳ないけれど、中国・韓国の愛国教育というのも、こんな感じなんだろうか・・・と、ちょっと軽い懸念を覚えます。
本書を読んで、私自身は、これからのニュースに見かたが間違いなく変わると確信したし、これから学ぶ公共政策の分野についても少し視点が広がった気がします。
高校生は言うに及ばず、ものの分別がついてしまっているオトナにぜひオススメです。
私を含む、日本のオトナの皆さんが、米国に寄り添う(本書では「追従する」となっている)道を選ぶのか?自主独立の道を目指すのか?
国際経済、国際社会における米国との相対的位置づけも鑑みながら、オトナとして自分の軸をきちんと持っていたいです。
経験ではなく歴史から学ぶ賢者になりたいものです。
♯ 岸 信介さん、宮澤 喜一さんについては、総理大臣在任中の仕事、対米国の立ち位置、総理大臣になる前・なった後も含めて、きちんと勉強しようと思います。
戦後史の正体 1945−2012
2012/12/02 02:18
日本人必読の書
16人中、12人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:在外邦人 - この投稿者のレビュー一覧を見る
著者孫崎亨氏はおそらく命がけでこの本を書かれた筈。
ツイッターのフォロワーが多い事で知られるが、ネットメディアにも
しばしば出演されているのは、身を守る一つの方法のようだ。
衆議院選挙投票前に有権者必読の書。
いっそ高校の教科書にすべき内容だ。
戦後史の正体 1945−2012
2016/01/04 01:23
日本への米国の干渉波想像以上!
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:美佳子 - この投稿者のレビュー一覧を見る
孫崎享氏の「戦後史の正体」(386p)、いろいろ衝撃的でした。想像以上にアメリカが日本の内政に干渉していることが克明に記されています。ザックリまとめると、アメリカに都合のよくない政権は短命になるということ。その為に活躍したのがGHQであり、CIAであり、親米派の官僚やマスメディアでした。きっと現在もそうです。
踏んではならないアメリカの「虎の尾」とは:1.米国抜きの日本の独自外交、特に日中関係の強化や、2.日米軍の削減・または撤退、3.冷戦後は日本の経済的繁栄(これを崩すためのプラザ合意、米国債買い、TPP)です。
政権を倒すパターンは孫崎氏によると以下の通り。
1.占領軍の指示により公職追放:鳩山一郎、石橋湛山
2.検察が起訴し、マスコミが大々的に報道し、政治生命を絶つ(検察、中でも特捜部の前身はGHQ指揮下の「隠匿退蔵物資事件捜査部」で、設立当初からアメリカと密接な関係):芦田均、田中角栄、小沢一郎、(竹下登のリクルート事件もこのカテゴリーに入る可能性あり)
3.政権内の重要人物を切ることを求め、結果的に内閣を崩壊させる:片山哲、細川護熙
4.米国が支持していないことを強調し、党内の反対勢力の勢いを強める:鳩山由紀夫、福田康夫
5.選挙で敗北:宮沢喜一
6.大衆を動員し、政権を崩壊させる:岸信介(60年安保にはCIAが日本の財界を通して資金提供)。
6のパターンはイランのパーレビ国王打倒・イラン革命、エジプトやチュニジアの『アラブの春』等でお馴染ですが、岸信介の場合、自身がCIAのエージェントだったという噂もある人なので、意外でした。どうも彼の「駐留米軍の最大限の撤退(有事駐留のみにする)」と「日中貿易拡大」路線がアメリカの逆鱗に触れたようです。
これに比べれば鳩山由紀夫の「最低でも県外」という要求など可愛いものですが、あっさり葬られましたね。
「米国からの圧力」を軸に戦後70年を読み解く、という本ですが、実際そういう視点で戦後史を見ていると色々と辻褄が合ってきて、納得できることが激増します。今後も様々な政治家のスキャンダルがマスコミで騒がれることがあるでしょうが、その渦中の人物がどのような政治姿勢を持っていたか、米国の「虎の尾」を踏んでないかどうかを考えてみれば、でっち上げかそうでないかが見えてくるかもしれません。