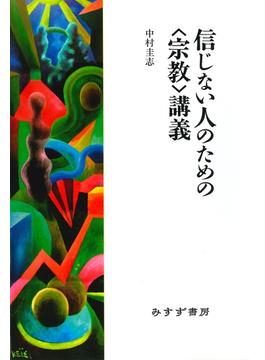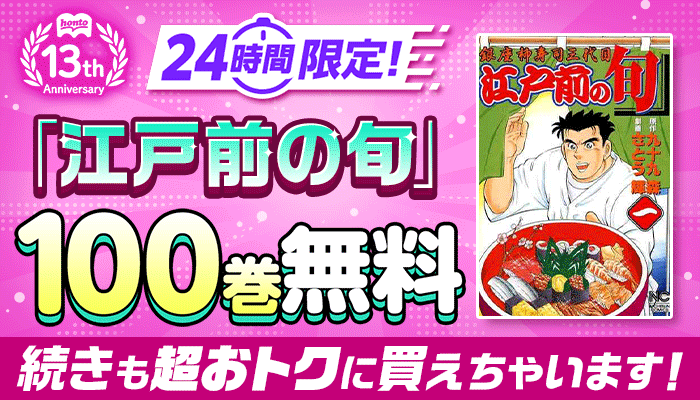- みんなの評価
 2件
2件
信じない人のための〈宗教〉講義
著者 中村圭志(著)
〈宗教〉なんて過去の遺物? あやしいもの? 怖いもの? そんなあなたのために、ざっくばらんな世界〈宗教〉ツアーをご用意しました。ご安心ください。何か特定の〈宗教〉へお誘いするようなことはありません。私もまたいわゆる〈無宗教〉の一人ですから。
「〈宗教〉という言葉はやや漠然とした言葉です。この茫漠と広がる意味領域を大雑把にひっくるめて述べるとすると、〈宗教〉とはなんらかの制度として存在している、とでも言っておくしかなさそうです。そうした制度の別の側面は、人びとの意識のなかに現れるさまざまな世界イメージです。
人びとは日々の暮らしのなかで世界イメージを自己のものとする努力を行なっています。この努力の世界に読者をいざなおうというのが本書の目的です」(はじめに)
宗教家や宗教学者にはちょっと書けない、この脱〈信仰〉型の宗教案内で、私たち自身の偏見や怖れをも、このさい解きほぐしてみましょう。
信じない人のための〈宗教〉講義
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
信じない人のための〈宗教〉講義
2007/11/09 11:54
「宗教」という言葉でまとめられている概念に、今、この時代の私たちは何を感じ、求めているのか。
5人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:銀の皿 - この投稿者のレビュー一覧を見る
かなりそっけなく、「宗教をどうとらえるか」という話が書かれています。語りかけるような、とても柔らかい、時には柔らかすぎるかな、と思わせるような文章。表紙カバーにも明るい彩色の抽象画。ちょっとこれまでの「みすず書房の本」のイメージを変えてくれるような印象です。ちなみに、この表紙カバーの画は著者自身のもののようですね。
短めの20章に分かれていて、前半はいろいろな宗教の来歴や概要説明が中心。「信じている人」には感情を害されるような表現もあるかも、とは思いますが、それでも「他者にはこのような見方をされている」と受け止めて欲しいところです。自分の信じている宗教以外は案外「こんなものか」と許して読んでしまうかもしれません。「信じない人」はすぱすぱと切ってまとめられて行く文章は爽快に感じるかも。例えばクリスマスの起源について、「ライバル宗教の祭日に裏番組としてぶっつけた(p53)」などと言うのはそんな部分の一例でしょうか。
個々の宗教を「柔らかく」概観していっても、著者の意図するのは「宗教とは何か」よりも宗教の捉え方を通して「私たちの時代とは何か」を考えること。「はじめに」に続く章のタイトルにいきなり「無限の多様性」とあるとおり、個々の宗教の定義をするより、しきれない多様性、言葉で切り取れない「宗教といわれるもの」の姿を浮き出させていきます。一神教、多神教という言葉でわけても、内情はどうか。世俗的な部分、精神的な部分、こころとかたちの問題にも境目はなさそう。それでも「宗教」で表現される「なにか」を人間は必要としてここまで来たのは確かなようである。。。
「宗教」という言葉でまとめられている概念に、今、この時代の私たちは何を感じ、求めているのか。世界を理解し、生きていく手段としての「宗教」。宗教といわれるものがそういう役割を果たしてきたことは確かです。「宗教とはなにか?」を問うより、そこに今の私たちは何を求めようとしているのかを考えよう、という著者のメッセージは最後の3章ぐらいを読むとよく伝わってきます。確かに、そうすることで見えてくるものがありそうです。
「もろもろの伝統のなかから「宗教」というカテゴリーあるいはアイデンティティーをデジタルに切り出したのは、近代西洋のロジックだったのではないか?(p231)」という著者の提示は、ちょっと虚をつかれた気もして「眼から鱗」でした。15章「どう語る?日本宗教」でも、古来の宗教である神道は、それまでは「そういう風になっている」と(ほとんど無意識に?)続いてきた慣習、考えであり、仏教という「言葉で定義された」宗教が入ってきて、それに対比されることで「言葉で定義、確立された」とありました。言葉で規定すること、切り取ることで理解は進展したのでしょう。しかし切り捨てたこともあるかも、と時々思い出す必要がある。これは「宗教」だけでなく、言葉で思考するすべての事柄に通用する警告だと思います。
宗教から始め、思考をさらに広げてくれるところもある本でした。
信じない人のための〈宗教〉講義
2007/09/05 20:19
私的でデジタルな宗教は可能か?
6人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:dimple - この投稿者のレビュー一覧を見る
中村圭志『信じない人のための<宗教>講義』(みすず書房、2007年)を読了した。
本書は、世界三大宗教(キリスト教、イスラム教、仏教)を中心に、世界の宗教について教科書的に概観した後で、「宗教」について考察する。
中村は、宗教を日常と離れた「あっち側」のものとする、二分法的な捉え方に疑問を投げかける。
すなわち、宗教のあり方は、日常における功利性のあり方、論理のあり方、生活のあり方によって支えられている、とするのである。
そこで、宗教について考えるとき、「日常圏における地理的・歴史的相違のほうをひとまず重視して捉えるべきでなないか」という考え方を提示する。
中村は現代日本人の宗教観について考察はしていないが、上記の考え方を敷衍して自分なりに考えてみると、21世紀を迎えた今、われわれ日本人は、形式的な「葬式仏教」すらも超越して、新たな宗教観を獲得しつつあるように思われる。
それを一言で表現するならば、「身近な人たちへの崇拝」信仰ともいうべきものである。それは、土着の祖先崇拝とも違う。
なぜなら、崇拝の対象は血族に限らないからである。血族といっても、親しく接したわけでもない、祖父母やそれ以前の人たちへの追慕の感情は生まれない。
追慕の感情が生まれるのは、両親や兄弟、配偶者や子供あたりの近親者に加えて、親しくしてきた友人やリスペクトする知人も含まれる。場合によっては、リスペクトする歌手やスポーツ選手、溺愛したペットも追慕の対象となるかもしれない。
そして、それら追慕(信仰)の対象は、デジタルカメラなどによってデータ化され、ウェブ上のサーバに蓄えられてブログやHP、SNSを通して時空を超えて存在し続けるのである。
この「デジタルにして私的・身近な信仰」は、世界に先駆けた21世紀の宗教観だと思うのだが、いかがであろうか。