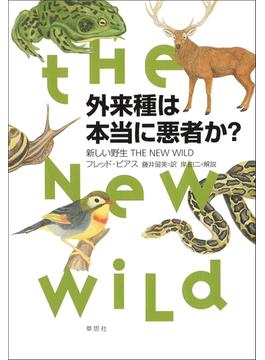外来種は本当に悪者か? 新しい野生 THE NEW WILD
よそ者、嫌われ者の生き物たちが失われた生態系を元気にしている! ?
生態系を破壊すると言われる外来種だが、実際には、環境になじめず死滅するケースが多い。定着したものも、むしろ、受粉や種子の伝播を手助けしたり、イタドリやホテイアオイなど、人間が破壊した生態系を再生した例もある。
著者は、孤軍奮闘する外来種の“活躍" 例を、世界中から集めた。
「手つかずの自然」が失われている昨今、自然の摂理のもとで外来種が果たす役割を「新しい生(ニュー・ワイルド)」としてあえて評価する。
外来種のイメージを根底から覆す、著名科学ジャーナリストによる知的興奮にみちたサイエンス・ノンフィクション。
R・ドーキンス『利己的な遺伝子』共訳者で進化生態学者の岸由二氏による解説付き。
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
外来種は本当に悪者か? 新しい野生THE NEW WILD
2016/12/31 19:49
「生態系は完成された隙の無いもの」というイデオロギーに一石を投じる
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:miyajima - この投稿者のレビュー一覧を見る
侵入生物学という学問分野があります。
生態系は一つの場所でともに進化してきた動植物の緊密な連合体だという考えをもとにしています。生態系は順調に動いている機械のようなもので、在来種だけで完成された状態にあるから侵入者が入り込む余地はない、と説きます。
さかのぼれば19世紀の植物学者フレデリック・クレメンツは、植物は群落をつくることで平衡に達すると考えました。これは今で言う生態系です。世界の気候帯はそれぞれに恒久的な植物群落が出来上がっていて、それを「極相」と名付けました。平衡状態が崩れると「遷移」を通じてかつての安定した状態を取り戻そうとするというものです。
20世紀に入るとクレメンツの考えは生態系の概念へと発展します。部分の総和よりも全体が大きくなる植物共同体であり、多数の個体が集まって一つの個体のようなふるまいを見せる「スーパーオーガニズム」だと規定されます。さらにそれが進んで、熱帯雨林は単なる樹木の集合体ではなく、システムとして機能しているという発想や、さらには地球全体が生態系の集まりだとする「バイオスフィア」論も出てきます。ジェームズ・ラブロックはバイオスフィア自体が一つの生命体だととらえ「ガイア」と命名しました。
さて、侵入生物学はこの四半世紀で学問分野として確立しました。ですがその狭量な姿勢に批判の声も高まっています。中でも問題視されているのは「外来種は悪者」という前提から出発しその見立てにあうテーマしか取り上げない、しかも引用の誤り、局所から地球全体への無茶な飛躍などがこれでもかと出ている点です。著者は実際に影響力のある学者の論文を丹念に調べ、あいまいな点は著者自身はあるいは引用元の原典に当たってそれらの嘘や誇張を明らかにしているのです。さらには新たな、あるいは古くからあっても無視されてきた研究を丁寧に紹介してもいます。
外来種は在来種を押しやると批判されますが、実際には在来種の減少でできた隙間にうまくはまっただけ、という場合の方が圧倒的に多いのです。それどころか外来種が生物多様性を高めていたケースの方が多かったのです。
このような事例がこれでもかと挙げられています。つまり、「自然は壊れやすく一度変化した生態系は二度と戻らない」という信念を揺るがすものばかりです。著者が挙げる事例を見れば、自然が一定の状態を続けることはなく、ダイナミクスこそ重要だということが分かります。
生物の活動単位は「個体」単位であり、自らの遺伝子や生理機能にしがって生命活動を営んでいるだけであり、より高次の目的とかスーパーオーガニズムなるものに制約されることはない、排他的で独立した群落をつくるために関係を結ぶわけでなない、という考え方も出てきています。偶然の出会いの積み重ねが複雑な生命相を形成したのであって、生態系で起きているのは共進化よりもむしろこういった「エコロジカルフィッティング」だというものです。
ということで、「外来種は何が何でも排除せよ」という自然保護論に対して当の生態学から寄せられる異論を丁寧に紹介することで一石を投じる本です。巻末に岸由二先生が解説を寄せていますが、この「旧来の自然保護論」に対してきわめて厳しい口調で批判をしておられます。ご自身の体験を踏まえたその論説は、本書の主張を大いに補強するのではないでしょうか。私も岸先生が批判的な解説をしていたことから本書に俄然興味を持った次第です。そうでなければ手にしなかった可能性が大です。
外来種は本当に悪者か? 新しい野生THE NEW WILD
2016/10/04 20:14
これはもう科学というよりイデオロギーの話。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:銀の皿 - この投稿者のレビュー一覧を見る
「環境を守ろう」「自然を大切に」との意識は高まっていると思いますが、「なぜ守る?」「なぜ大切?」という疑問に答えるのは意外に難しいです。考えるときによく「悪者」になってしまうのが外来種。本書では外来種をどう理解し、評価するかがテーマです。文章はテンポが良く、紹介されている世界の具体例をいろいろ知るだけでも勉強になります。ジャーナリストらしい著者の、ちょっとドキッとするような表現も記憶に残るものです。
外来種の問題を積極的に紹介してきたという著者は、わたしも「そういうこともあるかも」とどこかで思っていたことをすっぱりと文章化しています。もちろん、著者の主張したいことに都合の良い方向にアレンジされているのかもしれませんが、それでも「そういう風に考えてみることも必要、と思わされる個所が多数ありました。
「生物」は遺伝子で「複製=同じ物」をつくると同時に「変異=変化」で変わっていくことで続いてきた、という本質にまで著者は言及していきます。「在来の生態系を変えてはいけない」というけれど、実際は少しずつ変わっていくもの。「人間は今の自分を守りたいもの」というところまでつなげて考えた著者の言葉にもドキリとさせられました。「自分の作り上げたもの」「いまのわかっている状態」を護りたい、という性質を持っている。ここまで来ると「人間性」を考える哲学の本にも思えてきました。読んでいくとどうしても「外国人受け入れ問題」と被ってしまうところも多かったのが事実です。
考えてみれば外来種の中には「荒れた土地を緑に戻す」ために導入されたものもあれば、「綺麗な花」だからと園芸用に持ってこられた物だってあります。人間の都合で連れてこられたもの、知らないうちに連れてきちゃったもの。結局はそこにいる「人間の都合」で歓迎されたり悪者になったりしているようにも思えます。
外来種の力で変化してできる「新しい自然」。原題のThe New Wild:Why Invasive species will be nature's salvation by Fred Pearceはこういうことなのですね。
かなり刺激的な意見もあるので、索引などから調べ直す必要があるものもありそうです。きちんと索引(英語ですが)があるのはありがたいですが、いかんせんものすごく文字が縮小されていて読みづらい。年配者にはつらいところです。
解説を書いている岸由二さんは、三浦半島の小網代の谷の自然づくりにも携わっているかたで、著者よりの意見です。「現代生態学の核心的なテーマを扱う不思議な本」 P314とまで解説しています。この文章も併せて読む価値あり、です。
外来種は本当に悪者か? 新しい野生THE NEW WILD
2016/11/17 21:05
全てを悪者にしないで。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ロン - この投稿者のレビュー一覧を見る
外来生物は悪というレッテルは良くないことを改めて、認識できる本です。侵略的外来生物は駆除する必要がありますが、それ以外は、共存していくことが大切です。