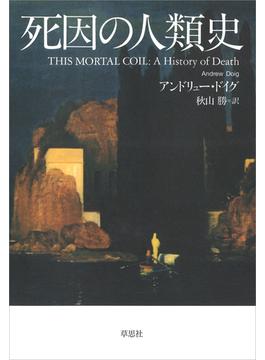- みんなの評価
 3件
3件
死因の人類史
著者 著者:アンドリュー・ドイグ , 翻訳:秋山 勝
人はどのように死んできたのか?
人類の歴史において「死因」は変化しつづけてきた。
現在、先進諸国の平均寿命は80歳を超え、おもな死因は
心疾患、脳血管疾患、癌、認知症などが占めるが、
100年前には平均寿命は約50歳、主要な死因は結核、
インフルエンザ、肺炎などの感染症だった。
中世には飢饉、ペスト、出産(産褥熱)、戦争が多くの生命を奪い、
旧石器時代は暴力や事故による死に覆われていたという。
次々と襲いかかる「死」に、人びとはどのように向き合い、克服してきたのか。
飢餓や疫病はどのように乗り越えられたのか。
さらに、遺伝子改変で人の寿命はどこまで延びるのか。
最新のデータをもとに歴史的、科学的に検証しつつ、背景にある
社会、経済、政治、宗教や文化などの変化と影響を分析し、
死因から世界史を読み解く初めての人類史。
死因の人類史
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
死因の人類史
2024/05/21 14:32
どんな死因が主か、時代それぞれ。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:名取の姫小松 - この投稿者のレビュー一覧を見る
飢饉や戦争、感染症など、人類の死の原因は様々で、時代によって変化してきた。文明の発展によって退けられた死因があり、あらたに問題になってくる死因が出てくる。それぞれの死因ごとの説明や、科学で判明した人間の遺伝子の不思議さに読む手が止まらない。
死因の人類史
2024/05/28 13:37
人類の最大の死因は、人類の発展そのものであった
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:kapa - この投稿者のレビュー一覧を見る
LPレコードやCDを、収録曲で買うのではなく、カバーやブックレット表紙のデザインが決め手となって買う、いわゆる「ジャケ買い」。本もカバーがつくことが当たり前で、デザインに工夫を凝らしているものもあるが、「カバー買い」というのがあってもいいだろう。本書カバーは、スイス象徴主義画家アルノルト・ベックリンの『死の島』が使われている。そこには、死者の霊が最後に行き着く先であると想像して書かれた島が三途の川の上に浮かび、そこへ向かう死者の霊を乗せた渡し守の船が描かれている。島の恐ろしい断崖絶壁やそそり立つ糸杉、不気味な水門、どす黒い波、白装束の渡し守など不気味な雰囲気を醸し出す絵であるが、当時人気のあった絵で、複製が多くの家で飾られていたという。また、死のイメージはナチスの思想とも共鳴し、ヒトラーは首相官邸に飾っていた。クラシック音楽の世界でもこの絵にインスピレーションを得て作曲された作品は多く、有名なラフマニノフやレーガーの作品を含めて、現在19人の作品が確認できる。
これまで「生ける屍」(ピーター・ディキンスン,ちくま文庫2013)と「魔王の島」(ジェローム・ルブリ,文春文庫2022)の二冊があったが、本書は『死の島』カバー買いの三冊目である。二冊はホラー・ミステリと「お気に入り」ジャンル作品であったので、買っただけ、ではなくちゃんと読んだ。二冊とも面白い本だった。「魔王の島」はブックレビュー済み。
そして今回は、生化学教授による初めての一般読者向け著作のようで、最新のデータをもとに歴史的、科学的に検証しつつ、背景にある社会、経済、政治、宗教や文化などの変化と影響を分析し、「死因」を通して人類の歴史を俯瞰する歴史書といってもいいだろう。
感染症から始まり、公衆生成の発展の歴史、飢饉と栄養不足、遺伝、中毒(最近何かと話題になった「賭博」も死因の一つとして考察)、事故、と扱う内容な多岐にわたる。人類の死因は人類の誕生とともに大きく変わってきたことがわかる。医学の進歩・公衆衛生によって、どんどん人類の平均寿命は延びてきているが、人類に体の構造からすると、生物的耐用年数は、「人生50年」なのだそうだ。平均寿命が耐用年数を超えていけばいくほど、ガタが来るのは当然で、そのガタが新たな死因となっていく。かつては「老化」「ボケ」といわれた症状も、今では「認知症」という病気になっている。また、聞いたところでは、「病気」とはそれを直す薬がある疾患と考えるのである。新薬開発によって特効薬・治療法ができれば、その適応症は病気であり、あらたな死因として認識され、死因のカタログに収載されることになるのだ。科学の進歩と死因の増加は「いたちごっこ」の歴史だ。中でも遺伝に関する章は、著者の専門領域なのか、かなり詳しく説明しているが、これも現代の「死因」なのだ。なぜなら遺伝子治療があるからだ。タバコ・自動車の章も、饒舌な語り口である。
ここまで読むと、永遠不易の死因、そして絶対に克服できない死因は「人間」であることがわかる。人類が狩猟・移動生活から農耕・定住生活になったことで、人と家畜が密集することによるウィルスの変異と感染症拡大、飢饉が死因となり、次いで技術の発展による移動手段の発展は、他の集団との争い(戦争)・侵略などは感染症も拡散するし、交通事故(今地球で最大の死因らしい)を招く。日本もそうだが、今死亡率と出生率の低下でおきる「人口転換」現象が見られ、いずれ地球人口は減少するらしい。死因を減らすには、人口を減らすことだ、という著者の言葉は示唆的であり、重い。
2024/06/01 18:49
死因
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:タタ - この投稿者のレビュー一覧を見る
死因から見るとその時代のことが、なんとなく見えてきて面白かったです。あまり見ない着眼点で楽しいなと思います。