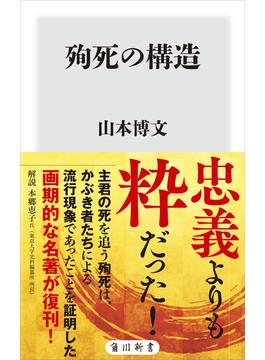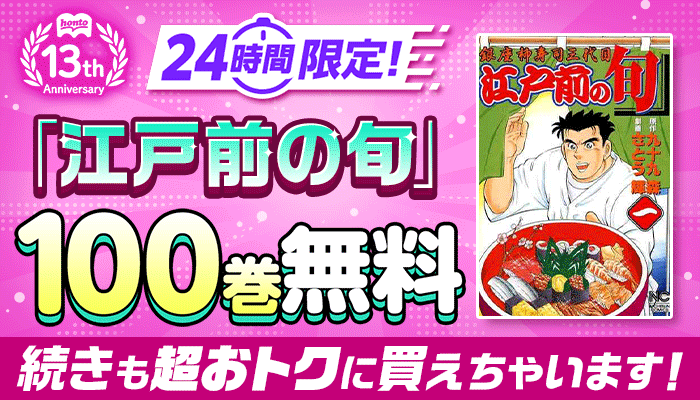- みんなの評価
 2件
2件
殉死の構造
著者 山本博文(著者)
江戸時代に社会現象となった殉死は、主君が自然死した場合に家臣や家族など関りがあった者が後を追って自害することを指すが、殉死した多くは主君と近い距離にあった上級武士ではなく、下級武士だったことがわかっている。いったいなぜ下級武士は距離の遠い主のために殉死したのか。殉死は主君の死を悲しみ、死後もお供をするという「忠誠心」によるものと思われがちであるが、そうではない。殉死の本質は、戦争が非日常となった17世紀、戦いに命を懸けることもなくなり、武士、特に体制から疎外された「かぶき者」たちの自己主張のひとつの形であったのだ。さまざまな殉死の実例から、殉死の新解釈に迫った名著復刊。※本書は、1994年に弘文堂より刊行され、2008年に講談社学術文庫で刊行された『殉死の構造』を復刊したものです。底本には講談社学術文庫版第一刷を使用しました。復刊にあたり、著作権継承者の御了解を得て、改題の他、難読漢字に読み仮名を付すなどの表記上の整理を行いました。
殉死の構造
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
殉死の構造
2022/11/08 16:07
御供
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:とめ - この投稿者のレビュー一覧を見る
寛永のころ主に下層の者に大流行した日本の死の文化としての死者に随従するための自殺行為としての殉死。武士の一分を守ろうとするかぶき者の心情や家臣の男道、自己陶酔の要素も考慮しながら当時の武士道を研究している。
殉死の構造
2022/10/13 23:18
文章が読みにくく、あまり理解できませんでした。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:広島の中日ファン - この投稿者のレビュー一覧を見る
殉死をテーマに、日本史での殉死した人物たちの事例をたくさん取り上げた1冊です。
当書は、もともと、20世紀に同タイトルで刊行された作品を、今回こうして新書化したものです。
再販されるあたり、当書は書物として昔からかなりの人気だそうです。ですが、私には文章が難解で、内容がよく理解できませんでした。個人的には期待外れでした。ですが、読む人によっては評価は変わると思います。