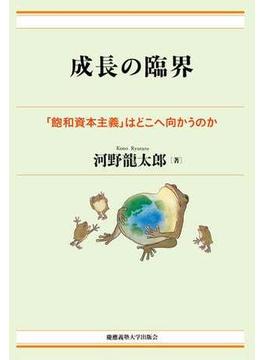- みんなの評価
 2件
2件
成長の臨界
著者 河野龍太郎(著)
「別の未来」は手にできるのか?
ローマクラブの『成長の限界』から50年、世界経済は新たな局面に突入している。地球風船は永遠の繁栄が続くという幻想を極限まで膨らませ、いつ破裂してもおかしくない緊張の中を漂っている。現状はもはや維持できないのか? 新しい秩序はどう形成されるのか? 著名エコノミストが経済・金融の視点からのみならず、政治学・歴史学・心理学などの知見も交えて現況を怜悧に分析し、迫り来る次の世界を展望する、読み応え十分の一書!
▼経済・金融分野でわが国きっての実力派エコノミストが満を持して書き下ろした本格経済解説書!
▼単なる時事解説とは一線を画す、深い洞察を伴った現代経済社会分析。
日本経済論、国際経済論、経済政策論、金融政策論、財政金融論、米国経済論から最近はチャイニーズ・エコノミック・レポートまで、著者の専門守備範囲は多岐に亘る。本書は、これら膨大な知識と著者独自の世界観を踏まえ、21世紀のグローバル金融・経済と日本の現状を考察し、将来に向けて展望する、大局観を伴ったスケールの大きな解説書。
著者は日経ヴェリタスの「債券・為替アナリスト エコノミスト人気調査」エコノミスト部門で数多く(2021,22年は2年連続)首位に選出されるなど、経済論壇では著名な人気エコノミスト。
成長の臨界
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
成長の臨界 「飽和資本主義」はどこへ向かうのか
2023/08/02 14:35
日本は長期停滞に陥っているのか。どうすれば脱却できるのか。
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ぴんさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
なぜ、日本は長期停滞に陥っているのか。どうすれば脱却できるのか。それが本書の最大のテーマである。考えられる要因は多々ある。グローバル経済による貿易の影響。日本人の働き方が変わったことによる所得分配のゆがみの影響。社会保障制度が時代の変化に対応できていないこと。金融システムや公的債務、さらに地政学の問題もある。これらの問題は、経済学だけではとても対処できない。関係する専門領域があまりにも細かく分かれてしまっているからである。そこで、経済学のみならず、グローバルな視点、歴史的な視点、政治的な視点も盛り込んで論じてみようというのが、本書の試みである。
成長の臨界 「飽和資本主義」はどこへ向かうのか
2022/10/16 20:38
日本は30年余り経済成長せず、今後どうするべきかを考える
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:雑多な本読み - この投稿者のレビュー一覧を見る
著者は経済学の研究者であるが、銀行や証券会社に在籍し、他の学問領域との連携を重視されている。
「はじめに」でさっそく、ローマクラブの「成長の限界」から50年経過し、世界経済は新たな局面に突入していると説く。地球は人口増を始め、永遠の繁栄が続くという幻想を膨らませ、緊張の中を漂っているという。これを指摘されている方も多い。エコノミストとして、経済・金融の視点からの展開は当然として、政治学や歴史学、心理学などからアプローチされ、現状の分析をされている。
目次を見ると、はじめにから、
第1章 第3次グローバリゼーションの光と影
第2章 分配の歪みがもたらす低成長と低金利
第3章 日本の長期停滞の真因
第4章 イノベーションと生産のジレンマ
第5章 超低金利政策・再考
第6章 公的債務の政治経済学
第7章 「一強基軸通貨」ドル体制のゆらぎー国際通貨覇権の攻防
終章 よりよき社会をめざして となる。
目次を見てわかるように、日本経済、国際経済から経済・金融政策や米国経済、目次ではわからないが、中国の動きまで多岐にわたる。ボリュームも500ページを超える。例えば、第3次のグローバリゼーションではホワイトカラーのオフショアリングの時代となり、現在の多額の国債発行は未来の需要の先食い、富裕層への財の集中は貯蓄を増やすだけで需要の喚起に至らないこと等多くの指摘が次々出てくる。超低金利政策で、日本の高齢者の多額の預貯金に対する金利の付け替えや金融機関の経営難を引き起こすだけでなく、急速な円安に打つ手が少ないという問題は多くの人が感じているだろう。結局、アベノミクスと言っても、日本経済の成長らしい成長はなく、現在に至っている。多くの指摘は貴重であるが、経済学というのは、分析はできても、処方箋を書くものではなく、政治家や実務家の仕事であろう。さらに突っ込んだヒントを期待したいが、一読の価値がある。