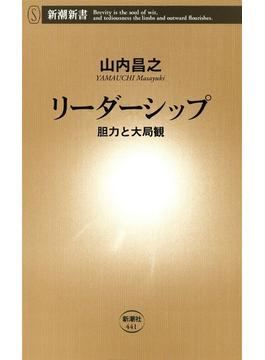リーダーシップとは何か、を歴史上のリーダーたちの具体的な行動から考えいきます。
2012/04/15 21:42
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:龍. - この投稿者のレビュー一覧を見る
リーダーシップとは何か、を歴史上のリーダーたちの具体的な行動から考えいきます。
本書が書かれたのは昨年の夏。従って、管前首相の退陣の前後の状況を考慮しつつ、その言動からリーダーシップとは何かを書いているということです。
よく「リーダーの器」という言葉を使いますが、為政者の役割は国家の果たすべき責任をリーダーとして人格的に担わなければならないとされています。
人格的ということですから、人間性も含めたところで、リーダーの資質があるかどうか判断されるということです。
その点、「管氏はひどかった」というのが本書の最も訴えたかったところのようです。
未曾有の大災害に直面したときに、一番リーダーシップが求められます。しかし、今回の対応はあまりにひどかったのは、国民の知るところでもあります。
「運が悪かった」と言えばそれで終わりかもしれません。それまでの歴代の首相であっても、優れたリーダーシップを発揮した人はごくわずかなのですから。ただ、リーダーは結果責任が問われます。しかも、運が悪かったでは済まされない場面もあるのです。
歴史上のリーダーたちの行動を見ていると、様々な形のリーダーシップがあります。というより、本書の構成がエッセイや講演からまとめられたものであるため、体系立ったリーダーシップ論とは言い難いところがあるのです。
リーダーシップとは何かという確定的な説明はありません。
ただ終わりの方に書かれているリーダーに求められる資質として、総合力、胆力、人心掌握力の三つは絶対条件であると言えるでしょう。
龍.
「歴史に学ぶ」という姿勢
2014/09/28 09:33
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:wayway - この投稿者のレビュー一覧を見る
何かのビジネス雑誌に載っていたことから、手にとってみた。
未だ民主党が政権を取っていた頃に発売されており、丁度、野田さん
が首相になったころの新書である。少し古い感じがするが、
かの東日本大震災の発生時に発揮されることのなかったリーダーシップ
を嘆きつつ、では「リーダーシップ」とは何たるかを実例(実名)
を挙げて分かりやすく書かれている。
リンカーン、山岡鉄舟、西郷隆盛、大久保利通らを挙げながら、リーダー
シップの偉人として「吉田松陰、山口多聞、松永弾正・織田信長」を
それぞれ、歴史的思考法、危機に積極策、悪のリーダーシップとして
取り上げている。
そして、リーダーの条件として次の3つを挙げる。
1.総合力(全体、全局を見通す力)
2.胆力(何があっても動じない強い平常心)
3.人心掌握力(人をうまく使う力)
また、こう言って締めくくっている。
時代の変化に対応する能力を育むということは、すなわち普段からの
「歴史に学ぶ」という姿勢が大切になるということである。
投稿元:
レビューを見る
山内先生の本は、イスラム関係で読んだことがあり、好感をもっていたので、職場の平積みから購入。
予想に反して、かなり感情的に山内先生は、鳩山総理、菅総理のリーダーシップの資質について批判している。
自分は、そういう総理を選んだのは、国民の選択であること、自分も役人の一人として政権を立場にあることから、外交、内政の混乱の責任は、自分も含めて国民全体が追うものと考える。
国民にふさわしい、国民のレベルにあった政治家しか得られないと思う。
国民の一人として、自分をもっと磨きたい。
その他の点については、引用文献も豊富で、納得できる。
①内閣や原子力担当の官僚や東電役員を初めとするエリートたちが、震災後の対応に四苦八苦している姿を見ると、学歴や年功序列を基本とした伝統的な人事秩序や組織的価値が、国難を迎えたときにいかに無力であるかを、日本人は改めて痛感しただろう。(p153)
対応が適切でなかったという批判を自分は真摯に受け止める。
②ミッドウェー海戦で、日本の空母が3隻しずめられて、山田多聞が指令官となって反撃にでるときの訓辞。「我が方は確かに苦しい。しかし、敵も苦しいのだ。死んでくれ。わしもあとからいく。」(p131)
鬼気迫る信念を感じる。こういう司令官のリーダーシップのもとで仕事をしてみたい。自分も部下にそういえるような実力をつけたい。
③外交にあたる政治家に大事なのは、未知の非常現象に遭遇したときに、恐怖心を何とか中和し、不安な感情を抑える術を身につけることっだろう。胆力ある政治家なら、心の乱れを免れない場合にも、それを「緩和」することができるからだ。(p180)
自分は、胆力があるとは思えないので、どうやって胆力を鍛えたらいいか、悩むところだ。
参考文献としては、『西郷南州遺訓』岡義武『近代日本の政治家』(岩波現代文庫)、本郷和人『名将の言葉』(バイインターナショナル)、北影雄幸『戦国武将の美学』(勉誠出版)を読んでみたい。
投稿元:
レビューを見る
途中、偉人が多く登場してくる。が、剛胆さ、先見性はわかるもののリーダーシップとはなんぞ?がボケている感あり
最初と最後に民主党のリーダーだった方について述べられているが、もっともである一方、新鮮味はない
むしろ、リーダーシップの資質がある、ありそうな日本の政治家を例に挙げて論じて欲しい
投稿元:
レビューを見る
震災後の日本のリーダー、管総理、民主党の対応のダメさについて、日本の世界の歴史を例にして確認。また、リーダーとはどうあるべきかについて、歴史上の人物からひもとく。ちいさな会社のひとつの小さな組織のリーダーとして学ぶべき点も多い。
投稿元:
レビューを見る
歴史上の名将、名宰相などから、リーダーとしてどう振る舞うべきかを論じた書だが、簡潔であるわりに引用する歴史上の人物も古今東西に多岐にわたり、あまりポピュラーとは言えない人物をフィーチャーしている点で、著者のこの研究に対する造詣の深さを示しており、この本をきっかけに気になった偉人に更に深く関連書に当たるのもいいのでは。
投稿元:
レビューを見る
対象としている人物について私が知らない人が多かったことと文書(文体)が平易とは言えなかったことから、スムーズに読むことはできず、ページを読み返しながらの読書となった。
何人かの人物が取り上げられているが、なかでも、日本海軍の山口多聞のリーダーとしての危機に状況を見て積極策に打って出ようとする振る舞い、考え方、戦略思考に感心させられた。
対照的に、現在の日本の首相のリーダーシップの無さを明快に説明させられて、不安を感じるとともに残念な気持ちになった。
リーダーのような立場になることもあるし、周りのリーダーを常に見て、仕事をしている。
総合力(全体、全局を見通す力)・胆力(何があっても動じない強い平常心)・人心掌握力(人をうまく使う能力)がリーダーには必要とまとめられているが、どれをとっても全然伴っていない。
少しでもそれらしきものが持てるように努力したい。
投稿元:
レビューを見る
やっぱり鳩山、菅のダメさ加減が実感できる。
吉田松陰の行動力、山口多聞の決断力と潔さが際立つ。
この二人の生涯を大河ドラマで観たくなった。
この二人を会社の上司にはまねできないだろう。
投稿元:
レビューを見る
歴史上のリーダーの行動を振り返りながら、
為政者に総合力・胆力・人心掌握力の3つの資質が必要であることを説いた本。
同時に、野田さん以前の民主党総裁がダメであった理由も言及している。
本書で著者の言いたいことを完全に理解できる人はかなり限定される。
理由はあまりに世界史・日本史のコアな知識が必要とされる点。
自分もそうであるが、この知識のない場合、事例にあげられている人物、
そしてシチュエーションが全く理解できず、よって納得は全くできない。
また事例が多すぎるため、ひとつひとつがどうしても浅い。
鳩山さん、菅さんの批判も感情的とも言え、全てを同感することは出来なかった。
但し、冒頭に挙げられている資質はやはり重要だと思う。
投稿元:
レビューを見る
歴史上の人物のリーダーシップを織り交ぜながら、民主党党首たち(鳩山さん、菅さん)を痛烈な批判、その対比を展開、ちょっとまとまりのなさも感じたが、俺なりには新発見(山口多聞中将など)もあり、興味深く読了。
投稿元:
レビューを見る
歴史上の指導者がいかに優れているかを羅列して解説することによってリーダーシップの満たす条件あげている。
塩野七生氏によれば、知力、説得力、肉体上の耐久力、自己制御の能力、持続する意志を上げており、筆者はこれを絞って、①総合力、②胆力、③人心把握力の3つを上げている。
筆者が上げた歴史上のリーダーと比較され、現民主党政権、とりわけ鳩山、管がいかにダメなリーダーであったか、ということが切々と書かれている。
投稿元:
レビューを見る
会社の後輩から借りた本です。
歴史上の政治家・戦略家達のリーダーシップの紹介が出ています。
いろいろな偉人が紹介されており、すべてが興味深いですが、吉田松陰の客観的な分析力を持った上での「前向きに、悲観せず」の姿勢が共感できました。このように振舞いたいと感じました。
投稿元:
レビューを見る
「賢者は歴史に学び、愚者は経験に学ぶ」とはドイツ帝国初代宰相ビスマルクの言葉。管首相の「奇兵隊内閣」という言葉を選んだセンスを歴史を知らない悲しさだと看破。佐藤一斎の「大臣の職は、大綱を統ぶるのみ」(言志四緑)という言葉が印象に残った。自分を顧みて、やや細部にまで入り込みすぎていないか。自分の職責において「大綱を統ぶる」とは?考えさせられた。
投稿元:
レビューを見る
著者はリーダーの条件として,総合力(大局観ないし国家観),胆力,人心掌握力をあげる。これは,全くその通りであり,前総理の菅直人,その前の鳩山”友”紀夫が,この3条件のいずれも満たしていなかったのは明らかだと思う。
さて,内容は,歴史上の名将・宰相らの事例を挙げて,「リーダーシップとは何ぞや」ということを論じている。ただ,その事例が多いこと,(僕の勉強不足ですが)焦点が当てられている人物がそこまでメジャーではないこと,結論部分の記載が薄いこと,から本書を理解できる人はなかなかいないのではないでしょうか。
示唆に富むものではありますが,その分,「リーダーシップとは?」という核心部分が見えにくくなっている気がします。
投稿元:
レビューを見る
読む間・・・
ちょっとこりゃ難しいぞ。読む前提の基礎知識がだいぶいる。
読み終えて・・・
総論のようなタイトルで、歴史的人物引用が豊富にありそうで購入したが、残念な書だった。
総論でもないので、本書にはサブタイトルがきちんといる。
史実から学ぶべき大事さは、充分分かるが、どの部分が現代の何に適応しているのか、説得力に欠ける。
著者は前提条件やご自身の前提理解を読者に強要しすぎている。
簡単にいうと、分かりづらいし、共感できない。
歴代民主党リーダーを歴史人物と比較し、不足を挙げる。あなたはどれほどの逸材なのか?人を評価するには、もう少し説得力と情報力がいる。
この本は最後のむすび7ページを立ち読みすれば充分だった。