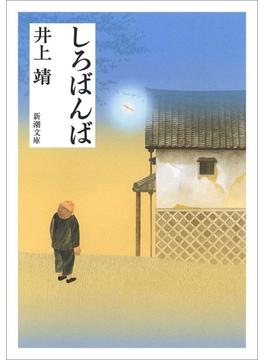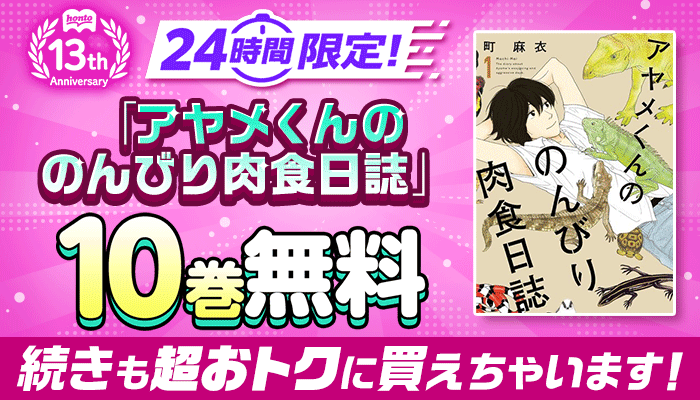- 販売開始日: 2012/04/20
- 出版社: 新潮社
- ISBN:978-4-10-106312-6
しろばんば
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
小分け商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この商品の他ラインナップ
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
ロングセラー
2011/06/08 19:12
6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:kumataro - この投稿者のレビュー一覧を見る
しろばんば 井上靖 新潮文庫
冒頭に「しろばんば」とは、夏の夕方に見られる空気中に浮遊する小さい白い生物で、その色は青みを帯びた白とあり、この小説の主人公である洪作を育てた親代わりのおぬい婆さんを指すと解釈しました。
洪作の少年時代において、幾人かの親族等が亡くなっていきます。また、赤子が生まれます。洪作少年は人の生死を通して心の成長を遂げていきます。そして彼を包むのが伊豆を始めとした日本の自然です。土蔵の家に咲く遅咲きの朝顔が目に見えるようです。人間は、ある時、ある場所に存在し、やがてこの世から消えていくのです。
大正時代の風俗や生活を検証するための読み物という位置づけもあります。馬車、日本に登場し始めた頃の乗り合いバス、縁側での談話、静岡県や愛知県を舞台として、列車の移動、タイムトラベル(時間旅行)を楽しめます。平和な世の中です。テレビを初めとした情報発信は乏しい。こどもの視点から見た大人の世界が描かれています。486ページにあるおぬい婆さんの言葉「のんきに暮らしていれば、神経衰弱にはならない」が心に残りました。
おそらく洪作少年は作者のことなのでしょう。頭脳優秀な家系に生まれています。小学生の頃から作文が得意で、小説家の素質が見受けられます。山の中で殺人を見た様子(実は逢引あいびきシーン)の部分では「トムソーヤの冒険」を思い出しました。そして、年上の女性に対する淡い恋があります。
小説は、前編8章、後編8章でできあがっています。長かった。読むのにずいぶん時間がかかりました。昭和37年に刊行された作品です。平成元年の時点、もう20年前に52刷目が出版されています。古本屋さんにて、105円で手に入れたロングセラーでした。
理想的な子供時代を過ごす少年の成長物語
2010/11/13 03:06
6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:楊耽 - この投稿者のレビュー一覧を見る
井上靖の自伝的長編小説で、主人公「伊上洪作」が伊豆湯ヶ島の小学校に通った六年間を主に少年の視点から描いています。
平成の現在、伊豆下田急行の黒船列車に乗ると、その車内に沿革を解説して曰く「開通当時はまだ陸の孤島だった南伊豆へ、第二の黒船として伊豆下田急行がやってきました。」というような記述を目にします。伊豆下田急行の開通は、昭和も戦後の1961年です。
物語は、おそらく大正元年(1912年)からの六年間で、小説の中で少年たちが「ずいどう」と呼ぶ旧天城トンネルがようやく開通(1904年)してから、まだ十年経っていない頃です。
小説の中で軽便鉄道と呼ばれる、現伊豆箱根鉄道駿豆線も修善寺の手前、大仁止まりで、つまり、物語の舞台である湯ヶ島は、半島ゆえに部外者が訪れることも稀な、山深いど田舎と言うわけです。
洪作たちが馬飛ばしを見に行くために歩いた山道を、僕も歩いたことがあります。中学生だった時で、クラスメイト六人、中伊豆と湯ヶ島の宿を予約して行った二泊三日の旅行でした。
初めての子どもだけの泊まりがけの旅行で、うかつにも、なんら観光スポットをチェックしていなかった僕たちは、中伊豆の宿を出た朝に、
「では、次の宿がある湯ヶ島まで歩いて行ってみよう。」
と、洪作たちが歩いたのと同じ山の中を歩いたのでした。
早春の筏場は、新緑に萌え、今は「日本一の棚田」と看板が立っている広い渓谷の山葵の棚田からちょろちょろと流れる清流は手ですくって飲めそうでした。
つまり、ど田舎と言うと、暗いじめじめした印象があったのですが、明るく緑豊かな山と渓谷が、この小説の舞台です。
読み終えて思ったのは
「少年の時に体験すべき事は、山深い村に住んでいても全て体験できるのだ。」
と言うことでした。
それは、例えば、洪作が級友と喧嘩をして怪我をさせてしまった時のエピソードです。
大人としては、「大事ないかな。」「ちゃんと反省してくれるかな。」と気がかりな場面ですが、物語の中では複数の大人が、それぞれに全く違った反応を示します。
同居しているおぬいばあさんは、以前口うるさい洪作の母親への当てつけで「謝っちゃれ。なんでも謝っておけば収まるから。」と洪作に言っていたのを棚に上げ、洪作を家の中にかくまい「誰にも手出しをさせないぞ。」とがんばります。
やってきた祖父は頭ごなしに「ばかもん」と怒鳴りつけ、怪我をさせた相手の家へ謝りに、洪作を引き連れていこうとします。
近所に住む耕作の親友=幸夫の母親が駆けつけ、祖父の肩を持ち「謝らせておくのが無難じゃ。」と、おぬいばあさんをなだめます。
母方の祖母は「あとでおはぎでも甘酒でも作ってやるから、何を言われても悪うございましたと謝ってきなさい。」と言う。
行った先の喧嘩相手の父親は、なんと「喧嘩は子供の仕事だ。いちいち謝っていたら、仕事が手につかないわい。」と、謝罪不要の太っ腹。
学校に行くと、先生には長い説教を食らうのかと思いきや「喧嘩はイカン。今度喧嘩をしたら、もう学校にはおいておけない。」と短い通達のみで授業を始めてしまう。
洪作自身は「大変なことをしてしまった。」としきりに反省し、つまり、健全な少年期の経験となり、以後怪我をさせるような喧嘩はしないようです。
僕の子供時代を思い起こしても「あぁ、あのとき取り返しのつかないことにならなくて良かった。」と言う危険な思い出があります。誰にでも似たような経験があるのでは無いでしょうか。(逆に、「ワタシは子供の頃にそんな悪いことは一切しなかったよ。」と言う大人は信用できないですよね?)
でも、僕には洪作のように、このような貴重な経験に加えて、「大人にはいろんな考え方があるんだなぁ。」と言うような事まで一緒に経験することは出来ませんでした。
必ずしも大人の誰もが模範的なワケではなく、それぞれ癖や個性があり、その中で生きていくことが大人になることなのだ。と、僕の場合は成人してだいぶたったころにぼんやり習得したように思いますが、耕作の場合には、こんな複雑な人間関係を、山深いど田舎で、小学生の時に経験したわけです。
その他、老人をいたわる心が芽生える瞬間や、自主的に学習に取り組み始める瞬間、女性を意識する思春期の萌芽、級友と将来つくべき職業を初めて語る、など、など、など、思いつける限りの全ての「小学生の時に経験すべき事」を経験し、成長していく洪作の物語でした。
青春の一冊
2009/01/07 14:19
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ゴルハム子 - この投稿者のレビュー一覧を見る
子供の頃から100回以上繰り返し繰り返し読んでいる小説です。
長閑な田舎町を舞台にした青春自伝小説ですが、どことなく面白い。
続編の「夏草冬濤」「北の海」もおすすめ。
井上氏の自伝的作品
2019/01/28 17:19
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ふみちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
主人公・洪作少年の中学受験前までを描いた井上氏の自伝的作品。父母から離れ、曾祖父の妾だったおぬい婆さんと土蔵で暮らした日々が綴られている。少年期の何とも言えない素直にものが言えない、ちょっと大人にみてほしいという背伸びした言動や態度が非常に上手に描かれていて目の前に洪作がいるような錯覚さえ覚える。一流の作家は、子供の描写も頗る達者だ、谷崎潤一郎の「細雪」での次女・幸子の娘・悦子の大人びた言動と幼い振る舞いなどの描写も見事だったが、この洪作少年と周りの子供たちの会話、とくに洪作が湯ヶ島から引っ越す前日に幼馴染たちとかわす会話はせつなくて涙がでる。出発当日、バスに乗った後、凸凹頭の少年のお辞儀に気を取られて、仲間たちの顔を見損ねてしまうユーモアもかわいい
昔読んだ本
2023/05/08 09:45
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:もこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
友人達と会話していて昔読んだこの本を思い出し、何十年ぶりかで、今回は電子書籍で購入しました。再び作者の世界観にどっぷりとハマっています。
みんな非常に個性的なキャラで 目に浮かぶよう
2021/03/31 23:53
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:いっしー - この投稿者のレビュー一覧を見る
昔からある有名な井上靖先生の本、それが「しろばんば」です。
主人公の多くは少年ですが、みんな非常に個性的なキャラで
目に浮かぶようです。
新潮文庫で持ち運びやすいので電車などどこでも読んでいます。
大人でも読み応えのある作品です。
2021/02/26 21:14
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:しゅ - この投稿者のレビュー一覧を見る
井上靖先生の非常に有名な作品です。
あらためて読み返すと静岡県伊豆地方の原風景に
行ったことのないわたしでも「なつかしさ」を感じます。
続編として『夏草冬濤』、『北の海』があります。
大人でも読み応えのある作品です。
子供は愛を受け止める天才
2002/06/26 07:14
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:読ん太 - この投稿者のレビュー一覧を見る
懐かしい思いがよみがえってくる小説である。と、言っても、舞台は大正時代の小さな村であるからして、私が子供時代を過ごした時期とは全く重なってはいない。洪作という男の子が成長していく物語である。季節ごとに巡ってくる行事に心躍らせ、友達と遊びまわり、時には喧嘩をし、生まれて初めての経験を数々する。私にも身に覚えのある感情が綴られていくので、時代や地域の違いなどは、実際より昔に遡ってもらって実際よりずっと田舎に設定される方が、却って懐かしい思いがが倍増する。
洪作は、おぬい婆さんとの二人暮しである。おぬい婆さんは、曽祖父の妾であった人である。洪作の両親から一時洪作を預かって以来、婆さんは洪作の養母という立場が自分の存在価値を示す唯一の手段として、洪作を決して手放そうとしなかった。こうして、おぬい婆さんと幼い洪作の生活は始まった。
おぬい婆さんは、いわゆる人質である洪作を大切に育てる。洪作を婆さんの手に託すことをよく思わぬ人々の事は、口を極めて罵り、それは洪作の耳にも毎日のように届いている。歪んだ環境で育っているともいえる洪作であるが、洪作独自、いや子供独自の感性で人を見て、大人の計り知れない気遣いをしながら育っていく様は、不憫というよりもたのもしい。
『しろばんば』には、色々な愛の形が描かれている。おぬい婆さんの洪作に対する愛は、溺愛である。公平にものを見て話をしようなどとの考えは全くないので、おぬい婆さんの言葉にはしばしば笑わせられるが、愛情の深さは直球でこちらに伝わってくる。
洪作の叔父は、小学校の校長である。ニコリとも笑わないし、洪作にやさしい言葉をかけることもない。しかし、愛は確かに感じられる。
洪作を手放した母にも、愛がある。手元に置いて育て上げなくても、愛情が古びたり薄れたりすることはない。
愛をしっかりと受け止めて成長する洪作が、最終章で、付き合いのほとんどない村の老人に言った言葉、『おじいさんも体に気をつけな』、これが洪作の初めての「愛情を言葉に表現したもの」だった。
言葉を持ち駒のように使っている今の私。子供の頃は、嬉しくてたまらない時に、「ありがとう。」の一言が出ずにうつむいていた。「ありがとうございます。」 「お世話になります。」 を、感情を置いてきぼりにして連呼する現在の自分に、赤面してうつむきたくなった。
井上靖
2025/03/16 17:21
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:みみりん - この投稿者のレビュー一覧を見る
井上靖さんの「夏草冬濤」「北の海」を読んで、同じ自伝的小説のこちらも読んでみることにしました。
順番は、しろばんばがいちばんはじめらしい。
井上靖さんの自伝的小説を読むといつも思うんだけど、井上靖さんは歴史小説の方が好きだなぁ。