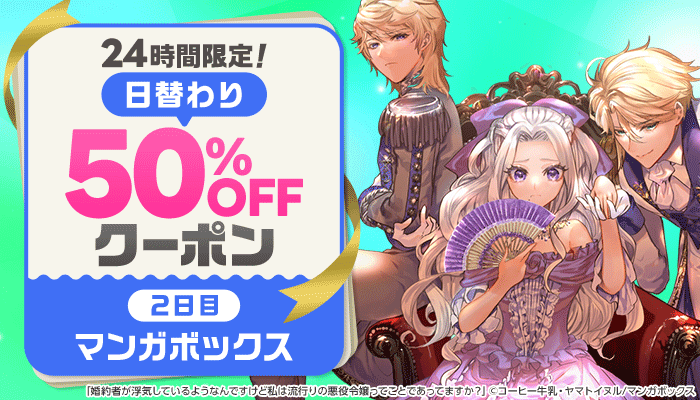0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:じゅん二 - この投稿者のレビュー一覧を見る
意外と、「理性の限界」より、読み良かった。「理性の限界」の前段階として、おすすめする。1「言語の限界」が、読み良い。
ファイヤアーベントが気になってくる・・・
2015/11/09 01:37
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:色鳥鳥 - この投稿者のレビュー一覧を見る
「完全なる民主主義はありえない」という説が痛快だった『理性の限界』、読んでいて、自分と考え方が最も近いかも?と思った登場人物が「方法論的虚無主義者」でした。
今回も、「彼」に肩入れして読んでしまい、ファイヤアーベントについてくわしく知りたくなりましたね。
なーんとなく知っていたつもりの知識、きっちり整頓するのに最適な1冊、でもありました。
投稿元:
レビューを見る
ほとんどどこかで読んで知っている内容であったが、さまざまな登場人物を織り交ぜた戯曲形式で面白おかしく書かれており、難しい内容のはずなのに割かしすっきりと読むことができた。
投稿元:
レビューを見る
理性の限界の続編。
内容は
・言語の限界
・予測の限界
・思考の限界
の3つ。
言語の限界は、Wittgensteinの言語ゲーム(特に論考が中心)を説明し、予測の限界は帰納法の限界やカオス現象による予測の不確実性、思考の限界は宇宙論での人間原理の紹介が中心。
前回の理性の限界と同じく、シンポジウム形式で各専門家が発言する方式。
内容はやや凡庸であるが、平易な言葉で本質をよく表すのは、理性の限界のそれと同じである。
哲学者の一般人向けのアウトリーチ活動としては最高傑作と言ってもいいかもしれない。
Wittgensteinの言語ゲームも「 はじめての言語ゲーム (講談社現代新書) (新書) 」よりもわかりやすいと感じた。
前回の著書に比べ、トピックは面白いものの、内容がやや凡庸であるという点が残念。
投稿元:
レビューを見る
んー、ファイヤアーベントは要チェック。コンテクストの共有によって言語は不要になると思うし、コンテクストによって個々の世界観が形成される、なーんて思いました。引き続き前著である「理性の限界」へ。
投稿元:
レビューを見る
ファイヤアーベントの「何でもかまわない」という主張自体は何でもかまわなくないのではないか。ヴィトゲンシュタインの「語りえないことは沈黙しなければならない」という主張と同様、自己矛盾をはらんでいるのではないか。
投稿元:
レビューを見る
「理性の限界」の続編。ウィトゲンシュタインの言語哲学、ポパーなど限界に関する哲学論考がディベート形式でわかりやすく説明されている。哲学の一端を触れるうえで、非常におすすめ。
投稿元:
レビューを見る
名著だと思います。
細かい内容に関しては語り尽くせるものではないので、簡単な内容の紹介と感想を。
この著書は「理性の限界」(私は読んだことが無いですが、かなり面白そうです)の続編であり、「言語の限界」、「予測の限界」、「思考の限界」の三編構成で成り立っています。
全ての内容はディスカッション形式で綴られており,司会者としての著者と仮想人格を持たされた多くの登場人物が対話を用いて議論を進めています。全体を通して哲学書の内容でありながら、広範な知識を取り扱っており、内容も非常に分かり易く興味深い。
言語の限界では、ウィトゲンシュタインの論理哲学論考、実証主義、実の言語への射影、語りえぬこと、ウィーン学団についてに関する話題を用いて従来哲学を統括、続いて後期ウィトゲンシュタイン哲学、実証主義の崩壊、言語ゲーム、副題でもある「指示の不可測性」、言語理解の限界、観察の理論負荷性、理論の決定不全性について述べて膜を閉じます。
簡単に言えば、言語に射影出来ないものは理解出来ない擬似問題であると断じ従来哲学を一蹴、しかし言語に出来ないが理解出来る事象の存在から新たに解析を進め、言語の完全なる習得・理解の不可能性を指摘し…、と言ったところですか。…言語化するのが難しいのは完全な理解が追いついて居ないからですね、すいません。
予測の限界ではまず帰納法と演繹法の説明から入ります。基本を押さえていますね。次に帰納法の正当化とヘンペルのパラドクスによる帰納法の否定、続いて反証主義によるポパーの科学、疑似科学判定、更に自己意思・宿命論、副題である「ナイトの不確実性」に基づいた危険性と不確実性の説明、最後に予測の限界と可能性についてです。
帰納法の用いられるべき・対象に出来る範囲、複雑性を織り込んだ予測の限界や大数の法則から求められる期待値に関する議論から予測の可能性について議論しています。
最後が思考の限界。まず宇宙物理物理学をネタにした微調整の原理から入っています。詰まるところ、現行の世界に於ける物理定数の凄さについてですね。そこから神の存在について議論、神の存在証明(宇宙論的証明、存在論的証明、目的論的証明)…インテリジェントデザイン。ここで出てくるのが、ファイヤアーベント。副題に於ける「不可知性」ですね。彼は「全ての事象や議論は無意味だ、何でも良い」と述べているようですが、適当な訳ではありません。これは私と同じような考え方で、言語や科学など、それが真であるか否かを測定し得る客観的な尺度が存在しない以上、全ての問題は不可知である。との考えです。
まぁ思い出しながら適当に述べてきましたが、非常に面白かったです。理性よさらば…。
投稿元:
レビューを見る
ゲーテル、カント、ウィトゲンシュタイン、ポストモダンあたりの哲学(+論理学?)をネタに、各立場の論客を登場させ、シンポジウムという場で議論させる。哲学に関連する書籍のスタイルとしてはどこかで聞いた話のような気もするし、内容としてはそれほど深くもない。基本的には、少しは”知っている人”に、「○○の考え方って、そういうところあるよね」と共感させるのが狙いのような作り。しかしながら、それぞれの論客のキャラが良いので、娯楽本としては成功しているのではないかと思う。物理学者のアラン・ソーカルによる科学用語満載の疑似哲学論文が著名な評論誌にアクセプトされた、いわゆる「ソーカル事件」の取り上げ方を見るに、著者は哲学の衒学趣味にはかなり批判的なのだろう。そのスタンスには、個人的にも共感するところがある。おかげで楽しく読むことができた。
投稿元:
レビューを見る
著者の@ShoichiroTさんの目論見どおり知的刺激を味わいました。美味しかった^^インタプリタ的に半端なく優れた「仮想パネルディスカッション」。前著も読もう。
投稿元:
レビューを見る
「理性の限界」よりはおもしろいかな。宇宙の「人間原理」については考える事多し。人間なしの世界、物質、宇宙とは何なのか。バークリー流には到底ついていけないが、かといって人間なしの世界の在り様は想像できない。
投稿元:
レビューを見る
思ったほどのものではなかったけど、確かにまとめ方としては上手くて読みやすかった。求めてたのはこんなことじゃない!って思ったのはたぶん僕の求める先が違ったんだと思う。
投稿元:
レビューを見る
「無限の苦しみを感じて生きていく知的生物を生み出す終わりのない宇宙を永遠に消失させるために、私たちは知的になりいつの日か宇宙を完全に消失させる方法を見つけなければならない」というハルトマンの考えに妙に共感してしまった。
限りなく悲観的であるけれど、ある意味でこの上なく大きな挑戦で、どこかワクワクしてしまう発想でもある。宇宙を社会的な制度に置き換えて考えてみると非常に理性的で建設的な考え方でもある。
私はこの本の中でいろいろな考え方について体系的に学んでいくことができたが、最も驚嘆したのは一番最後に出てきたこの発想だった。
最後の方で出てきた形而上学による3種類の神の存在証明もハルトマンに次いでハッとさせられた考え方だった(特に2番目の「存在論的証明」)。
そう考えると、さまざまな考え方をさらっと紹介しているように思えるこの本も、実は1つのストーリーを構築するように設計されているのではないかとすら感じた。
投稿元:
レビューを見る
前作に引き続き哲学に対して「サッパリ」と入っていける名著。相変わらず様々な分野の学者が登場しては個性的な議論を繰り広げてくれる、しかもそれがなんだかリアルさがあってまた面白い。今回は方法論的虚無主義者の影が薄いなぁと思ってたらしっかりと最後に出てきました。
今回、特に印象的だったのは「帰納法の自己矛盾」と宇宙の存在論の二つです。夜寝る前に誰もが考えた経験のあるような話を、専門性を保ちつつ平易で分かりやすく議論していく様は著者の学者としての力量に加え小説家的な力量を強く感じます。
カジュアルに、しかしじっくりと哲学を楽しみたい人にお勧めの一冊です。
投稿元:
レビューを見る
仮想ディベートという形式に馴染めなくて棚上げしていたけれども、読み始めたらイッキ読み。そういえば、仮想ディベートって、プラトン以来の由緒ある哲学の語り方なんだよね。それに、読み手がツッコミたくなるところを的確に突っ込む登場人物が必ずいて、かなり親切。
本書をざっくりまとめると、760円(超お買い得)の觔斗雲で巡る、「知性の限界」という御釈迦様の手のひらツアー。稀代のツッコミ役ファイヤアーベントや究極の悲観主義者ハルトマンについては本書で初めて知った。
ツッコミ役といえば、「そのお話は、また別の機会にお願いします」でおなじみの司会者。あなたこそ<全知全能>だ(笑)。