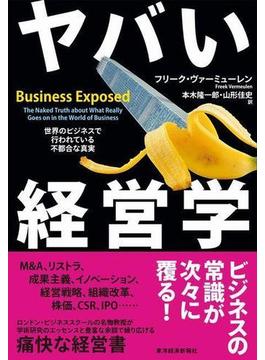0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:しろ - この投稿者のレビュー一覧を見る
業績が良いと、投資資源がたくさんあるから、新規事業に進出する。不況になると「選択と集中」でコア事業に投資する。しかしそれは間違っており、不況こそ、生き残るために、好調時には見向きもされていなかった顧客や分野が鍵となるという。
また、大成功を収めた経営者は、単に幸運に過ぎない場合もある。よく考えれば当たり前だが、これを経営者は自分の有能さのためだと考えてしまうという。
本書はこういった、世間の「常識」となっている物事の別の側面を"expose"するものである。背景には豊富な事例研究による統計データがある。「何となくみんなが思っていること」を、数字で真実を明らかにしていくのは、気持ちがよいものだ。
どちらかというとエピソード中心で、全体として流れやまとまりは乏しいが、それがリズムがあって読みやすくて良い。
わかりやすい でも深い
2016/11/09 22:37
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Anna - この投稿者のレビュー一覧を見る
経営学においてはまだど素人の私。それでも長く続く/続かない企業 一気に利益をあげる企業/あげない企業 それぞれの特徴や長所短所など傾向について書かれており、勉強になりました。傾向においてだけではなく各企業のリーダーの気質の違い、それに伴う従業員のモチベーションの違い等… 心理に関する事も書かれており面白い。企業として、よりリーダーとして必要なモノが学べたと思います。
イマイチ伝わってこないです
2017/11/13 12:28
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:こぶーふ - この投稿者のレビュー一覧を見る
翻訳の問題か、内容が体系だっていないからか、イマイチピンとこない本でした。結局のところ、じゃあどうしたらいいというのが、よくわからない本でした。まずは王道の経営学の本を読んだうえで、さらりと読んでみるのがこの本はいいのかもしれません。
投稿元:
レビューを見る
「よその成功事例のケーススタディなんかやっても、スタディしているうちにビジネスの環境は変わるからあまり使いものにはならない」ということを某社で健在の創業者社長が言っていたのを思い出した。
その意味ではビジネススクールの研究に裏打ちされた失敗事例集みたいな本。
経営者と経営学の研究者の関係は、芸術家と批評家の関係に似ている。
投稿元:
レビューを見る
表題からして裏の世界の話かと思ったが違った。現代の企業の抱える問題点を学問的にあぶり出しているのが本書である。会社員にとっては、「あぁ、うちだけじゃないんだ」という妙な共感を得られる書物でもある。
経営とは何か?
買収は何故繰り返されるのか?
企業は誰のものか?
株主の利益の最大化は正しいのか?
取締役会は機能しているのか?
そういう企業の本質に対して、悉く学問的な研究成果を以て切り込んでいく。バサバサと切り捨てていく様はなるほど一種の快感である。しかし、今後どうするべきかというと答えに詰まる。最終的には、現状否定だけでは、何もなし得ないということを思い知らされた一冊だった。
投稿元:
レビューを見る
経営学のエッセイ集。だが実際の論文をベースに議論を展開しているので結構鋭い。
常識に一石を投じるまさにthat's interesting的な面白さに溢れた一冊。
投稿元:
レビューを見る
流行りの経営手法、買収、取締役会、その他多くの企業で当たり前のようにやられていることや言われていることが、実は意味がなかったり、時には害でさえあることを実例や根拠を示しながら、論じている。逆に、何も商品を産み出していないような研究開発や不要と思えるような組織再編に意味があると言う主張も面白かった。
投稿元:
レビューを見る
ふだんビジネス系の本はあまり読まないんですが、これは面白かった。自分の会社に当てはめたりすると特に。
投稿元:
レビューを見る
入山章栄『世界の経営学者はいま何を考えているのか』(英治出版、2012年)には、経営学の三大ディシプリンを①経済学、②認知心理学、③社会学としている(p.46)。その分類に従えば、フリーク・ヴァーミューレン『やばい経営学』(東洋経済新報社、2013年)は②に該当する。著者は本書で企業経営の非合理な側面をあぶり出しており、社会心理学の書籍を読むような驚きがあった。
たとえば第6章(経営にまつわる神話)には、ISO 9000の導入によって企業の長期的なイノベーションが阻害される調査結果が記されている(p.193)。ISO 9000に限ったことではないが、プロセス最適化に関するマネジメントシステムは形骸化しやすいので、無理もない。しかし、短期的な利益(世間の評判や株価の上昇)は得られるので、流行に従って導入してしまいがちだ。そのほか、研究開発部門の真の貢献は研究開発ではなく競合企業の新発明を素早く模倣することにあるという点も興味深い。
情報システムとの関連では、知識データベースである「ノウハウ管理システム」の事例(p.212)が興味深い。プロジェクトに入札するためのノウハウ管理システムが構築・運用された企業で、システムの効果を検証するために社員のデータベースの活用が入札成功率に与える影響が調査された。すると、内部データにアクセスすればするほど入札に負けるという、予想を覆す事実が判明した。過去のノウハウが見つかると、それで満足してしまって思考が停止するためだ。著者は、「高価な文書データベースは廃止したほうがよい」と述べている。
また第7章(暗闇の中での歩き方)では、イノベーションをめざすと失敗するリスクが大きくなるうえ成長もしないという結果が示される(p.228)。むしろ、うまくいっている他の会社を「そのまま」コピーするのがよいという。優良企業の成功要因は複雑に絡み合っていて、1つ1つを取り出すのは難しい。従って、最初は完全にコピーし、時間をかけて修正していくのがよいのだそうだ(p.246)。
また、組織再編についての助言も納得のいくものだ。著者は、たとえ明確な理由がなくても組織再編を行うべきだと主張する(p.253)。それは社員同士のつながりを活発にさせるとともに、過度の権力の集中を止め、変化に対する適応能力を高める効果がある。
学生のころ、『Dilbert』というエンジニアを主人公にした米国のコマ漫画で、効率化のために機能を集中させ、その1年後にボトルネック解消のため機能を分散させる経営層の説明を聞いた主人公が「こいつはマネジメントの天才だ」と独白するシーンを思い出した。あれはまんざら間違いではなかったのか。
投稿元:
レビューを見る
「ヤバい経営学」は別のヒット書籍からの転用らしいですが、この邦題の軽さが、内容の軽妙さとシンクロしていると思いました。「会社って組織ってやつは…」「経営者って存在ってやつは…」なんかデータと事例を多用して皮肉っぽく展開していくのですが、その根底は決してネガティブなものではなく、会社という仕組み、会社経営という行為についてのポジティブな期待を感じました。最近のビジネススクールでは数字による効率化だけではなく、人間の本性を活用することへの言及が増えている、という話を聞いたことがありますが本書のその流れに位置するするのでしょう。基本は「ヤバい」からこうしたら、じゃなくて「ヤバい」からどうする?なのでもうちょっと突っ込んで考えたくなりますが、まずは、「気づけ!」ということだと受け止めました。
投稿元:
レビューを見る
経営の意思決定と組織に関する、極めて真っ当な本。視点が新しく、すごく勉強になる。有用な情報なりコネなりを集めることができる組織が強いのかな、と読んでて思った。
投稿元:
レビューを見る
素直に面白い。訳もこなれていて読みやすい。
まさに自分が普段感じているビジネスの現実を思い浮かべながら「あるある」と笑ってしまうことを、各種の論文等で裏付けてくれるので楽しい。
投稿元:
レビューを見る
とても良い本です。是非経営者の皆さんに読んでほしい。私も裸の王様にならぬよう、頑張らねば!
しかしこの題名はちょっと軽すぎるのでは、、
投稿元:
レビューを見る
ヤバい経済学をはじめて読んだときと同じ衝撃度。ただし、経済学ヤバい(超おもしろい)とは違って、経営者ヤバい(間違いだらけ)、世に出回っている経営理論ヤバい(間違いだらけ)というところがミソ。
経営戦略ヤバい(役に立たない)、優良企業ヤバい(今がピークで後は落ちるだけ)、リストラヤバい(やると潰れる)、M&Aヤバい(ほとんど失敗)、カリスマ経営者ヤバい(ほとんど運の世界)、社内データベースヤバい(金太郎飴化が進んで差別化できない)、イノベーションヤバい(たいてい潰れる)、株主重視ヤバい(長期的には社員重視のほうが生き残るかも)、エトセトラエトセトラ。
本書を読み終えた人は声を大にして叫ぼう、「王様は裸だ!」
投稿元:
レビューを見る
訳がちょっと固いような
内容自体は(本当に裏付けがあるのかはともかく)科学的でまっとうな手法を使って常識に反すると思われることを述べるという良いスタイル
まあたしかにこんなもんなのかもねーとは思うけど、まゆつばなところが散見されることも